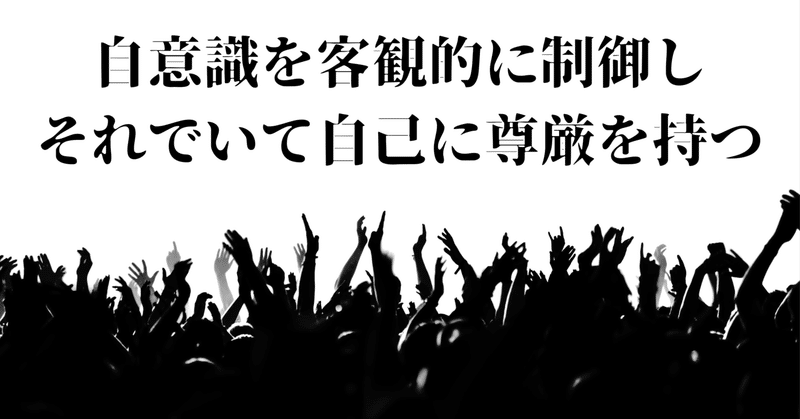
メインチャンネル『三大幸福論』解説の書き出し文置き場(ラッセル・アラン・ヒルティ)
提供:ハイッテイル株式会社
こんにちは。
哲学チャンネルです。
メインチャンネルで公開した「三大幸福論」の書き出し文置き場です。
ラッセル→アラン→ヒルティの順で並んでいますので、ご興味のある内容がございましたら、どうぞご覧ください。
不幸の最大の原因は過度な自意識である『ラッセル|幸福論』
バートランド・アーサー・ウィリアム・ラッセルは19~20世紀におけるイギリスの哲学者、数学者です。
彼は、連合王国貴族ラッセル伯爵家の当主であり、祖父にはイギリスの首相を二度務めたジョン・ラッセルがいます。まさにエリート中のエリートです。
当時の貴族の中では、子供の初等・中等教育において、正規の学校ではなく、家庭教師などによる特別な教育を受けさせることが多かったと言います。ラッセルも例外ではなく、ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに進むまでは、学校に所属していませんでした。
ケンブリッジ大学卒業後、そのまま同大学で教鞭を取ります。そこで出会ったウィトゲンシュタインとのエピソードはあまりにも有名ですね。
ラッセルの業績といえば「ラッセルのパラドックス」や『数学原理』による数学と論理学への貢献。『西洋哲学史』における哲学史学者としての仕事 *1『表示について』による「記述理論」の提唱など。様々な分野にわたって数多くの業績を残したわけですが、忘れてはいけないのが、彼が最も熱心に取り組んだ仕事の一つである「反戦・平和運動」です。
ラッセルはとても現代的な感覚を持っており、当時勢いのあった共産主義による暴力革命に反対したり婦人解放運動に力を入れたりと、平等や平和に対して尽力した人でもありました *2
第一次世界大戦中の平和運動では、大学の職を失ったり、6か月もの間投獄されてしまうこともありましたが、それでも彼は反戦・平和運動をやめませんでした。
第二次世界大戦においては、反戦というよりも、ナチズムに対する徹底的な対抗を唱えます *3
戦後の1955年には、(平和に対しての)思想が近かったアインシュタインと共同で「ラッセル=アインシュタイン宣言」を発表します *4
この宣言は、2年後に開催されたパグウォッシュ会議に繋がり、その会議では全ての核兵器およびすべての戦争の廃絶が訴えられました。
どんな分野から見ても「巨人」であるラッセルは、個の幸福についてどのように考えていたのでしょうか。
ラッセルの『幸福論』は、三大幸福論の中でもとびきり「論理的」で「現実的」で「無神論的」です。そういう意味では、現代を生きる(日本人である)私たちにとって一番理解しやすい内容なのかもしれません。
本書は大きく二つの章で構成されています。前半は「不幸の原因分析」後半は「幸福の獲得方法提示」です。この構成も非常にわかりやすいですね。
構成に倣って、まずは「不幸の原因分析」を確認しましょう。
ラッセルは不幸を引き起こす原因となるものとして
悲観主義・競争・過度な刺激・疲れ・妬み・罪悪感・世間の評価
などを挙げていますが、その中でも特に重要なのは「過度な自意識」による「被害妄想」であると言います *5
人はえてして、自分のことを過度に重要視します。
自分という存在が他者に及ぼす影響。
自分がやった仕事や行為が世の中に及ぼす影響。
自分という存在それ自体の大きさ。
これらの自己評価を無駄に大きく見積もることにより人は不当にストレスを感じ、不当に悩む。
「過度な自意識」は被害妄想を生み、本来なかったはずの悩みを発生させます。
確かに、わかる気がします。
例えば、ある仕事に就いている人が「自分がいなくなったらこの職場は回らない」と考えて、働きすぎてしまうことがあります。私個人としても、アルバイトなどをしていたときはそんなことを考えていた気がします。
しかしほとんどの場合、自分がいなくなっても職場は回ります。これはまさに「過度な自意識」の代表的な例ですね。
また「自分はあの人にどう思われているんだろう」と考える際の質感と、実際にその人が自分に対して抱いている質感の間には大きなギャップがあることも少なくありません。
嫌われていると思っていたけど、そうではなかった。もっと言えば、相手は自分に対して何も思っていなかった。みたいなことは往々にしてありますよね。
これも「過度な自意識」の代表例と言えそうです。
ラッセルは、この「過度な自意識」を排除することで不幸の要因の多くを消し去ることができると考えます *6
そのためには、世界における、宇宙における「自分」という存在の位置関係を正確に認識する感覚が必要です。
フォロワー数や、数字による評価が基盤になっている現代社会は「過度な自意識」が生まれやすい環境だといえます。その環境とどのように距離を取るかという問題は、今この時代だからこそ、とても重要なテーマなのかもしれません。
また、彼は不幸の原因を考える際に「物質的に不幸な人」を排除しました *7
物質的に不幸な人はどうやっても不幸である。だから、最低限の物質的環境を手にしているのにも関わらずそれでも不幸な人を考察するのが良いだろう。という考えのもと、不幸の原因を考察したわけです。
そして、こと日本においては、ラッセルがイメージする「物質的に不幸な人」はそう多くないと考えられます。
もちろん、そういう方も一定数いらっしゃるとは思いますが、ほとんどの日本人は、物質的に恵まれた生活をしています。
よって、ラッセルの提示する「不幸の原因」は、おおよそ全ての日本人に当てはまるものであり、それだけに「過度な自意識」を前提に自身の人生を客観的に観察する意義は大きいと思います
さて、彼は幸福論の後半で「幸福の獲得方法」について述べています。
まず前提として、幸福には二つのパターンがある *8
一つは地味で、動物的で、感情的なもの。もう一つは凝っていて、精神的で、知的なもの。
結論からいうと、私たちが手にできるのはほとんどの場合後者のタイプの幸福です。
前者の幸福について、ラッセルは「読み書きができないものが手にする類の幸福」だと表現しています *9
言い換えると「情報があまりに少ないために手にできる幸福」ですね。
例えば、回転寿司でしかお寿司を食べたことがない人は、回転寿司で一定の満足=幸福感を感じることができます。しかし、回らないお寿司屋さんに行くことで舌が肥えてしまった人は回転寿司に行っても、前者の人ほどは満足=幸福感を感じられません。
私たちは、世界で起きていること(情報)をリアルタイムかつ大量に受け取れる環境で暮らしています。つまり「知らないままでいる」ことが難しくなっているのです。
二つの幸福に優劣はありませんが、「知ってしまった」場合に、前者の幸福に辿り着く術はありません *10
よって、現代人が目指すべきは後者の幸福です。
その上で彼は、熱意・愛情・家族・仕事・趣味・努力などが幸福を獲得するために必要な要素だと考え、それぞれについて検証をします。
特に重要視しているのは「仕事」についてでしょう。ラッセルは、熱意を持って社会に役立つ仕事をし、それに健全な誇りを持つことが幸福の直接の源泉となると言います *11
ここで着目すべきは「仕事で成功すべき」と言っているわけではないということです。
一番大事なのは、仕事を通して自尊心を獲得することであり、確かにそのために一番簡単なのは「成功すること」ではあるものの、世間一般的な「成功」ではなくても、仕事に従事する結果として自尊心が得られれば、それで良いのです。
そういう意味では、それが「仕事」でなくても良いのかもしれません。広義での仕事、つまり「活動」的なものの結果として自分に自信を持つこと。これが重要だと言っているわけですね。
熱意と努力を以てすれば、仕事に誇りを持つことができます。仕事で得た自尊心により、他者へ愛を与える余裕が生まれます。その愛が家族や友人関係を作り、仕事以外の時間を満たします。
結びの章で、ラッセルはこのようなことを主張します。「幸福になるのはそんなに難しいことではない」 *12
幸福になるための条件には外的/内的という二種類の要素があります。外的な環境が変化することで幸福になる場合もあるし、自分自身の感覚が変わることで幸福になることもありえる。
彼の幸福論では、特に後者に力点が置かれています。だからこそ、幸福になるための必要な条件に「仕事での物的成功」ではなく「仕事による自尊心」を挙げるのです。
自分に対しての過度な期待を辞め、世界においての自分の位置を冷静に客観視する。それでいて自分に対して誇りと自信を持ち、その自尊心を中心に生活を充実させる。
こうまとめてしまうと味気がないですが、彼の主張は概ねこのようなものです。
ラッセルの『幸福論』のポイントは「バランス」でしょう。
内的/外的な要素それぞれをバランスよく意識する。まずはじめに内的な要素を客観視して「過度な自意識」から脱却する。そして外に関心を持ち、自己実現を目指す。
彼の『幸福論』はあくまでも個人を念頭に置いて構成されていますが、その先には明らかに「平和」が想定されています。おそらく彼にすれば「個の幸福」が実現されることが平和への十分条件だったのでしょう。
不幸と幸福を構成するそれぞれの要素についての議論は、ぜひ、本書を読んで確かめてください。
古い常識も散見されますが、現代でも十二分に通用する幸福論だと思います。
□注釈と引用
*1 一説によると、哲学書の中で「Western(西洋)」という形容詞を採用した初めての書が『西洋哲学史』であるとされています。本書では「西洋」の哲学だけではなく、ユダヤ哲学やイスラム哲学にも言及しており、その対比として「Western(西洋)」という形容詞が用いられています。
*2 一方で優生学には好意的だったとされています。例えば、精神欠陥者の「選別」に賛同したり、優秀な人間に「贔屓」することにも賛成したいたようです。また「倫理的に問題はあるが」と前置きした上で、優秀な人間を試験で選抜して、その人間たちを交配していけば、最強の国家を作ることができるとも述べています。(『ラッセル結婚論』岩波文庫 18章)
*3 ラッセルの平和論はよく「現実主義」だと称されます。絶対的な方法論によって平和を目指すのではなく、そのとき取りうる最良の(それが最高ではなくても)方法で、そのとき起きている最悪な出来事に対処する。そのような思想です。そういう意味で、第一次世界大戦の際は「戦争をやめるべき」という意見だったのが、第二次世界大戦では「戦争はやめるべきだが、ヒトラーが実権を握っているうちは(致し方ないが)戦争によって悪を消し去るしかない」と考えたわけです。この変化については当時めちゃくちゃに叩かれていたみたいです。
*4 ちなみにアインシュタインは、この宣言に署名した1週間後に亡くなっています。
*5 ラッセル幸福論 安藤貞雄訳 岩波文庫 P124 第一部 第八章
ー本章での私の目的は、各個人が自分の中に被害妄想(この病気には、大なり小なり、ほぼ全ての人がかかっているのだ)の要素を見つけ出し、見つけ出したなら、それを取り除くことのできるような一般的な考察を述べることにある。これは、幸福獲得の重要な部分である。というのは、私たちは万人が自分を虐待していると感じているかぎり、幸福になることはまるで不可能だからだ。ー
*6 ラッセル幸福論 安藤貞雄訳 岩波文庫 P130 第一部 第八章
ラッセルは過度な自意識を避けるための方法を四つの公理として示しました。
①あなたの動機は、あなたが思うほど利他的でないことを知ること
②あなた自身の美点を過大評価しないこと
③あなたが自分自身に寄せているほど大きな興味を、他の人があなたに寄せていると思わないこと
④大抵の人は、あなたを迫害してやろうと特に思うほどあなたのことを考えている、などと思わないこと
*7 ラッセル幸福論 安藤貞雄訳 岩波文庫 P14 第一部 第一章
ーこの問題を論じる場合、私は、極端な外的不幸の原因のない人たちにのみ注意を向けることにしたいー
*8 ラッセル幸福論 安藤貞雄訳 岩波文庫 P157 第二部 第十章
ー私の言う二つの種類は、じみなものと凝ったもの、動物的なものと精神的なもの、感情的なものと知的なもの、といったふうに区別できるかもしれない。これらの対立する名称のどれを採るかは、もちろん、論証されるべきテーゼによって決まってくるー
*9 ラッセル幸福論 安藤貞雄訳 岩波文庫 P158 第二部 第十章
ラッセルは前者の幸福を「どんな人間でも得られるもの」後者の幸福を「読み書きができる人間にしか得られないもの」と表現しています。そのため前者の幸福を「読み書きができないものが手にする類の幸福」とは表現していないし、厳密な意味ではそう表現してしまうのには語弊があるのですが、事実上後者の幸福が必要な状態になった場合、前者の幸福を純粋に感じるのは不可能であることから、この動画ではそう表現させていただきました。
*10 記憶を消すことができればあるいは。
*11 ラッセル幸福論 安藤貞雄訳 岩波文庫 P230 第二部 第十四章〜
*12 ラッセル幸福論 安藤貞雄訳 岩波文庫 P266 第二部 第十七章
ー明白なことだが、幸福は、一部は外部の環境に、一部は自分自身に依存している。本書で扱ってきたのは、自分自身に依存する部分であった。そして、この部分に関するかぎり、幸福の処方箋は実に単純である、という見解に到達したのであったー
悲観主義は気分、楽観主義は意志『幸福論|アラン』
アラン、本名エミール=オーギュスト・シャルティエは、フランス生まれの哲学者です。
彼は学生時代に哲学を専攻し、哲学の面ではカント、ヘーゲル、スピノザ、プラトンなどから、文学の面ではバルザックやスタンダールから影響を受けますが、とりわけ受けた影響が大きかったのが、当時大学で教鞭を取っていたジュール・ラニョーによる大陸合理主義哲学の講義でした。
彼の『幸福論』には、内的な「理性」を重要視する傾向がありますが、ここには学生時代の経験が大きく影響していると思われます。
大学卒業後、アランは高等学校の教師として働き出します。
彼は教師職の合間を縫い「プロポ(哲学断章)」という自身の考えを綴った語録を新聞社に送っていました。その数なんと3000以上。彼は8年間1日も休まずに新聞社にプロポを送り続けたのです。
彼が残した断章は、世界・理性・政治・宗教など様々なテーマを扱っていますが、その中でも「幸福」に関して言及された98篇のプロポを集めたのが、今回紹介するアランの『幸福論』です。
前回、ラッセルの『幸福論』を紹介する際に「論理的」で「現実的」で「無神論的」だ、と表現しました。対比して考えると、アランの『幸福論』はとびきり「詩的」で「抽象的」で「精神的」です。
彼は物事を体系化することを嫌ったと言います。
それは哲学的な主張に関しても同じです。
だからこそ、理路整然とした説明ではなくて「断章」という形を取った抽象的な表現に拘ったのです。
そこには少し東洋的なエッセンスを感じます。
例えば釈迦は自身の思想を体系化しませんでした。
彼がやったのは、そのときその人に対して一番心に響くような「断章」を語ることであって、それは決して自身の理論の押し付けではありません。
古代ギリシアが東洋の思想に出会った時代にはソクラテスが活躍しました。
彼も、自身の思想を体系化することを考えませんでした。
彼がやったのはもっぱら「対話」であり、そこにこそ「何か」がある、と考えていたわけです。
ちなみに、アランの弟子であるフランスの評論家アンドレ・モーロワは、1949年にアランの生涯や教えをまとめた著作を発表しています。彼はその中でアランのことを「現代のソクラテス」と評していますが、個人的にこの評価には強く共感できます。
さて。
アランの『幸福論』の根底には悲観主義があります。
彼は人生を「本質的にしんどくて、辛いものである」と考えました。
ここにも仏教的な要素が見え隠れしますね。
人生は本質的に「苦」なのだから、何も意識・行動しないならば悲観主義が真理である。
これだけでは単なる厭世主義で終わってしまいますが、アランはここから楽観的な主張を展開します。
曰く、人生は本質的に苦なのだからこそ、それを上機嫌に捉えることが重要である *1
つまり、幸せになれるかどうかは元々苦痛があって当たり前の人生をどう捉えるかという自分の心の持ちよう次第だと言っているのですね *2
この主張は『幸福論』においての「人は幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ。」という名言に集約されています。
自分で積極的に幸せになろうとしないと不幸になるのが必然である、というわけですね。
ラッセルは、外的な環境よりも内的な環境の方が重要だと主張しました。
ただ、彼が主張した内的な環境、例えば「自尊心」などはあくまでも「仕事の充実」などによる外的な環境から生まれる質感です。アランがいう「心の持ちよう」は、もう少し内向きなベクトルを持ちます。
「外的な物的環境によって心を変化させよう」ではなく「最初に心を変化させよう」とするわけです。すなわち「まずはじめに幸福になることを誓う」*3
とはいえ、彼の『幸福論』は外的な要因を無視するものではありません。
そもそも、外的な入力なしに内的な変化はあり得ないですからね。
そこで彼が最も重要視したのが「食事」と「運動」でした。
明言こそしていませんが、アランは人間の心を物理主義的な目線で捉えているように思えます。
例えば人間の身体は何で作られているかを考えたとき、そこに「食事」と「運動」を挙げない人はいないと思います。そして、心を物理的な目線で捉えると、心と身体にそれほど優位な違いはないと考えることができ、心にとっても「食事」と「運動」が重要であると言えます。
「食事」と「運動」に気を使うことによって心が変化する。
心が変化すれば、人生に対する感じ方が変化する。
その変化がポジティブな方向であれば幸福になる。
なんだか当たり前のことすぎて新鮮味がないですが、彼はこのことを何度も繰り返し表現しています。
ちなみにアランは「笑うこと」も運動の一つだと考えました *4
笑うことで筋肉が収縮し、そのようなストレッチが不機嫌を遠ざける最良の手段の一つだというのです。
彼は不機嫌を遠ざけるのは判断力の仕事ではないと主張します。
判断力というのは、自分で自由に操作できるものではないため、これを無理やりどうにかしようとすると、苦しみが生まれます。私たちが自由にコントロールできるのは筋肉の動きだけであり、その動きから連続して、最終的に判断力や意志が生まれる。やはり、非常に物理主義的な考え方ですね。
また、アランは「悲観主義は気分、楽観主義は意志」と主張します *5
何も意識していないと人は悲観主義に陥ります。「気分」とは受動的な状態であり、「意志」とは能動的な状態です。
そして、能動的な「意志」で以て何をすべきかというと「不機嫌な気持ち」に「無関心」でいることです。
この辺りが少しややこしいですね。
「無関心」とは通常、受動的な印象を受ける概念です。
しかしアランはそう考えません。
人は、気分(受動的な生き方)で生きているとどうしても「不機嫌」に関心を持ってしまうようにできている。だからこそ、能動的に「不機嫌」に対して無関心でいないといけない。
だから、幸福になるための唯一の方法は、その「無関心を実現する意志」を手に入れることなのです。
アランの『幸福論』は外的なマイナスを肯定します。失敗や挫折や後悔や嫉妬や苦痛や恥。これらは人生の本質だという理論がスタートにありますので、決してそういったマイナスの要素を否定することはありません。
そうではなくて、一度それらを全部肯定して、それを楽観的に捉えられる自分を手に入れようと言うのですね。
そしてマイナスの要素を持つ事柄の「二次災害」である不機嫌から解放されようと。
ですから、彼は鬱状態も否定しません。
それどころか、人間は誰しも鬱状態と躁状態を持つと考え、それは天気が移り変わるのと同じぐらい自然なことだと言います。
不機嫌に対して無関心でいることは重要だけど、それができないぐらいの鬱状態に陥ることもあるだろう。そういうときはしょうがないから、しょうがないと思っていれば良い。
ちなみに、アランはラッセルと同様に、仕事も重要だと考えました。
ただ、ラッセルとは仕事に対する感覚が少し違います。
アランは、人生が暇だと不機嫌に関心を持ちやすくなり、余計なことを考えだして不幸になると言います。
だから、人生は忙しいぐらいがちょうど良い。
そして、人生を忙しくする方法のうち、一番妥当なのが、やりがいのある仕事に就くことだとするのですね。
こうやって彼の考えをまとめていると、私自身の幸福論は、彼から大きな影響を受けているなと再認識できます。
冒頭に触れた通り、彼の『幸福論』は体系立ったものではありません。
ここで解説したエッセンスが少しずつ含まれている散文が不連続・ランダムに提示されるような形式を取っています。
ですから、彼の『幸福論』は一気読みするタイプのものではないと感じます。常に本棚に置いておいて、気が向いたときに読みたい章を読みたいだけ読む。そして、その行為は「食事」や「運動」と同じように、不機嫌への能動的な無関心を実現する「意志」の栄養になる気がします。
□注釈と引用
*1 『幸福論|アラン』神谷幹夫訳 47ーアリストテレス
ー「楽しみは能力のしるしである」と彼(アリストテレス)はいうのだ。これはすごいことばだ。このことばは表現さの完璧さのゆえに鳴り響き、学説をよそにしてわれわれの心を捉える。ー
『幸福論|アラン』神谷幹夫訳 92ー幸福にならねばならない
ー幸福になろうと欲しなければ、絶対幸福になれない。これは、何にもまして明白なことだと、僕は思う。したがって、自分の幸福を欲しなければならない。自分の幸福を作り出さなければならない。ー
*2 『幸福論|アラン』神谷幹夫訳 26ーヘラクレス
ー人間に苦境を脱出する力があるとしたら、人間自身の意志の中だけだー
*3 『幸福論|アラン』神谷幹夫訳 93ー誓わねばならない
ー最初はどんなおかしな考えに見えようとも、幸福になることを誓わねばならないー
*4 『幸福論|アラン』神谷幹夫訳 12ーほほ笑みたまえ
ー気分に逆らうのは判断力のなすべき仕事ではない。判断力ではどうにもならない。そうではなく、姿勢を変えて、適当な運動でも与えてみることが必要なのだ。なぜなら、われわれの中で、運動を伝える筋肉だけがわれわれの自由になる唯一の部分であるから。ほほ笑むことや肩をすくめることは、思いわずらっていることを遠ざける常套手段である。ー
*5 『幸福論|アラン』神谷幹夫訳 93ー誓わねばならない
ー悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである。気分に任せて生きている人はみんな、悲しみにとらわれる。(中略)幸福とはすべて、意志と自己克服とによるものである。ー
人は本質的に怠惰である『幸福論|ヒルティ』
カール・ヒルティはスイスの哲学者です。彼は哲学者だけではなく、下院議員、法学者としての顔も持っています。また、敬虔なキリスト教徒としての思想から様々なテーマについての著作を残し、それらの作品は「現代の予言書」とも評されています。
特徴的なのは、彼はテーマとして「愛」「死」「神」といった形のないものを扱っているのにも関わらず、その思想は決して空想的/非現実的に偏らないことです。
その姿勢には明らかにストア哲学が影響しています。
ヒルティの一番の愛読書は聖書で、次いでエピクテトスとマルクス・アウレリウスなどを愛読していたといいます。それもあって彼の思想のベースにはキリスト教とストア哲学が強固に根付いているのです。
その影響で、彼は「享楽」を避けることを重視します。
特に喫煙と飲酒は絶対に避けるべきであると考えていて、生涯を通じてスイスでの禁酒運動に力を入れていました*1
ヒルティの『幸福論』は三大幸福論の中でもとびきり「敬虔」で「実用的」で「ストイック」です。
彼の『幸福論』は他の二作と比べてダントツに長いです。
文庫本ベースで比較すると、ラッセルとアランの『幸福論』が300ページ程度の長さなのに対し、ヒルティの『幸福論』はおおよそ1000ページものボリュームがあります。それだけに、(キリスト教的な色合いが強いということもあり)一番敬遠されがちな『幸福論』であると言えるかもしれません。
しかし、その内容はとても論理的で実用的なものです。
「幸福を得るためにはどうしたら良いのか?」という問題に多様な具体的方法を提示しており、実践という観点で考えると、一番参考になる『幸福論』かもしれません。
そういう意味で、やはりストア派的なんですね。
さて。内容を見ていきましょう。
本書では幸福を手に入れるために必要なこと、そしてその方法論が説かれます。
彼は前提として「人は生まれつき怠惰である」と考えます *2
人間が「無意識に」生きている、いわば通常の状態を、彼は「感覚的に受動的な状態」と表現します。つまり、人間という生き物は、何も考えずに生きていると受動的で怠惰な存在に堕落してしまうと言うのですね。
ですから、重要なのは自分でよく考えることです。
生を具体的に意識して、能動的に人生を送る。
能動的に人生を送ることで、様々な経験が生まれます。
その経験は「働きの喜び」を呼び起こし、その「喜び」が人生を、充実した豊かなものに変化させます *3
ヒルティはこのように、人生を怠惰に過ごすことなく「勤勉に」生きることが、幸福になるための何よりの方法だと考えました。
すごくストア派チックです。
ラッセルの『幸福論』を取り上げた際に「幸福は外的なものではなく内的なものである」というような説明をしました。
ヒルティに関しても同じようなことを論じているのですが、こちらは「なぜ内的なのか」についてラッセルよりも踏み込んで説明を試みています。
まず彼は「自分の力が及ぶ範囲」を明確にします。
世の中を構成するあらゆる要素は「自分で解決できるもの」と「そうでないもの」に二分できます *4
「自分で解決できるもの」にあたるのは「意志の所産の一切」すなわち「判断」や「努力」や「嫌悪」などの内的な要素です。
ストア派の哲学では、そもそもの不幸の原因として「自分の自由にならないことを自分の自由だと思い込むこと」を挙げるわけですが、ヒルティの主張も全く同じです。
例えば「富」などはその最たるものです。
もちろん「努力」によって「富」を得ることは可能です。しかし、そこには一定量の運や偶然の要素が含まれており、それを含めて「富」を「操作可能」なものだと認識すると、途端に「富」の操作不可能性に苛まれてしまいます。
人間は、あらゆる「操作不可能な外的要素」を「操作可能」と思い込み、それが原因で自ら勝手に不幸を作り出しています。
そうではなくて、私たちは操作可能な内的感覚に集中しなくてはなりません。そのためには、何が内的で何が外的なのかを理解しないといけないわけですが、ヒルティの『幸福論』では、それらが詳細に論じられています。
例えば「もの」に対する観念はどうでしょうか。
私たちは何かの「もの」を愛したり、それを失って悲しんだりします。
しかし「もの」は完全なる外的な存在です。「もの」がどうなるかを私たちが完全に操作することはできません。
いくらものを大事にしていても、壊れるときは壊れるし、いくら誰かと愛し合っていても、その関係はいつか終わります。
「外的なものは操作不可能」で「いつか自分の希望通りにならなくなる」
これを真に理解していれば、「もの」を失って悲しむことはなくなるはずだとヒルティは考えます。
まぁ、その境地を目指すのは流石に難しいとしても、外的な事柄は変化を続け、それは操作不能だと思っておくことで、実際にそれがなくなってしまった際に感じる悲しみを軽減できるのは間違いないように思います。
ちなみに、ヒルティは「所有する」という言葉を嫌い、代わりに「借りている」と考えた方が良いと言います *5
これもストア哲学ではよく見られる主張ですね。
自分が「所有している」と思い込んでいる諸々を「一旦預かっているだけだ」と認識することができたら、執着に悩まされることは少なくなるような気がします。
とはいえ、そのように達観するのは難しい。
そもそも、ヒルティが主張する『幸福論』は特段目新しいものではなく、なんなら多くの人が「そりゃそうだよ」と知っていることです。
でも、そうは思っていてもそれができないから困ってるわけです。
ヒルティはそれに対して「だからこそ」と言います。
だからこそ、日常において不機嫌や不幸がやってきたとき、それを「心の平穏を買うための訓練」であると認識する必要がある。
もし仮にお金を盗まれたのなら、それは自身の心を平静にするための貴重な訓練をお金を出して買ったと思いなさい。こう言うのですね。
ここまで来ると、どこか宗教色が強いような気もしますが、個人的にはこの考え方はとても実用的だと思います。
そもそも『幸福論』の多くは「不幸という内的感覚」とどう折り合いをつけるかを論じているわけです。
それは暗に「不幸という感覚は必ずやってくる」ことを表しており、だからこそ、その感覚をどう処理するかが幸福になるための重要な要素として挙げられているのです。
そういう意味で「不幸を感じたら訓練と思ってしまえ」という考え方は、直接的で実用的な対策なのではないでしょうか。
プラトンはイデア界という真実の世界を想定し、魂はイデア界を通して何度も転生すると考えました。
そして身体は魂の入れ物に過ぎず、魂が体に入っている状態、つまり個体の人生というものは魂の徳を高めるための修行の場だと言いました。
その思想は紆余曲折を経てストア哲学に吸収され
古代ローマの根幹を支えることになります。
ヒルティは、そのストア哲学とプロテスタント的なキリスト教をうまく融合して言語化した哲学者だと考えることもできそうです。
ヒルティの幸福論は三部立てになっていて、語弊を恐れずに分類するならば、一部がストア派的な内容、二部と三部がキリスト教的な内容を扱っています。そういう意味で、まずは第一部だけでも読んでみることをおすすめします。個人的には、ヒルティの『幸福論』の本質は二部と三部にあると認識しているのですが、一部だけでも、さまざまなことが学べると思います。
彼の『幸福論』には「真面目であれ」「よく働け」「節制しろ」「信仰しろ」というようなストイックな主張が多く見られるので、読んでいて耳が(目が?)痛くなる人も多いと思います。
つまり、多くの人にとって、彼の主張する生き方は「今の自分とは距離が離れているもの」なのですね。
逆に考えると、そこには実践の余地が大量に眠っているわけです。
全部は無理にしても、一部だけでも参考にして、それを「実践」してみることには、大きな意味があると感じます。
以上です。
三回に渡り三大幸福論を取り上げさせていただきました。それぞれの『幸福論』にはそれぞれの特徴があるため、人によって好みが分かれることでしょう。
とはいえ、どれが正解でどれが間違っているというものではありません。
少なくとも100年以上読み継がれている古典ですから、それぞれの『幸福論』には、何かしらの有用なヒントが隠されているはずです。
もしご興味があれば、まずはご自身に合っていそうな『幸福論』から試していただき、よければ三大幸福論を全て味わって欲しいなと思います。
ちなみに私個人としては、もともとストア派の思想が好きなこともあって、ヒルティの『幸福論』がロジックとしてはしっくりきます。読みやすいのはラッセルで、何度も読みたいのはアランという感じでしょうか。
いずれにしても全部好きです。
「どの幸福論が好き」「この幸福論には反論がある」など、コメントをいただけるとすごく嬉しいです。
□注釈と引用
*1 とはいえ、彼自身が禁酒生活に成功するまでには一定の期間を要したと残っています。
*2 『ヒルティ|幸福論』草間平作・大和邦太郎訳 第一部P22
ー仕事ができるのを妨げるのは、主として怠惰である。ひとは誰でも生まれつき怠惰なものだ。感覚的に受動的な通常の状態からぬけ出すためには、常に努力を必要とする。ー
*3 『ヒルティ|幸福論』草間平作・大和邦太郎訳 第一部P22
ー働きのよろこびは、自分でよく考え、実際に経験することからしか生まれない。それは教訓からも、また、残念ながら、毎日証明されるように、実例からも、決して生まれはしない。ー
*4 『ヒルティ|幸福論』草間平作・大和邦太郎訳 第一部P43
ー世には我々の力が及ぶものと、及ばないものとがある。我々の力の及ぶものは、判断、努力、嫌悪など、一言で言えば、我々の意思の所産の一切である。我々の力の及ばないものは、我々の肉体、財産、名誉、官職など、我々のせいでない一切のものである。我々の力の及ぶものは、その性質上、自由であり、禁止されることもなく、妨害されることもない。が、我々の力の及ばないものは、無力で、隷属的で、妨害されやすく、他人の力の中にあるものである。
*5 『ヒルティ|幸福論』草間平作・大和邦太郎訳 P54
ー何事につけても、「自分はそれを失った」と言ってはならぬ。「自分はそれを返した。」というべきである。君の息子が死んだなら、それは返したのである。君の財産が奪われたなら、これもまた返したのである。それを奪ったのは、確かに悪人である。しかし、送り主が誰の手を通してそれを取り戻そうとも、君に何の関わりがあろうか。彼がそれを君に委ねる間は、それを他人のものとして所有するが良い、一夜泊まりの旅人が宿谷をそうするように。
□参考文献
幸福論(ラッセル) (岩波文庫)
https://amzn.to/46M4UpZ
幸福論(アラン) (岩波文庫)
https://amzn.to/45l6gXX
幸福論 1 (岩波文庫 青 638-3)ヒルティ
https://amzn.to/3LWP4Rt
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
