
【Facebookアーカイブ③ 異分野学習 情報爆発など】
<異分野学習の楽しさ>
いろんな課題を見つけ 様々な人にヒアリングを休みの日に続けているうちに気づいたことがありました。
課題はある程度皆さん気づいていますが、様々な理由を言われました
しかし、理由としては
「面倒」
「やり方わかんない」
「儲かるの?」
「僕一人でしても変わらない」
「自分が苦労して作った手術室をなんで他人に貸さなきゃいけない?」
「患者さんにはわからない」
「他院との競争なので協業してどうすんの?」
などのコメントが得られました。
先日の記事で、アメリカ時代は なにか課題があって話題にすると「じゃあ、LEGAL的には、、、、FINANCE的には、、、、HR(人事)的には、、、、」などとみんな寄ってたかって 感情論ではなく具体的な数字などをあげて TO GO、OR NOT TO GOかを理論的に理解できました。
しかし、上記を見てもわかりますが 感情語で伝えられることが多く 議論になりにくいことがありました。 医療ではバッチリ 数字や理屈を患者さんに説明している 立派な先生方がです。
そして、対する私も実際に理論でお応えすることができず無力さを痛感しました。
外科手術でもまぐれで上手にできたとしても、やはり再現性を持って手術できなければ意味がありません。 そのためにはそれぞれの手技の意味付けとテクニック(理論と実践)を積み重ねる必要があります。
「習うより慣れろ」とも言われ、トラブルのないものであれば ビデオの見よう見まねで手術できるかもしれませんが、 トラブルになったときは 一度立ち止まって これまで学習や経験で蓄積された基礎的なストックの中から答えを導きだしながら手術を行っていく必要があります
今後、なにかPROJECTを行う際にもこのままでは 理論武装やチーム形成ができないと思い、「急がば廻れ」戦略を取ろうと考えました。 つまり世の中の仕組みやプロジェクトを推進するのに最低限必要な教科書的な体系やお作法を身につけたいと思い、夜間に勤務時間後に通えるビジネス系の大学院を見学に行き2年間の進学を決心しました。
これがまた楽しいんですね。 知らないことを知る喜び。別に企業で働くわけではないので本当に目の前に喫緊の課題を突きつけられているわけではないので 趣味で勉強して 目の前の雲が晴れるように理解ができる喜びは 高校時代以来くらい(笑)。

<大学院で学んだこと 医師に期待すること>
ビジネス系の大学院で学んだこと
・医師のブランド力はまだあるようだが、それは消費されているだけかも。
・ビジネスマンとの経験格差に愕然。
・高校時代は理系だと思ってましたが、今やそうではない仕事。逆に、文系だと思っていたビジネスに数学的要素が多くビジネスマンは駆使している
・すべてが新鮮ということは世間知らずだったことを痛感。
など個人的に辛い経験もありましたが
・やはり、医療のインサイトやリタラシーについてはまだまだ医師であることにまだまだ利があるなーと感じます
このように、先日の記事でも書かせていただきましたが、楽しくEYE OPENINGな経験を2年間の大学院時代にさせてもらいました。
クリニックの運営にも非常に役立っており、大学院に行かなくてもエッセンスをすこし学習するだけで医療業界が変わるのではと感じました。
患者さんを救うために当然全力投球が必要ですが、それは個人ではなくチームプレーです。マネージメント力の必要性が増していく中で 大学入学以降殆どの医師や医療従事者はマネージメントをせずに生きてきました。
一般企業ではマネージメント経験を少しずつ積み重ねていきます。大病院では事務やマネージメント部の方がいらっしゃいますので 医師にマネージメントの必要は少ないです。
しかし、開業などを行うといきなり社長みたいなものです。クリニック院長以外も、教授や部長になるような先生にもマネージメントを学んでもらう必要性感じました。少しでいいんです!
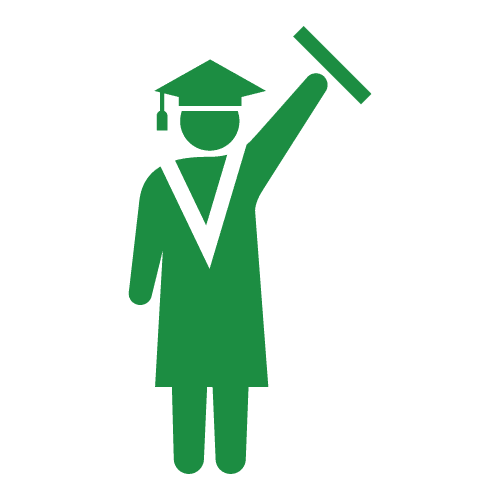
<ONAKAMA(お仲間&同じ釜>
医学部・研修医時代には、大事な思い出がたくさんあります。(看護師さんや薬剤師さんなどの医療従事者のみなさんもそうであると思いますが、個人的な経験として医師をあげさせていただきました。)その中で、一本の背骨になっているのは「他者のQOLを預かる医療従事者としての基本を形成する緊張感」ではないでしょうか。このような時代を共に乗り越えてきた仲間たちとは、思い出ばかりではなく、この背骨を共有しています。医療従事者にとって、こうした「同じ釜の飯を食べた仲間(ONAKAMA)」は、かえがたい、大切な宝物でしょう。
そんな仲間たちはいま、多様な人生をおくっています。患者さんを預かる身として、責任感に押しつぶされそうになりながら、日々必死で働いています。同時に、卒後年数が経過して「同じ釜の飯をたべる 仲間(ONAKAMA)」のような存在が得難くなってはいないでしょうか。同時に、時代の変化を受けて、そうした仲間の存在が、ますます大事になってきていると感じます。
仲間が得難くなっている背景には、専門性に分化し、他分野の医師やコメディカルとの交流が減ってきているのもその理由の一つです。同時に、卒業して、仕事や人生の価値も多様になった医療従事者同士が、同じ「志」を共有する機会が減ってきていることは無視できません。
いまこそ、医療従事者としての存在価値を共有し、あらたな「同じ釜の飯を食べた仲間(ONAKAMA)」を増やしたいと考えています。以下、この課題を解決する意義と、具体的な方法についてFACEBOOKで背景がわかるように述べて参ります。この考えに賛同いただける医療従事者のみなさまとともに、我々は、この解決策を社会に実装していきたいと思います。NYAUW!

<情報爆発と医学リタラシー①>
‘STANDING ON THE SHOULDERS OF GIANTS(巨人の肩の上に立つ)’
これは、GOOGLE SCHOLARの検索窓の下にある表記です。この言葉は「先人たちが積みあげてきた知見の上に、あたらしい知見を積み上げる」という意味を持ちます。いうまでもなく、医学は多くの患者・医師・研究者などの貢献と犠牲の上に成立しています。医療従事者は、この言葉の重みを十分実感していると実感していると、私は思います。
とくに現代は、ICT 「Information and Communication Technology(情報通信技術)」 の発展によって、科学技術の積み上げ速度が上がっています。俗にいう情報爆発です。これ自体には、当然、良い面もあります。たとえば、これまで対応不可であった疾患が、治癒可能になるまでの期間も、かつてないほどに短縮されてきています。あたらしい治療法を前にして「もっと早くこの医療技術が完成していれば」と嘆いた経験は、どの医師にもあるでしょう。その意味では、こうした情報爆発は大歓迎です。

<情報爆発と医学リタラシー②>
しかし同時に、情報爆発によって非常に困ったことが起きてもいます。医学情報の総体が倍増するのにかかる時間は、1950年には50年かかっていました。これが2020年には73日(0.2年)になるそうです。現役の医師が、自分の専門分野をUPDATEし続けるためには、論文を週に160時間読む必要もあるそうです。1週間=24X7=168時間ですから、160時間をUPDATEするだけにつかってそれ以外、寝る時間なども含めて1週間に8時間しか残らないことになります。これは事実上不可能ということです。知識の陳腐化が非常に早いことを示唆します。
先日の投稿でも書かせていただきましたが、専門的な情報というのは、その情報だけではあまり役に立たないものです。とくに、生体をあつかう医学に関する情報(医学情報)の場合、それがいかに優れた情報であったとしても、その情報だけで現場の医療が改善することはまれです。このあたりは、医療現場の実情に触れることのない一般の方々には、なかなか理解されないところではないでしょうか。
(参考文献 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116346/.)
(参考リンク: https://www.forbes.com/sites/steveandriole/2015/04/07/doctor-d-will-see-you-now/#578cc062a2f2)

<情報爆発と医学リタラシー③>
医学情報は、そもそも個体差や研究デザインの違いなどによって「ゆらぎ」が大きいものです。たとえば、特定の患者には大変有効な薬が、同じ疾患をもった別の患者の毒になるというケースは多数あります。「この疾患にはこの薬が有効だ」という情報だけでは、現場の医療は変わらないのです。
そこで重要になるのが、入手した医学情報の文脈を読み取り、臨床実地での経験と照合しながら、その情報の意味をとらえるという医学リタラシーです。医学情報というのは、こうした医学INDISERとしての医学リタラシーを踏まえて、はじめて意味を持つものです。医療従事者は、プロフェッショナルとして日々こうした医学リタラシーを鍛えてきたわけです。
従って、自分が対応できない、自分の専門外になる疾患に出会った場合、自分とは異なる専門性を持った(異なる医学リタラシーを持った)医師に、リスペクトを払って、患者を紹介するという行動に出るわけです。それはなにも恥ずかしいことではなく、そうして紹介できる仲間がいることを、むしろ誇りに思うものではないでしょうか。
例えば 外科の先生は内科の先生がいるので外科に専念できるのです
自身は自立しているつもりでも それは他の先生が他分野をカバーしてくれているから 専門にダイブできるのです NYAUW!
よろしければサポートお願いします。 NYAUWの活動は現在マネタイズを考えずに意義のみを追求するフェーズです。 ニッチな分野のやせ我慢プロジェクトですので お気持ちだけでも嬉しいです。
