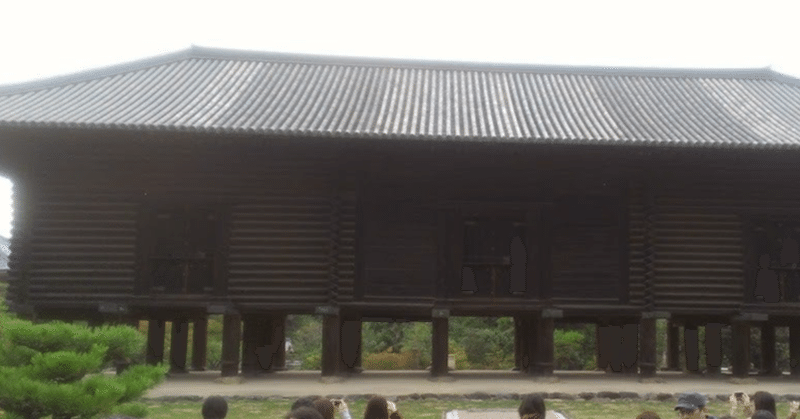
【SS・オチなし話】雑です、大坂さん7 ~蘭奢待(らんじゃたい)~(2281文字)
「なぁなぁ、東くん」
不意にー。隣の席の大阪さんが僕に話しかけてきた。
「東くんは、織田信長と豊臣秀吉と徳川家康のうち、誰が一番好き?」
「いきなりな質問だなぁ」
大坂さんはTPOをわきまえずに話しかけてくる時が多々ある。というか、彼女がTPOをわきまえた発言をした記憶がほとんどないような気がする。
「ふと気になって。安定志向の東くんは徳川家康かなぁと」
「まぁ・・・そうだね。徳川家康が一番好きかなぁ。他のふたりよりアクは強くなさそうだし。結局最後に天下をとったわけだし」
僕は素直に返事をする。
「うわぁ。ほんとに面白味がないね、東くんは」
質問に答えただけなのに、このひどい言われ様である。
「悪かったね。でも三人の中じゃ、一番、人が良さそうだろ。信長なんて比叡山を焼き討ちしたり、蘭奢待(らんじゃたい)を切り取ったりとか、なんでも力ずくでしてるじゃないか」
「蘭奢待(らんじゃたい)?」
大坂さんは、ちょっと驚いたように目を大きく見開いた。
「知らないの?正倉院にある香木だよ」
大坂さんが知らない筈はないのだけれども、そう思いながらも僕は言った。
蘭奢待(らんじゃたい)は、東大寺の正倉院に保存されている全長1.5mにもおよぶ日本最大の香木だ。
いつから正倉院にあるのかはわからない。
推古天皇の時代に中国から献上されたという説もあり、また空海が中国から持ち帰ったと言う説もあり、とにかくその伝来の経緯は謎につつまれているらしい。
室町幕府の将軍、足利義満・義教・義政などの時の権力者たちが、蘭奢待の一部を切り取っており、時の天皇である正親町天皇に、信長が強引に申し入れ、実に110年ぶりに蘭奢待を切り取ったのは、天正2年(1574年)のことだった。
「知ってるよ、蘭奢待くらいは。それに、家康が蘭奢待を切り取らなかったのは、切り取ると不幸が起きると言い伝えにビビっただけやし。そういうビビりなところ、東くんと似てる」
大阪さんが失礼なことを言うと、ふと何かを思い出したような顔をするや、急にノートになにやら字を書いて、僕に見せた。
「ほら、東くん、見て見て」
ノートには、『東 大 寺』と書かれていたが、大きさがマチマチで、決して綺麗な字ではなかった。
「大坂さん、もっと字を綺麗に書く練習をしたほうがいいよ」
「やかましわ。ここからが肝腎なんやから、余計なこと言わんと黙っとき。この『東大寺』の文字に、さらに書き加えると・・・」
大坂さんは、手に持ったペンを走らせて、『東大寺』の文字に書き加えていく。
「ほら、蘭奢待やよ」
そこには、『蘭 奢 待』の文字があった。
『あ・・・、蘭奢待(らんじゃたい)の中には、東大寺の文字が入っていたんだ・・・」
僕が言うのを見て、大阪さんは満足そうに目を細める。
「うんうん。その反応を期待してたんや。関西の人は知ってる人が多いから言っても、そんなん知ってるわって言われるけど、東くんはやっぱり知らんかったんやね。いいなぁ、その新鮮なリアクション」
「へぇ、偶然にしては出来過ぎているね」
僕はちょっと驚いた。
だから、気づかなかったのだ。
僕と大阪さんの背後で不穏な気配を漂わせ、怒りに身を震わせて立っている人がいることをー。
* * *
放課後。
「はぁ・・・。やっと書き終わった・・・」
僕は図書室の自習用机で、反省文をなんとか書き上げた。
授業中にもかかわらず、私語の会話をしていた僕と大坂さんは、先生にしこたま叱られた上に、二人して廊下に立たされ、さらには反省文を提出するように言われたのだ。
「大坂さんは出来たかい?」
「んなもん、出来るわけないやん」
大坂さんは、怒っているような泣いているような、どちらともとれるような声で返事する。
どうせ反省文を書いても心から反省はしないだろうと、先生に見透かされた大坂さんは反省文の代わりに、『蘭奢待(らんじゃたい)』の文字を400字詰め原稿用紙10枚分、びっしり書くように言いつけられたのだ。
「もう、一生分の蘭奢待(らんじゃたい)の字を書いた気がする・・・。右腕の筋肉がつりそうや・・・。東くん、わたし、あなたに、一生のお願いがあるの・・・」
大阪さんは潤んだ瞳で、訴えかけるように僕を見た。
「手伝わないよ。筆跡が違うからすぐにバレちゃうだろ」
「チッ。ほんまに頼りがいが無いやっちゃなぁ」
大坂さんは、また大きくため息をついて原稿用紙に向おうとして、ふと思いついたように言った。
「蘭奢待の字を書いて、右腕の筋肉がつりそうになる・・・つまり、これが本当の筋肉蘭奢待・・・」
「いや、全然似てないし、脈絡ないし、ついでに全然面白くないし。なにがこれが本当の、だよ。とりあえず大槻ケンヂさんに謝れ」
大坂さんは僕の言葉を無視し、自分で言って自分でツボに入ったのか、クックッと笑いをかみ殺している。
「バカなこといってないでさっさと書く。でないと僕ら、帰れないだろ」
「はい、はい。書きますよ、書けばええんでしょ、書けば」
全く反省している様子もなく、仕方なく原稿用紙に向かう大坂さん。
やれやれー。僕は肩をすくめると、図書室の窓ガラス越しに、校庭の隅にある満開の桜の木を見た。すっかり春である。
今度の日曜日、天気がよければ東大寺に行かない?と言ったら、大坂さんはどんな返事をするだろうか、と思った。
きっと、『なにからなにまでひっくるめて全部、東くんのおごりやったら、ガイドしてあげてもええよ、まかしとき』と言うに違いない。
そう。彼女は、反省とロマンチックから、もっとも遠いところにいる存在なのだ。
【終わり】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
