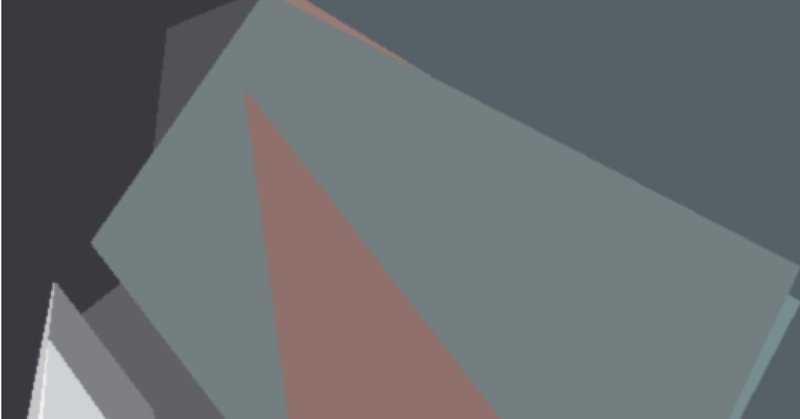
23. サーカスの夜
母が捻挫してしまったので、今年は急遽、僕がサーカスへ行くことになった。
練習する時間はないが、まあ、何とかなるだろう。それなりに切り抜けられるはずだ。なんといっても、サーカスなんて空想力がすべてなのだから。
僕はリュックサックに紙やハサミや、必要そうなものを詰め込んだ。ついでに週末用に買ってあったポップコーンを作り、隙間に押し込む。サーカスと言えばポップコーンは外せない。何に使うという具体案があるわけではないけれど、念のために持っていく。
サーカスへは二年前、一度母について行ったことがある。
今回は本当に急だったので、母から直通のチケットを受け取る時間がない。だが手順さえちゃんと踏めば、きちんと到着できるはずだ。多少面倒くさいし、時間がかかってしまうけれど。
まずは地下鉄に乗り、旧市街の駅を目指す。
それから、駅を出て、近接線のホームへ行き、そこの階段から地下に戻る。再び地下鉄に乗って、次は下へ行く。三つ目の駅で乗り換えて、北へ向かうホームから、赤い駅まで直通電車を使う。各駅停車でもいいのだが、そうすると銀の駅で右のエスカレーターを降りなければならないので、少し手間がかかるのだ。
赤の駅に着いたら、あとは単純だ。
エレベーターで七階まで上がって、非常階段横のエスカレーターで二階降りる。北口のドアで切符を変えてもらい、土産物が並んでいるキオスコの前を振り返らずにまっすぐ行けば、サーカスへたどり着くことができる。
やっとたどり着いたサーカスは、駅前の大きな広場の中に、今年も堂々とそこに立っていた。天を突く天幕がなんとも誇らしげだ。曇りのない赤と白のテントがまぶしい。
開演前だというのに、広場では多くの人が待っている。
それを目当てにした食べ物売りや、気の早いお土産売りのピエロがいたりして、なかなかの賑わいだ。僕はその光景に、少し胸が躍るのを感じる。しかし時間がないので、早々に裏口へと回った。
クリスマスサーカスは毎年、一度だけ開かれる。
観客は特別なチケットがないと、入ることができない。逆に言えば、チケットさえあれば子ども一人でも入れるし、本来なら資格のない者でも、訪れることができる。
母がこの公演に参加するようになって、今年で三年目になる。
僕はサーカスで借りた燕尾服に着替えながら、そのことについて考えそうになったが、首を振って、頭からそれを追い出した。思い出にふけるのは今じゃなくていい。とりあえず、ショーを終わらせなければ。
僕たちのような特別な出演者のためにいくつも並べてある仮面の中から、大きなくちばしのついた鳥のものを選んだ。僕は鳥が好きなのだ。陳腐だけれど、自由そうなところに憧れる。そして、できるだけたくさん、ポケットに折り紙を詰め込んだ。
前の演目は、ネズミの王による、地上曲芸だった。
ネズミたちが複雑に組み合わさって、エッフェル塔や自由の女神になるのは壮観で、観客の子ども達だけではなく、僕も思わず拍手をした。
ネズミの王は幕間の僕に気が付いて、赤い目でお茶目にウインクしてくれる。そういうことに慣れていないので、僕は赤面したかもしれない。ちょっと伏目になりながらも、目を離すことなく、ネズミがキリンになり、マーモットになり、ネコになるのを眺めた。
やがて、僕の出番となる。
人前に出る瞬間は、さすがに緊張を隠せない。フラミンゴの少女が並べてくれた机の前に立つと、足が震えて仕方がなかった。このサーカスはとても大きいのに客との位置がとても近いので、余計に動きが固くなってしまう。
僕は胸に入れていた絹のレースハンカチを取り出すと、二回息を吹きかけて、机の上へ大げさに広げて見せた。机上に落ちる前、ハンカチが腕を広げくるりと一回転して見せたので、観客から小さくため息が漏れる。
上ずった声で、つっかえながら口上を並べた。まず僕は黄色の折り紙を取り出すと、折りたたんで鳥の形に切り抜く。広げるとそれは、永遠に続くカナリアの行列となって、天幕の中を飛び始めた。
カナリアの合唱を聞く間に、緑の紙で、今度はカエルをたくさん切り抜いた。コツはたくさん重ねて切ることだ。緑と、そして反対側の白のカエルたちは、二足で立ち上がると、ぴょこぴょこと愛嬌のある足並みで、机の周りに紙を並べる。それらに箱を折ってもらい、僕は金と銀の紙で鶴を折る(実をいうと、それしか折り紙は知らないのだ)。
切り抜かれた方のカエルたちが、地面でラインダンスを踊り始めた瞬間に、タイミングよく鶴を放す。彗星のように空中に光を残し、鶴は観客の頭上を巡る。歓声が上がり、僕はやっと緊張から解放された。
最後にポップコーンを空中に撒く。鶴とカナリアがそれをくわえ、そこからもれて落下したものはカエルたちが捧げ持った箱でキャッチした。それは観客たちへの振る舞いとなり、それで僕の演目は終わりだ。
僕はせいぜい優雅に見えるようにお辞儀をし、万来の拍手を背に、その場を去る。
切り紙達はいくつかは観客の元に残り、最後までショーを見ていくらしかった。金の鶴が、真ん中らへんの席に座った小さな女の子の、手に乗っているのが舞台から見えた。
団長に挨拶し、衣装を返還して帰路につく。
せっかくだから見て言ったらどうだ、と勧められたけれど断った。
クリスマスサーカスは確かに面白い。きっとどの見世物も楽しいだろう。だが、終わったあとの悲しさを知っている僕は、このまま帰らなければならない。
帰りの地下鉄に乗りながら、姉のことを考えた。
七歳年上の姉はろくでなしで、若くて浅はかな子どもが思いつく悪事を一通り、さんざんやらかした後、家を出て行ってしまった。それが三年と少し前のことだ。多分どこかで死んでいると思う。それはドラッグのオーバードーズによるかもしれないし、恋人からの暴力によるものかもしれない。
少しでも娘の罪滅ぼしになるようにと、母は毎年、クリスマスサーカスで興行をする。僕はそれについて、特に意見を持たない。母がそうしたいのなら、そうすればいい。というか、あまり多くを考えないように努めている。
それは特別な子ども達のための、特別なサーカスだ。
誰もが行けるわけではない。でも訪れることができたなら、空想が具現化したような、美しく甘やかで、そして終わりは少し悲しいショーを見ることができる。
それ以上は、考えても詮無きこと、だ。
読んでくださってありがとうございました。少しでも楽しんで頂けたらうれしいです。
