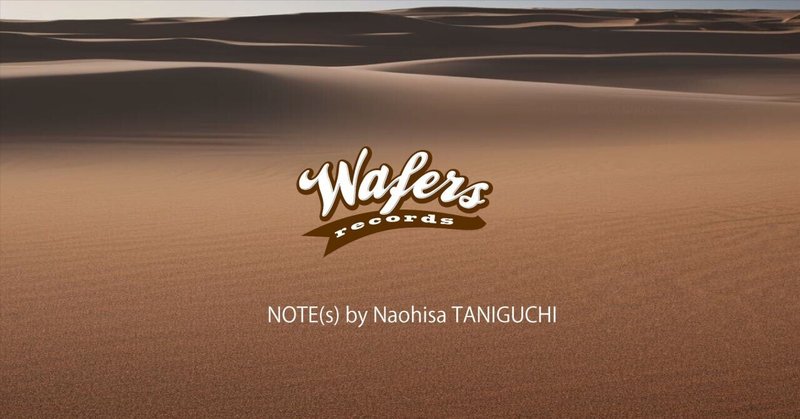
過去のレコ評(2020-1)
(2020年「SOUND DESIGNER」誌に寄稿)
「to the MOON e.p.」Yogee New Waves
一聴して、こういう音のバンドだったっけ?と不思議に思い、過去の音も聴いてみた。明らかにこれまでと違う。音の画面が大きくなっている。高い周波数の成分も増えている。以前はもっと中域に寄っていたのだが、明らかに今の時代の「良い」音になっていて、それでも彼ら特有のノスタルジックさをキープしている。画面が大きい分、ギターやドラムスを左右に広げて、それぞれの余韻を楽しむことが出来る。声のエフェクト成分だけを右に振ったり、オクターブで重ねたコーラスを左に振ったり、という遊びも可能だ。考えてみたら、ステレオレコーディングが珍しかった60年代の始めには、よくあった手法ではある。が、当時とは違ってリバーブのハイ成分の使い方が違う。解像度が増している分、細やかな手触りを楽しめるのだ。と思って聴いていたら、4曲目はモノラルミックスだ。大胆さが良い。個人的にはどうしてもフィッシュマンズの音像と比較してしまうが、ダブ要素は無いのに同じ世界観に向かっているのが興味深い。リバーブの選び方だろうか。とにかく気持ちの良い一枚。
「CROSS」LUNA SEA
まず最初に思ったのは、ボーカルの音量が小さいこと。バンドとしてのアイコンであり、文字通り「顔」である河村隆一の顔が小さい音像なのだ。だがそれにもすぐ慣れてくる。音量が小さくても主張してくる歌い方と声質を持ち合わせているからだ。それはもともと持っていた個性であるとともに、ライブで培われた部分でもあるのだろう。アタックは強く、こするような声質で耳を奪う。音程は決してフラットすることなく、シャープ方向に揺れるビブラートで浮き上がってくる。とにかくドラムの音量が大きく、ギター類は左右にパックリと広がっている。これはライブでの臨場感を思わせる。そして彼らがライブバンドであることの証であると言えるだろう。それは曲の長さにも言えることである。5分以上の曲が多い。グルーブを体に馴染ませるためにはある程度の時間が必要であるということだ。飛び道具に頼ることなく、楽曲そのもので11曲を聴かせる。そんな中で11拍子という複雑なイントロで始まる10曲目は異彩を放ち、音楽的な余裕を見せつける。
「0」Superfly
タイアップの多い楽曲群を支えるのは、彼女の歌詞。プロフェッショナルだ。少し前までは、タイアップ曲だからと言って、内容に寄り添いすぎるのはNGだった。コンテンツと歌の内容に少しの距離があり、響き合うことが重要だった。しかし昨今は、映像が歌詞に引っ張られ、リンクすることを楽しむようになっている。だから、ドラマなら台本を読み込み、漫画原作のアニメなら原作を読み込み、CMならプレゼン資料や絵コンテを読み込む必要がある。それは楽曲を縛るものであって、ラクではない。しかしそれでも、こうしてアルバムとして並べた時に、作品性を捻じ曲げたとは思わせないところに彼女の凄さがある。そしてそれを支える編曲家は島田昌典 ・UTA・蔦谷好位置などのベテラン揃いであるが、タイアップのない2曲にはトオミヨウと八橋義幸の名前がある。そしてこの2曲にSuperflyとしてのアイデンティティがあるように感じる。何かに合わせるのではなく、ギターロックバンドとしてスタートした立ち位置。それが素直に出ている。歌詞カードを見ればそれが分かる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
