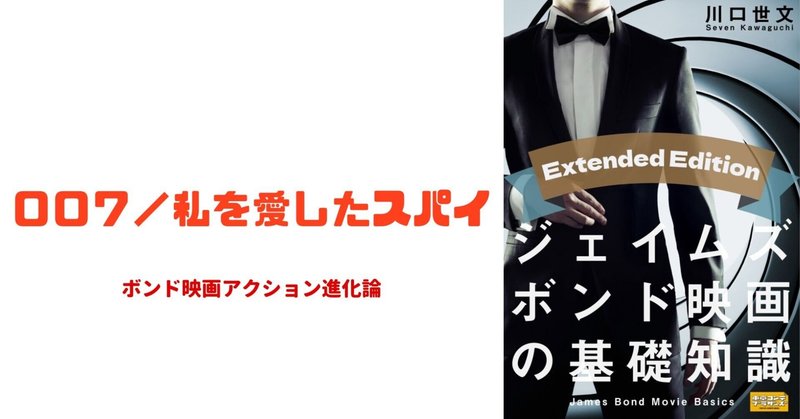
ジェイムズ・ボンド映画アクション進化論10『007/私を愛したスパイ』
Amazon Kindle電子書籍『ジェイムズ・ボンド映画の基礎知識 増補改訂新版』から、最新の「増補部分」を毎週1作、全25作分、公開していきます。
☝ すべてを先に読みたい方は、こちらから。Kindle Unlimited対応です。
第10作『007/私を愛したスパイ』

前作と『私を愛したスパイ』の間の3年間はシリーズ最初の危機だった。その結果、共同プロデューサーのサルツマンが去り、ブロッコリ一人で「提供」することになる。彼はシリーズの総力戦を挑み、そして勝利した。
ムーア=ボンドの3作目は、ガイ・ハミルトンからルイス・ギルバートに監督が交代した結果、『007は二度死ぬ』を骨格に据えることになった。
『二度死ぬ』といえば最初に「高さ」のあるアクションをはじめた作品だ。プレタイトルで初めてムーア=ボンドが登場するこの作品では、それを桁違いのスケールに拡大させた。
久しぶりのスキーシーンは前半こそ『女王陛下の007』の縮小版だが、明らかに後半が違う。設定はアルプスだが、実際の撮影はカナダのバフィン島で行われ、何台も用意したカメラのなかで奇跡的に一台だけがこの大ジャンプを撮影していた。それはシリーズ最初の15年を締めくくり、のちの45年を決定づけた「飛翔」といってよかった。

ムーアの最初の2作では「徒手空拳」の闘いとアクションシーンでの「観客」の存在を特徴に挙げたが、いよいよここでは秘密兵器が解禁される。なかでも特筆すべきはロータス・エスプリだ。公開前に完璧にネタバレしていたが、Qを現地出張させておきながら、その「説明」を観客には聞かせない演出がとられて、ギリギリまで何が飛び出すか「切り札」が伏せられていたのが面白い。

ロータス・エスプリを使ったカーアクションはたっぷり15分ある。演技の“構成点”は満点に近い。砲弾のように発射されるサイドカーや、ジョーズの乗った車、ナオミが操縦するヘリを撃退し、いざ「海中」へ。同乗していたアニヤ・アマソワ少佐のこのときの驚いた顔こそ「映画の観客」自身の表情であり、ムーア=ボンドのアクションシーンに必ず「劇中の観客」が用意されてきた意味がここではっきりした。

それならば前回のペッパー保安官だってそうだということになるが、決定的に違うのはアニヤがソ連の情報部員であることで、このシーンでは同時に二人のマウントの取り合いが起きている。その証拠にアニヤはソ連側が二年前にこの車の設計図を盗んでおり、詳しく知っていたと話す。二人の緊張関係はアクションの間も途切れないのである。

ロータス・エスプリはいわばムーア版のアストン・マーチンで、当然DB5へのオマージュだが、『007は二度死ぬ』のリトル・ネリーの要素も兼ねている。そもそもこれは「ウェット・ネリー」とも呼ばれている。そして、一歩外に出たら死んでしまう状況的スリルをはらんでいて、DB5ほど「無双」ではない点でも「ネリー」なのだ。

プレタイトルのパラシュートのデザイン(ユニオン・ジャック)は『ゴールドフィンガー』の白いタキシードに相当するビジュアルインパクトだったし、海中でロータスがウィンカーを点滅させたり、ワイパーを動かしたりする「視覚的ユーモア」も徹底されて、ムーアと秘密兵器の相性は抜群によかったといえる。そういう意味で前二作の方針はまったくの誤りだった。

そして、殺し屋ジョーズの存在。オッドジョブ的な怪人でありながら、グラントばりに列車内での格闘シーンもある。まるで過去に登場したすべての殺し屋を合体させたような存在なのだ。ラストは彼自身の必殺武器をボンドに逆利用されるが、それでも死なない。ついに最後まで生き残って次作では「ジョーズ劇場」を演じることになるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
