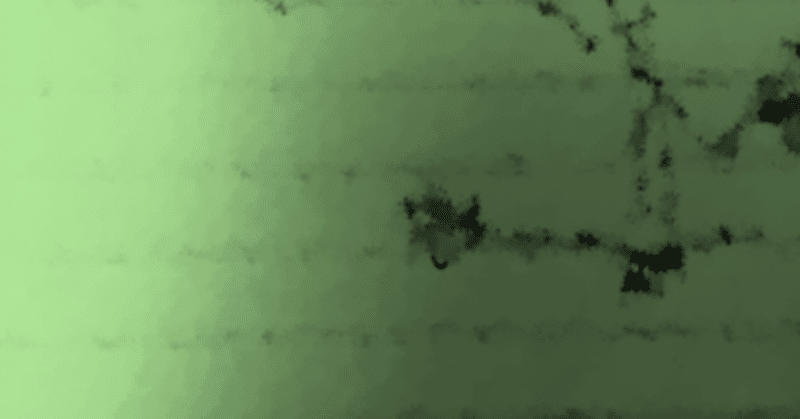
ガブリエル・夏 30 「山田くん」
ショルツ似の運転手が、まみもの質問に、親切に英語を絞り出しながら答えている。
「3時、4時、5時、6時、7時。……はいはい、8時、9時……。」
まみもはまだ、ありがとう、ハブアナイスデイとバスを降りない。
「はい、でも、本当に今日もその時間に出ますか?」
「はいはい。さっきも言ったでしょう。3時、4時、5時、……。……の……にも書いてあるし、あの〜、……の、……で見るやつ、……にも出てるから。全部。ぜーんぶ。」
運転手は、まみもの携帯を指差して、タップしたり、スクロールしたりするジェスチャーをする。めんどくさいと感じ始めた雰囲気。詳細情報はみんなウェブサイトに出てるからそれを見なさいってことか。
「まみもちゃん、行ーくーよー。」
とっくにバスを降りて、最後部に座っていたカップルらと同じ方向に進んでいるレイが言ってる。多分1回目ではない。
これ以上粘っても、運転手から新しい情報を得て安心することはできなさそうなので、まみもは諦めて、運転手に挨拶してバスを降りた。
「ガブくん、ちょっと待ってね。帰りのバス停見つけてから行きたい。時刻表も見たいから。」
「まみもちゃん、場所も時間もさっきのサイトに載ってるよ。早く行こうよー。」
「だってさ、この人たち、いや、今なんとかの祭日だからとか、閑散期だからとか、ストライキしますからとか、ピーターの家でお葬式があるからとかさ、いろんな理由で書いてる通りに運行しないじゃん。バス停めるところも、急にうんと向こうの方に停めたりさ。あ〜大丈夫、あ〜ノープロブレムって言うけど、よくプロブレムあるじゃん? 今日どうしても絶対21時35分にグフスタインのナイトジェット に乗りたいのに。」
「わかった。」
レイは、まみものところまで戻ってきて、ぐるっと周りを見回す。
「あった。こっち。」
レイが1/3周ぐらいで見つけたところに、細長い木材を2本組み合わせて立たせてるだけの置物があり、雨風に強い、硬いプラスチックのケースに入った時刻の表が吊るされていた。運転手が言っていたのと同じ、15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 とグフスタイン駅行きの出発時刻が書いてある。これがバス停か。21:00 が最終らしい。そのあと小さい文字が続くが、何を書いているのかはわからない。多分重要ではないことが書かれているだけだろうとは思いつつ、念のため翻訳アプリで確認しておきたい。
「バス、ちゃんと出るね。たくさん。」
Sophisticated の人たちが、ホテルのフロントなどで嫌な対応をされた時に、ぐっと我慢で不快感を全く示さずに、ニコッと笑顔で Thank you very much! ということがあるけれど、今微笑んだレイは、そういうののようだったと感じる。レイに我慢されていると思うと、胸から喉へ、熱いのが込み上がってくる。その熱いのが、頭の後ろ側を通って頭頂まで行って、そこから流れ出ていくようで、段々クラクラしてくる。 標高のせい? 白と黒にチカチカする風景の中、レイはまた、さっき一緒にバスを降りた人たちがみんな入って行った山小屋風の建物へと、歩き始めている。まみもは、小さい文字を読み取るのを諦めて、レイを追った。でも頭は、まだバス停から離れていかない。
(バスに乗ってきた時間は1時間ぐらいだったから、乗車時間が同じなら20時発のでも間に合う。けど乗車時間は同じじゃないかもしれない。遠回りしたり、なんか荷物を載せてったりすることもあるから要注意だ。)
「まみもちゃん、レンタルは向こうだ。スキーにする? ボードやる?」
「ん。……スキーかな。」
「あれ使う? あれ、こういうやつ。」
「(こういうやつ?)……使うかなぁ。」
(19時発でいけるかな。1.5倍で90分かけて下山したとしても20時半に駅につくから……。でも急に19時発は乗客が少ないから20時まで待つとかになったら? よくあるよね、田舎の長距離バスとかで。)
「あ、まみもちゃん、コースの地図だよ!4つも滑れるコースがある。」
「うん。そっか……。」
(18時発にした方がいいのかな。そしたら最後のリフトは何時まで? レンタル屋に返すときに、チンタラチンタラされて時間がかかったりするかな。)
「まみもちゃん、僕やっぱり先にトイレ行ってくる。」
「うん。」
(そうだ。トイレも行かなきゃいけないし、電車に乗る前に若者にちゃんとした夕飯を食べさせなきゃ。食べられそうなところあったっけ。)
「まみもちゃん、僕トイレやめる。このまま帰って途中でお漏らしする。何回も。」
「うん。トイレやめるか。」
(ん? お漏らし? 何回も?)
まみもはレイを見る。視線を水平にずらしたところは、レイの肩と口の高さだった。走って打ち付けられたり、バスの座席で押されたりして、よれよれになったプレッツェルが、まだかろうじて首にかかっている。少し上へ顔を傾ける。そこに、イライラ100%を通り越して、ほとほと呆れました、もう君に希望は見出せません、という顔があった。ドキーんとする。
「ガブ、ガブくん、」
まみもの声は小さく、多少震える。
「トイレはやっぱり行こうか。お漏らし困るよね?」
「まみもちゃん、」
レイの顔、この顔嫌だ。
「僕のお母さんみたい。全然僕の話聞いてない。」
そうだった。聞いてなかった。レイの顔を見るのさえ、久しぶりに感じる。いつこんな怖い顔に。あの1個1個のパーツからこんな表情が出てくるの、知らなかった。レイは、怖い顔を、まだ怖い顔のまま、不機嫌な時か困った時の顔に少しだけ近づけて、まみもの眉毛を、通常時あるべき位置に押して戻しながら言った。
「バスから降りた時、僕がなんて言ったか聞いてた?」
「……ううん。」
まみもはもうだめかと思う。逃げろー、と走っていなくなりたい。
レイがまた眉毛を直す。
「……なんて言ったの?」
「もう一回やろう。バスを降りるところから。今度はよく聞いててね。」
スタート位置の、バスの降車場のある小さなロータリーに戻ると、山の空気に、さっきのんびり歩き回って、その後長距離ダッシュをした、グフスタインの駅の辺りより湿り気が多いのを感じた。少し寒い。雪をかぶっているとんがった山頂部と、その近くへ登っていく2人乗りリフトが見えた。乗っている人がいる。見えている1人は半袖だ。上の方で、滑っているらしき人が1人、2人見える。 夏に、ドラマチックな形の山から、薄着の人たちが滑り降りてくる。フー!と言ってる声が聞こえる。 まみもが指差して何か言おうとすると、その前にレイが「うん。」と言う。もう一つ何か言おうとすると、まみもの声が出る前にまたレイが「うん。」と言う。
「あの、……」
「うん。うん。うん、うん、うん。」
さっきバスを降りた時に、レイはこれをみんな見たのか。一人で。
「いい? 降りるよ。」
「うん。」
「山田くん! 雪ちゃん!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
