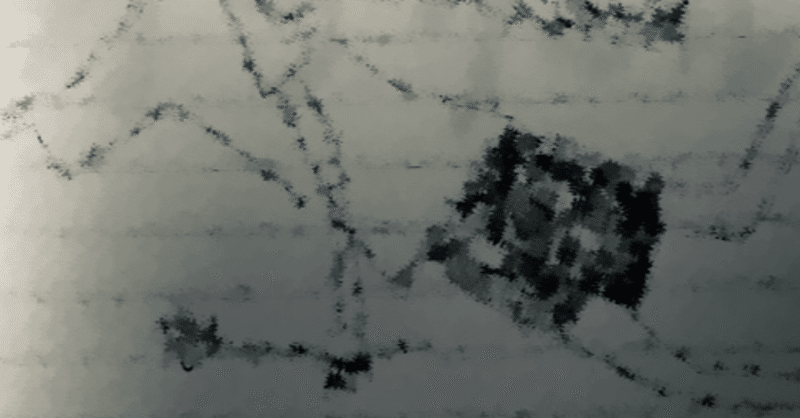
ガブリエル・夏 31 「笑わない」
「ガブリエルくん、これはいいホリデーになりそうですね。」
「うん。」
「山田くんと雪ちゃん、ガブくんの到着を喜んでるみたいね。」
「うん。」
「さっき、ごめんね。」
レイはまみもを見ただけで、うんとか、いいとか、許すとかは言わなかった。でもその顔はさっきまでのおっかないのではなかった。
それから2人は、早送りのスピードで、トイレに行って、入場券を買って、手袋を買って、板とブーツのレンタルの手続きをして、コースマップをポケットに突っ込んで、いらない荷物をロッカーに預けた。
「ぅオイラのクッキーは置いて行かないでね。あとで食べる。」
「うん。カモも持ってく方に入れたよ。カタツムリは、そこで大丈夫?」
「気をつける。連れて行きたいから。」
ここから普通のスピードになって、レイは、胸ポケットに入ってる折り紙のカタツムリを一度出して、異常がないのを確認し、大事そうにそうっと腹部の膨らみと角の角度を直し、戻した。まみもは、それをしてるレイを見るのが嬉しかった。ほっとして、大きなかたまりの息が出た。レイが気づいてちらりとまみもを見たけど、何も言わない。笑いもしない。カタツムリは、今はポケットに深めにおさまっていて、もう角もはみ出ていないから、何か感知して知らせてくれそうではない。さっき吐いた息が、全部また全身の毛穴からまみもの中に戻ってきたようで、張り詰めた感じになる。
2階の出口から外に出る。
一面白銀の世界、ではない。緑の草と木と、光る白の雪、濃い青の空。浮かれた顔の人たち。後ろにはトンガった山の頂部分が重なりあっていて、奥の方のとんがりの中には、黄色ピンクっぽい、斜めの太陽色を跳ね返しているところもある。シュワ〜ッ、シュワ〜ッという、誰かのスキーが、冬より水分の多めの雪を滑る音がする。上の方から、歓声と笑い声が聞こえてくる。まみもの隣りの、浮かれてない顔の青年は、淡々とスキー板の金具にブーツをはめ、コースマップを見て、ポケットに戻した。まみもの準備ができると、「あれに行くよ。」と、1番近くのリフトへと、滑り降りていった。緩い傾斜を、自分でこいでスピードを出して滑っていくけど、楽しそうじゃないのが背中からもわかる。まみもはレイの通った後を、滑って降りた。リフトの乗り場に待ってる人は4、5人しかいないので、すぐに順番が回ってくる。スキー場のリフトといえば、流れてくる椅子に座る時、大抵は後ろを確認しながら、用心深くタイミングを合わせて、1、2のよいしょ、と座るものだけど、レイは、自分の家の食卓につくときのように、カジュアルに座った。結構高速のリフトで、すぐにぐいーんと高いところへ引っ張られる。地面の泥まみれの雪からは15mぐらい上にきた。最初のポールのところで、ガタンと小さく衝撃がある。レイはスキーのついた足をブラブラさせる。まみもはレイの顔を見てみる。水分のいっぱい詰まった肌に、まみもの好きな、黒々して強そうな眉毛と、レイだけの見え方でものが見える緑の目のセットがついてる。瞬きするたび、カーブの綺麗な睫毛が少しだけ振動する。少しズームアウトすると、髪の毛がたくさん見えてくる。あっち向きこっち向きに自由にくるくるしていて、レイという人間にぴったりだと思う。まみもがアリのサイズだったら、巨大ジャングルジム迷路に見えるだろうか。
しつこ目の長い視線を浴びて、一度レイがまみもを見る。これをどういう表情というのかわからない。悲しそうにも退屈そうにも見える。まみもの頭が一度ズキンと痛む。もうすぐ笑うのか、ずっとこのままなのか、わからない。笑ってほしい。まみもの方は、年長者らしい余裕の微笑を試みるが、わざとらしかったかもしれない。効果はなかったよう。もう少しズームアウトすると、レイの後ろに世界が広がっているのが見えた。山と雲と、アリより小さいサイズの人々の村々。
「ガブくん、後ろ見て。」
レイは後ろを向いて、しばらくそのままの体勢でミニチュアの世界を見ていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
