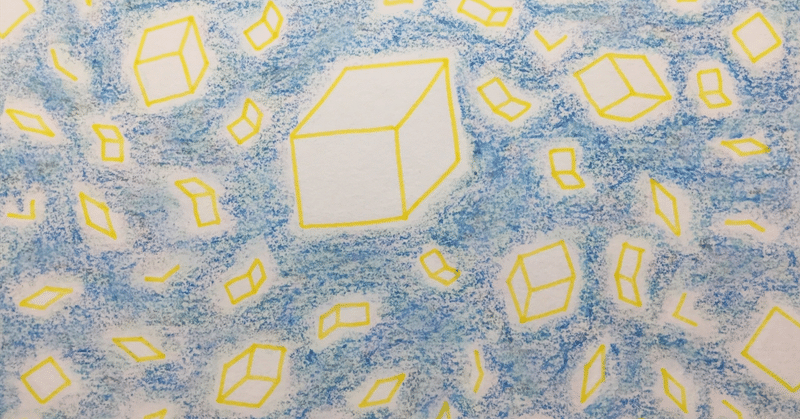
「この公衆便所女」とわたしに罵ったのが最後の言葉になった君へ
※この文章には、性的な描写や性被害を想像させる描写などが含まれています。ご注意ください。
きょうはFacebookやInstagramで、ご無沙汰している友人や知人にお知らせしたいことがあって、珍しくある投稿をした。
個別に伝えられる関係の人には伝えたりもしたのだけど、「全体」にたいして個人的なことを発信するというのは、マスメディアで記者として「読者」なり「視聴者」なりに届けるよりも、ずっとむずかしいと個人的には思う。
ひとりひとりのことを知っているから、どんな文章を綴ろうか考えるたびに、それぞれの顔を思い浮かべてしまう。Aさんにはこの言葉で伝えたいけど、その表現を見たBさんはぴんとこないかもしれないな、とか、Cさんにこの表現をしたらもしかしたら誤解を与えたり傷つけてしまうかもしれないな……などなど考えながら「全体」への文章を綴っていくと、最大公約数で伝わる言葉を選ぶことになり、それで間違っているわけでもうそでもないのだけど、自分が本当に伝えたい温度感とはかけ離れたような、他人事のような文章になってしまう。
また、同じSNSといってもFacebookとInstagramでは属性もちがうので、同じ内容を伝えるにしても、そこでも調整する必要があったりして、そんな時間はかからないだろうと思っていたけれど、思った以上に時間もエネルギーも使ってしまったのである。
なによりも、普段メインに利用しているこのnoteや、Twitterに加えて、FacebookやInstagramからの発信を行なったことで、この「わたし」がいまどこに立っているか分からない、普段よりもさらに足場のぐらぐらした状態になってしまって、精神的に不安定ぎみになってしまった。
みずから個人的なことを発信しておきながら、そういう状態を繰り返すたびに、つくづく自分はSNSに向いていないなと思い、距離をとりたいなと思う。そこで「つながっている」感覚に安心できる人にとってはいいと思うけど、わたしにとっては明らかにデメリットの方が多い。
自分にとっては、あまり親和性にあるメディアとはいえないことはわかっていて、いつでも辞めてもいいという気持ちでいたら、だらだらともう10年以上、近づいたり離れたりしながらも、結果的に続いているというかんじだ。
そんなネガティブぎみな精神状態だったから、ジムへ体を動かしに行ったのはいいものの、イヤホンから聴こえたYUKIのベストアルバムの音楽が、そんなつもりで聴こうと思ったわけではないのに、冒頭の、けっこう衝撃的なタイトルだと自分でも思うのだけど、そうわたしに言い放った日が最後となった彼のことを思い出してしまったのである。
彼とは、わたしが社会人となって初めて新聞記者として働き始めて2年目に出会った。
まだASD(自閉症スペクトラム)という診断を受けていなかったころの当時、わたしの「普通」に擬態しようとするふるまいやしゃべり方や態度は、擬態していることを誰にも悟られたくなくてそれはぜったい恥だから隠そう隠そうとするなかでも、やっぱり出てしまっていて浮いていたのではないかなと、いまとなっては思う。
もともとがくそ真面目にしかなれないつまらない性格で、やるからにはすべて全力以上にがんばらなければ満足できない悲しいくらいに不器用かつ完璧主義なので、社会人になるまでは、人が見ていないところで隠れて100倍がんばることや、持ち前の根性というか執着心でもって、劣った自分を必死でカバーしてしていた。
だけど、社会人になると、そういった「マイルール」だけを押し通せばいいわけではなくなってくる。わたしの「普通」の物真似は、「ぎこちなさ」や「こっけいさ」や「すっとんきょうさ」や「イタさ」などとして、同業者同士だけではなく、社内や同期同士でも競争が激しく、常に足のひっぱりあいがあるようなマスメディア業界では、すぐに格好の「いじめ」や「からかい」の的となった。
そこに「若い女」というアイコンが加わればなおのことだ。新聞記者2年目のとき、おそらくわたしが女性でなければこんなかたちにはならなかったと思うけれど、わたしのそうした振る舞いを、「女性記者」というアイコンでもって、性的おかずネタとしてあることないこと書いたゴシップ記事が、週刊ポストと文春で立て続けに取り上げられたことは、いまも忘れられない。誰もがもう、すぐに忘れてしまっているだろうけど。
わたしは、自分ががんばってネタをとったり取材先に迫ろうとしたりしたあげく、裏目に出てしまうなんていう最高にかっこわるいことを、誰にも知られたくなかったし、ずっとそれを恥だと思って、ひた隠しにして、涼しげな顔を装っていた。けど、事件が起こるたびに、そのへんの同業者同士で固まって愚痴りあったり井戸端会議のようなことをしてずるく器用にサボっている男性記者たちを見るにつけ、そんな彼らよりもわたしはずっと髪も振り乱して自分の性別なんて考えるひまは一度もないくらい、靴も服もぼろぼろになるくらいにがんばっていると自負していた。
そんなわたしについて、誰が週刊誌の記者に、わたしのあることないことの性的おかずネタや携帯電話、自宅の住所といった個人情報、果てには当時いた横浜支局で、休刊日の箱根旅行の宴会の際に、新人が出し物をする伝統があったのだが、そこでミニスカの女子高生の服を着て踊らされたときの写真まで(事前に新聞社が内々で入手できる週刊誌のゲラの時点では、そのときのわたしのモザイク写真までが見開きで大きく載っていた)を提供したのかは、知る由もないけれど。
とはいえ、そんなことをされたら誰でも疑心暗鬼になるだろうという状況のなか、立て続けに週刊誌に載ったことで同業者間や社内でも、「あいつだ」ということで笑いの種にされたり、こそこそと陰でなにかを言われたり、「これだから女は」と中傷されたり、女性であるということの色眼鏡でやることなすことにやにやと見られてしまうことは、普通にこたえた。
それ以上に、さらにこたえたのは、社内で「これだけ世間を騒がせたのだから謝罪しろ」と謝罪と土下座を要求されたうえ、同僚たちからすれ違いざまに「早く辞めろ」などとつぶやかれたり、「どうせ取材先に媚び売ったり寝てとったネタなんだろ」という理由で、記事を書いても書いてもボツにされたり、自分だけに必要な情報が共有されないといったいじめが続き、その影響で不本意な人事異動をさせられてしまったりしたことだった。
組織としての対応に向き合うまえに、当時の管理職や上司、同僚がいっせいにしらを切り、個人の問題にすり替えられ、すべてを押し付けられてしまったことが、いまもわたしの心に暗い影を落としている。そこで初めて精神を病むという経験をし、主治医から「すぐに辞めろ」と何度も忠告されたものの、それが余計になにくそと意地になってしまい、辞めずに10年弱はとどまってはみたけれど、その新聞社を去ってさらに10年ほど過ぎたいまも、傷が癒えることはない。
週刊誌に立て続けに載った際は、記事を読んだり、一連のわたしにかんするうわさ話を聞きつけて、慰めや心配の声をかけてくれたやさしい人たちもたくさんいた。君のことがおもしろいからとか、実は前から買っていたんだ、などと、それをきっかけに飲みなどに誘って近づいてきたずるい男性たちもいた。
誰もが色眼鏡をとおしてしかわたしを見ようとしないことに辟易しているなかで、わたしの痛々しさをそのままに受け止めて、そばにいてくれた人が、彼だった。
これまで、痛々しさがばれないようにつきあうのが、恋愛だったり、人間関係だったりだと思っていた。無理して、その場に合わせてキャラをつくって、そのたびに疲れて、一人になった瞬間、どっと倒れてチャージして、その繰り返しが人間関係だと思っていた。
だけど、彼との出会いは、そんなわたしのパンドラの箱を開けることになってしまった。開いた以上は、もう戻れなかった。これまで自分一人で抱えてきたものが、うわーっとマグマのように噴き出して、止めることができなくなった。
わたしはそれから、注いでも注いでも、水が漏れたコップのような、愛を乞う人そのもののような、自分でもコントロール不能なくらいに、性をはじめとするあらゆる逸脱行為がとめられない困った人になってしまった。
彼とはそんなこんなで10年以上、お互い離れたくとも離れられないような関係になった。その関係性の名前は、他人からも名づけられたくないし、自分でも名づけてはっきりさせる必要はないと思った。
彼と出会ってからの十数年間、わたしはとても精神的に不安定な時期が続き、これまで何度か精神科閉鎖病棟への入退院を繰り返した。
その情報を知った記者時代の男性たちから「精神病院なんて見られる機会なんてめったにないから、見舞いがてら見学させろ」とか「精神病院って、鉄格子の檻に閉じ込められたりしてるの?」とか「会うと普通なのに、わざとじゃないの?」とか「ルポを書け、おれが本にしてやる」とか、色眼鏡からのわたししか見ようとしない人たちからの、好奇心や興味本位からの連絡にうんざりした(わたし自身も元気なときしか見せてこなかったし、下ネタもなんでもおっけーなおっさんのようなおもしろい女キャラでしかかかわってこなかった責任もある)。
そんななか彼は、近くの道の駅で買ってきたという色ちがいの2種類のぶどうを一緒に食べようといって、ふらっとやってきた。ぶどうジュースも3本くらい買ってきてくれたのだけど、瓶だったので、閉鎖病棟ではカミソリや綿棒や通信機器やドライヤーなどのコード類も没収されてしまうくらいなので、看護師さんから持ち帰るように言われた。
わたしにとって、外界からの余分な情報が一切入ってこない環境はベストこのうえないので、そうである限り、わたしは、なんでここに自分がいるのか分からないくらいに、とても元気でいられた。一生、こんなふうに「無」の場所にいられればいいのにと、下界のことを思い出しては思った。
むしろ彼のほうが不安定になっていた。昨日、車で高速に乗ってトンネル入ろうとしたんだけど、おれもういまつらくてほんと死にたくて、ハンドルをそのまま左に切って、ああもう死ぬんだなって思ったんだけど、ふと君のことを思い出したら我にかえって、きょう見舞いにいこうと思ってここに来たんだというようなことを話した。
とにかく、彼は、わたしと一緒に、廊下のいちばん隅にある窓際のテーブルに座って、ひたすらぶとうを一粒一粒、皮をむいて食べながら、「死にたい」「死にたい」という言葉を繰り返しては、たわいの話をしていた。わたしは彼が、しんどくなると、誰かのためになにかをすることで心をチャージしようとする人であることを知っていたから、一緒にもくもくと手と口を動かしていた。
こうやって書くと、どろどろの闇のなかにいる共依存ストーリーかなにかなのかと思われてしまうかもしれないけれど、いい思い出もたくさんあった。だけどそれは二人のなかで完結しているから、あえて書く必要はないようなたぐいのことばかりだ。でも、ひとつだけここで「光」のようなエピソードを書こうと思う。
別の回でも書いたけど、わたしは、普通の同級生が知っているテレビや音楽といったものと遮断された、普通ではない環境で育っていた。そんな状態のまま大人になったわたしに、初めて映画や音楽を教えてくれたのも彼だった。
そのなかの一つに、JUDY AND MARYと、解散後ソロになったボーカルのYUKIの音楽があって、わたしたちは、何度も彼らの音楽をCDが擦り切れるくらい、ドライブ中の車内や、砂浜では寝転がってイヤホンを二人で分け合って聴いたりした。歌詞も聴き込んでは、その感想を熱く交換し合った。家ではライブのDVDを何度も見て、朝になるのも気づかずに踊り続けた。
わたしをみつけてくれた彼のこと、あるいはわたしたちの定義できない関係性に、いじわるなことを言ってくる人はたくさんいる。間違いだらけだなんてことはわかっている。けれども、幸せになる切符を握りしめたわたしたちだったら、口笛を吹きながら、花咲く丘までずっと進んでいける、そう信じていた。
だけど……最後の夜がきた。
わたしはそのとき、とある町にいることがしんどくなって、急きょ彼が一人で暮らすマンションにしばらく住まわせてもらうことにした。
そのとき本州の果ての港町に住んでいた彼は、わたしが電車で移動してくる間に、市場でその日にとれた海産物をたくさんそろえて待っていてくれた。
なんとかローカル線の最寄駅まで終電で滑り込むことができ、深夜過ぎ、彼の自家製の梅酒のソーダ割りで乾杯をした。
彼と出会ったばかりのころは、わたしたちは毎晩のようにお互いの肉欲と肉欲とを奪い合うかのような勢いでセックスをした。
だけど、ほどなくして彼は、あることに気づいてしまった。わたしがあらゆる男性から、一人の意思を持った人間としてではなく、むしろ「女」として暴力や支配欲の吐け口に、みずから進んでなることで自分を傷つけようとしている「歪み」に。
新聞記者時代に、わたしをわたしとしてではなく、「女」や「女性記者」というアイコンでもって、性的おかずとして消費したり侮辱したり、性的に加害してきた人たちになにくそという気持ちを持てばもつほど、思い出してしまうたび、どういうわけかわたしは悔しくなって、彼らの想像をもっともっと上回るような、セックスにおぼれたくるった「女」になって、より支配、加虐されようとしてしまうのだった。そしたら、あのときのちっぽけな自分が、強くなれるはずだと信じていた。
そんな倒錯した苦しい快感を感じることでもって、わたしは、エキセントリックかもしれないけれど、そこであえで「性」や「女」を遠ざけてしまうのではなく(そんなのは悔しいし、もったいない)、傷つきやトラウマを克服しようとしていたのだった。
だけどそれは、彼にとっては、自分を愛しているゆえではないという、深い悲しみを味わわせることになってしまった。そのことを言語化し合ったことはないけれど、わたしのセックスへの感じ方が普通でないことは、きっと感覚的なほうが伝わりやすいのだと思う。
なんとなくその感覚ができて以来、わたしたちは徐々にセックスをしなくなっていった。わたしもわたしで、ほんとうに好きになった人には、自分の傷つきやトラウマの克服のためにセックスを利用したいとは、はっきりと思えなくなった。一般的には、それを性的に不能だというのだろうけど。
だけどなぜかその夜の明け方、彼はわたしを突然、求めてきた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

