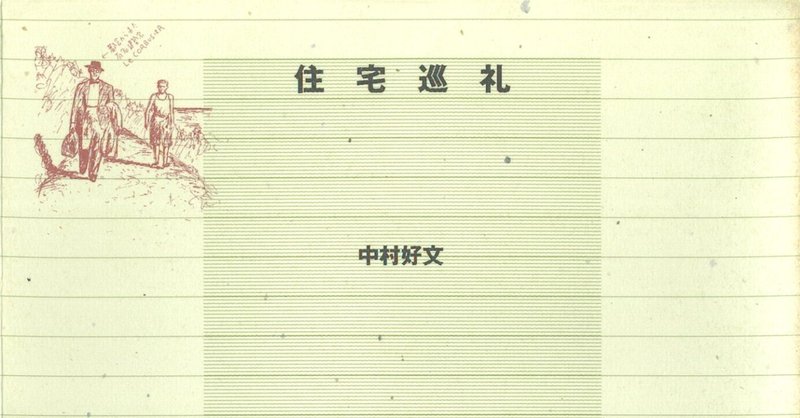
建築家の住宅論を読む<7> ~中村好文~
今、住宅建築家の第一人者といえば、建築家 中村好文(なかむらよしふみ)の名前を挙げる人が多いのではないでしょうか。
エッセイの名手だった伊丹十三を尊敬し、暮らしや住まいについて多くのエッセイを書き残した建築家 宮脇檀を先輩に持つ中村好文もまた、住宅の良き語り手のひとりです。
『住宅巡礼』、『普段着の住宅術』、『住宅読本』など、その著作のタイトルからうかがえるように、中村好文が語るのは、主義主張を声高に語る大仰な住宅論というよりは、長年の住宅づくりの経験から滲み出てきた、静かな確信に満ちたエッセンスのようなものです。

質の高い日常品としての住宅を目指すその作風にも通じる、奇をてらうことのない、しごく真っ当な話しは、住まい手である私たちが住宅を見つめ直してみるときに、あるいは、住まいを新築したり、リノベーションしたりするときに、すこぶる示唆に富むことばかりです。
住宅作家にして住宅の名語り手である中村好文が語る言葉をご紹介しましょう。
「建築的」であり、「生活的」であること
中村好文は師である吉村順三の軽井沢の別荘(吉村山荘)を何度も訪れ泊まった経験から、住宅は、「建築的」であり、「生活的」であることが大切だと身体でわかったと述べています。
「その山荘では「建築的であること」と「生活的であること」というふたつの概念はいささかも対立するものではなく、穏やかに融合していました。そのことを、私は頭ではなく、まず身体的な感覚として学んだように思うのです」
建築家は、建築や住宅のプロである前に、人間とその生活の優れた観察者であることが求められるとも述べています。
「建築家は構造、設備、材料、性能などのプロフェッショナルであり、さらに芸術の理解者かつ表現者でなければなりません。しかし、それと同時に、あるいはそれよりもまず、卓越した人間観察家でありたいものです。人間の生活という雑駁で、矛盾に満ち、曖昧で、所帯じみた、滑稽で、皮肉で、自分勝手で、愉快で、退屈で、混沌とした代物を、まるごと穏やかに受け入れる器量と、それを暖かく見つめる眼が何よりも要求される」
小説や映画の話題が多く語られるのは、優れた生活観察者であることの現れです。
「優れた小説家や映画監督なら備えている、人間観察の能力と柔軟で自在な想像力は、建築家にも不可欠な能力に違いありません」として、時の流れのなかで変りゆく人と家族の姿を静かな諦念と愛惜のうちに描いた『東京物語』を撮ったときの小津安二郎が、まだ50歳に手が届かない年齢だったことを思い起こします。
映画を観るときは、メモ用紙と筆記用具を手元に用意して気になる間取りやインテリアを描き写すことが「一種の職業病」になっていると言い、映画『赤ひげ』に登場する小石川療養所の一室の壁一面に造りつけた薬のための抽斗(ひきだし)に惹かれ、観るたびにスケッチしてしまうことをうれしそうに告白します。
「良い映画には「この映画はここで極まった!」と感じられる、その映画全体をひとつのシーンが象徴してしまうようなカットがありますが、住宅にもそういうシーンやディテールを持ちたいものだと思っています」
映画ファンは、この一言で、この建築家に思わず親しさを覚え、自然と信頼感を抱いてしまうに違いありません。
仕立ての良い普段着としての住宅
中村好文は自らの理想とする住宅をこう表現しています。
「普通に見えるんだけれども、きちんと仕立てられている、そんな腕の良い町の仕立屋(テーラー)のようなイメージが僕の理想とする住宅建築かな」
「理想をいえばそういうモノとしての魅力をたたえつつ、そのことをあざとく感じさせない、じっくり煮込んでいってあっさり薄味に仕立てたような滋味のある住宅がつくりたいですね」
「普段着で、普通の声で、しみじみ語りかけてくるような住宅を目指すと、自然に「生活のための、良くできた容器」に帰着することになるのです。無理も、無駄もなく、威張ったり、いじけたりしない自然体の住宅が私の理想ということになります」
テーマや工法やスタイルにはこだわりはないと言うこの建築家ですが、「いっそう私の意に添わないのは、いわゆる斬新さや、新奇さや、作品性ばかりが声高に主張する「建築家の満足」とでもタイトルを付けたくなるような、これ見よがしの住宅です」と主張し、「システムキッチンのショールームが引っ越してきたみたいなヒンヤリした台所を備え付けたりするのは、建築家としての信念とプライドが許しません」と断言する、芯の通った建築家でもあります。
「美しく散乱する台所」。キッチンは「真剣勝負の制作の場」である
優れた生活観察者である建築家は、当然ながら地に足の着いた生活の実践者でもあります。自らも料理好きで食いしん坊の建築家の事務所では、昼食は所員が当番で作って、みんなで食べるのが習慣となっているそうです。そうした生活者としてのリアリティがよく表れているのがキッチン(中村好文は「台所」という言い方をしています)を語る言葉です。
「美しく散乱する台所、あるいは多少の散乱ぐらいでへこたれない大らかな台所が、私の理想です」
美しいシステムキッチンの「隅々まで磨きたてられ、整然と整理整頓されすぎているシラッとした写真をみるだけで、(中略)せっかくの明るい料理気分がヒンヤリ冷えてしまうからです」
「画家や彫刻家の住宅などを想像してもらえればお分かりいただけると思うのですが、アトリエという空間に特別な魅力を感じたりするのは、そこが真剣勝負の制作の場であることが一目にして了解できるからです。台所も一種の制作の場、すなわちアトリエと考えれば、その場所は生き生きとしたモノ作りの雰囲気に包まれていて欲しいと私は思います」
男女を問わず料理好きの人にとって、思わず膝を打つような理想のキッチンではありませんか。
書くことと建築設計が似ているように、料理と建築設計もどこか似ているのかもしれません。
失われつつある「手ざわり」が感じられる住まい
「美しく散乱する台所」のほかに「風景におさまる」「とっておきの居心地を」「遊び心」「建築家はワンルームによって記憶される」「箱型」「住まいの中心には火を」「家具といっしょに暮らす」などさまざまなキーワードで、中村好文好みの住宅が語られます。最後に「手ざわり」のことをご紹介したいと思います。
自らを「触覚人間」と称する建築家は、「愛着は手ざわりから生まれる」と言い、「手ざわり」のある家にこだわります。とりわけ階段の手摺は、この建築家が特に大切にしているディテールです。
「一度さわりにきませんか」という言葉とともに載せられている、職人といっしょに試行錯誤しながら作ったという「加地さんのすまい」の階段手摺の写真は、見る者に触ったときの手のひらの感触や将来、経年で艶が増しさらに手に馴染んだ様子なども想像させて止まないような、そんな佇まいの手摺です。まさに「手摺史」に残る「さわりたくなる」手摺の写真です。
あばれや不陸(ふりく)のリスクがなく、コストパフォーマンスが抜群の量産部材や工業製品が主流となった今の住宅では、「手ざわり」のある家はますます遠くなるばかりです。美しく清潔で整ってはいるが、どこか実感が希薄な今の住宅に失われつつあるのが、この「手ざわり」とそこから生まれる住まいへの愛着であることに改めて気づかされました。
中村好文(1948-)
武蔵野美術大学建築学科卒。都立職業訓練校木工課で家具製作などを学び、吉村順三建設計事務所を経てレモンミングハウス設立(1981)。100件を越える住宅を設計し、「三谷さんの家」で吉岡賞受賞、「一連の住宅作品」で吉田五十八賞特別賞受賞。現在、日大生産工学部住居空間デザインコース教授。世界の名作住宅をスケッチ・写真などともに紹介した二冊の『住宅巡礼』は住宅好きにお勧め。
*参照文献 : 中村好文『住宅巡礼』(新潮社、2000年) 中村好文『続・住宅巡礼』(新潮社、2002年)
中村好文『普段着の住宅術』(王国社、2002年)
中村好文『住宅読本』(新潮社、2004年)
初出 : houzz site
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
