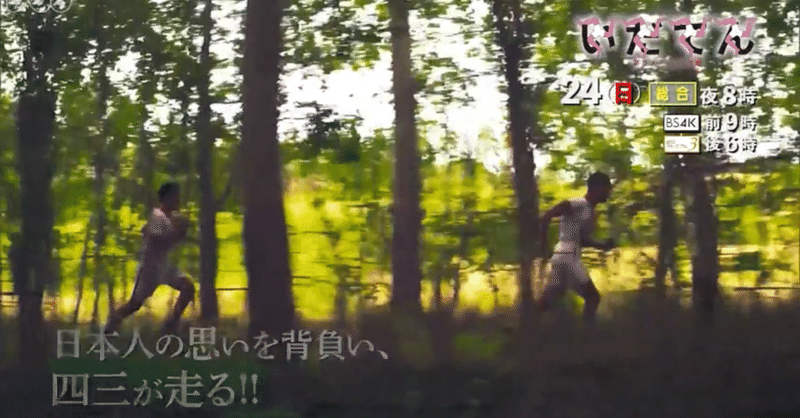
大河「いだてん」の分析 【第12話の感想】 走ってないと死んでしまう“呪い”にかかる瞬間
第12話は、ついにストックホルムオリンピックもクライマックス。マラソン競技の当日を迎える。
今週も、印象的だったシーンの分析を書きとめておく。
※これまでの感想と分析はこちら
1、“行方不明という記録”までの克明な経緯
第12回が描くのは、1912年7月14日。
ストックホルムオリンピックのマラソン競技の当日。
今回の大河が描こうとする“歴史”にとっては、ひとつの節目となる日。
主人公の金栗四三が、炎天下で日射病にかかり倒れてしまい、スタジアムまでゴールできず、“行方不明”として公式記録された日だ。
あとにも先にも“行方不明”なんていうオリンピック記録は他に存在せず、現地ストックホルムでは今も語り草になっている“歴史”だ。
その“史実の瞬間”が起こるまでの経緯と状況を、今回の第12回は1時間をかけて克明に描いてみせた。
“行方不明”になった時、本人はどう感じたのか、周りの仲間はどう立ち振る舞ったのか。
歴史の教科書だとたった1行で書きおえるような史実の背景を、生々しくリアルにじっくり追体験することができる。そういう“大河ドラマらしい醍醐味”が味わえる回だったといえる。
(金栗四三は歴史の教科書には出てこないが。)
2、この日を境に分かれる“長距離走と短距離走の命運”
結局、日本人初のオリンピック参加は、成績だけ見ると散々に終わる。金栗四三と三島弥彦。
ただ、“オリンピアンふたり”のその後の人生は、大きく二方向に分岐する。
三島弥彦は、これ以降スポーツにはまったく関与しなくなり日本短距離界の歴史からその名前は消え、
金栗四三は、ストックホルムを皮切りに“日本マラソン界の発展の中心人物”へと成長していく。
なにがふたりをここまで分かつのか。
少なくとも競技結果の影響ではない。結果だけなら四三も散々だからだ。
「それは、こういうことなのかな」と個人的に考えたことがある。
四三の故郷である玉名市の公式サイトには特別掲載の金栗四三関連コンテンツが充実しており、その中に「大会翌日に四三本人が書いた日記」の文章が残っている。これを引用しよう。
大敗後の朝を迎う。終生の遺憾のことで心うずく。余の一生の最も重大なる記念すべき日になりしに。しかれども失敗は成功の基にして、また他日その恥をすすぐの時あるべく、雨降って地固まるの日を待つのみ。人笑わば笑え。これ日本人の体力の不足を示し、技の未熟を示すものなり。この重圧を全うすることあたわざりしは、死してなお足らざれども、死は易く、生は難く、その恥をすすぐために、粉骨砕身してマラソンの技を磨き、もって皇国の威をあげん。
四三は、自己分析ではストックホルムを「(ただの)失敗」と捉えているし「技の未熟」を磨くために「粉骨砕身して」努力することを日記の中で誓っている。
つまり、“どうにかなる”と評価している。
前回の第11話で触れたように、三島弥彦のほうは、
「金栗君。日本人にはやはり短距離は無理なようだ」
と言ったという。
欧米選手との競争の結果、
それを“無理”と体感するか、“どうにかなる”と体感するか、この“解釈の温度差”がのちのちに大きく響いてくる。
そういうことなんじゃないかな、と今は思う。
もちろん精神論だけではすまなくて、
実際に日本人の体格や特性には、短距離走よりも長距離走のほうが向いているという科学的事実もあろうが、でも、
この1912年を分岐点として、
「長距離走は日本の得意種目となり、短距離走は日本の苦手種目」となった。
それには訳がある。長距離走の選手育成の環境は年々整い、選手人口は徐々に増え、日本各地にレースが準備され、有名選手が生まれ、その引退後に教育者が育ち、また育成環境が強化される。グッドサイクルが生まれていく。
たったひとりの人物の『終生の遺憾のことで心うずく』からの奮起と情熱が、道をつくり拓いた。
その差は大きいのではないか。
レースに負けた四三が「すみません、すみません、すみません、すみません」と何度も何度も泣きながら謝るのを聞きながら、僕はそう考えるのである。
3、走っていないと死んでしまう“呪い”
時を同じくして、美濃部孝蔵(森山未來)は初めての高座の演目を『富久』に決めた。
しかし、いくら一人稽古をしようとしても、物語の続きが出てこなくて、口ごもってしまう。
そこでふと気づいて、車夫として人力車を引きながら落語をさらってみると、スラスラと話せるのである。
どうやら、長いあいだ、師匠を背中に乗せて人力車を引きながら稽古をし続けてきたから、そういうカラダになってしまったようだ。走れば走るほど、饒舌に落語が語れる。
孝蔵は止まれなくなる。
四三がストックホルムでマラソンを走っているあいだじゅう、遠く浅草では、孝蔵が人力車を引いて東京中を走り回っている。
ストックホルム。
カラダに変調をきたす、四三。
調子がよくてどこまでも永遠に走れそうな気がすると四三はつぶやきながら走る。
しかし突然、めまいがして、立ち眩みがして、行く先をまばゆい光がつつんで視界がよく見えなくなっていく。幻覚が見え、記憶が交錯してしまう。
東京浅草。
止まれなくなってますます加速をする、孝蔵。
孝蔵の後ろにはどす黒く不吉な大火事の背景が浮かびあがり、孝蔵を取り囲む。まるで戦時中の空襲のようだ。「どけどけ」とあたりを蹴散らしながら、盲目になった孝蔵が走る。
気味の悪いシンクロ。
これについて、公式Twitterを通じて演出家がコメントをのべていたので引用する。
「同じ時間に走っている二人の魂が、いつしか触れ合っていくようなイメージを作りたいと思いました。 四三の無言に対して、邪魔だー!と蹴散らす孝蔵。暑さに苦しむ四三に対して火事だー!と叫ぶ孝蔵。四三の魂を感じている、そんなロマンを込めました」(演出 一木正恵)
演出家は“ロマンを込めた”と言う。そんな明るいものなのか。まあ、わかりやすい、ある一面だけをコメントしたんだろうと思う。大衆に向けて。
走ってないと死んでしまう。不吉な予感ばかりを感じさせた。退廃的で暴走的で。戦争への不安。このふたりは“止まりたくても止まれない”のかもしれない、呪いなようなもので。まさに1912年の今、ふたりは永遠に呪われる。街を走りながら。

以上。
コツコツ書き続けるので、サポートいただけたらがんばれます。
