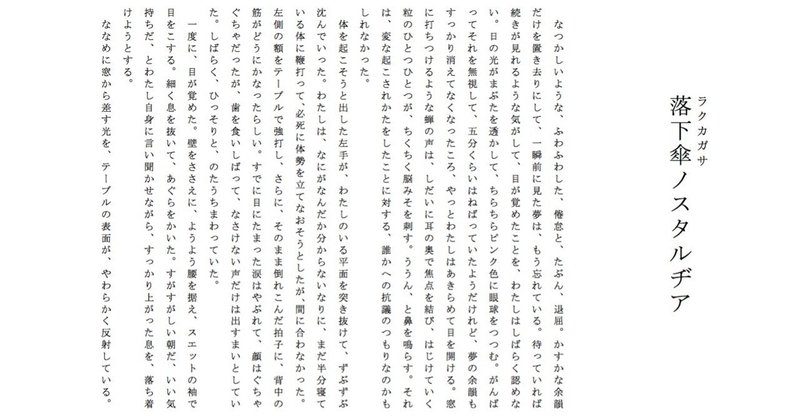
落下傘ノスタルヂア(1)
なつかしいような、ふわふわした、倦怠と、たぶん、退屈。かすかな余韻だけを置き去りにして、一瞬前に見た夢は、もう忘れている。待っていれば続きが見れるような気がして、目が覚めたことを、わたしはしばらく認めない。日の光がまぶたを透かして、ちらちらピンク色に眼球をつつむ。がんばってそれを無視して、五分くらいはねばっていたようだけれど、夢の余韻もすっかり消えてなくなったころ、やっとわたしはあきらめて目を開ける。窓に打ちつけるような蝉の声は、しだいに耳の奥で焦点を結び、はじけていく粒のひとつひとつが、ちくちく脳みそを刺す。ううん、と鼻を鳴らす。それは、変な起こされかたをしたことに対する、誰かへの抗議のつもりなのかもしれなかった。
体を起こそうと出した左手が、わたしのいる平面を突き抜けて、ずぶずぶ沈んでいった。わたしは、なにがなんだか分からないなりに、まだ半分寝ている体に鞭打って、必死に体勢を立てなおそうとしたが、間に合わなかった。左側の額をテーブルで強打し、さらに、そのまま倒れこんだ拍子に、背中の筋がどうにかなったらしい。すでに目にたまった涙はやぶれて、顔はぐちゃぐちゃだったが、歯を食いしばって、なさけない声だけは出すまいとしていた。しばらく、ひっそりと、のたうちまわっていた。
一度に、目が覚めた。壁をささえに、ようよう腰を据え、スエットの袖で目をこする。細く息を抜いて、あぐらをかいた。すがすがしい朝だ、いい気持ちだ、とわたし自身に言い聞かせながら、すっかり上がった息を、落ち着けようとする。
ななめに窓から差す光を、テーブルの表面が、やわらかく反射している。おとぎ話の湖みたいに、しずかで、やさしくて、まっさらな絵本を見開いたときの、つんとしたにおいまで立ちのぼってくるようだ。リサイクルショップで買った、九八〇円のビンテージものだと思い出すまで、修復のために塗ったニスが溶けているのだと気づくまで、わたしは、たしかに額の痛みを忘れていた。テーブルの下は足が伸ばせるように、掘りごたつ式で、わたしがはまったのは、手前の、角に近いところらしく、かきむしった髪の毛が数本落ちていた。そいつらをつまみ上げて、座敷の上がり口から捨てる。わたしの寝床として、五枚一列に敷いていた座布団は、さっきのさわぎの名残に、討死にしたような無残な姿をさらしている。は、は、は、は、よ、とテンポよくかさねて、隅に積んである座布団と一緒にして、これで証拠はなにもなくなったはずで、あとは、本当に痛みが引くのを待てばいいだけだった。
寝ているすぐそばに、こんな大穴が開いているのは、やはり考えものだった。寝相がいいからと、特になにも対処はしてこなかったが、とうとう、やってしまった。寝つきと寝相がいいかわりに、寝起きは悪い。穴をふさごうか、柵でもつくろうか、なにかしようということははっきり決心し、今日の仕事に入れておくことにする。
携帯を探しながら、一週間もたつのにまだ慣れないな、と、なんとなく考えていた。修学旅行のような、親戚の家に泊まったような、新鮮で、非現実的で、心細い感覚はしつこく毎朝のわたしを襲った。それがきらいなわけじゃない。なまけもので、めんどくさがりのわたしが、誰にも指図されないのに、ひとりでこつこつお店の準備を進められているのは、毎日リセットされて、連続していないわたしが、何人もの別のわたしが、そのたびに新鮮な気分で仕事をはじめられるから。テーブルのむこう、なぜか灰皿のなかに入っている携帯を見つけ、まわりこんだほうが楽だとは分かっていても、横着して体をねじり、腕をいっぱいに伸ばして拾いあげる。寝ているあいだに、電池が切れていた。
充電器を差しこみ、電源を入れようとすると、蝉の声を引裂いて、ピアノの音がぽろぽろ降ってくる。ラジオ体操だった。携帯のディスプレイが明るくなり、はたして、時刻は六時半。ずいぶん早起きをしたものだ、とわれながら感心する。次に、七月二十日の日付が目に飛びこむ。なるほど、世間的には今日から夏休みだった。この座敷の裏が、ちょっとした緑地になっている。近所の公務員宿舎に住んでいる子供たちでもが、集まっているらしい。すりガラスのサッシに指をかけ、そっと隙間をつくる。すだれが、じゃまだった。いろんな角度に頭を動かし、やっとのぞけるくらいの隙間を見つける。Tシャツ姿の小学生が、五六人ほど見えた。正面にしているのはななめ右手の、少し高くなった石のステージで、かろうじて子供たちの横顔がここからうかがえる。当然、こんなのは、予想していたとおりの情景でしかない。ふうん、と思う。夏休みはじめの日だというのに、子供たちはもう健康的な小麦色に日焼けしていて、しっとり濡れた肌に、ビーズのような汗のしずくをちりばめている。近く、遠く、ラジオ体操の音楽に合わせて、目のなかで、光の粒がふらふら、ぽろぽろ踊る。あくびをしながら、ぼんやりながめていた。と、全員一斉に、ジャンプをはじめる。かわいた地面から細かいほこりが入道雲のように舞いあがり、見ているうちにも、ぶよぶよ、どこまでもふくれていく。わたしは顔を引きはがし、窓を閉める。やれやれ、と、わたしは口に出して言った。
テーブルに頬杖をつき、これが終わったらごはんを用意しようと決めて、ラジオ体操のピアノを頭のなかで追いかけていた。正確にそれが頭のなかで、どんな動きなのか再現することができる。十年と少し前、わたしが毎朝通っていたのは、近所の神社だった。北国、新潟の夏は暴力的に暑く、神社の境内は低い木が申し訳のように生えているばかりで、わずかな日陰を独占できるのは、ラジオを持ってくる上級生の特権だった。田舎だし子供の絶対数も少なく、集団登校の班ごとにやっていたから、四年生や五年生でラジオ体操のリーダーになれることもよくあるのだが、わたしは六年生でやっと最上級生になることができた。わたしは、はりきって、毎朝ラジオを神社に持っていった。ハンコを押すのもわたしの係で、責任も多少は感じていたのだろうが、たぶんそれが得意でとうとう皆勤した。ノートか、えんぴつか、ボールペンか、ごほうびをもらえた。
深呼吸が終わる。さて、と立ちあがろうとすると、ピアノは、そのままラジオ体操第二になだれこむ。中腰で、なにがなんだか、ちょっととまどったが、なじみのない音楽とあの合いの手が、じっと聞いていると違和感にむずむずする。そそくさと、逃げるように、座敷から這い出した。サンダルをつっかけて、カウンターのなかにもぐりこみ、冷蔵庫からパンと納豆を取り出す。それらを皿に乗せて、わたしの朝食の用意は終わる。口に箸をくわえ、なにげなく表のほうに目をやった。はすむかいのスーパーは、まだひっそりしている。今日は早起きして時間があるし、昼は少し手のこんだものをつくろうか、などと、計画するというほどでもなく、ぼおっとしていると、たるんだ糸を切断するように、さっと、自転車のおじいさんが前を通りかかる。なにがじゃまをしているというのか、やかましくベルを鳴らして、横切っていく。わたしの思い描いていた献立は、粉々にかき消される。そして、首をねじり、目をぎょろつかせ、店のなかをたっぷりと観察していくそのおじいさんの視線と、わたしの視線が衝突する。反射的に頭を下げてしまい、はっとしたおじいさんは、顔をそらした。痴漢されたような、半分嘘を言えば、強姦されたような虚脱感に、しばらく立ちつくしていた。入口側は一面ガラスで、開放感があっていい、客が入りやすくていいと気に入っていたのに、まるで、水槽のなかの熱帯魚になった気分だった。ブラインドかカーテンが必要だと思い、今日やる仕事のひとつにしておく。頭をかきながら、座敷にパンと納豆の皿を運ぶ。まだ、ラジオ体操第二は続いている。
朝食を片づけると、穴をふさぐ、ブラインドかカーテンを買う、昼ごはんまじめにつくる、奈津美に電話する、と、今日の予定を書き出す。ブラインドかカーテンは、売っているところがなさそうだと思いなおし、矢印をひっぱって、またいつか、としておいた。いままでこんな習慣はなかったが、お店の準備という仕事には、いろいろな次元の細かい作業が輻輳していて、思いついたことをそのままにしておくと、高い確率で忘れてしまう。あとでよっぽどめんどくさいと学習した。さしあたり今朝浮かんだことを書きとめ、さて、本格的な仕事はなにかと考えていたところだった。入口の扉を押したり引いたり、がちゃつかせているような気配がして、
「こんにちは」
と棒を突き出したような声が、奥まで飛びこんでくる。まだ七時をちょっとすぎたくらいで、おはようございますではないかと思った。が、そんなことよりも、こんな朝っぱらからたずねてくるのも変だし、そもそも開店準備中の店舗をたずねること自体が、なんの用があるのか、よく分からない。三軒続きのテナントで、うちはそのまんなか。右隣は、荒れはてたドイツ表現主義のようなありさまで、はじめはギャラリーかと勘ちがいしていたが、単に、あまり片づけず撤退していっただけらしい。左隣は、居酒屋。まちがえているのではないかとも思ったが、しつこくがちゃがちゃさせ、もうあきらかにこの店をねらっているのが無視できず、出ていくしかなかった。
「こんにちは」
逆光で、輪郭だけがくっきりと浮かんでいる。後ろにたばねた長い髪で、女の子だとは分かったが、遠近感の死んだ平面的な顔は、部品ごとにばらばらに目に入ってくるばかりで、全体としてどんな顔か認識されるには、まだわたしの目が外に慣れていない。
「はあ、おはようございます」
わたしは、さりげなくあいさつを訂正してやる。
「すいません、こんな朝早くに」
「いえ、別に。なんです」
「先日、お電話したものですけれども、ええと、覚えてらっしゃいますか。あの、バイトの件で」
「ああ」
「ええ」
「なんだっけ。泰子ちゃん」
それで安心したのか、跳ねるように顔を上げて、
「そうです。どうも」
と下手な会釈をする。汗に濡れた前髪の下で、目、鼻、口、が、そろそろ、たがいの距離をはかって、バランスをとりはじめる。
ここのところ、不動産屋、内装業者、銀行、電気、ガス、水道、それに奈津美、いろんなところとひっきりなしに連絡していたので、ついそのひとつにまぎらして、忘れていた。そういえば、ときどきアクセントが変な場所につくが、実家のあたりの方言なのだろうか、やや高くて、木管楽器の響きに似たその声にも、聞き覚えがある。
三日くらい前の、その本人からの電話と、奈津美から聞いた間接的な知識がすべてだった。その知識にしても、奈津美の妹であること、いま浪人生であること、親もとを離れておばあちゃんの家から予備校に通っていること、おばあちゃんの家からは奈津美とわたしのお店に近くて、バイトをしたがっていること、重要なのはそれくらいで、そのほか、シナモンのにおいがきらいだとか、いまだにMDをつかっているとか、どうでもいいことはたくさん聞いた。
「小犬って、チワワとか、あんなに小さいのに、どうして動くんだろう」
「草が成長して大きくなるのは、なんでだろう」
「米を炊くのを思いついた人って、すごいね」
奈津美が馬鹿にすると、馬鹿じゃない、いろいろ考えている、ということを示すために、こういう長年の疑問を披露するという。
「ああ、そう。はじめまして」
「はじめまして、どうも」
「さすがに似てるね、お姉ちゃんと。いくつちがうんだっけ」
「六歳です」
「そっかそっか」
奈津美の部屋に泊まりに行くと、よくこの顔で起こされた。正確には、すっぴんの奈津美にそっくりだった。眉のあるべき場所が不毛の地で、切れ長の目は、とてもきれいな一重だった。細いあごと八重歯は、奈津美にはないものだったが、そのせいで、一段と姉につけた辛辣なあだ名を彷彿とさせる。わたしは、奈津美の素顔を般若と呼んでいた。これ以上姉に似ないように、そして、早く化粧を覚えるように、胸のなかでひそかに祈ってやる。
「本当にお店に寝泊りしてるんですね」
「そう。まあ、急だったし。奈津美とルームシェアみたいにして部屋借りよう、ってことにしてるから、奈津美がこっちに来るまでは、さしあたりここでいいかと」
「暮らせますか」
「快適だよ、ぜんぜん。ちょっとのあいだだから、ホテルとかとるのも馬鹿馬鹿しいじゃない。この店は、もうお姉ちゃんとわたしたちのものなんだから」
「なるほど」
話しながら、泰子がなにをしに来たのか、がんばって推理していたが、さっぱり分からなかった。用はなくて、ただ近くに来たからあいさつに寄っただけ、というのでもよかったが、とにかく時間が非常識である。だぶだぶしたジャージと、黒地に血の飛び散ったこわいTシャツが、なんのための格好ともつかず、よけいにわたしを混乱させる。
泰子が髪をかき上げるのを見て、つられてわたしもそうする。さっきぶつけたところに爪があたり、痛みとともに屈辱的な気分を思い出す。その表情を泰子は曲解したのか、さっさと本題に入ることにしたようで、背中に隠していたものをわたしに見せる。そうとう年季が入っている、うすい緑の、かくかくしたラジカセだった。直感的にラジオ体操とそれが頭のなかで結びついたが、案のじょう、そういうことだった。
「今日からなんですけど、すいません、なんとなくそんな気がしてたんですけど、裏の公園でラジオ体操してます。うるさくなかったですか。お休みではなかったですかね」
うるさくなくて、お休みでも、あんなに大声であいさつされれば起きる。
「うるさくないことはないけど、まあ、今日は起きてたから。やってるな、って思っただけ。え、ラジオ体操やってるの、泰子ちゃんが」
「まあ」
「ふうん。奇遇と言えば、奇遇なような。なんと言うか」
「すいません」
「いや、おもしろいと思う」
なにを言っているのか、自分でもよく分からなかった。
「ボランティアみたいな。ラジオ体操の監督ですよ。ひまだったし、健康にいいし、子供は好きなので、やってみようかと」
「いいんじゃない、うん。あ、わたしは気にしなくていいよ。早く起きれて、いいと思う」
今日からずっと、ということに、言ったあとで思いあたる。うんざりしないこともないが、こう言うよりしかたがない流れ。
「すいません、本当に。そういえば姉の店の近くだな、とか、友達の人がお店に泊まってるとか、聞いてたような記憶はあったんですよね」
「まあ、そうね、でも、こんなところで寝てるわたしが悪い、という見方もあるから。まわりに人のいなさそうな空き地を選んでるんでしょ。それはいいから、ええと、来週ね。面接、ってわけじゃないけど、軽く、これからがんばっていこう、みたいなね。奈津美が来たら、なんかしようよ、なんか」
「はあ、ぜひ」
「おもしろいね。そう、おもしろい顔合わせだった、ということで。なかなかない、と思う」
「そうですね、本当に」
素直すぎるのか、多少腹が立つが、姉よりすれていないぶんだけ、かわいいのもたしかだった。恐れ入りながら去っていくのを見て、バイト代ははずんでやってもいい気がした。ひまつぶしにしても、ラジオ体操のボランティアなど選ぶあたり、健全でいい。わたしは十六から飲酒喫煙をしていたので、こんなに早く来やがるのは、まだアルコールの抜けきっていない朝帰りだろうというくらいに予想したりもしていた。あたりまえのようにそんなことを考えつくわたしのほうが、よほど汚れている。全体的にやや変な子だとは思うが、ぜんぜん合格だろう。
額を、人さし指の腹でそっとさする。こぶになっているか見てみようとトイレに行きかけたが、まだ鏡がないことを思い出す。鏡を買う、というのも予定に加えておくことにする。買いものなんかは別として、人に会う予定もないので、ずっと化粧はさぼっていた。おかげで肌はちょっとだけ若返ったようだが、初対面ですっぴんを見られたのはくやしい。わたしの素顔は、奈津美に、イグアナと呼ばれている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
