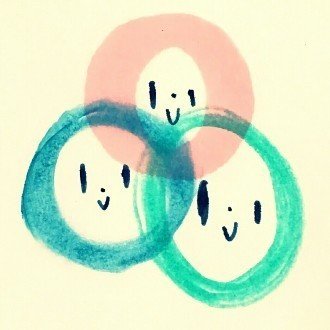[全文無料: 小さなお話 006] 猫の呼ぶ声
[約2,000文字、3 - 4分で読めます]
伊豆半島の奥深く、南伊豆町の子浦という小さな漁村に住んでいたときの話です。
中学時代からの友だちのお父さんが小さな会社を経営していて、その税金対策の意味もあったのでしょうか、伊豆にちょっとした別荘を持っていました。
「ちょっとした」というのは、この場合「ものすごい」という意味ではなくて、本当に「ささやかな」ということです。
その小屋は、村はずれの二面をコンクリで張られた小さな川の土手の上に、立っていました。プレハブの十畳二間の小屋で、その小屋の周りに"「"の字型に廊下が建て増してあり、その廊下が台所兼物置になっていました。廊下と小屋は直接出入りすることができません。部屋からは一旦外に出て、別の入り口から廊下に入らないとならないのです。いえ、本当は窓から出入りすれば、雨に濡れずに行き来することはできたのですけれども。そしてトイレは、小屋の外に現場用のものがぽんと置いてありました。
東京の世田谷で生まれ育ったぼくがそんな奇妙な小屋に、一人目の奥さんと二人で移り住んだのは、そろそろ二十代も終わろうというころでした。
その小屋には二年ほど住みました。その間ほとんど仕事らしい仕事はせず、畑の真似ごとや、そこで知り合った友だちの田んぼの手伝いをする以外は、気が向くと日記程度の文章を書くくらいのもので、世間的に言えばまったく無為の暮らしをしていたのですから呑気なものです。
その小屋に住むようになってしばらくすると、野良猫が二匹やってくるようになりました。一匹はキジトラでしっぽが丸まっているのでたま尻尾と名付け、略称としてタマと呼びました。もう一匹は白猫なのですが、両目の色が違って右目は青、左目は黄色をしていました。それで違い目のチガと名付けました。
奥さんは猫が好きだったので、二匹の猫に餌をあげ始めました。といっても、当時ぼくらはほとんど完全な菜食だったもので、大してあげるものもありません。白いご飯にコーヒー用の粉クリーマをかけてあげたり、たまにもらいものの鰹節をかけてあげたりといった程度の質素な猫ご飯です。
それでもほかに餌をくれる人もいないのでしょう、喜んで食べに来てどちらの猫もすぐになついてくれました。ぼくはそれまで猫とのつき合いはなく、実家ではヨークシャテリヤを飼っていたので、なんとなく自分は犬が好きなように思い込んでいましたが、実際につき合ってみると猫というのもなかなかいいもので、それまでは犬派だったのが、すっかり猫犬派になりました。猫犬派と猫を先にしたのは、どちらかというと猫が好きだけど、犬も好きという意味です。
さてその小屋に住み始めてしばらくしてからの夏のことです。ぼくたち二人は、四国の今治の友だちのところに遊びに行きました。青春十八切符を使っての鈍行列車の旅でした。そして二週間ほど友だちの世話になって楽しく過ごしたあと、南伊豆の小屋にまた戻ったのです。
小屋には昼過ぎに帰り着きましたが、夏の二週間というのはなかなかエネルギーがあるもので、その間に小屋の周りには大いに草が生い茂っていました。自然の力というものはあなどれないものだなあ、などと思いながら、とにかく長い移動のあと自分たちの家に帰ったところでほっと一息ついて、片付けなどすませ、夕食も食べ終わって夜になり、台所でお茶を飲んでいたときのことです。
どこか遠くの方から奇妙な音が聞こえてきます。何かの機械音のような、それともぐわーっという何ものかの叫び声のような、おかしな音がンぐぁー、ンぐぁーといったふうに鳴り続けているのです。耳を澄ませても、それがなんの音なのか、聞いたこともない音なので分からないのですが、初めは小さかったその音が、だんだんと近づいて大きくなってきます。一体これは何の音だろうと思いながら聞き続けているうちに、ぼくははっと思いました。
出口のアルミサッシの引き戸を開けて外に出てみると、間違いありません、大声を上げながら川向こうの道を村のほうから、たま尻尾がすごい勢いで走ってくるのが、真っ暗な夜の闇の中でも、その声を聞くだけで分かります。
分かってからもしかし、猫がこんな声を出すものだろうかと、もちろん発情期の猫の声のすごさも知らないわけではないのですが、餌を求めて猫が走りながら、こんなものすごい声で叫び続けるのかと、本当にびっくりしたものです。
ぼくは薄情な人間なので、小屋を出るときには猫のことなどこれっぽっちも考えていませんでしたが、そのあまりに強烈な猫の呼び声を聞いて、可哀想やら、おかしいやら、なんとも不思議な気持ちになったものです。
ものすごい勢いで小屋に飛び込んできた猫に、奥さんがいつも通り粉クリーマごはんを用意してやると、これまたものすごい勢いで、がつがつがつと食べていく。その姿を見ながら、生き物が持つ食欲という命の根源的な力の、今までまったく気づかないでいた一面を思い知らされた夏の日の夜だったのです。
[2018.12.08 西インド、プシュカルにて]
☆有料部には何もありません。投げ銭として購入していただけたら跳び上がって大喜びします。
いつもサポートありがとうございます。みなさんの100円のサポートによって、こちらインドでは約2kgのバナナを買うことができます。これは絶滅危惧種としべえザウルス1匹を2-3日養うことができる量になります。缶コーヒーひと缶を飲んだつもりになって、ぜひともサポートをご検討ください♬