
「TECHNOLOGY POPS的」80年代アルバム/曲ベスト30(性懲りもなく参加してみました)【後編:楽曲編③10位〜1位・終】
この80年代アルバム/曲ベストランキング企画にわざわざ投票するということには理由があります。このTwitter上での投票企画に参加する音楽マニアの方は恐らくほとんどが自分よりも10歳以上は下の世代(なかには80年代リアルタイム世代もいるようですが)で、ジャンルとすれば洋楽中心、しかも恐らく専門は90年代という方が多いような印象がありました(アルバム編の投票結果を見た印象です)。また、ミュージックマガジンやレコードコレクターズ、ロッキンオンなどの音楽雑誌の選盤に大きな影響を受けていて、その視点でサブスクでも漁るでしょうから、意外と票が偏るものなんだなあ・・という感想を持ってしまいます。個人的には1989年は80年代ではないよな、という偏見もいいところの持論がありますので、ただ1年の平成である1989年の作品が多くランクインしていたことには驚いた次第です。
当方が今回選びましたアルバムや楽曲は当然ほとんどが入らないことは承知の上ですが、どうやら今回の投票に参加された皆様とはパラレルワールドの80年代を過ごしていたようです。ということも予想通りでして、こうした現在(ネット上での)主流?の音楽マニア達との距離感を確認するための必要な作業なのです。独特のランキングかもしれませんが、自身半径10m以内の世界では80年代とはそういう空気であるということと、皆さんご存知の楽曲にもかかわらずここで選ぶことには理由があるということを理解していただければ本望かと思います。
ということで、ラストのベストテンカウントダウンです。
10位:「Samurai」
Michael Cretu(1985)
(シングル「Samurai」収録)
作詞:Richard Palmer-James 作曲:Michael Cretu
Vocals・Keyboards・Electric Drums・Drum Programming:Michael Cretu
Sax:Christian Felke
Producer:Michael Cretu・Armand Volker
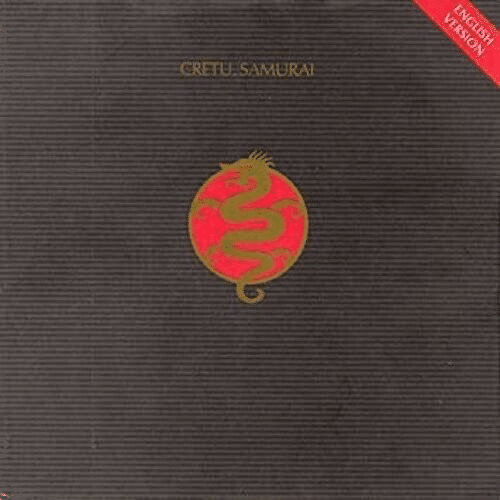
ルーマニアのスターEnigmaことMichael Cretuについては先日の非英語圏オールタイムベストでも取り上げましたので、ここでは生い立ちやディスコグラフィなどは割愛させていただきますが、彼はやはりどうしても外せない名曲を残しておりますので、ベスト10に選出させていただきました。1985年リリースのシングル「Samurai」です。英米では語るほどの売上ではありませんでしたが、英米以外の欧州諸国では何故かウケたようで、ギリシャでの第1位のほか、スイスで2位、オーストリアで3位、イタリアとスウェーデンで4位、フィンランドで5位となんとなく北欧やドイツ圏(ドイツでは惜しくも12位)、イタリアといったシンセポップ好きな国々においてトップ5に入る大ヒット曲で、しかも日本語の「サムライ!サムライ!」と連呼するものですから、日本人の耳にもどうしても馴染み深く届いていたポップソングでした。当時Michael Cretuは本当に日本にハマっていたようで、自身がプロデュースしたドイツのガールズヴォーカルグループArabesqueの1人・SandraのソロシングルはAlphavilleのカバー「Big in Japan」(Japan ist weit)でしたし、1990年にはDavid Morganのカバー「Hiroshima」でヒットに導き、98年にはこの「Samurai」もカバーさせるなど、Sandraをダシに日本をテーマにした楽曲を次々と蘇らせていました。
とはいえ肝心の楽曲やサウンドは安易にオリエンタリズムやジャパネスクを感じさせない硬派な仕上がりとなっています。イントロでは場末の酒場的なサックスでムード歌謡のような雰囲気を醸し出したかと思えば、突然のどデカイオケヒットの連打でシャキッと目覚めさせてくれます。その後歌がスタートするまではいなたいフレーズでイントロを進めていきますが、サウンド面で日本っぽさを出すというよりは、日本の流行歌や歌謡曲を意識したバタ臭さを感じさせるところが実に秀逸です。洋楽ですからね。そしてAメロが始まると今度は独特の加工されたスネアを中心とした打ち込むドラムパートがデジタル感を演出、歌とリズムが主役のAメロを進ませておいて、ここで日本刀のシャキーーンッ!という効果音を初めて使用してテーマを回収すると、これまたバタ臭いメロディのサビ、サムライの連呼が始まります。ここではモジャ毛にヒゲにデカサングラスのインパクト抜群なルックスのCretuが「アウア!アウア!」と熱唱するなど非常にパワフル。このとおりこの曲は楽曲を進める中での緩急のつけ方が絶妙で、それでいてサウンド面ではエレクトリック度を忘れておらず、いかにも85年ならではの音を出していたと思います。この洋楽らしからぬ歌謡度とどこかデジタル空気感は80年代になくてはならないサウンド風景ということで、いい加減にこのあたりの楽曲も再評価が進んでほしいと願っています。
9位:「Salty Lady」
中川勝彦(1984)
(アルバム「してみたい」収録)
作詞:微美杏里 作曲:NOBODY 編曲:白井良明
Vocal:中川勝彦
Guitar:白井良明
Bass:奈良敏博
Drums:かしぶち哲郎
Keyboards:岡田徹
Turntable:小野誠彦

今では中川翔子の父親というイメージの方が強いかもしれない若くして白血病で世を去った夭逝の貴公子・中川勝彦は、そのあまりのルックスの良さからヴィジュアル系に近い扱いをされていた時期もありましたが、晩年の音楽性を見てもわかるように彼は基本的にロックの人で、俳優や声優もこなしてはいましたが、シンガーとして生きていこうという意志ははっきりしていたと思われます。しかし前述のようにどうしてもルックスが良過ぎることから、1984年のデビュー時には既に沈静化しつつあったニューロマンティクスよもう一度の期待を背負わされたのかどうかはわかりませんが、デビュー曲「してみたい」ではド派手なメイクに煮え切らない哀愁メロディ、そしてアンニュイなE-bow風ギターフレーズによるニューウェーブ風味のサウンドでキャラクター形成がなされていました。
このサウンドメイクを任されていたのが当時実験的かつ挑戦的なサウンドで尖りに尖っていたムーンライダーズの白井良明と、気鋭のエンジニア小野誠彦(セイゲン・オノ)です。彼らはまだまだ未知数であった中川勝彦を肴にレコーディング実験をやりたい放題していくわけですが、その最たる楽曲が中川の1stアルバム「してみたい」収録の2曲目「Salty Lady」です。冒頭の電子リズムから微妙なヨレ具合とヒップホップという言葉もほとんど知られていない時代のスクラッチ(ターンテーブルを操作するのは小野誠彦)でいきなり怪しさ満点のスタートを切り、奈良敏博のベースはJAPANのコクを深くしたような胸焼けするフレーズを奏で、中川はウィスパーボイスで妖しげに歌う不思議ソングですが、極めつけは白井良明のギタープレイの音処理です。蚊が飛ぶような細く掠れるような音色を継続するフレージングなのですが、この独特の音色を生み出しているのはなんと糸電話(!)で、小野がレコーディングに糸電話を持ち込んで、ギター音を糸電話を通して録音することによってあの微妙なフレーズを表現しているのです。そのようなアヴァンギャルドな手法でエンジニアリングしながら、ターンテープルプレイによるスクラッチでリズムをフニャフニャにしたり、アウトロでは白井のギターソロと奈良のベースを尻目に一瞬ケチャのサンプリングを放り込むなど随所にハバネロをキメ込む小野誠彦の奇天烈な大活躍が堪能できる楽曲をどうして外すことができましょう。80年代きっての奇曲として「Salty Lady」をベストテンに文句なしにランクインさせました。
8位:「The Scene」
Sparks(1986)
(アルバム「Music That You Can Dance To」収録)
作詞・作曲:Ron Mael・Russell Mael
Vocals:Russell Mael
Fairlight CMI・Roland Jupiter-8・Yamaha DX7:Ron Mael
Endodyne Guitars・Roland Synthesizers・Backing Vocals:Bob Haag
Bass・Backing Vocals:Leslie Bohem
Drums:David Kendrick
Keyboards:John Thomas
Producer:Ron Mael・Russell Mael

SparksといえばRussell MaelとRon Maelの兄弟ユニットで、とにかく作風が目まぐるしく変わるカメレオンのようなロック&ポップスユニットです。1974年リリースの3rdアルバム「Kimono My House」や同年リリースの4thアルバム「Propaganda」のヒットによってトップアーティストとしての足がかりをつかみつつあった彼らが、マンネリズムを打破するためにサウンド面を全面的にリニューアルしたのが、Giorgio Moroderプロデュースによるミュンヘンディスコ全開エレクトロニクスサウンドの名盤(1979年リリース)「No. 1 in Heaven」でした。以降Sparksはシンセポップバンドとして80年代に突入し、「Terminal Jive」「Whomp That Sucker」「Angst in My Pants」「In Outer Space」「Pulling Rabbits Out of a Hat」(ここらへんはコミックバンドのようなジャケットデザインが多い)と1984年までに毎年のようにアルバムをリリースしていきます(ライブに電子楽器を持ち運びするのに面倒という理由で生バンドにこだわるようになりますが)。しかし例のようにとにかく数多く作品をリリースしていきますのでマンネリズムに陥るようになるにつれて売上も減少、80年代中盤から後半にかけてのSparksは一般的にはやや忘れられた存在になっていきます。
そのような中で「No. 1 in Heaven」のようなダンサブルな楽曲を集めてみようということで制作された1986年リリースのアルバムが「Music That You Can Dance To」です。Fairlight CMIの導入と、ベーシストのLeslie Bohem、ドラマーのDavid Kendrick(本作の後Devoに加入)を迎え4人体制を中心に作り上げられた本作は、音の質感がミドル80'sということもありまさにバキバキのエレクトロポップに仕上がっていますが、Sparksが愛されてきたゆえんのいわゆる「ひねくれ度」としては物足りなく、結果的には特に爪痕を残すことなく地味な作品として扱われています。しかしながら本作収録の中でひときわ光る楽曲がございまして、それが今回選出させていただきました「The Scene」です。タイトルの通りまさに映画のワンシーンを切り取ったようなドラマティックな展開を見せるこの楽曲は、大げさ過ぎるシンセオーケストレーションのイントロに騙されますが、ひとたびバッキバキのベースライン(リフレインがしつこい!)が始まればアップテンポのリズムとオーケストラルヒットの連発(無駄なパワーがしつこい!)で、Fairlight特有のゴリゴリ感を楽しめます。中盤で再びオーケストレーションが挟まって無音のブレイクの後からはサンプリングによるインダストリアルリズム(と粋なパーカッションパート)がスタートし、さらにゴリゴリ度が増していきます。その後はサビの連呼とオケヒットとバキバキベースで狂乱状態になりながらラストのオケヒット「ジャンッ!」でまとめ上げて6分のドラマが終焉を迎えます。アルバム中でもこの楽曲だけなぜか非常に力の入ったサウンドメイクになっていて、かつSparksのひねくれた「やりすぎ感」も堪能できるということで、(80年代中後期の彼らの作品はほぼ無視されがちな中で)隠れた存在ではありますが80年代のSparksきっての名曲ということで、再評価を求めたい楽曲の1つです。
7位:「No money No breath」
布施明(1985)
(アルバム「愛した女(ひと)たちのために」収録)
作詞:岩里祐穂 作曲・編曲:安西史孝
Vocal:布施明
Keyboards・Fairlight CMI:安西史孝

1970年代にヒットを飛ばした実力派の歌手達もしくは歌謡界のスター達は、80年代に入ると円熟期に入ってまいりますので、王道からは少し外れたような実験精神溢れる楽曲に挑戦していくようになります。沢田研二や郷ひろみはニューロマ&ニューウェーブに接近し、西城秀樹はエレクトロシティポップに目覚め角松敏生とコラボしたりといったところが代表的な例ですが、1965年のデビューから70年代にかけて、「霧の摩周湖」「シクラメンのかほり」「君は薔薇より美しい」といった大ヒット曲を歌ってきた声量オバケの布施明は、80年代に入っても古き良き昭和歌謡で勝負し続けていきますが、1985年のアルバム「愛した女(ひと)たちのために」で、突然お茶目な方向へ彼なりの実験精神を垣間見せることになります。このアルバムは前半と後半で全く趣向が変化する構成となっており、前半(A面)はなかにし礼の作詞・コンセプトによるラジオドラマのような女々しい男の歌謡組曲「愛した女たちへのバラード」ですが、問題は後半(B面)で布施明の概念からひっくり返すほどの爆弾のような楽曲が2曲提供されています。それが「成城婦人」と今回選出いたしました「No money No breath」の2曲です。この後半部分をプロデュースしたのが、前回の投稿でも取り上げましたつくば万博公式ソング「HOSHIMARUアッ!」を手掛けたFairlight音楽制作集団・TPOです(当時は既に天野正道と安西史孝の2名によるクリエイター集団となっていました)。布施明になぜTPOなのかと申しますと、2人になったTPOは当時はイメージアルバム関連等の日本コロムビア関連の仕事が多くなっていまして、加えて実は布施明と同じ事務所の同僚ということもあり、本作に抜擢されたということでした。クラシカルな素養がある天野正道は前半の組曲でもアレンジを手掛けていますが、後半のスタートを飾る「成城婦人」のアレンジも手掛けていて、その余りの過剰に盛り上げるFairlight CMIを駆使したアレンジと狂人と化した布施明の取り憑かれたような歌唱も相まって、突然変異の奇曲としてTVで披露された際には共演者を唖然とさせました。
当然今回の企画においても「成城婦人」を選出するかどうか最後まで悩みましたが、1アーティスト1曲縛りという自分ルールに準じて泣く泣く諦めて、もう1曲のキテレツソング「No money No breath」を選びました。この曲は「HOSHIMARUアッ!」と同じく安西史孝のニューウェーブ&プログレ風味がダダ漏れの楽曲で、よく布施明に歌わせたな・・とその後のイメージを心配させるほどのチャレンジングなFairlight歌謡です(「成城婦人」もそうなのですが)。Fairlight CMIによるサンプリング音とこれでもかと注ぎ込み、シーケンサー機能ページRを駆使したバッキバキのサウンドをバックに布施明が朗々と歌い上げるわけですが、これだけの歌の上手さにボイス変調をかますなどいい加減ファンに怒られるだろうというギミックが満載です。特に圧巻なのは間奏の長尺な高速早弾きシンセソロ(恐らく早回しのシーケンサー機能=Fairlight CMIのページR?)。一応歌謡アルバムの1曲のはずなのですが、ここまで狂ったキーボードソロは聴いたことがありません。脳髄が掻き回されるようなソロの後は自動車のブレーキ音サンプルで事故を起こしてしまうという制御不能な感じが、いかにも暴走特急という感じで面白くて仕方がありません。いくらなんでもやりすぎだろう・・・と思わせる安西史孝のマッドな側面を楽しむことができる貴重な楽曲ということで、当然のベストテン入りと言えるでしょう。80年代はこうした無茶苦茶な歌謡ポップスを布施明に歌わせることが許容されていた大らかな時代であったのです。
6位:「Twelfth House」
New Musik(1982)
(シングル「All You Need Is Love」収録)
作詞・作曲:Tony Mansfield
Vocals・Keyboards・Guitar:Tony Mansfield
Keyboards・Vocals:Clive Gates
Percussion・Vocals:Cliff Venner
Producer:Tony Mansfield

ここまでFairlight CMIを使用した名曲が続いておりますが、80年代の重要なサウンド革命の1つにサンプラーの登場を欠かすことはできません。特に80年代前半はサンプラーはまだまだ高価で、EmulatorやSynclavier、そしてFairlight CMIといったサンプリングキーボードはシンセサイザーでも創り得なかった最先端のサウンドを生み出すマシンとして音楽業界で瞬く間に重宝されていったのでした。その中でもFairlight CMIはサンプリングのみならずシーケンサーや倍音加算方式のシンセサイザーなど音楽制作を1台で完結させることができる総合音楽システムツールとして、当時の価格にして1200万円という超高価格で流通したにもかかわらず、多くのクリエイターたちがこぞって導入し、後年にAKAIやEnsoniqあたりが廉価版のサンプラーを普及させ、さらにKORG M1の登場によるPCM音源ロンプラーの普及により衰退していくまでに「時代の音」としてコアなリスナーを楽しませてきたのです。
英国のエレクトロポップバンドNew Muzikの中心人物・Tony MansfieldもFairlight CMIに魅せられたクリエイターの1人で、Fairlight流通当初から自身の制作環境に導入することで、2ndアルバムまでメロディセンスに秀でたギターポップを軸にしたシンセサウンドの使い方に定評があったNew Muzikの作風を全面的なエレクトロニクスの実験場に一変させました。バブルガムエレポップと称されたその人工甘味料的ポップスに昇華させたのが、1982年リリースの3rdアルバム「Warp」ですが、本作に先立ち前年にシングルカットされたのが言わずとしれたThe Beatlesのカバー「All You Need Is Love」で、そのB面であるアルバム未収録曲として収録された「Twelfth House」が今回の主役です。
Tony Mansfieldが彼のメロディセンスの贅を尽くして作曲したこの名曲はもちろんその哀愁のメロディラインだけでも心を打つものがありますが、まず英国のシンガーSteve Kentに楽曲提供され(こちらはTony Mansfield流エレクトロニクス寄りでNew Muzikバージョンに近い)、
さらに英国のソウルボーカルグループDelegationにも「12th House」としてカバーされます(こちらはメロディの良さとコーラスが生かされた哀愁ポップ寄り)。
この2曲ともそのロマンティック加減が絶妙な仕上がりになっていますが、Tony MansfieldみずからNew Muzikとしてリリースした完全版「Twelfth House」ではSIMMONSによりエレドラをフィーチャーしつつFairlight CMIのサンプラーをはじめとした斬新な機能を全面的に活用したまさにトニマン式人工甘味料ポップチューンの最高傑作に仕上がっており、前2曲も良い仕上がりなのですがやはり本家には敵わないといったところでしょう。Tony Mansfieldの相変わらずの滑舌抜群のボーカルも素晴らしく、後にプロデューサー業に転向する彼が手掛けた数々の作品(Naked Eyes、Captain Sensible、Mari Wilson、Vicious Pink、そしてa-ha etc)の源流としての名曲ですし、Tony Mansfieldは80年代の音楽シーンに欠かせないコンポーザー兼サウンドデザイナーであったということで、彼が関わった楽曲から今回はこの「Twelfth House」を挙げさせていただきました。
5位:「アリスの恋」
真璃子(1986)
(アルバム「真璃子」収録)
作詞:ありうべ雁子 作曲・編曲:山川恵津子
Vocal:真璃子
Guitar:今剛
Drums:宮崎まさひろ
Keyboards・Backing Vocals:山川恵津子
Backing Vocals:木戸やすひろ
Backing Vocals:比山貴咏史
Synthesizer Operator:松武秀樹

80年代後半の女性アイドルの中でも歌唱力には定評があった真璃子。苗字+名前が定番であった当時のアイドルの中でも名前だけ、そして瑠璃の「璃」という漢字を使用することでどこか不思議な雰囲気を醸し出していた彼女のデビュー曲が「私星伝説」(1986年)でした。山川恵津子の繊細なアレンジがHAMMERのシンセサイザープログラマー森達彦がThe Art Of Noiseな重厚ドラムと逆回転ストリングスのパッドでエレクトリック に仕立て上げたサウンドにより、メルヘンティック&ミステリアスな音空間を演出したこの1stシングルはインパクト十分で、このコンビは日本レコード大賞新人賞を獲得した「夢飛行」等の真璃子楽曲の強力なカラーとなっていきます。さて、同年には「私星伝説」が収録された1stアルバム「真璃子」がリリースされますが、10曲中7曲を山川恵津子がアレンジしており、「魔法の時間」のような「私星伝説」路線のファンタジー路線な佳曲も収録されてはいるものの、彼女の歌の上手さが方向性を迷わせていたのか、純粋な古き良き歌謡曲路線でいくのか、ミステリアス路線でいくのか、アルバム収録曲の中でもくっきり分かれてしまい、作品の出来としては散漫な印象を受けます。しかしながら、本作には圧倒的な存在感を放つ楽曲がラストに据えられています。それが今回選出させていただいた「アリスの恋」です。
これぞ真璃子ファンタジアの最たる楽曲とも言える「アリスの恋」(タイトルからしてファンタジー度全開)のサウンドを手掛けるのはもちろん山川恵津子なのですが、ここではプログラマーは森達彦ではなく大御所・松武秀樹です。いきなりのギラギラしてマジカルな山川自ら弾く印象的なシンセフレーズから始まり、木戸やすひろ&比山貴咏史(と山川)のコーラスと特徴的なクリアな音質のドラムが絡み合う見事な音像に引き込まれます。そして全編にわたりあのギラギラマジカルなシンセは異世界ストーリーを展開するかのごとく空間エフェクトを巧みに使いながら夢心地な世界へ誘っていくわけですが、圧巻なのは後半のCoda部分(アウトロ)から。それまでのシンセが前後左右から降ってくるような立体感が非常に気になっていたのですが、ラストからはサウンド全体にモジュレーションがかかりブラックホールへ引きずり込まれるようなミックスが施されています。これは原田真二&クライシスやチャゲ&飛鳥、THE ALPHA等の一癖あるエレクトロポップサウンドを手掛けてきたエンジニア・石塚良一の功績が大きいと思われますが、左右をパンするだけでなく奥行きまで移動しまくりヘッドフォンで聴くと脳髄を掻き回される感覚に襲われる音場に惑わされます。まだ5.1chバーチャルサラウンドといった概念が存在しない時代に、それに近いようなミックスで不思議音響を作り出していたのが、トップとは言えないアイドルのデビューアルバムという事実に驚愕を禁じ得ません。ということで、そのような画期的な楽曲を80年代ベストソングに挙げないわけにはいかないのです。是非5.1chバーチャルサラウンド対応ホームシアターで聴いてみたいです。
(なお、「アリスの恋」は1992年リリースのベストアルバム「The Best」にも収録されていますが、アウトロのMIXは微妙に異なっています。この1stアルバムの収録バージョンの方がより過激にモジュレートされています。)
4位:「Budapest By Blimp」
Thomas Dolby(1988)
(アルバム「Aliens Ate My Buick」収録)
作詞・作曲:Thomas Dolby
Vocals・Keyboards:Thomas Dolby
Guitar:Larry Treadwell
Synthesizer:Mike Kapitan
Bass:Terry Jackson
Drums:David Owens
Vocals・percussion:Laura Creamer
Backing Vocals:Lesley Fairbairn
Trombone:Bill Watrous
Congas:Arno Lucas
Hungarian aria:Csilla Kecskesi
Hungarian translation:Erica Kiss
Producer:Thomas Dolby・Bill Bottrell

1982年の1stアルバム「The Golden Age of Wireless」、そしてシングル「She Blinded Me With Science」が大ヒットとなり、エレクトロポップの新星として颯爽とスターダムに登場したThomas Dolbyですが、ソロシンガーとしての彼はエレポップにとどまらない幅広い音楽性の持ち主で、彼が標榜するミュージックワールドを表現する格好のツールが電子楽器であったということなのでしょう、彼は1984年の2ndアルバム「The Flat Earth」や坂本龍一との共作「Field Work」等決して多作とはいえない作品をリリースし続けるにつれて、ファンク色を強めるなどマッチョな作風に徐々に変化していきます。一方ややスターダムから一歩引き始めた彼の名前が再び脚光を浴びるようになったのが、Prefab Sproutの2ndアルバム「Steve McQueen」のプロデュースで、瑞々しいネオアコメロディアス楽曲が魅力であったPrefab Sproutに繊細なエレクトロニクスを導入したサウンドデザインは現在もなお高く評価されています。
このようにプロデューサーとしてもその才能を発揮し始めていたThomas Dolbyはソロシンガーとしての3rdアルバム「Aliens Ate My Buick」を1988年にリリースします。本作は前2作のストイックなエレクトロポップから進化して、エレクトロニクスの使い方は当然センス溢れるものの、ダンディかつファンクに傾倒したかのような生演奏中心の肉感的な(マッチョな)仕上がりで、実は役になりきるタイプのThomas Dolbyの新境地といった作品でした。しかし、本作の中で異質にして究極のバラードと言える楽曲が最後に収録されています。それが本企画の第4位、洋楽第2位の「Budapest By Blimp(邦題:霧の浮かぶ街、ブダペスト)」です。
ファンク色の強い本作の中にあって「Budapest By Blimp」はPrefab Sproutのプロデュースの経験をそのまま移行してきたような美しいコード展開によるバラードソング、しかも8分を超える長尺の大作に仕上げているわけですが、この繊細なエレピによるコードワークは前述の「Steve McQueen」に収録されている「Desire As」を彷彿とさせるものです。Blimp(飛行船)がテーマということですので、全体的に浮遊感漂うシンセサイザーサウンドに彩られており、そこにDolbyの囁くようなボーカルが絡みます。2周目のBメロからはこの楽曲のもう1つのテーマであるハンガリーの首都ブダペストを表現するハンガリアンボイスによるアリアを、ハンガリー人Csilla Kecskesiに独唱させるこだわりようですが、Cパートではサンプリングボイス連呼からのタイトルコールで締める構成は見事というほかありません。曲が進行するにつれて少しずつパートが増えていき、アリアも言葉を持つようになり、中盤では躍動感のあるファンキーな演奏に移行する部分はPrefab Sproutにはなかった要素です。この中盤に見せる激しさは8分もの楽曲の中では一瞬の輝きといった風情で、その他は淡々としたリズムにコードを奏でるエレピ&浮遊するシンセおよびエフェクティブ処理を中心に流れていきますが、ラストの大人数アリア&疑似コンサートホールの臨場感でエンディングを迎えるといった様々な趣向を凝らしていることもあり、Thomas Dolbyという希有なアーティストの奥深さといいますか、底知れないセンスを感じる最高傑作であると思います。現に近年のライブパフォーマンス(上記の動画)をご覧いただいても理解していただけると思いますが、すっかり頭もツルツルになったDolbyの独演というスタイルでも、その見事なリアレンジと構成力&パフォーマンスには脱帽しかありません(ツルツルなだけに)。リアレンジしてもその魅力を決して失わない名曲なのです。
3位:「セシールの雨傘」
飯島真理(1985)
(シングル「セシールの雨傘」収録)
作詞:松本隆 作曲:飯島真理 編曲:清水信之
Vocal:飯島真理
Guitar:土方隆行
Bass:富倉安生
Drums:山木秀夫
Keyboards・Programming:清水信之
Chorus:EPO
Chorus:杉真理

常々飯島真理と最も相性が良かったアレンジャーは清水信之であると思っております。1stアルバム「Rosé」は坂本龍一がサウンドプロデュースを手掛けましたが、皆が認めるクオリティの高い名盤とはいえYamaha DX7を使用した独特の輪郭を持つ音ということもあり特殊性が高く、2ndアルバム「blanche」の吉田美奈子アレンジに至っては弱冠21歳と若かった飯島にとってはやや前作とのギャップもあって背伸びしすぎた仕上がりで、この1983年〜84年初頭にかけての2枚のアルバムが微妙に飯島の音楽性にはマッチしていなかったのではないかと今さらながら思い返しているのですが、1985年リリースの3rdアルバム「midori」を担当した清水信之は、その繊細で艶やかなエレクトリックサウンドが等身大の飯島真理楽曲を投影するのに最適解であったことを証明するような素晴らしいアレンジメントで、ようやく飯島はデビュー当初からの萎縮した印象から脱却を図ることができたのでした。奇しくも当時は飯島本人が余り良い印象を持っていなかった1984年の大ヒット曲である劇場アニメ「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」主題歌「愛・おぼえていますか」や「天使の絵の具」は清水信之アレンジでしたが、このヒットには人気アニメのタイアップという要因もあったと思われますが、清水信之サウンドとの相性の良さも影響していると個人的には感じています。
1984年にはシングル「1グラムの幸福」もTVクイズ番組「わくわく動物ランド」のテーマソングとしてタイアップ、清水アレンジのこの楽曲はお茶の間にも知られる存在となりましたが、前述の3rdアルバム「midori」を経た後の5thシングル「セシールの雨傘」は、清水信之コラボレーションのラストにして彼女の最高傑作との呼び声も高い名曲として語り継がれています。エレガントな「midori」のサウンドとは似つかわしくない重厚なドラムがイントロから響き渡る重い空気の中スタートしますが、飯島真理渾身の切なさと哀愁を帯びたメロディとストーリー性を感じさせる80年代きっての作詞家・松本隆の職人ぶりが際立つ楽曲ということで、全体を帯びる雰囲気作りが半端ではありません。サスペンスタッチのリフをバックにしたBメロからこちらも重厚なフィルインでサビに移ると、繊細な細かい譜割の下降するシーケンス(雨を表現?)とキレの良いギターのカッティングに幻想的なフレーズでメロディを橋渡しするなど手の込んだアレンジを聴かせてくれます。そして何といってもCメロの"パンフレット"の高音が秀逸で、そこから後半のサビに向けての転換点となる豪快なギュルルンフィルインが唐突ながらも場面転換としての効果が抜群。こうしてクライマックスは哀愁のメロディで最後まで押し切っていきます。メロディとサウンドが高次元でマッチングしつつ映画のワンシーンのような物語が完結する奇跡の楽曲が、この「セシールの雨傘」です。間違いなく80年代を代表する名曲と言えるでしょう。
なお、この楽曲は飯島本人も気に入っているのか数回リアレンジされてセルフリメイクされますが、どれもがオリジナルアレンジには到底及びません。このシングルバージョンでしか成し得ないマジックがあるのです。
(下記のライブバージョンはギリギリ合格点でしょうか。)
2位:「Another Day, Another Ray Of Hope」
Bill Nelson(1983)
(ミニアルバム「Chimera」収録)
作詞・作曲:Bill Nelson
Vocals・E-Bow Guitar・Synthesizer・Piano・Bass・Drum Computer:Bill Nelson
Percussion・Tom Tom:Preston Hayman
Producer:Bill Nelson
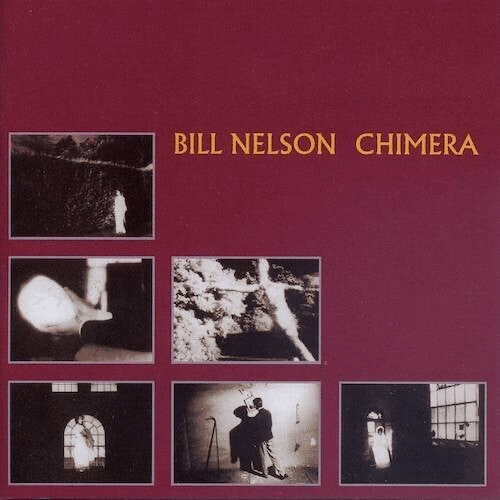
個人的な感想ですが、80年代において最も再評価されていないギタリストはBill Nelsonなのではないかと思っています。Bill Nelsonといえば高橋幸宏の1982年の4thアルバム「What Me Worry?」への参加を皮切りに、1983年にはYMOのテクノ歌謡化アルバム「浮気のぼくら」や再び高橋幸宏の5thアルバム「薔薇色の明日」のレコーディングに参加するとともに、高橋のライブツアーメンバーとしても活躍するなど、日本人とのコラボレーションに積極的なギタリストというイメージが強いのですが、もともとは先鋭的なグラムロック→ニューウェーブバンドBe Bop Deluxeのフロントマンであり、過激なテクノパンクとして名盤「Sound On Sound」を残したBill Nelson's Red Noiseとして、そしてそれらの実験的ポップサウンドを昇華すべく自主制作レーベルCocteau Recordsを設立し数々のソロアルバムをリリースするなど、ギタリストとしてだけでなく、非常に精力的に活動を続けてきた一流のアーティストです。
とはいえ、80年代前半のBill Nelsonの作風に多大な影響を与えたのは高橋幸宏との共同作業でした。それは特にコンポーズの面において顕著でして、シンセポップ転向後も良くも悪くもグラムロック感が抜けなかったBill Nelsonが、前述の「What Me Worry?」への参加を契機にシンセサイザーの使い方やリズムワーク等全体的にブラッシュアップされ、特に非常にポップなメロディを書けるようになりました。その傾向は本企画のアルバム編でもランクインした「The Love That Whirls (Diary of A Thinking Heart)」に集約されるわけですが、1983年にはさらに高橋幸宏~YMO的路線を推し進めたBill Nelsonもう1枚の傑作ミニアルバム「Chimera」がリリースされます。高橋幸宏や松武秀樹が全面的に参加するとともに、JAPANのMick Karnとのコラボにも挑んだ6曲という少ない収録曲の中でも濃い内容の作品に仕上がっている本作の最後に、Bill NelsonがBill Nelsonたるゆえんともいうべき、珠玉の名曲「Another Day, Another Ray Of Hope」は収録されています。本企画の第2位、洋楽としての第1位としてこの楽曲を推したいと思います。
アルバム編でも申し上げましたが、Bill NelsonといえばE-Bow、E-BowといえばBill Nelsonと言われるほど彼の代名詞となっている電磁的磁気共鳴装置E-Bowによる半永続的にサスティンを流し続けるギタープレイがこの楽曲ほど堪能できることはまずないでしょう。天空から降りてくるようなE-Bowフレーズからスタートし、バスドラ(キック)を連打するようにプログラミングされたTR-808リズムマシンに乗ったスピード感を備える究極のシンセポップで、高音で推移する開放感溢れるメロディラインと軽快なリズムのシンプルな音像が鮮やかですが、やはり圧巻なのは後半で、E-Bowソロのアウトロから怒涛のようになだれ込んでくるゲートタムのフィルインが実に豪快で気持ち良さ抜群です。好き放題に叩き続けられるフィルインに天上を浮遊するようなE-Bowの響きは余りに神々しく、その永続的に途切れない滑らかに上下する音程に魅了されることこの上ありません。こういったプレイこそBill Nelsonの唯一無二の武器であり、80年代音楽シーンの象徴として記憶に残すべきサウンドアイコンであると主張したいです。
この貴重なライブ音源では彼の生のE-Bow演奏がたっぷり堪能できます。ラスト2分ほどは最後まで一度も音を途切れさせることなく持続させながら音階を操るソロプレイを披露、この独特なサウンドは彼でしか出せない音です。現在でも国内外でE-Bow奏法を披露するプレイヤーは存在しますが、ここまで大胆に、しかも効果的に楽曲とマッチさせながらE-Bowを操るギタリストはBill Nelsonただ1人でしょう。どれほど速弾きしようとも味のある演奏テクニックを披露しようとも、彼が発明したこのE-Bowプレイと比べればそれらは色褪せて聴こえます。故に当方にとっての80年代最高のギタリストはBill Nelsonしかあり得ないのです。そんな彼に敬意を表して洋楽としての楽曲編1位の座を贈りたいと思います。
1位:「ランニング・ショット」
柴田恭兵(1986)
(シングル「ランニング・ショット」収録)
作詞:吉松隆・門間裕 作曲・編曲:吉松隆
Vocal:柴田恭兵
Guitar:松原正樹
Bass:美久月千晴
Drums:青山純
Keyboards:富樫春生
percussions:浜口茂外也
Chorus:EVE
Programming:浦田恵司

ここまで前編・中編・後編と全3回にわたって結局長々と選出理由やポイントについて解説してまいりましたが、第1位が皆様が良く知っておられるネタ曲と言われるこの楽曲かい!と思われるかもしれません。しかし個人的には(国内外を含めて)80年代を最も代表する名曲と捉えていますし、その強い推薦に耐え得る最高のクオリティと斬新な構成力、そして究極のダンディズムを兼ね備えた、それでいて他者が決して真似のできないパフォーマンスを引き出した、10年に1曲とも言えるミラクルなポップチューンであるということを、いま一度皆様にも再認識していただき、音楽史の記憶の片隅に残していただきたいと願いまして、今回の企画のトリを飾らせていただきたいと思います。
和製ロック・ミュージカル劇団「東京キッドプラザーズ」の看板俳優であった柴田恭兵は、70年代後半にはTVドラマへ進出、1979年放映の「俺たちは天使だ!」のダーツ役で人気を博すと、以降ドラマや映画が主戦場となっていきます。そのかたわらロックミュージカル俳優出身ということもあり、早くから歌手活動も始めており、東京キッドプラザーズ関連でリリースした数枚シングルのほかに、1979年に主演ドラマ「赤い嵐」主題歌「5マイル・アヘッド」を柴田恭兵名義でリリース、ソロ歌手としてのデビューを果たします。そして1981年には田中康夫のベストセラー小説を田中自身が歌詞にして近田春夫が曲を書いた「なんとなく、クリスタル」をリリース(同名映画の主題歌ではありません。イメージソング的な扱い? なお、ヒロインかとうかずこの相手役は作曲家の亀井登志夫)、この楽曲がスマッシュヒットとなり早くも柴田は歌手としても一躍脚光を浴びることになります。
しかしそれから柴田は一旦歌手活動を停止し、本業である俳優業へ邁進していくことになります。その間に柴田は映画初主演を果たしますが、その映画が1984年配給の東宝映画「チ・ン・ピ・ラ」です(ジョニー大倉との共演)。この映画にピンと来た方もいらっしゃると思いますが、同映画の主題歌はあの超絶技巧ニューウェーブバンド・PINKの2ndシングル「Private Story」で(タイアップの関係で曲タイトルを「チ・ン・ピ・ラ」に決定されそうになり、PINKのメンバーが必死に抵抗したという逸話あり)、はからずも柴田がニューウェーブに接近していたともいえるエピソードとして頭の片隅に置いておいて損はないかと思います。
閑話休題ということで、柴田恭兵の俳優としての大きな転機が1986年に訪れます。あの大ヒット刑事ドラマシリーズ「あぶない刑事(デカ)」の大下勇次(ユージ)役への抜擢です。舘ひろしとのW主演による軽妙なコメディ要素もあり、かつアクション性にも富んだこのドラマは一大ブームとなり、柴田も一気に俳優としてブレイクを果たしました。そのような絶頂期にあって、「あぶない刑事」挿入歌として好評であったユージのテーマソングが、遂に5年ぶりの柴田恭兵名義のシングルレコードとしてリリースされることになりました。それが、80年代を代表するアヴァンギャルドな歌謡POPSの金字塔である「ランニング・ショット」です。
まず楽曲の構造が異質です。「レディ!」の掛け声からゲートの効いたバスドラが8分音符で1、2、3、4、5、6、7と刻まれて8回目で「アクション!」と柴田がコール。ここから軽やかなオルガンのリフとギターのカッティングに合わせてねちっこいスラップベースでファンキーな空間に一気に引き込んでいきます。ここにきてもリズムは8分バスドラにスネアの代替となるハンドクラップ、そしてフィルインとしてゲートタムと共にダンッダン!というスネア、これがほぼ延々と続いていきます(フィルイン代わりにスネアが使用される部分が珍しい)。それがAメロに至るまでのイントロと思いきや実はこのリフがAメロのバッキングでして、そのリフのまま柴田が歌を重ねていきます。その自然な歌の入り方は誰も気づかない死角に入ってくるヒットマンのようです。そして転換場面のBメロからやっと普通に歌モノらしくなるのですが、これがサビへの前振りとだけしか機能しておらず、「いくぜっ!」(ドコドコドコのゲートタム入り)のコールでいよいよサビに移行します。しかしこのサビが非常に厄介で、EVEらしいいかがわしさを同胞したコーラスで盛り上げたかと思えば、柴田はいつまでたっても「ハッ!」やら「オーイェー」やら「ウ〜〜ン」やら「テイコン!」やらの相槌を打つばかりで一向に歌う気配がありません(実質はEVEに合わせて何か歌っているのですがEVEのコーラスの圧が強いため柴田ボイスが完全にカブっているのです)。するとサビの最後になってやっとこさ「時のゆくまま〜♪(棒読み)」で何事もなかったようなアリバイ工作を完結する厚かましさ。完璧な演奏陣のテクニカルなプレイにどうしても耳が行ってしまいますが、楽曲としては初聴では呆気にとられてしまうでしょう。
基本はこの構成で続いていくこの不思議な楽曲ですが、1周目サビと2周目入りまでには短めの1stギターソロが、2周目サビの終わりからは柴田の渋い台詞回しと共にテクニカルな長めのギターソロでダンディズムを演出、そこから3周目のBメロに移るわけですが、ここではEVEのコーラスが壁のように鳴り響き最後のサビまでしっかりと盛り上げてくれます。そこからはもうお祭り騒ぎで、柴田という上級国民が周囲を煽るだけ煽って演奏陣はギターソロも含めて最高のプレイを繰り広げ、EVEは白目を剥きながら半狂乱で「トゥルットゥルットゥルットゥルットゥルッ」「リッスンベイベ〜〜!」と叫び出す始末。にもかかわらず最後には「時のゆくまま〜♪(棒読み)」で何事もなかったように(賢者モードで)真顔で締めにかかり強引に現実の世界へ引き戻されます。このわけのわからない状況をどのように表現すればよいか難しいのですが、個人的には世界のナベアツの「3がつく数字と3の倍数の時だけアホになる」というギャグを思い出してしまいます。特に30以降のアホになり続けるお祭り状態からの「40〜」のドヤ顔ですね。この「40〜」が「時のゆくまま〜♪(棒読み)」というわけです(もう自分でも何を言ってるのかさっぱりわかりません)。
なお、ラストはEVEの1人の「ア〜〜」のため息からバスドラが1、2、3、4、5、6、7と刻まれて「カット!」でエンディング。聴けば聴くほど斬新です。
このストレンジかつエキサイティングな楽曲を制作したのが吉松隆です。交響楽や協奏曲を多く手がけるバリバリのクラシック音楽家であると同時に、EL&P大好きのプログレッシブロックマニアでもある吉松がポップス作品を手掛けることは現在でもほとんどなく、前述のプログレフリークが高じてロックナンバーをクラシック風にリメイクしたりマッシュアップすることはあっても、ロック&ポップス、ましてや俳優ソング(歌謡曲)を作編曲するなんてことは奇跡に近いわけです。そのような中でも柴田恭兵には(ツテがあるのか)何曲か提供をしているようですが、「ランニング・ショット」のようなエレクトロファンクを軸にしたアヴァンギャルドポップスを手掛けたのは後にも先にもこの曲だけでしょう。しかしこの1曲だけでもプログレとクラシックを素養とした前衛精神が凝縮された吉松隆という稀代の作曲家の底知れない才能は火を見るより明らかであると思います。既存のフォーマットにとらわれない自由な発想力の勝利であると言えるでしょう。
こちらは歌番組バージョンです。リズムはSIMMONSの乱れ打ちに差し替えられていますが、これもアプローチとしては間違いないと思います。なお、このバックバンドの2人のギタリストのうち、カッティング中心のプレイと1stギターソロを弾いていた右側のギタリストは、当時KEDGEでデビュー前の修行時代であった、皆さん大好きな現在の音楽シーンを代表する作編曲家・冨田恵一です。彼は柴田恭兵バンドのほかにも(2ndアルバムリリース時期の)種ともこバンドのギターも担当していました。
これはライブバージョンにして高速スキップによる華麗な入場シーンが有名な動画ですね。パーカッションやブラスセクション、そしてまともなドラムが加わって格段に演奏がゴージャスになっています。ここまでくるとオリジナルのイビツさがなくなって寂しい思いもありますが、ダンサブルを好む方にはこちらの方が燃え上がるでしょう。
ちなみに「ランニング・ショット」はその名曲たるがゆえんなのか、人気ドラマ→映画のタイアップなのか、いくつものバージョンでリメイクされています。上記の動画では3バージョンを聴くことができます。1曲目がオリジナルバージョン、2曲目の1998年の"SHOT GUN MIX"はトレンドに合わせてドラムンベース風味にBPMを上げた高速バージョンに料理されています。アレンジは浅倉大介仕事のエンジニアでもある大里正毅でした。3曲目は2016年の柴田恭兵 feat. T.NAKAMURA,SENRI KAWAGUCHI&SHIGEO NAKAバージョン。エレピによるコードワークでジャジーに仕上げていますが、これもスピード感溢れるリメイクとなっています。確かに「ランニング」ですからスピードを求めたくなるのもわかるのですが、やはりオリジナルの腰の据わったリズムによる8分音符の魅力には勝てないと思います。
そのようなわけで1986年のオリジナル「ランニング・ショット」、この楽曲を本企画のNo.1ソングとさせていただきます。80年代にはもちろん今回挙げさせていただいた楽曲のほかにも名曲は数多くありますし、意図的に外している楽曲もありますので、「本気で」で80年代ベストを選出する際には独自でいつかやりたいとは思います。今回は多くの(特に洋楽ファンの多い)音楽マニアの方々に混じってということで多少独自性も意識しましたが、80年代として外せない楽曲を多く紹介することができましたので、ある程度の満足を得ることができました。改めまして本企画を進めていただきましたJMXさんに敬意を表して、本稿を締めさせていただきます。どうもありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
