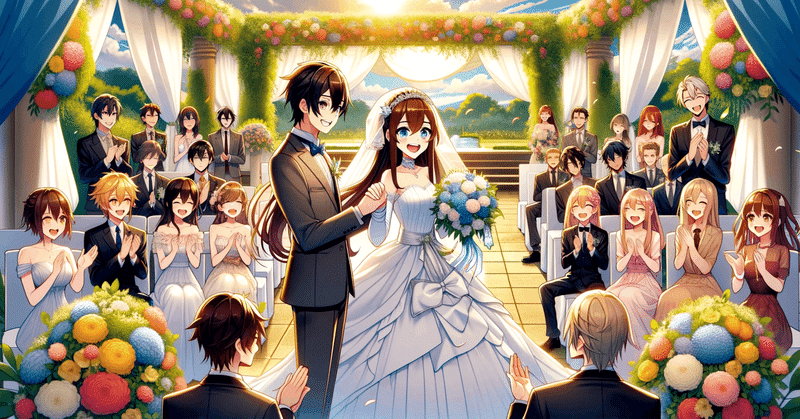
再婚禁止事件
こんにちは。
今日は、女性だけに設けられた再婚禁止期間が憲法上の男女平等に違反するかどうかが問題となった最大判平成27年12月16日を紹介したいと思います。
1 どんな事件だったのか
前夫と離婚した女性が、別の男性と結婚しようとしたところ、民法が定める6か月間の再婚禁止により、再婚の時期が遅れてしまいました。女性は、再婚の遅れによって精神的な苦痛を受けたとして、女性にだけ再婚禁止期間があるのは憲法上の男女平等などに違反していることを理由に、国に対して165万円の損害賠償を求めて提訴しました。
2 最高裁判所大法廷判決
憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。そして、本件規定は、女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から6箇月の再婚禁止期間を定めており、これによって、再婚をする際の要件に関し男性と女性とを区別しているから、このような区別をすることが事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものと認められない場合には、本件規定は憲法14条1項に違反することになると解するのが相当である。ところで、婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係につい ての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって、その内容の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は、このような観点から、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。また、同条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定しており、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は、これにより、配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか、近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると、上記のような婚姻をするについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる。そうすると、婚姻制度に関わる立法として、婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっている本件規定については、その合理的な根拠の有無について以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で検討をすることが必要である。そこで、本件においては、上記の考え方に基づき、本件規定が再婚をする際の要件に関し男女の区別をしていることにつき、そのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容が上記の立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から憲法適合性の審査を行うのが相当である。
昭和22年の民法の一部改正により、旧民法における婚姻及び家族に関する規定は、憲法24条2項で婚姻及び家族に関する事項について法律が個人の尊厳及び両性の本質的平等に立脚して制定されるべきことが示されたことに伴って大幅に変更され、憲法の趣旨に沿わない「家」制度が廃止されるとともに、上記の立法上の指針に沿うように、妻の無能力の規定の廃止など夫婦の平等を図り、父母が対等な立場から共同で親権を行使することを認めるなどの内容に改められた。その中で、女性についてのみ再婚禁止期間を定めた旧民法767条1項の「女は前婚の解消又は取消の日より六カ月を経過したる後に非ざれば再婚を為すことを得ず」との規定及び同条2項の「女の前婚の解消又は取消の前より懐胎したる場合に於ては其分娩の日より前項の規定を適用せず」との規定は、父性の推定に関する旧民法820条1項の「妻が婚姻中に懐胎したる子は夫の子と推定す」との規定及び 同条2項の「婚姻成立の日より200日後又は婚姻の解消若くは取消の日より300日内に生れたる子は婚姻中に懐胎したるものと推定す」との規定と共に、現行の民法にそのまま引き継がれた。現行の民法は、嫡出親子関係について、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し(民法772条1項)、夫において子が嫡出であることを否認するためには嫡出否認の訴えによらなければならず(同法775条)、この訴えは夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(同法777条)と規定して、 父性の推定の仕組みを設けており、これによって法律上の父子関係を早期に定めることが可能となっている。しかるところ、上記の仕組みの下において、女性が前婚の解消等の日から間もなく再婚をし、子を出産した場合においては、その子の父が前夫であるか後夫であるかが直ちに定まらない事態が生じ得るのであって、そのために父子関係をめぐる紛争が生ずるとすれば、そのことが子の利益に反するものであることはいうまでもない。 民法733条2項は、女性が前婚の解消等の前から懐胎していた場合には、その出産の日から本件規定の適用がない旨を規定して、再婚後に前夫の子との推定が働く子が生まれない場合を再婚禁止の除外事由として定めており、また、同法773条は、本件規定に違反して再婚をした女性が出産した場合において、同法772条の父性の推定の規定によりその子の父を定めることができないときは裁判所がこれを定めることを規定して、父性の推定が重複した場合の父子関係確定のための手続を設けている。これらの民法の規定は、本件規定が父性の推定の重複を避けるために規定されたものであることを前提にしたものと解される。以上のような立法の経緯及び嫡出親子関係等に関する民法の規定中における本件規定の位置付けからすると、本件規定の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解するのが相当であり、父子関係が早期に明確となることの重要性に鑑みると、このような立法目的には合理性を認めることができる。これに対し、仮に父性の推定が重複しても、父を定めることを目的とする訴え(民法773条)の適用対象を広げることにより、子の父を確定することは容易にできるから、必ずしも女性に対する再婚の禁止によって父性の推定の重複を回避する必要性はないという指摘があるところである。
確かに、近年の医療や科学技術の発達により、DNA検査技術が進歩し、安価に、身体に対する侵襲を伴うこともなく、極めて高い確率で生物学上の親子関係を肯定し、又は否定することができるようになったことは公知の事実である。しかし、そのように父子関係の確定を科学的な判定に委ねることとする場合には、父性の推定が重複する期間内に生まれた子は、一定の裁判手続等を経るまで法律上の父が未定の子として取り扱わざるを得ず、その手続を経なければ法律上の父を確定できない状態に置かれることになる。生まれてくる子にとって、法律上の父を確定できない状態が一定期間継続することにより種々の影響が生じ得ることを考慮すれば、子の利益の観点から、上記のような法律上の父を確定するための裁判手続等を経るまでもなく、そもそも父性の推定が重複することを回避するための制度を維持することに合理性が認められるというべきである。
そうすると、次に、女性についてのみ6箇月の再婚禁止期間を設けている本件規定が立法目的との関連において上記の趣旨にかなう合理性を有すると評価できるものであるか否かが問題となる。
上記のとおり、本件規定の立法目的は、父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解されるところ、民法772条2項は、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取 消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定して、出産の時期から逆算して懐胎の時期を推定し、その結果婚姻中に懐胎したものと推定される子について、同条1項が「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定している。そうすると、女性の再婚後に生まれる子については、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の推定の重複が回避されることになる。夫婦間の子が嫡出子となることは婚姻による重要な効果であるところ、嫡出子について出産の時期を起点とする明確で画一的な基準から父性を推定し、父子関係を早期に定めて子の身分関係の法的安定を図る仕組みが設けられた趣旨に鑑みれば、父性の推定の重複を避けるため上記の100日について一律に女性の再婚を制約することは、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められ る合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、上記立法目的との関連において合理性を有するものということができる。よって、本件規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項にも、憲法24条2項にも違反するものではない。
これに対し、本件規定のうち100日超過部分については、民法772条の定める父性の推定の重複を回避するために必要な期間ということはできない。旧民法767条1項において再婚禁止期間が6箇月と定められたことの根拠について、旧民法起草時の立案担当者の説明等からすると、その当時は、専門家でも懐胎後6箇月程度経たないと懐胎の有無を確定することが困難であり、父子関係を確定するための医療や科学技術も未発達であった状況の下において、再婚後に前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不和を避けるという観点や、再婚後に生まれる子の父子関係が争われる事態を減らすことによって、父性の判定を誤り血統に混乱が生ずることを避けるという観点から、再婚禁止期間を厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間に限定せず、一定の期間の幅を設けようとしたものであったことがうかがわれる。また、諸外国の法律において10箇月の再婚禁止期間を定める例がみられたという事情も影響している可能性がある。上記のような旧民法起草時における諸事情に鑑みると、再婚禁止期間を厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間に限定せず、一定の期間の幅を設けることが父子関係をめぐる紛争を未然に防止することにつながるという考え方にも理解し得る面があり、このような考え方に基づき再婚禁止期間を6箇月と定めたことが不合理であったとはいい難い。このことは、再婚禁止期間の規定が旧民法から現行の民法に引き継がれた後においても同様であり、その当時においては、国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものであったとまでいうことはできない。しかし、その後、医療や科学技術が発達した今日においては、上記のような各観点から、再婚禁止期間を厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間に限定せず、一定の期間の幅を設けることを正当化することは困難になったといわざるを得ない。加えて、昭和22年民法改正以降、我が国においては、社会状況及び経済状況の変化に伴い婚姻及び家族の実態が変化し、特に平成期に入った後においては、晩婚化が進む一方で、離婚件数及び再婚件数が増加するなど、再婚をすることについて の制約をできる限り少なくするという要請が高まっている事情も認めることができる。また、かつては再婚禁止期間を定めていた諸外国が徐々にこれを廃止する立法をする傾向にあり、ドイツにおいては1998年(平成10年)施行の「親子法改革法」により、フランスにおいては2005年(平成17年)施行の「離婚に関する2004年5月26日の法律」により、いずれも再婚禁止期間の制度を廃止するに至っており、世界的には再婚禁止期間を設けない国が多くなっていることも公知の事実である。それぞれの国において婚姻の解消や父子関係の確定等に係る制度が異なるものである以上、その一部である再婚禁止期間に係る諸外国の立法の動向は、我が国における再婚禁止期間の制度の評価に直ちに影響を及ぼすものとはいえないが、再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという要請が高まっていることを示す事情の一つとなり得るものである。そして、上記のとおり、婚姻をするについての自由が憲法24条1項の規定の趣旨に照らし十分尊重されるべきものであることや妻が婚姻前から懐胎していた子を産むことは再婚の場合に限られないことをも考慮すれば、再婚の場合に限って、前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不和を避けるという観点や、婚姻後に生まれる子の父子関係が争われる事態を減らすことによって、父性の判定を誤り血統に混乱が生ずることを避けるという観点から、厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間を超えて婚姻を禁止する期間を設けることを正当化することは困難である。他にこれを正当化し得る根拠を見いだすこともできないことからすれば、本件規定のうち100日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約 を課すものとなっているというべきである。以上を総合すると、本件規定のうち100日超過部分は、遅くとも女性が前婚を解消した日から100日を経過した時点までには、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして、その立法目的との関連において合理性を欠くものになっていたと解される。
以上の次第で、本件規定のうち100日超過部分が憲法24条2項にいう両性の本質的平等に立脚したものでなくなっていたことも明らかであり、上記当時において、同部分は、憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項にも違反するに至っていたというべきである。 本件立法不作為の国家賠償法上の違法性の有無について国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の 適用上違法の評価を受けることがあるというべきである。
そこで、本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるか否かについて検討する。本件規定は、前記のとおり、昭和22年民法改正当時においては100日超過部分を含め一定の合理性を有していたと考えられるものであるが、その後の我が国における医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等に伴い、再婚後に前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不和を避けるという観点や、父性の判定に誤りが生ずる事態を減らすという観点からは、本件規定のうち100日超 過部分についてその合理性を説明することが困難になったものということができる。平成7年には、当裁判所第三小法廷が、再婚禁止期間を廃止し又は短縮しない国会の立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるかが争われた事案において、国会が民法733条を改廃しなかったことにつき直ちにその立法不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかである との判断を示していた(平成7年判決)。これを受けた国会議員としては、平成7年判決が同条を違憲とは判示していないことから、本件規定を改廃するか否かについては、平成7年の時点においても、基本的に立法政策に委ねるのが相当であるとする司法判断が示されたと受け止めたとしてもやむを得ないということができる。また、平成6年に法制審議会民法部会身分法小委員会の審議に基づくものとして法務省民事局参事官室により公表された「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」及びこれを更に検討した上で平成8年に法制審議会が法務大臣に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」においては、再婚禁止期間を100日に短縮するという本件規定の改正案が示されていたが、同改正案は、現行の嫡出推定の制度の範囲内で禁止期間の短縮を図るもの等の説明が付され、100日超過部分が違憲であることを前提とした議論がされた結果作成されたものとはうかがわれない。婚姻及び家族に関する事項については、その具体的な制度の構築が第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねられる事柄であることに照らせば、平成7年判決がされた後も、本件規定のうち100日超過部分については違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかった状況の下において、我が国における医療や科学技 術の発達及び社会状況の変化等に伴い、平成20年当時において、本件規定のうち100日超過部分が憲法14条1項及び24条2項に違反するものとなっていたことが、国会にとって明白であったということは困難である。
以上によれば、上記当時においては本件規定のうち100日超過部分が憲法 に違反するものとなってはいたものの、これを国家賠償法1条1項の適用の観点からみた場合には、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。したがって、本件立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。
以上のとおりであるから、女性の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。
3 再婚禁止期間を定めた規定の削除
今回のケースで裁判所は、女性の国家賠償請求を認めなかったものの、女性の再婚禁止期間を定めた民法733条1項の規定が憲法上の法の下の平等や両性の本質的平等を定めた憲法に違反するかどうかについて、再婚禁止期間6か月のうち100日を超える部分を違憲としました。
また、令和6年4月1日より再婚禁止期間の規定自体が削除されることになっていますので、注意が必要でしょうね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
