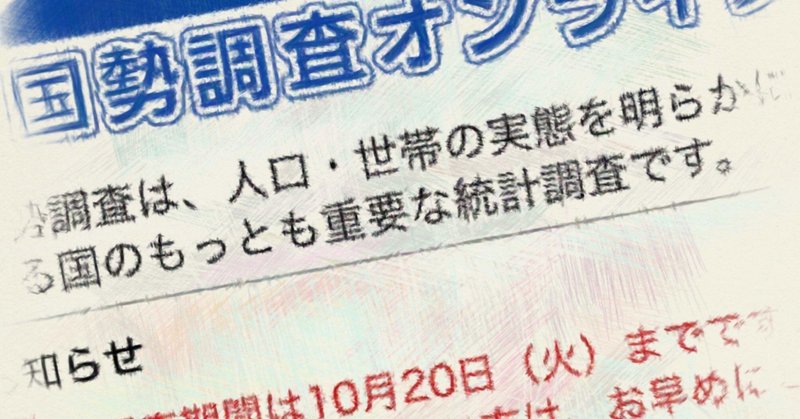
国勢調査、しませんか?
国勢調査、もうお済みでしょうか?僕はオンライン回答で早々に、ソファでくつろぎながらスマホをポチポチして済ませました。いまどきは国勢調査もずいぶん手軽なものだと思いますが、その回収率はいまのところ振るわないようです。
総務省によると、1990年までの回収率は「ほぼ100%」。しかし、プライバシー意識の高まりなどを受け、95年に初めて未回収が0.5%発生した。その後、未回収率は増え続けている。(略)6日時点で、ネット回答は35.1%にとどまるという。郵送は18.0%で、あわせた回収率は53.1%。総務省統計局の担当者は「今回はかなり下がりそうで困っている」とため息をつく。
プライバシーが回答されなくなった理由のようですが、逆に僕が回答する理由、回答しておいた方がいいと思っている理由をお伝えして、もう一度だけ考えてもらえないかなと思っています。
国勢調査は年代とか家族構成とか収入とか各業種の就業人数とか、いろんな政策を検討し国や地方自治体のお金や人を割り振っていくときの判断材料になるデータです。それから統計データとして結果が公開されています。僕たち民間企業の人間も、どんな層のための製品やサービスを開発し展開していこうかと考えるときなどに、とても参考にします。
いまの政治は若者のことを見てくれない「シルバー政治」だという声がありますが、「若者の投票率が低いからだ」という反論もあります。政治はそれではいけないと思うけど、でも投票率は20代が33.84%、60代が72.04%と知れば、候補者は選挙戦の中でどちらに向けた政策を掲げるか考えてしまいそうです。そして当選したならば、若者に向けた政策も「行うべき」だけど、掲げた政策は公約として「行わなければならない」。実現できる政策数に限りがある中で公約から進めていけば偏ることは考えられそうです。
国勢調査でも同じようなことは起こるかも知れません。
国勢調査出さないと、例えば僕が出さなかったとすると、そこに貧乏な独身男性などいない事になって、避難所の席を一つ無くされ、貧乏人などいないから公共サービスは有料にしてもだせるよね?って民間委託されたりするのよね。(@mahirmon)
行政が「どのあたりに必要としている人や受益者が多そうかな」を考えるように、上に書いた通り民間企業も「どのあたりにお客様になってくれる人が多そうかな」を考えてビジネスを作っています。国勢調査結果というのは、その時にもっとも広い範囲で行われた国内調査なので、そのデータは非常にあてにされるわけです。
国勢調査に回答することは、行政や経済、ひっくるめて言えば社会に「僕の方を見て」とアピールする手段だと思っています。そう考えた時、回答しなくて本当にいいですか?
記事中で触れてる国勢調査の期限延長の話、さきほどオンライン調査のページにアクセスしてみたら、10月20日までに期間延長されてました。青と白の封筒で届いている「国勢調査のお願い」、これの中のQRコードから回答ページにアクセスできます。回答がまだだったらこれだけでも持って出かけて、お昼を食べながらでもちょっと回答に参加してみませんか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
