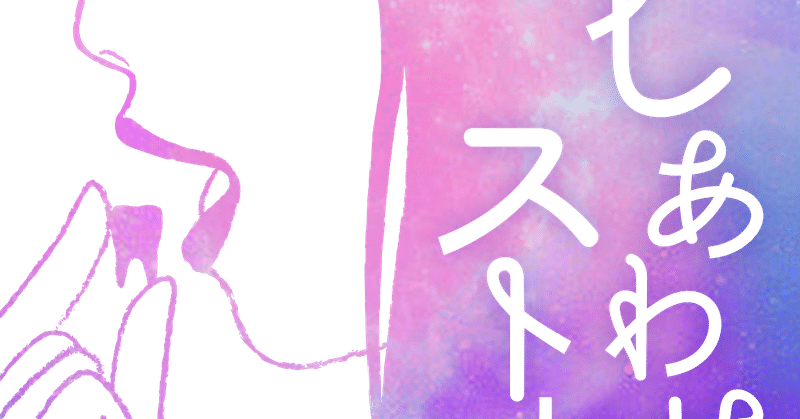
しあわせストーカー日記
1.すべてが嘘でありますように
タクシーの中での私はおしゃべり。だって会話の相手とは、もう二度と会うことがないから。一期一会の運転手、もしくは隣に座っている男の人との目的地に着くまでのやり取りは、降車の瞬間に夜の空気の中に消えてしまう。掃除機のコードを収納するボタンを押したみたいに。
星の見えない繁華街や自分のヒールの音だけが聞こえる住宅街で、深い夜の中に吸い込まれていった私の話は、もうどれくらいあるんだろう。最近あったかくなってきた、とか、ビールが値上がりするらしい、とか、明け方に流星群が来るそうですよ、だとか、どれも取るに足らない世間話ばかりだ。
そういう他愛ないやりとりを、私はタクシーの中でしかできない。とりとめのないおしゃべりの中に気恥ずかしさなく身を置くことができるのは、酔っているときか相手との関係の継続を意識していない場合のどちらかだけだった。
今年は桜の開花が遅くて、世間ではみんな、そのことばかり口にしている。
「このまま咲かないで終わるんじゃないの」
昨日、バイト先の店長もそんな軽口を叩いてきたけど、タクシーの中にいない私は調子良く切り返すこともできない。せめて愛想笑いでもしておけばいいのに。
「はあ、そうですね」
発した言葉は相手に届く前に、どこかに消えたみたいだ。店長はスマホの画面に目を落として会話はそれ以上続かなかった。
タクシーの中でなら、私はどんな風に対応しただろう。「そんなわけないじゃないですか!」とか「えー、そうなったら困りますぅ」とか、軽い調子で返せそうだ。そういう風にいつでもできれば、私はもっと健やかな人生を歩めているのかもしれない。そう立ち止まって考えてみることもあるけれど、空気を悪くしないように気を遣うばかりでいるのも息が詰まりそうだな。くだらない世間話の展開なんて本当はどうでもいい。桜は咲くんだ、なんとしてでも。
スープの中にずっと浮かべていたパンみたいに脳みそはふやけきっていた。起きてから時間はずいぶん経っている。惰性でつけた昼のワイドショーを流し見しているものの、それ以外まだ何もする気になれない。
画面では桜の様子が中継されていた。例年なら、もう見頃を迎えていてもおかしくないのに、花見客の頭上にはまだ空の色ばかりが広がっている。その映像を見ていたら、急に、テレビが嘘をついているんじゃないかと疑いたくなった。
今映っているつぼみは、実はもう何日も前に撮影されたもので、本当はとっくに花は開いているのかもしれない。花見客たちが空を見上げれば、薄桃色の花は雲のようにたなびいているんじゃないだろうか。
昨日までは同じようなニュースを見てもそんな風に思いはしなかったのに突然そう考えたのは、今日が四月一日だからなのかもしれない。嘘なんて毎日のようについたりつかれたりしているはずなのに、エイプリルフールを意識して妙に疑り深くなっているなんておかしな話だ。一年の中のたった一日にだけ免罪なんてもらわなくても、私は三百六十四日間を日々悪びれることもなく過ごしているというのに。
ベッドに寝そべったまま、ペットボトルの水を喉に流し込む。頭はスープをすっかり吸いきったパンだ。ずっしりと重く、側頭部は軋むように痛んだ。左のこめかみあたりの血管では粘度の高い不健康な血が渋滞を起こしている。嗚呼、この二日酔いの不快感も嘘だったらどんなにいいだろうか。昨夜の自分の行いが悔やまれる。空になったペットボトルを床に放った。
もっと欲を言えば、昨夜の出来事そのものがまず嘘であればいい。私の隣ではまだ、大学三年生だというプロフィールしか記憶に残っていない男が寝息を立てていた。
顔が小さくて、体の線の細い、華奢な男だ。声をかけられたとき、わりと好みの外見だったから朝まで過ごしてしまったけれど、酒が入っていなければそこまで魅力は感じない相手だったかもしれない。
化粧も落とさず寝てしまった顔に再びファンデーションだけおざなりにのせてフロントに電話を掛けた。ひとりで出ていくと告げると、確認を取るために男性に代わって欲しいとフロント係は言った。布団にくるまっている男を軽く揺すって、押し付けるように受話器を渡す。男は寝惚けた声で「大丈夫です」と数回発して受話器を置いた。
「鈴(りん)ちゃん、もう出ていくの」
「ごめんね。そろそろ仕事だから」
いい加減な嘘でいなしてベッドから立ち上がる。男は私の腕をつかんでそれを制止した。
「仕事って夜からなんじゃないの?」
「そうだけど、色々準備もあるし」
「でも、まだ昼過ぎでしょ。一緒にメシでも食おうよ」
「そんな時間ないかも」
「ちょっと待ってて。すぐ支度するから」
さっき電話に出させたせいで彼はすっかり目を覚ましてしまったみたいだった。早くひとりになりたかったのに、まだ一緒にいなきゃいけないなんてめんどくさい。
「急がせたら悪いし、いいよ」
顔面の筋肉運動にしか過ぎない笑顔を向けると、相手は私の腕を引いてこちらを見上げた。
「冷たいね」
男が腕に力を入れ、私の上体はベッドに引っ張られる。
「痛い」
小さな悲鳴は無視されている。上に倒れ込むかたちになった私の背中に腕をまわして、男は唇を寄せた。ごめん、彼の口からはそう漏れた気がしたけど、不明瞭な言葉は次に続いた長いキスの中に溶けてしまった。謝るくせに止める気配はない。抗うのもめんどうになり、私も無気力に受け入れる。
口腔内を犯されるようなキスの途中で、彼の舌が驚くほど柔らかいことに気付いた。嫌々されていたはずなのに、ばかみたいに浅ましくそんなことに気付く。昨夜は酔っていて分からなかったけれど、その瑞々しい肉質ははじめて味わう種類のものだった。
「舌、すごく柔らかいね」
唇を離した後でそう告げると、彼はきょとんとした。こんな感想を伝えられたことが今までなかったのかもしれない。
薄く開いたままの彼の唇に親指を引っかけるようにして軽く引っ張ってみる。少し紫がかった薄桃色の粘膜は、いかにも新鮮な色味だ。まだ生まれたてで産毛も生えていないツバメの赤ちゃんみたい。
「気持ちいい」
柔らかな肉質を求めて今度はこちらから舌を絡める。彼のほうはもう飽きてしまったのかおざなりに舌を動かしながら、私の服の下に手を入れていた。下着をずらされ指で乳首を弾かれると小さく声が漏れた。
男は上体を起こし、私を下に組み敷く。相手の目鼻立ちや、くっきりと浮き出た鎖骨、そこかしこにある美点に視線を這わせる。彼の整った容姿を冷静に認識し、データを記憶しようと努めた。その静かで冷たい情熱は、恋心とは別の性質のものにちがいなかった。容姿に優れた異性と交接するたび、私は決して少なくない優越感を覚えるけれど、それはいつも機微のない満足に終わる。
下半身へと伸ばされた男の指が私の中に抵抗もなく沈んでいく。行為に集中しているわけでもないのに刺激に律儀な反応をしている自分をいやしく感じた。男の下腹部に目を遣ると、ソフトビニール人形の質感に似た性器が直立している。いかにも二十歳そこそこの男に付いていそうな、元気でチープな生殖器。
「ゴム」
避妊を促すと、彼は目線をヘッドボード付近に向けた。
「もう、ないや」
「……フロントに電話しよっか」
「このままでいいじゃん」
「無理」
そう返しはしても、別に抵抗はしなかった。断片的にしか再生されない記憶ではあるけれど、昨夜だって私は自分のおへそのあたりに精液が溜まっているのを見た気がする。ちゃんと外に出してくれるのであれば、そこまで相手にうるさく言う必要もないと思った。
男の体が私の中に入ってくる。なんだか今日は気持ち良さよりも苦しさがまさった。喉のところでフローリング掃除用のコロコロをかけられているみたい。何度も同じところを行き来されるとたまに粘着テープが肌に張り付いて引っ張られるように痛くなったり喉をゴリッとつぶされたりして、だんだん腹が立ってくる。
ふいに、男の動きが止まった。
「中に出しちゃた」
相手は悪びれる様子もなく言った。最悪。
「最悪」
どうして簡単にこの男を信用してしまったのだろう。こんなことをして、笑って済まされるとでも思ったのだろうか。信じられない。
「信じられない。あり得ない」
行きずりの女なら何かあっても責任を取らずに逃げ切れるとでも思っているのかもしれないが、名前も住所も大学もすぐ特定してやる。少しでも隠れようとしたら実家の親を脅迫する。許さない。土下座しろ。家族全員で土下座しろ。そこにガソリンかけて燃やしたい。もう殺したい。死んでほしい。
「死んでほしい。てか、マジ死んで。燃えて」
冷静に処理できない感情のままに言葉が口をついて出た。男はばつが悪そうに言った。
「嘘だよ」
彼は私の顔から目を逸らしたまま言葉を続ける。
「ちょっと驚かせようと思っただけ。嘘だから、安心して」
今さらそう言われたところで、さっきまで彼に向けて発した言葉も「嘘だよ」と弁解できるわけでもない。男は、背を向けて枕に顔を埋めた私の耳元に口を寄せた。
「続き、していい?」
ひとりでシャワーを浴びて下腹部にかけられた精液を流し、やはりひとりでホテルを出た。彼は私を引き留めようとはしなかった。エントランスを出てしばらくすると、さっきまでの出来事に、もう実感がなかった。「嘘だ」私は口の中だけでつぶやく。少し気持ちが軽くなって、唇から笑いにも似た吐息が漏れた。
迷路のような渋谷のホテル街を抜け、大通りへとつながる横断歩道で信号待ちをしていると、街路に植えられた桜の木が目に入る。花はまだ開いていない。さっき見たテレビの情報はどうやら嘘ではなかったようだ。薄曇りの空を背に、くすんだ緑色の帽子をかぶったつぼみが頭を垂れて連なっていた。
春が来たというのに毎日は色褪せたままだ。時間だけがいたずらに流れ、自分は止まっているばかりで。泥沼にはまったみたいにみじめに立ち尽くしていることに焦りや罪悪感は覚えるけれど、そうだったところで、泥の中から足を引き抜くバイタリティはない。このまま頭の先まで沈んで窒息してしまえるなら、それでもいい。私が生きていることが嘘ならば、それがいちばんいい。
「嘘だ」
信号を渡ってセンター街を進んでいる間、目に入るものすべての「嘘」を暴きながら歩いていた。春は嘘、ドブネズミの大きさは嘘、人の群れも嘘、これはレミングの行進で、この先にある渋谷の海でみんな小さな青白い泡になる。
ファーストフード店のオーダー待ちの列で私の前には二人組の女子高生が並んでいた。少女たちは途切れることなくおしゃべりをしている。背の高いほうの少女が、手にしたスマホで彼氏とのやりとりを見せるたび、もうひとりの少女は笑い声をあげた。その笑顔も、嘘であればいい。
背が低いほうの少女は、のろけ話をしている友達の彼氏と密かに寝ていて、その男の汗の匂いも知っている。友達が目を細めて話す彼氏の癖やよく使う言い回しについても、頭の中でその様子をしっかり再生できるから、顔に浮かべている表情とは裏腹に、内心は冷や汗をかいていてくれればいい。そこに少しの優越感と、何も知らずに彼氏を共有されている友人への哀れみに浸って悦に入る気持ちがあれば、なおさらいい。
そんなくだらない「嘘」をいくつも勝手に暴いたところで少しも愉快な気分にはならなかったけれど、やめようとも思わなかった。手もとのスマホには客からの着信が何件もきているけど、これだって嘘。私にウザい連絡をしてくる電話の向こうの相手は本当はすでに死んでいて、今スマホが震えるのは霊障なんだ。
だから当然、彼を見つけた瞬間にも、これは嘘だと私は思った。
ハンバーガーの乗ったトレイを持った私の前でポップアップ式の絵本が前触れもなく開く。「彼」だけが目の前にぽんと飛び出してきて、その瞬間まわりのすべてがツルンとした背景になった。店内の雑音も、女子高生の群れも、よどんだ清潔感のない空気も、ぜんぶ一気に白くスパークして消え去って、世界には、私と彼のふたりだけになった。そんな気がした。
彼はふたり掛けのテーブル席にひとりで腰かけていた。少しだけ上げた顔の下に片手をついて、スマホの画面を眺めている。
「夢で一度、会ったことがありますよね」
「はあ?」
「ずっと夢に見ていたような理想のタイプの方だったので思わず声を掛けてしまいました。良かったら一緒にお茶でもどうですか?」
「うるせーよ、死ね!」
彼を視界に認めながら私は頭の片隅で、以前自分にばかばかしいナンパを仕掛けてきた男とのやり取りを思い出していた。あのくだらない冗談と同じことを今、そっくり彼に伝えてみたくなる。
一目惚れというのは、ずっと夢見てきた理想的な姿かたちにある日突然出逢ってしまうことなのかもしれない。
私は花に吸い寄せられる蜜蜂のように、空席だった彼の隣のテーブルに席を取った。
わずかな距離を隔てたところに彼がいる。自分の左半身だけ熱を帯びているように感じた。視界の端にいる彼はスマホで動画でも見ているみたいだった。
私の目は確かに彼の姿をとらえているはずなのに、やはり彼の存在を「本当」のものだと確信することはできなかった。なにも、世界一の美形を見たというわけではない。それどころか彼は抜きんでた美青年とも言えないかもしれなかった。むしろ、一般的な価値観で言えばどこにでもいる普通の男性と呼んで差し支えないのではないだろうか。それなのに、その目鼻立ちや彼を取り巻く雰囲気は、おそらくそのすべてが私の欲していたものに当てはまるように感じられた。どこにいてもおかしくないのに、今までどこにもいなかった。そんな人がどうして今、私の前に現われたんだろう。
バッグから鏡を取り出し、自分のメイクを確認するふりをして彼の姿が映るように左側にゆっくりと傾ける。丸い鏡面は月蝕のように少しずつ彼の姿を映していく。
年齢は私とそう変わらないように思えた。もしかしたら少し年上なのかもしれないけれど、色白の肌と細身の体つきからは少年を思わせる清潔さが感じられた。ラムネの瓶のように涼やかで、はじめて見るのにどこかなつかしさを覚える人だった。
鏡の中の彼の姿に右手を伸ばす。瓶の口をふさいでいたビー玉がラムネの中に落ちて、勢いよく泡を立てた。彼の頬に私の指先が重なった瞬間、これは嘘ではなく本当だということを、私はしっかりと信じた。今日見てきた他の何が嘘であっても、これだけは絶対に本当のことなのだと、そのときに私は、分かった。
魔法の鏡を眺める。いくら眺めていても飽きるということがないように思える彼の顔立ちや細い首筋をうっとりと眺めていると、不意にその姿が鏡の中から消えた。私はあわてて魔力を失った鏡を自分の顔に近づけ、目に入ったゴミを探すような仕草を始める。左側に座っていた彼がソファーから立ち上がる気配を感じた。私の行動に気が付いて席を離れようとしたのだろうか。びくびくしながら様子を伺っていると、彼は荷物をそのままにして私のテーブルの前を通り過ぎ、通路の奥へと進んで行った。そこには男女共用のお手洗いがひとつある。
顔を正面に向けたまま聴覚だけで彼の動向を追う。後方から、ドアの閉まるような音が聞こえた。どうやら警戒はされていなかったみたいだ。私はテーブルの上に置かれたままになっていた彼のスマホに手を伸ばした。
それはほとんど無意識の行動だった。私の心にいるはずの天使と悪魔は争いを好まない種族のようだ。スマホにロックはかかっていなかった。素早く画面を操作して、持ち主のプロフィールを表示させ、私は自分のスマホにデータを飛ばす。興奮している脳みそとは裏腹に、私の動作や表情筋はとても冷静だったようで、誰に不審がられる様子もなく素早くその作業を終えることができた。
お手洗いから戻った彼は、ソファーには腰を下ろさずにスマホとテーブルの上のトレイを持って店を去った。
遠ざかる彼の後ろ姿を食い入るように見つめながら、あの時ためらわずに行動しておいて良かった、と心の底から思った。彼が私の隣からいなくなってしまった寂しさを感じながらも、私の中にはこれがふたりの別れではないという確信めいた気持ちがあった。さっき私のスマホに送った十一の数字の羅列といくつかの英数字の組み合わせは、私と彼をつなぐラッキーコードだ。
空いた隣のテーブル席へ移動すると、ソファーにはまだ彼の体温が残っている。私はたまらない気持ちになって、彼のデータが表示された液晶画面に口付けをした。
あおいちゃんを待っている間、頭の中で何度も彼の姿を反芻していた。
短い記憶の中からその顔や身体の様々なパーツを選び取り、そのひとつひとつを脳内で優しく愛撫するように再生していく。切れ長の目元、筋の通った高めの鼻、口角のあがった薄い唇と、あくびをした時にのぞいたチャーミングな八重歯、なめらかで長い指、その爪の根元の半月がきれいなかたちであったことも思い出され、やがて私の心の目が彼のすべやかな肌の皮下組織にまで入り込もうとする頃、前方から私を現実に引き戻すあおいちゃんの声がした。
「りんちゃん、お待たせ」
シフォン素材のブラウスに身を包んだあおいちゃんが、私を見つけて向かいの席に腰を下ろす。
「ううん。急だったのに来てくれてありがとう」
「祐一の家にいたから渋谷近かったですし」
「彼氏さん、祐天寺だっけ」
「うん。もうずっと半同棲気味なんですけどね」
「そうなんだ。上手くいってていいなあ」
「うふふ、おかげさまで……」
久しぶりに会ったあおいちゃんの近況報告を聞きながら、私の心はここにあらずだった。他人の恋愛の状態なんて、どうでもいい。あおいちゃんが語るのろけ話に愛想良く相槌をはさみながら、私はずっとどのタイミングで「彼」のことを切り出すかを考えていた。恋に落ちたばかりの心音のビートに任せて話し始めたら、制御不能のマシンガントークにも陥りかねない。
話題のスタートを慎重に考えていると、祐一君の話をしていたあおいちゃんが急に話を止めた。
「そうだ、いいもの見せてあげます」
上の空で話を聞いていた私は、ハンドバッグの中をかき回しはじめたあおいちゃんに慌てて注意を向ける。彼女が取り出したのは、手のひらよりも小さなサイズのチャック付きポリ袋だった。割れものを扱うように静かにテーブルの上に置かれたその中には、根元から引っこ抜かれた人間の歯が一本入っていた。
「何これ、おもちゃ?」
「本物の歯ですよ。祐一の親知らずです。可愛いでしょ?」
あおいちゃんはピンと立てた右手の人差し指を顎に当てて、上目遣いで私に微笑みかける。
「今日、祐一が歯医者さんで抜いてきたんです。持って帰るかどうか聞かれてなんとなく持ち帰ったらしいんですけど、結局どうしていいか分からないから捨てるなんて言うので私がもらっちゃいました」
「持ってても仕方ないんじゃないの」
「祐一の口の中に二十六年も存在したパーツを簡単に廃棄処分するなんて、そんな残酷なこと私は絶対にできません」
「そう。でも、これどうするの?」
「大切に保管して、毎日眺めるとか、かな」
「ふーん」
「ちょっぴり血が付いてるところがいいんだなあ」
あおいちゃんはうっとりした表情でポリ袋の上から親知らずの根元をなぞっている。私はその様子を見つめながら、こんな風に好きな人の身体を持ち歩くことの出来るあおいちゃんに徐々に妬みに近いうらやましさを覚え始めていた。あおいちゃんの目には祐一くんの親知らずの少し虫歯が食っている部分でさえも、琥珀の美しさに映るのだろう。今の私にはそれがなんとなく分かる。
「あおいちゃん、私ね、好きな人が出来たの」
「そうなんですか」
「そうなんですか、って、それだけ?」
「うーん、だって、そもそも私そんなに他人の恋愛に興味ないですもん」
あおいちゃんがトレイの上のジュースにストローを差し込む。オレンジ色の液体が吸い込まれていくのを私は黙って眺めていた。
「運命だと思うの」
私はそうあおいちゃんに訴えかけた。
「はじめて彼を見た瞬間から、ずっと泣きそうなの。まだ出会ったばかりで、相手のことを何も知らないのに、こんなに思い詰めるなんて自分でもばからしいと思うんだけど、気持ちが溢れて止まらないの」
あおいちゃんはストローに口を付けたまま、こちらを見つめている。私の話を真剣に聞くべきなのか茶化すべきなのかを考えているのかもしれない。もう一押し、必要みたいだった。
「私の彼への想いはね、あおいちゃんの祐一君への気持ちと同じだよ」
女は、共感で動く生き物だ。自分の中に相手と共通するものを見出すことでその行動や感情を理解しようとする。女は自分のために泣き、自分のために怒る。私は自分のために、あおいちゃんの力を借りたかった。今日、彼女をここに呼び出した理由は、この恋の協力を頼みたかったからだった。
「……ガチってことですね。それで、相手はどんな人なんですか?」
あおいちゃんがはじめて質問を口にする。
「千塚さんていうの。千塚貴之さん。ついさっき、このお店の中で見掛けた人なの」
「……ついさっき? エイプリルフールか何かですか?」
「くだらないこと言わないで。今日、世界中の何が嘘だったとしてもこれだけは本当、私、千塚さんが好き!」
そう。私、好きな人が出来たの。今ここで出会った人。千塚さんていうの。ううん、まだ喋ってもないよ。なんで名前分かるのって? 相手のスマホからデータ盗んで知った。うん、そう、エイプリルフールってことにしておいて、その部分は。ねえ、そんなことよりも千塚さんのこと聞いて! 千塚さんてめっちゃ私のタイプで、すごくかっこいいの。あ、一般的に言ったらイケメン扱いされるかは分からないんだけどとにかく私の好きな顔なんだよね。右目の下に小さな涙ぼくろがあって、それがなんとも言えず可愛いんだ。あの小さなほくろは千塚さんの繊細な顔立ちを引き立てる最高のチャームポイントだと思う。千塚さんの目元にほくろを作るプログラムを組んであったDNAにマジ感謝! 嗚呼、千塚さんの涼しげな目元を思い出したらなんだかもう涙が出てきちゃった。それでね、千塚さんは八重歯もチャーミングで……。
千塚さんへの気持ちをオープンにしてしまうと、堰を切ったように言葉が溢れて止まらなかった。あおいちゃんは質問を交えながらも、カウンセラーのように冷静な態度でこちらの話を聞き続けてくれている。やはり、あおいちゃんに声をかけて良かった。私のこの様子を見てすぐに引いてしまったりお説教めいたことを口にしたりする人間を前にしていたら、千塚さんへの恋心に水を差された気分になって不条理にブチ切れてしまっていたかもしれない。
「それで、りんちゃんは千塚さんとどうなりたいんですか?」
私の冗長な説明が一通り終わるとあおいちゃんは尋ねた。こちらの目を射抜くような彼女の視線はすでに返ってくる答えを推定しているようでもあった。
「私ね、千塚さんが欲しいの」
あおいちゃんは短く「なるほど」と言ってうなずく。私は相手の予想通りの答えを返したのだろう。彼女は右手の人差し指を顎に当て、斜め上に目線を遣ったまま、言った。
「運命を仕掛けましょう」
祐一くんの親知らずは、あおいちゃんのオレンジジュースの隣に丁寧に並べられている。私の手にしたラッキーコードをもとに彼女はスマホで熱心に何か作業をしてくれていた。この頼もしい協力者が恋人の親知らずを手に入れたのと同じように自分もいつか、千塚さんの口内から抜かれた親知らずを所有することを想像する。
千塚さんの親知らずはきっと私の親指の先ほどの大きさで、生まれたての赤ん坊のように無垢な白さに輝いている。千塚さんの親知らずを手にした私はそれを手のひらの上で充分に愛でたあと、好奇心のままに自然と舌を這わせるだろう。彼の親知らずを口の中に入れて、飽きるほど舌で転がし、その触感を楽しんでいるうちに感極まって、私は、ごっくん! と喉を鳴らしてそれを飲み込んでしまう。食道は歓喜に満ちて躍動しながら千塚さんの親知らずを胃へと運び、妄想を繰り広げる脳みそはたちまちの内に千塚さんの親知らずを受け入れた胃の断面図に占拠される。淡い黄金色のシャンパンにきめ細やかな泡が立ち上るように千塚さんの親知らずは消化液でゆっくりと溶けていき、私の胃の中では、今まで自分の身体に入れたどんな食品とも比べ物にならない慈愛に満ちた消化が始まる。そして千塚さんの親知らずの成分を十二指腸はうきうきしながら分解し、小腸は最大限の歓迎を以て栄養素を吸収していく。
ついに千塚さんの親知らずが私の身体の一部になった瞬間に、もう私はほとばしるイメージを自分の内だけに秘めておくことが出来なくなって、あおいちゃんにこのキュートな心象風景をまくしたてるように話していた。一度、心音のビートのままに愛と欲情を語ることを己に許可した私は、きっともう自分を止めることが出来ない。
「素敵ですね」
あおいちゃんは作業の手をいったん休め、私の欲望に同調する言葉をくれた。
「私も祐一の親知らずごっくんしたいです。でも、飲み込んじゃったらもう眺めることは出来なくなるから、ちょっともったいないかもしれないですね」
「確かにそうだね。じゃあ私、千塚さんの親知らずを手に入れたら、しばらくはキャンディーみたいに毎日舐めたり口の中で転がしたりするだけにしよっと。うーん、だけど私、舐めるだけで我慢できるかな」
「たぶん、りんちゃんは出来ないと思いますよー」
想像力に欲望を刺激されるままに千塚さんの親知らずに想いを馳せる中で私の頭にある不安がよぎった。千塚さんの口の中には、果たしてまだ親知らずが抜かれずに生えているのだろうか。もしも、彼がすでにすべての親知らずを抜いてしまっていたら、私は湧きあがるこの衝動にどう始末をつけたらいいのだろう。どうか、千塚さんの親知らずがまだ彼の口の中にありますように、私に再び出逢う時まで無事でありますように、痛みに疼くことがありませんようにと、千塚さんの口腔内の健康を両手を組んで祈った。
2.IDLING FOR LOVE
まなこはぐしゃぐしゃに泣いていた。
これから私にされることを予感しているのだろう。それが楽しいことでないのは、彼女の身体がコンクリートの冷たい台の上に拘束され、その顔の前にナイフがかざされていることが教えてくれている。
身体の端々に刃先が当たるたびにまなこは泣き叫んで、それが、当たり前だけれどいつも聴いているその声と同じなので、私は分かっていても我慢ができなくなってしまう。自分の聴覚をサイレントモードに切り替え、ナイフをまなこの薄い胸へと滑らせた。
赤いミニドレスの胸元が縦に裂け、刃先はその間をもぐり込んで彼女の身体に血のにじむ線を作っていく。肋骨の間を深く刺すとまなこは大きく身体をのけぞらせた。いい気味だ。鯉のようにぱくぱくと大きく開くまなこの涎まみれの口にナイフを差し込み、何度も何度もFUCKするみたいに出し入れする。まなこが咳き込むたび、粘性を持った赤い液体が噴出した。舌の切れ端とどろどろの体液にまみれたナイフを引き抜いて、彼女の青白い喉元に突き刺す。その一撃でまなこは絶命した。
千塚さん、あなたが好意を抱いている女の子がいるということを知ったせいで、私はついついこんな想像をしてしまいます。その相手がたとえ、自分とは何の面識もなく、あなた自身も知り合うことができない相手だったとしても。
運命を仕掛けると言ったあおいちゃんが最初にやったことは、あらゆるSNSを調べて千塚さんの登録の有無を確認することだった。私が彼のスマホから入手したプロフィールには、電話番号といくつかのメールアドレスが入っていた。それを元にあおいちゃんが「Linx」というSNSでかけた検索で千塚さんのアカウントはあっさりと見つかった。
Linxは一時期、社会現象と言われるほど流行ったSNSだったが、今では登録されているだけでまったく使われていない「死んだアカウント」も多く、以前のような活気はなくなっている。私からすれば、そこにログインするのは半ば朽ちかけた黴くさい蔵に足を踏み入れるような感覚だったけれど、一部の人の間ではいまだに情報交換の場として使われていることもあるらしい。千塚さんのアカウントは「生きていた」。彼がLinxへ最後にログインしたのは一時間前で、最終の更新は二日前だ。
目玉をあおいちゃんのスマホにくっつけるようにして千塚さんのプロフィール画面をのぞき込む。千塚さんのアイコンには何かのロゴマークのようなものが設定されていた。カラフルな色が踊るデザインは、さっき見た彼の雰囲気にはあまりマッチしていないように思えるが、その意外性のあるチョイスにも、新鮮な楽しさを覚える。
たったの数分前には無機質な英数字の羅列のみだった彼の情報が、今ここに視覚に訴えるかたちとなって現れ、多分な意味とイマジネーションを含んだ言語となって広がっている。早く千塚さんのことを色々知りたいという期待と、なんだか知るのが怖いような緊張とが入り混じる中、彼のプロフィールを味わうように目で追った。
「三十四歳なんですね」
千塚さんの生年月日を目にしたあおいちゃんが素早く計算して私の耳元でつぶやく。
「嘘! もっと若く見えるよ。あの見た目で三十代なんて詐欺だよ」
「最近は若く見える人も多いですしね。りんちゃんと十一個違いですか。まあ、SNS上での記載なので生年月日を偽っている可能性もありますけど、あとでゆっくり検証していきましょう」
「うん。でも何歳だって私は千塚さんが好きだから関係ないけどね。あ、ねえ、千塚さんて血液型はB型みたい」
「ふーん、自己中心的でエキセントリックなB型ですか」
「ちょっと、自立心旺盛で大物タイプのB型でしょ?」
千塚さんの情報が入ってくるたびに自分の脳細胞が喜びに震えるのが分かるようだった。砂糖のたっぷり入ったお菓子を食べたときみたいに、体中に甘い気持ちが広がっていく。もっと、もっとと、お菓子に伸びる手は止まらない。しかし、ページを読み進めるうちにだんだん、私はそこに書いてあることにどう反応をしていいのかが分からなくなってきていた。千塚さんのプロフィールは下方の欄の「趣味・好きな休日の過ごし方・好きな言葉」など私が欲しい情報すべてが、初めて目にする同一の単語で埋められていた。
「なに、この『ゆめいろファクトリー』って」
「……調べましょう」
ふたりでのぞいていたスマホを手に取るとあおいちゃんは早速その単語を検索にかけたようだった。表示された結果を追うあおいちゃんの大きくて丸い目がほんの数秒の間に針金のように細くなる。
「あ、りんちゃんどうしよう。この千塚さんていう人、キモいかも」
「ちょっと、失礼なこと言わないでよ。私の千塚さんに気持ち悪いところなんてあるわけないでしょ!」
あおいちゃんからひったくったスマホの画面には、カラフルな衣装に身を包んだ少女たちの画像が表示されていた。検索結果によれば、「ゆめいろファクトリー」とはアイドルグループの名前で、五人のメンバーたちは現在全員が中学生であるらしかった。
「ロリコンのアイドルオタクでしたか」
「別に、誰だってアイドルを好きになったりすることはあるじゃない」
「普通は大の大人が自分の自己紹介ページを中学生のアイドルグループの名前で埋めたりはしないでしょう」
「まあ、そりゃそうかもしれないけどさ。冗談でやってるだけかもしれないじゃん」
「だといいですね」
「……。ねえ、Linxって確か日記も投稿できたよね。千塚さん何か書いてるかな」
「さあ。ゆめいろファクトリーのことでも書いてるんじゃないですか」
あおいちゃんは針金の目つきのまま手元だけを素早く動かして、私のスマホに千塚さんの日記のページのURLを送った。
3月30日 23:35:46
うわああー!
ゆめいろのライブ行って来ました!
最高だったああああ!まなこおおおおおお!
本当にゆめいろからは元気をもらいます!
物販でまなこのTシャツが買えなかったのだけがマジで心残りですが、今度のライブでリベンジしてきます!
とりあえず今日は余韻に浸りながらゆめいろの曲聴いて寝ます!
最新の日記を読み終えると、自然とため息が漏れた。あおいちゃんも自分のスマホで同じ画面を見ているようだった。私に伝えるわけではないのだろうけれど、その口元からは千塚さんに対する否定的な言葉が漏れていた。
1月26日 21:17:45
今日のまなこのブログに載ってたゆめいろの変顔がツボです。
アイドルであそこまで出来るってすごいよね。可愛いけど!
まなことねねとりんの仲の良さには毎回癒されます。まなこってなんであんなに可愛いんでしょうねえ。
10月22日 22:59:00
限定版のDVDのポスター、ねねとりんのバージョンがかぶってしまったのでねねとりんのファンで欲しい方いたら教えてください。
ちなみにまなこバージョンは今三枚うちにあります。もったいなくてまだ貼ってないけど。
ところで皆さんは壁に貼ったポスターの劣化ってどうやって防ぎますか?
彼の更新頻度は週に一度程度だったが、日記はどこまで遡ってもゆめいろファクトリーの話題一色だった。
「やっぱりロリコンのアイドルオタクじゃないですか」
今度はしっかりと私の目を見据え、あおいちゃんは言った。その眼差しは有刺鉄線だ。
「ロリコンがそんなに嫌い?」
「気持ち悪いです。犯罪者予備軍じゃないですか」
「は? 言い過ぎじゃない? 実際に手を出さない限り単なる性癖じゃん。てか、アイドル好きだからロリコンだって決めつけるのも短絡的じゃない? そんな風に言うのって偏見だと思うよ。そんなことより、『まなこ』ってどの子?」
千塚さんがゆめいろファクトリーのことを語る中でも登場頻度の高いその名前が私は気に掛かっていた。あの書き方を見る限り、どう考えてもその子が彼の「推し」なんだろう。
「この真ん中の子みたいですね。江藤真奈子ちゃん。ニックネームが、まなこ。この春、中三になるみたいですよ」
あおいちゃんが画像の中央に映る赤いミニドレスを来た少女を指差す。彼女はそのまま、画面に記載されているプロフィールを読み上げていく。
「誕生日は五月三日」
「ゴミの日じゃん」
「血液型は自立心旺盛で大物タイプのB型です」
「はあ、自己中心的でエキセントリックなB型ね。絶対性格悪いよコイツ」
「身長148センチ」
「そのわりには顔でかく見えるね」
「特技は変顔と一発ギャグですって」
「あー、なるほど。自分の容姿が平均より上だからって反感買わないようにわざとそういう少しはずしたこと言ってくる感じね。あざといクソガキだわ、こりゃ」
エスプレッソのように苦い感情が胸に広がる。こども相手に低レベルな憎まれ口を叩くことを恥ずかしいと思う気持ちはあるものの、デミタスカップよりも器の小さい私は直情的になってしまう自分を抑えることができない。
「まあ、まなこのことはひとまず置いて、落ち着きましょう。幸いなことに千塚さんの日記はLinxにアカウントがある人なら誰でも読める設定になっていますし、彼が入っているコミュニティやSNS内の交友関係を探っていけば千塚さんの情報は色々と読み取れるはずです」
たとえば……とあおいちゃんはつぶやくと、千塚さんの「友人」が一覧できるページを開いて表示されたアカウントの一つを示した。
「このマスオさんという方、彼は千塚さんとの関係性を、中学からのつながりと書いています。千塚さんと同級生だというこの方は、東第一中学校卒業生のコミュニティに入っているんです」
「ってことは、千塚さんもそこの卒業生ってことだよね?」
「おそらく。東京出身で今もこっちに住んでいるなら実家暮らしの可能性もありますから、その場合は住所もすぐに特定できそうですね」
あおいちゃんはLinx内のページをさくさくと切り替えながら、そこかしこに散らばっている千塚さんの情報のかけらをひとつ、またひとつと私に渡してくれる。その速度と洞察力は昔とまったく変わっていないようだった。
「さすが、だね」
「祐一のパトロールで鍛えてますから」
あおいちゃんは顔色ひとつ変えずクールに答えた。
私が働いていた目黒の小さな雑貨屋に「かつひろ」がやってきたのは二年前の夏だ。インターネットを通じてずいぶん親密に交流してきた相手だったけれど、実際に顔を合わせることになったのは、そのときがはじめてだった。
当時私がやっていたSNSを彼にフォローされたのが出会いのきっかけ。そのアカウントでは顔出しもしていなかったし、恋愛の愚痴ばかりを書き込んでいたから、知らない男が何かアクションをしてくるのは珍しかった。警戒心と興味から相手のプロフィールをのぞきにいった。そろそろ生活習慣病が気になり始める三十六歳のシステムエンジニア、という自己紹介。アイコンはその原因をつくっていそうなデカ盛りラーメン。積極的に仲を深めていきたいとは思えない相手だった。
何の興味も湧かない男、深く関わることはない他人、早死にしそうなメタボおっさん、ファーストインプレッションでそう片付けたはずのかつひろと私の心が通じ合うまでに、そう時間は掛からなかった。
ただし、私たちのつながりは恋愛関係ではなく、あくまで友人としての結びつきだ。私とかつひろは、恋愛の価値観がとても似ていた。
「りんちゃんは悪くないですよ!彼氏さんの行動が悪いんです。相手に意思があるのが悪いんです!」
「いつだって全身全霊の愛情で向き合ってくれなきゃ嫌ですよね!」
「彼氏さんの目に映る女が全員死にますように!」
付き合っていた彼氏への不満や愚痴を投稿すると、必ずと言っていいほどつけられるかつひろからのコメントは、そのほとんどすべてが私を気持ち良くさせた。彼は私の理解者で、同志だった。彼にもまた恋人がいて、私と同じように相手に関する話題ばかりをSNSに投稿していた。
「だけど、どうせ彼女は僕のことが嫌いなんだ」
恋人とのデートを楽しんだという報告のあとに、かつひろはたびたび後ろ向きでひねくれた文章を投稿する。彼女の笑顔を見ると、不安になると語る。自分が相手を思う気持ちが強すぎて、向こうは内心それを疎ましく感じているのではないか、と。
恋人同士ではあってもお互いがずっと同じ気持ちでいることは難しいと世間では言われることもあるけれど、かつひろはそういう意見に耳を傾けるつもりはないようだった。自分が望む分だけ相手が愛情をくれないならば、それは裏切りだとすら考えていたように私には読み取れた。そうだとすれば、大いに共感を覚えるところだった。
ふたりでひとつになれないなら意味がない。私たちはお互いに相手を選んだのに、天秤がどちらかに傾くだなんて許せない。こちらが欲しがる愛情を充分にくれない恋人なんてラーメンを出さないラーメン屋と一緒だ。赤地に白抜きの文字が書かれたいかにも食欲をそそる暖簾を出しておきながら客に水しか出さないラーメン屋があるとすれば、私はその店を理性を以て許すことが出来ない。恋を貫かない恋人なんてあり得ない。看板の偽りを許さない。ラーメンのスープみたいに愛を継ぎ足し継ぎ足し継ぎ足し続けて変わらない秘伝の味を保っていてほしい。
いつしか私たちはお互いの投稿へのコメントでは飽き足らず、ダイレクトメッセージで毎日のようにやりとりをする仲になっていった。
ある日、いつものようにおっさんと恋バナに花を咲かせていると、かつひろから恋人の誕生日が近いという話が出た。その流れで、私は自分の働く店で彼女へのプレゼントを探してみてはどうかと提案した。かつひろが店にやってきたのは、その翌日だ。そこで私は、初めてあおいちゃんと対面する。彼女はややはにかんだような笑顔で「かつひろ」というSNS上で使っていた名前を私に告げた。
「ごめんなさい。性別も、年齢も嘘ついてて」
私に頭を下げたのは、かすみ草のブーケのような女の子だった。小柄な彼女に潤んだ瞳で見つめられるとこちらが何か悪いことをしてしまったように感じ、彼女の嘘を追求する気持ちも阻まれる。しかし、同年代の女の子が中年のおっさんを騙り、私に会いに来るまで正体を明らかにしなかったのは不自然で、さらに言えば怖かった。警戒心から、むしろ私は努めて明るく彼女に接した。
「謝らないでください。おじさんだとばかり思っていたかつひろさんがこんなに可愛い女の子だったなんて、かえって嬉しいくらいですよ」
「そう言ってもらえると、救われます」
微笑みの表情をつくった私につられるように、彼女も少し顔をほころばせる。狭い店内に二人きりだった。相手は私に気を遣ってか、ペアグラスを購入してくれていた。モロッコ風のモチーフが描かれたグラスを梱包しながら、私はレジに立って彼女と向かい合うかたちで話をしていた。ちょうど夕立が来たところで、この店が面している小さな通りには人の姿も見えない。誰もこの接客から私を助けてくれそうにはなかった。
「でも、りんちゃんに話してたこと自体は、本当ではあるんです……」
「彼女さんのことですか?」
「はい。性別は逆に置き換えて書いてますけど。つまり彼女って書いていたのは、彼氏のことで」
雨音は強くなっていた。強い風が店のドアにぶつかってくる。私はすぐに商品の梱包が完成しないようにグラスを包む紙を指先でくしゃくしゃと丸めたり、セロテープを貼り直したりを繰り返していた。グラスじゃなくて傘を買ってくれていたら、会計の作業もすぐに終わらせて笑顔をキープしたまま彼女を送り出せるのに。
「りんちゃん、篠田祐一って、覚えてます?」
「……」
「今、私が付き合ってる彼氏なんですけど」
その名前を聞いたのは久しぶりだった。また、そのときまでもう耳にする機会はないとも思っていた。あおいちゃんの現在の恋人だという祐一くんと私は、ふたりが付き合う以前に何度かデートをしたことがある。
私は当時付き合っていた彼氏とうまくいかない時期で、気分転換になんとなく飲み会で知り合った祐一くんに誘われるまま食事に行ったりどこかに遊びに行ったりしていた。ただ、彼との仲はとくに発展せず、連絡を取り合うことも自然となくなっていた。
「祐一って自分の恋愛遍歴をぜんぶ私に喋るんですよ。元カノ、片想いの相手、過去にデートした子まで。その中に、りんちゃんの話もありました。なんか、好きだったみたいですよ」
そう前置きしてあおいちゃんは、祐一くんの話から個人を特定できそうなキーワードを抽出し、私を探し出した経緯を語った。
私にはこれまで、恋愛のトラブルが原因で見ず知らずの女の子に同じようなことをされた経験があった。SNSで一方的に私のことを探るようなメッセージを送ってこられたり、嫌がらせをされたりしたこともある。だけど、実際に私のところまで会いに来た女の子はあおいちゃんが初めてだった。
「全員見つけ出したなんて、すごいね」
「まあ皆さん、セキュリティが甘いので。りんちゃんだって、本名をひらがな表記にしただけでしょ。宮下鈴さん、この店が紹介されてたネット記事にも名前出してましたよね。ここで働いていたこともずっと知ってましたよ」
「……みんなに会いに行ってるの?」
「りんちゃんが初めてです。たぶん、他の人には会いには行かないですね」
私が理由を尋ねる前に彼女は言葉を続けた。それは、自分の気持ちを確かめるためでもあったのかもしれない。得意料理のレシピを説明するようなさっきまでの口調とは違い、少したどたどしい様子だった。
「やりとりしてたのは、りんちゃんだけですし。あとの人は、ネットから観察してただけで。……祐一がどんな女と関わっていたのか気になって、みんな特定したけど……そのあとのことは、とくに考えてなかったんです」
沈黙の中に雨の音が入ってくる。風は止んで、しとしととした小雨に変わっていた。彼女と話している間に夕立は過ぎようとしていた。
「ごめんなさい、こんなことして」
目を伏せて彼女が言う。もうすぐ、何事もなかったように雲も晴れるだろう。こうして話が一段落して、雨が止んだら、彼女は梱包の終わったグラスを持ってここから出ていくのだろうけれど、「そのあとのこと」はどんな風に考えているんだろうか。
「平気です。気持ちは分かりますから。あと、祐一君とは、なんていうか、肉体関係とかはなかったからそこは安心して欲しいというか」
「知ってますよ。祐一ってそういうところも素直に話すし、嘘つけないから。てか、ヤッてないって分かってるから会いに来られたっていうのもあります。そういうことしてた女だったら出会い頭に殺してます」
彼女の大きな目が見開かれる。笑顔に似た勝ち気な表情をつくったあおいちゃんに、今度は別の場所でゆっくり会いましょうと切り出したのは、私のほうだった。私は彼女が考えてもいなかった「そのあとのこと」を知りたいと思っていた。
「千塚さんを攻略するには、やっぱりゆめいろファクトリーがキーになりますよね」
友人一覧のページをスクロールしながらあおいちゃんがつぶやく。
「千塚さんの友人たちのアイコンを見ると、このグループに関する画像を使用している人が非常に多いんですよ。彼自身もそうですし」
千塚さんのアイコンがゆめいろファクトリーのロゴマークであったことは公式ページを開いた際に判明していた。友人一覧に並ぶ画像も、メンバーの顔写真やCDのジャケットだと思われるアイコンで埋め尽くされている。
「友人数の多さから考えて、彼は同じファン同士だったらすぐにつながってもいいって思うタイプなんじゃないかな」
あおいちゃんは喋りながら自分自身の言葉に頷いている。
「りんちゃん、千塚さんと近づくために彼女たちのファンのフリをしてLinxに登録しましょうか」
「は? 私にあの子たちのファンになれっていうの?」
「千塚さんと仲良くなるためにファンを装うだけです。まあ、多少は彼女たちのことを勉強する必要も出てくるでしょうけど。もしかしたら知っていくうちに好きになれるかもしれませんしね」
「あおいちゃん、自分の好きな人が興味を持ってる他の女の存在、許せる?」
「ごめんなさい。ひどいことを言ってしまいました。……まあでも、行きたい大学に合格するために受験勉強するようなもんだと思えばいいんじゃないですかね。どうでもいいプライドにとらわれてないで、とっとと千塚さんを手に入れましょう。彼が欲しいって言ったのは、りんちゃんでしょ。いいじゃないですか、やり方になんかこだわらなくたって。心にもないことを言ったって。すべての道は千塚に通ず、ですよ!」
あおいちゃんが指し示した以外の道がまだ見つからないなら、今はそこを進んで行くしかないのだろう。この道が千塚さんに通じているという希望だけを抱いて、私はその場でLinxの新しいアカウントを取得した。
偽装アカウント講師のあおいちゃんの説明によれば、千塚さんとつながるためには相手から警戒されないような下地づくりが大切らしい。Linxにある「コミュニティ」機能で自分の属性や嗜好をきちんとアピールし、千塚さんに友人申請を行う前にゆめいろファクトリーファンの友人を数十人単位で集め、適度に交流をしておくべきだと彼女は言う。
「応援するメンバーがかぶるのは、意気投合するか敬遠されるか賭けになるので、千塚さんお気に入りのまなこ以外の女の子を推している設定にするのがいいと思います。さあ、誰にしますか?」
私の水先案内人が示したゆめいろファクトリーの集合写真から、黄色い衣装を来たショートカットの女の子を指差す。
「ねねとりん、ですね。大人しそうで性格良さそうな子じゃないですか。ねねとりん、変なあだ名ですけど」
「コイツが一番マシ。千塚さんにポスター要らないって言われてたから」
「うんうん。では、りんちゃんのアイコンはねねとりんの画像に設定しましょう。ちなみに、千塚さんと友人になったとしても、すぐにお誘いのメッセージを送るのは避けましょうね。まずは日記にコメントをして様子を見ること。距離感をはかりながら、とっかかりができるのを待つのが肝心です」
サバンナで狩りをする動物たちの特番を見ていたときに、同じようなナレーションを聞いたことがあった。
ゆめいろファクトリーは、明るくて元気なリーダー「まなこ」こと何も考えていなさそうなお調子者の江藤真奈子、ちょっぴり天然ボケの「まぽ」ことあざとくて性格の悪そうな井上麻保、最年少のピュアガール「ねねとりん」こと低年齢である以外にとくに特徴のない橋野寧々、ダンスがうまい「ゆきうー」こと機敏なチビの谷中由布紀、みんなの盛り上げ役「あやちゅん」こと一番年上で声のでかい大友綾という五人のクソガキどもで構成されている。
名前を覚えるだけでも苦々しい。私は歯を食いしばりながらゆめいろファクトリーの知りたくもない情報を検索し、聴きたくもない音楽を再生し続けた。動画共有サイトでは、ライブで披露されたまなこの特技だという一発ギャグも見た。シンバルを叩く猿のおもちゃのように反応するファンの中に私も放り込まれたなら、バベルの塔が崩壊した直後のディスコミュニケーション状態を覚えるだろう。
私は、ときにまなこを惨殺する妄想でストレスを発散させながら、ゆめいろファクトリーの情報を必死で脳みそにインプットし続けた。
何度も推敲を重ねて書き上げた友人申請のメッセージを千塚さんに送ったのは、Linxのアカウントを取得してから五日後だった。返信はその夜のうちに来た。
「かつひろさん、友人申請ありがとうございます。ゆめいろファクトリーのファンなら大歓迎ですよー。よろしくお願いします」
彼からの短い文面を確認してすぐ、あおいちゃんに連絡を取る。
「千塚さんが友人申請受理してくれた。ヤバい、付き合えるかもしれないコレ!」
「良かったね、りんちゃん。Linxで彼と自然に交流していけば、ライブ会場で合う口実とかできるかもしれないですもんね」
「うん。私、千塚さんと結婚するね」
「はい。応援しています」
こんなに簡単に千塚さんと連絡が取れるとは思っていなかった。メッセージを送る前は不安でいっぱいで、送ってからは返信がもらえないのではないかとさらに心配で仕方のなかった私は、あまりのあっけなさに拍子抜けさえしていた。
私の脳裏には、すでに千塚さんとの明るい未来が広がっていた。そう遠くない未来に私はきっと彼と再び出会い、恋に落ちるはずだと信じていた。もう一度巡り合うチャンスがやってきているこのスムーズな流れが、私と千塚さんとの間に確かな縁があることを感じさせてくれるようだった。。何もかもがうまくいきそうだった。いや、うまくいく。運命の恋をするための準備はきっと整った。
3.まぼろしの男
私は千塚さんの指を想像してしまう。
しなやかな長い指。今、私の口の中にあるこの指が千塚さんのものだったらいいのに……と、いつも、千塚さんではない、私の目の前にいる誰かの指に。
夜が更けていくひとり暮らしの部屋で私は、スマホを手に取るたびにLinxを開いては千塚さんの日記の更新や彼からのメッセージが届いていないかを確認していた。千塚さんの動きの見えないSNSの画面を見ていると、飢えて死ぬ寸前の獣のような気分になってくる。
千塚さんのアカウントにメッセージを送ってみようかと新規作成画面を開いたところで、あおいちゃんに忠告された言葉がよみがえって手を止めた。代わりに私は、もう何十回も読んだ千塚さんからのメッセージを再び開き、その文面を黙読し音読しながら、千塚さんがスマホの画面上に指をすべらせ、私のために人生の貴重な時間を使ってメッセージを書いてくれた場面を想像する。千塚さんを見つけたその日から、彼の日記を読み込み、SNS上の交友関係を探り、コミュニティをチェックしては彼の嗜好の傾向を把握しようと努めてきたけれど、そんなデータのみで満足できるわけがなかった。私が本当に知りたいのは今千塚さんが何をして何を考えているのかということであり、どこにいてどんな言葉を口にしているのかということなのだから。
ゆめいろファクトリーのことを調べるのとは違い、一般人の千塚さんの情報を手に入れるのはとても難しい。インターネットで「千塚貴之」と検索しても本人の情報にはまったく結びつかない。私は、彼とは何の関係もないことが分かっていながらりんご農家を営む長野県の千塚貴之さんのブログを延々と追ってしまったり、千塚貴之という名前の持つ運気を解説する姓名判断のサイトを読み込んでしまったりしている。とにかく何かをしていないと居ても立ってもいられなかった。
千塚さんの卒業年度の東第一中学校の卒業アルバムはすでに必要な部分のコピーを手に入れていた。彼のSNS上での友人たちとのやりとりから千塚さんが今も実家で暮らしていることは知っている。
実家の住所をネットの地図で検索すると千塚さんの住む家を見ることが出来た。少年時代の千塚さんの写真を眺めながら、この家で彼が過ごしていた日々や今そこで彼が送る時間に想いを馳せる。私は今、距離も時代も隔ててしか千塚さんに触れられないことがひどくさびしい。
酔って好きでもない男とイチャつくなんて最悪。誘われた飲み会に軽く顔を出すだけのつもりでいたのにいつの間にか私は泥酔していて、カラオケでふたりきりになっていた男の指をくわえていた。その人の指は、たぶんどこか千塚さんのものに似ていたんだろう。まったく似ていなかったのかもしれないけれど。酔っているから、よく分からないな。
相手の指を吐き出して体を離すと、男はこちらが正気に戻ったことに気付いたようだった。それで酒を勧めてくるから、「いらない」うつむいたまま気分が悪くなったふりをして、はねつける。
男がお手洗いに立ったすきにそのまま店を出た。千塚さんと出会った街、ここ渋谷で私は一体何をしているんだろう。おとなしく自宅にいればよかった。もう絶対に、家から出ない。誰に呼ばれてもどこにもいかない。さびしさは千塚さん以外の人やものでは埋まらない。私の心と体はすべて、千塚さんのものなんだから!
それであたしは、嗚呼、さっきの相手が千塚さんだったらいいのに、せめて口に含んだあの指だけでも千塚さんのものとすげ替えられていたらいいのに、と考えて、あ嗚呼うああ、私、千塚さんが好き! と心の中で獣性の狂った咆哮を上げる。
千塚さんが好き。千塚さんが大好き。千塚さんがいいの。千塚さん以外全員嫌い。千塚さんと会いたい。千塚さんと手を繋ぎたい。今の私が千塚さんに触れることが過ぎた贅沢ならせめて、千塚さんの手や腕を一晩私に貸して欲しい。千塚さんの片腕を貸して。次の朝、千塚さんが目覚める前までにはきちんと返しておくから、どうかこの願いを叶えて欲しい。
私は千塚さんが欲しいのに、千塚さんとなら仲良くお付き合いしていけそうな気がするのに、どうして今すぐに一緒にいられないんだろう。
「前にライブで興奮した隣の人にタックルされて鎖骨折っちゃったことあるんですよ」
今日千塚さんが更新した日記にはそんな一文があった。私は千塚さんの身体を怪我させる原因を作ったゆめいろファクトリーに対して慰謝料を請求したい気分だったけれど、その話題でコメントを書くきっかけができたから今回は特別に許してやって訴訟は見送ることにした。
友人申請を受理してもらって以来、千塚さんの日記には何度かコメントをしている。そこで私が「いつかライブで会えたら良いですね」と書き込んだときには、千塚さんから「そうですね」という積極的で優しい返信も来ている。
千塚さんに会いたいって伝えちゃダメかな、そうあおいちゃんに相談すると、相手はまだ社交辞令で言っているだけだと思うし理由もなく会うことを打診するなんて不審だと反対されるけれど、やっぱり早く千塚さんに会いたい。声が聞きたい。どんな話題でどんな風に笑うのかを知りたい。彼の好きな食べ物だとか、小さい頃の思い出だとかを心置きなく尋ねてみたい。千塚さんが好きだ。千塚さんの長い指、悪戯っぽい八重歯、実年齢とそぐわない妙な若さ、好きなものに対する突き抜けたパワー、髪の毛、唇のかたち、鎖骨が折れていたこと、純粋で、可愛くて、あったかくて優しいところ。 そしてこれからゆっくり知っていくであろうもっとたくさんの千塚さんの素敵なところ。
新しい洋服を見に行ったりネイルサロンでデザインを選んでいたりするとき、千塚さんと会うことばかりを考えてしまう。可愛い服を買ったら彼に見てもらいたいし、手をつないだときに指先が目に入ったら、きれいだと思って欲しい。
最近どうですか、ネイリストさんから話を振られればもう、千塚さんの話題は止まらない。春が来たことを小鳥がさえずりで告げるように、恋をしたら弾む気持ちをまわりに触れてまわりたくなる。
私はSNSを通して知った千塚さんの情報を、さも彼の口から直接聞いたように、彼と触れ合う中で知り得たように会話の相手に話して聞かせた。少し都合の悪い部分は隠しながら自分なりにアレンジを加えると、千塚さんとの関係はもはや交際まで秒読み段階と伝えざるを得ないのだけれど、不思議とそれも真実からは遠くないような気がする。
色付いていく指先を見つめながら、春に花が開くことについて考える。花は、春が来てあたたかくなるから咲くのではなく、春が来て嬉しいから咲いてしまうんじゃないだろうか。千塚さんと出会った日にはつぼみだった桜も、もう花開きあっという間に七分咲きを超えそうだ。今、春が来ている。この世の中に、私の心に、千塚さんと共に!
千塚さんのことを誰かに話しているとき、そこにいくらかの嘘があっても、妄想で補足されている箇所があったとしても、語るほどに私の彼に対する想いは増していき、ふたりの関係を信じることができた。そういうとき、私は自分が強くなったような気持ちになる。どんなさびしい夜だって、いつか千塚さんとともに過ごせる日々のためなら乗り越えていけると感じる。
「ねえ、私、彼氏が出来るかもしれない」
「そうなんだ、私の知ってる人?」
「ううん。知らない人。千塚さんていうの」
「へー、おめでとう」
私と千塚さんの愛を祝福したいずみは、そのまま同じトーンで話を続ける。
「ところで、女衒から連絡来てるんだけど、今日の夜お花見クルーズ行かない?」
「話聞いてた? 私、彼氏出来そうなんだよ」
「だから何?」
「そのタイミングで出会いの場に行くわけないじゃん」
一瞬間を置いて、いずみは首をかしげる。
「そうなの?」
私は当たり前のことを言ったつもりだったけれど、相手にはまったく届いていないようだった。たしかに、彼女が誘ってきた集まりを「出会いの場」と呼ぶのは語弊があったかもしれないけれど、少なくとも異性との交流の場ではある。いずみが「女衒」と呼ぶ三十過ぎの女が主催している飲み会やイベントは、経済的に余裕のあるおじさんと若い女をマッチングさせる趣旨のもので、私たちは条件が合えばそういうものに参加してキックバックを受け取っていた。
「まあ、出会いの場というより、単なるバイトみたいなもんじゃん。気にしなくていいでしょ」
「千塚さん以外の男の人と、もう話したくない」
「相手を男だと思うな、金だと思え」
「千塚さんにも悪いし……」
「ふーん。まあ、まだ早い時間だしもうちょっと飲んでから考えよう」
いずみは片手をあげて店員を呼び止めるとレモンサワーを注文し、私にも次のドリンクを促した。どいつこいつもみんな私のことを、「酔わせればなんとかなる」と思っているようだけど、千塚さんを想う私の心はもうそんなに軽くはない。
気がつくと私は、大横川を走るクルーザーの上にいた。
居酒屋ですっかり出来上がってしまい、いずみから「このあとシャンパン飲もうよ!」と乗せられるままに女衒がセッティングした船に乗せられた記憶はうっすらある。もういずみもすっかりやり手ババアの側にいるようだ。それとも私がばかで軽薄なだけなのだろうか。夜に重しが欲しい。
川の両岸には桜並木が続いていた。クルーザーは緩急をつけてその間を進んでいく。ライトアップされた夜の桜は乳白色のオパールのような光を放ち、その連なりがホログラムのトンネルを作り出している。桜の花自体に光が宿り、そこからひとつひとつ音の震えが感じられるようだった。同乗している騒がしい酔っぱらいたちの声がもしも止むなら、一帯に花の奏でる音色が響きそうな夜桜。
この桜を千塚さんと一緒に見られたらいいのに、と自然と考えてしまう。船を降りたら二度と会うつもりもない女の子やおじさんたちとこの瞬間を共有しても、ただむなしいだけだった。
桜の枝が川面にしなだれかかるように垂れ下がる場所で、船は速度をゆるめる。みんなが一斉にスマホで写真を撮り始めた。私も何回かシャッターを切るけれど、画面に表示される桜は目に映るものとはまるで違っていた。
「鈴ちゃんも入って。みんなで撮ろう」
おじさんのひとりが集合写真の枠内に私を押し込む。さっきまでもう少し酔っていたときには気持ちよく喋れていた相手だったのに、今はどうしてこの人が馴れ馴れしく私に触れるのかも、分からない。グラスで顔を隠してその場をやり過ごし、残っていたシャンパンをあおった。そのまま上を見遣ると、花びらが空飛ぶ魚のうろこのように銀色に輝きながら舞い散るのが目に入る。川面にはもういくつかの花びらが浮かんでいた。
私はこの桜の下で、千塚さんと触れたときに覚えるであろう感触を想像する。
四月の夜、彼の鼻の先はきっと少し冷たい。千塚さんとキスするなら、その冷たい鼻先は唇よりも先に私に触れるだろう。お互いの鼻がぶつかるやや硬い感触を覚えるとすぐに、千塚さんの唇が私の口元を覆う。下唇のほうが少しだけ厚い千塚さんは、やさしく包み込むようなキスをしてくれるはずだ。睦み合う長い口付けの途中に、彼の指が私の髪を梳く。それは少し、くすぐったかったりもするのだろうか。
「ねえ、鈴ちゃん、写真送るから連絡先教えてよ」
「あ、彼氏いるから無理です」
おじさんの一言で現実に引き戻されたせいで、とっさに相手を拒絶してしまった。
こういう答え方をすることは、当たり前ながら女衒主催の飲み会では歓迎されない。別に、彼氏はいるならいたでいいだろうけれど、それを公言するにしてもおじさんたちの期待を潰してはいけないのだった。こういう場での男の優しさは、チャンスを感じさせてくれる女にのみ向けられる。それがなくなるということは、こちらへの当たりが厳しくなるということだから、自分にとっても得になる話ではなかった。
「絶対、鈴のせいだよ」
タクシー代が出なかったことにいずみは腹を立てていた。私だって、憤りで血管がブチ切れそうではあるが、自分で蒔いた種なのだから仕方ないと思うしかない。
クルーザーを降りた後、みんなで店に入って飲み直す流れになったけれど、場の雰囲気はどんどん悪くなっていくばかりだった。船の上で私が連絡先の交換を拒否したおじさんは、他の女にターゲットを変えればいいものの次の店でも私に照準を絞り、そのたびにこちらの対応に不満を示した。彼はおじさんたち側の中心人物だったようで、まわりもなんとか私たちをうまくいかせようと援護してきたけれど、彼氏がいるからどうのこうのとネチネチ言ってくるおじさんに途中から本当に嫌気がさしてしまってシカトし始めたら彼の一声で場はお開きになり、私は他の女の子にもおじさん連中からもうとまれて店を後にしたのだった。
いずみは吊り革に片方の手首を通してぶら下がるような格好になっている。彼女と電車で帰宅するのは、はじめてかもしれない。
「盛り下げちゃってごめん」
私が話しかけるとスマホに目を落としていたいずみは顔を上げ、ほんの短い間、何も言わずにこちらの目を見つめ小さく口を動かす。
「本当」
にらまれたわけではないけれど、何も言い返せない。飲み会のキックバックとタクシー代はお互いにとって大事な収入源だった。それを知っていながら自分の事情だけを優先するなんて、本当はしてはいけないことだったんだと思う。
「対価発生してるんだからちゃんとしようよ。向こうも接待飲みっぽかったし、ああいう態度とったらまわりの人も可哀想じゃん」
正論めいたことを言ういずみの言葉を黙って聞いていた。そういうことはまともな場所でまともな相手にだけ言って欲しいというのが本音だった。ギャラ飲みなんて体のいい援交みたいなものなんだから、そんな倫理観を持つ必要はないと思う。だけど、現実の問題として彼女が手にするはずだった収入の一部を私がおじゃんにしてしまったことは心苦しい。相手に何の補填もしてあげられないなら、こうしておとなしく叱責を受けるしかない。神妙な表情を作るだけなら、無料(タダ)だ。
「……彼氏いるって言ってたけど、まだ付き合ってはないんじゃなかったっけ」
私の反省を感じさせる姿勢を見てか、いずみのほうから話題を変えてくれた様子だった。
「うん、でも、もうすぐって感じだから」
「ふーん。彼氏いるから連絡先交換できませんってウケるね」
「ごめんね。千塚さんのこと、裏切りたくなかったの……」
「そんな真面目な人なんだ」
「うん。それに優しいし、情熱的で、すごくいい人」
今のところ千塚さんの情熱的な面はゆめいろファクトリーに関してしか発揮されているのを知らないけれど、間違った情報というわけではない。
「どこで出会ったの?」
「……SNS」
本当のことを言うべきか否か、葛藤があった。中途半端に倫理的ないずみには、千塚さんとのなれそめを話せそうにはなかった。余計なことで叱られるのは趣味じゃない。
「そうなんだ。ツイッターとか? 何がきっかけで会うようになったの?」
だけど、相手から質問されるうちに、少しだけ試してみたくなる気持ちが生まれる。千塚さんとのことは、まだあおいちゃんしか事実を知らない。他の人に話すことはあっても、その内容は私の編む物語だという自覚はあった。だからこそ不安だった。自分が置かれている状況に客観的な意見が欲しかった。占うようなつもりで、私はいずみに今の状況を伝えた。
「まだふたりで会ってはいないんだよね」
相手の眉根に軽くしわが寄る。彼女は私が言ったことを飲み込めていないようだった。薄墨をこぼしたようにさっと胸に広がった動揺を隠して、私は話を続けた。
「SNSで仲良くなって、メッセージのやり取りとかをしてるの。それで、それが、その……とってもいい感じで」
「はあ。だけど普通、そういう風に仲良くなったら男の方から食事に誘ってきたりしない?」
「まあ、そうだよね」
「その気配はあるの?」
「多分ね。彼は恥ずかしがり屋さんなんだと思う。女性は苦手って言ってたし」
どこからも入手していないでっち上げの情報で切り返す。いずみはまだ、要領を得ないような顔をしている。
「めんどくさい男だなあ。っていうか、本当に会えるの、それ。なんか会えないような気がしちゃ……」
「会える。会うよ、絶対会う!」
悪い結果の出る占いなんて信じない。食い気味にいずみの言葉を遮ると、相手の目が少し泳いだ。
「ちなみに、その人の顔は知ってるんだよね」
「うん」
「まあ、それにしてもさ……」
地下を走る真っ暗な車窓に私といずみの顔が並んでいる。ガラスの中のいずみと目が合い、彼女は私から視線を外す。
「ネット上で交流を深めるのもいいけど、なるべく早く会ったほうが良いんじゃないの」
「出来るだけ頑張ってみる」
「そうして。実物がどんな感じかは分からないもん。写真なんてどんな風にでも加工できるし、そもそも別人の写真かもしれないからね」
それだけは否定出来ることだったけれど、言い返せば出会いの経緯との矛盾が生まれてしまうので黙っているしかない。
「でも、もし相手の顔が写真と違ってても私は別にいいよ。千塚さんの見た目を好きになったっていうわけじゃないし。性格いいのは分かってるんだから大丈夫」
「そうは言っても、会って喋ったり遊んだりしなきゃ分かんないじゃん。ネット上での発言なんていくらでも取り繕えるでしょ。そこだけで相手がどんな人か判断するなんて……」
心配無用、とはねつけたかった。占いの時間はもう終わりだ。いずみにはもっと現実を見て欲しい、リアルな千塚さんの姿を。そうすれば、彼がどんなに素敵な男性か分かってもらえるはずだ。千塚さんとお付き合いして、早くいずみを彼と会わせてあげたかった。私の愛する千塚さんを前にすれば、彼女はきっと自分が誤解をしていたことを詫びるだろう。私には、両手をついて謝るいずみの体を起こし、その額についた泥を白いハンカチで拭ってあげるところまでイメージできている。未来の予想図が頭に浮かぶと、車窓の中の私の口元もほころんだ。その横で、いずみの警告的なアドバイスはまだ続いていた。
「そんなのってまぼろしに恋してるのと一緒じゃん」
最後に私の耳に入ってきた言葉は、すぐに消えてはくれなかった。地下を走る真っ暗な車窓に私といずみの顔が並んでいる。ガラスの中のいずみと目が合い、私は彼女から視線を外す。
早く千塚さんに会いたい。千塚さんに触れたい。Linxにアクセスしてもまだ千塚さんの日記の更新はなく、仕方なしにもう何度も読んでいる二日前に投稿された彼の最新の投稿にまた目を通す。
書かれている内容は相変わらず、ゆめいろファクトリーのことだ。日記にはまなこのブログに飛べるURLも貼り付けられていた。こちらも、もちろんチェック済みだった。ブログには父親の誕生日に自宅で手巻き寿司パーティーをしたという報告と、家族と思われる四人の手元が映った写真、それから手巻き寿司を頬張るまなこの顔が上げられていた。アホ面の背後に映る窓の外はまだ明るい。昼間から、ずいぶんとおめでたいことだ。私の脳みそには、また無駄なまなこの情報ばかりが蓄積されていく。こいつの好きな手巻き寿司の具がイクラとサーモンとキュウリの組み合わせだと知ったところで嬉しくもなんともない。私が知りたいのは、千塚さんなら何を巻くかだ。
千塚さんは、寿司を巻くまなこが可愛いという。お父さんを大切にしていてえらいねという。まなこを持ち上げる千塚さんの日記を読んでいると、いつの間にか自分が両の奥歯を食い縛っていることに気付く。悔しくてたまらないけれど、千塚さんだって、ずっとこんな風にまなこのファンでいるわけではない。アイドルでいられるのなんて若い間のほんの短い期間だけだし、いずれはグループも解散する。うまくいけばそこでまなこは引退するだろうし、そうならなかったとしてもどのみち、いずれは死ぬ。千塚さんもそこまでの過程で、きっと目を覚ましてくれるはずだ。これだけ何かを好きになれる人なら、きっと私と恋をしても情熱的な想いを持ってくれるだろう。私だって、千塚さん以上にいつまでも彼を愛し続ける自信がある。大丈夫、千塚さんなら大丈夫、私と最高の関係が築けるはず、そう言い聞かせる。
いずみと別れて帰宅してから、化粧も落とさずベッドに横になって千塚さんのSNSの画面をずっと眺めていた。それ以外には、何もする気になれなかった。
いずみは私の千塚さんへの想いをまぼろしと一緒だと言ったけれど、そもそも恋そのものが相手にまぼろしを見ることなんじゃないだろうか。千塚さんだって、恋とは違うかもしれないけれど、実際に知り合ってもいないまなこに夢中になっている。
私は千塚さんを一目見ただけで気がついたらもう彼のことを好きになっていた。考えを巡らせる余裕もなく、どうしようもなくなってしまっていた。春が来て開く花が我慢も逡巡もしないように、私の恋は千塚さんに巡り合ったことでただ喜びを覚え、始まってしまった。人を好きになる気持ち自体かたちのないまぼろしのようなものだというのに、それをいちいち現実と照らし合わせて過度に期待をしていないか確認するなんてばかげていると思う。己の胸に宿る熱い想いを信じてさえいれば、夢見ることを恐れなくてもいいはずだ。私の中には、自分が想う千塚さんの姿がまぼろしであったとしてもこの気持ちを貫いていく覚悟がある。彼に出会って恋に落ちたことが始まりで、そこで話は完結している。今日のいずみの言葉には引っかかりを覚えたけれど、本当は、疑うことなんて何もないんじゃないだろうか。揺らぐ必要だってどこにもない。恋はいつでもアルファ・オメガ。始まってしまったらもう、終わりまで突っ走るしかない。
Linxを閉じて、いずみに今夜のことを謝るメッセージを送った。
「今日は本当にごめんね。あの後で、千塚さんと会う約束できたよ!」
追加した一文はまだ予言ではあるものの、そう書いてみるとそれは確かに、本当になることのような気がした。
4.赤い私とミドリの彼女
「来週、ランチ行かない?」
美南から送られてきたそのメッセージに、もう三日も返信をしていない。千塚さんのいるLinxにはこまめにアクセスできても、それ以外のことになるとからきしダメ。メッセージを受け取った時点での来週はすでにもう今週だ。彼女にはいつも世話になってばかりなのに、なんて不義理で失礼なことをしてるんだろうと自己嫌悪を覚えるけれど、それでも指は動かない。脳みそも働かない。まるで、自分の体が自分のものじゃなくなったみたいだ。
深夜二時には魔物がいるって、誰が言ってたんだっけ、誰に言われたんだっけ。
たぶん誰も言っていない。だけど私は知っている。たぶんみんなが知っている。だけど誰も口にはしない。クラクラと起きているひとりの部屋で、二時の魔物は厭なことばかり考える、思い出す。魔物は脳みその中にいる。もしくは、脳みそにいるのだと私に錯覚させている。魔物はいつだって飢えていて、欲望のサティスファクションを求めている。欲しがる疼きは私に伝わる。私の脳みそは千塚さんを求めてる。身体中を掻き毟って叫び出しそうになるほど彼が欲しい。どうして私はこんなにも千塚さんが好きなんだろう。千塚さんのすべてが欲しくて、すべてが好き。
そう、私が千塚さんのどこを好きなのかという質問がナンセンスなのは、私が千塚さんのすべてを好きだからで、だけれどもしも千塚さんの身体がバラバラにされて世界の七ヶ所に散らばってしまったのならば私はまず顔から探しにいくから、やっぱり私は千塚さんの顔が好きなんだなって思うんだけど、それってわりと一般的に広く理解される世界の七ヶ所に愛する人の身体を散らされた者が回収しにいく部位の順番のように感じるから、それだけでは私が千塚さんの顔が好きという確固たる理由にはならないんじゃないかと思うの。だって男の人の足や肩甲骨のあたりから自分の手元に取り戻そうとする女の子なんて、なんだか変態みたいだし少しマニアック過ぎない?
私はこの場合、顔から回収するのがすごくスタンダードなやり方だと思っているけれど、違うのかな。だって顔があったら、おしゃべりもできるし、キスだっていっぱいできるもん! そういう行為は足や肩甲骨ではこと足りないものだから。じゃあ、もしも世界の七ヶ所に散らばるのが千塚さんの身体の各部位ではなくて顔のパーツだったら、私はどこから彼の顔を回収し始めるのかと考えると、うーん、可愛い唇かな、涼しげな目元かな、憂いを感じさせる涙ぼくろも捨てがたいし、八重歯だってスペシャル可愛い! 嗚呼、もう大好き。なんて可愛いの千塚さん! と、錯乱状態に陥ってしまうから私にはやっぱり千塚さんの「どこが好き」っていう部位指定はなくて、全部が好きっていう包み込むような愛情でしか彼を想えないことがきっと誰にでも分かってもらえると思うの。
運命という言葉はきっと私と千塚さんのためにあるんだから絶対にチャンスを逃さないわと決意をしてから早二週間、彼とはいまだに顔を合わせてお話することもままならず、私は勝ち気と気後れをループしたままパッとしない日々を送っているし、その上ここ二、三日は生理前特有の不眠で眠ることもままならない。やっと眠れたと思ったら千塚さんが出てくる悪夢なんて見る始末で飛び起きた脳から溢れ出す厭な汁がPMDDの不調と重なって私の脳内は見事なまでのホルモンテロに遭ってハイパー鬱!
仕事なんて行く気にもならないし、友達からの連絡もスルー。金もないし元気もない。
千塚さんのことを好きで好きで仕方がない私は、千塚さん以外の他人と向き合うのがもう嫌なの。千塚さんのこと以外の話題を千塚さん以外の人に発信して、千塚さんに関すること以外の内容を受信するのが嫌なの。千塚さんのこと以外のすべてのどうでもいい話題を発信してそれに反応されて対応しなきゃいけないことがめんどくさいの。だから私は自分の頭の中だけで千塚さんに奉げる幾つもの空想、抒情詩、愛の言葉を生み出しているときだけがとてもしあわせ。
幸福の青い鳥は実はそばにいるものだっていうけれど、今私の右手の中でさえずっている青い鳥は不幸のはけ口になっているみたい。露悪ギリギリの自己顕示欲と不安と倦怠感をブチッとちぎって140字以内にまとめて、私は千塚さんのことを想うしあわせ以外の感情をツイッターに投稿する。
夜な夜なタイムラインを徘徊しては140字以内の鬱を読み140字以内の鬱を書き、鬱を投稿し鬱にリプライされ鬱をRTし鬱にフォローされ鬱をリムーブし鬱々として鬱のままもののはずみでリンクされていた風俗嬢達のホンネ掲示板なんかににうっかりアクセスして彼女たちの鬱な書き込みに反応した脳からまた厭な汁が溢れ出す。このまま仕事にも行かなくなってもっとお金がなくなったら、私も風俗をやるのかもしれない。嫌だな、と思うけれど、そういう想像ほど止まらない。私は毎日死にたい気持ちになりながら、生きるために体を売るのだろうか。考えるだけで吐き気がするけど、もっと悲しいのはそういう風に働いたとしても、今はたいしたお金にならないとこのサイトでもみんなが愚痴をこぼしていること。そんなの本当に、死にたくなる。
「昔はAVも、もっと待遇良かったけどね」と書き込んでいるのは、たぶん私より年上のおばさんだと思う。風俗もそうかもしれないけど、AVの業界も今は、若くて可愛い子しか採用されないらしい。人並みでしかない女は門前払いされるなんていう話を聞くと、昔はそうでもなかったと思うけどね、と、自然と頭の中で過去の思い出や出来事が参照される。それはまた、厭な記憶だった。やっぱり、千塚さん以外のことを考えるとロクなことにならない。私の心に光を射してくれるのはもう、千塚さんしかいない。千塚さんに好きになってもらえないのなら私の存在理由なんてないし、もう人生どうなってもいいやと思ってしまう私は間違いなく馬鹿なんだけど、この思考回路を正せる利口さは持ち合わせていないから私に目をつけられたことがもう運の尽きだと思って、私と付き合ってもらえませんかね千塚さん。私のこと好きになったり私とセックスしたりしてくれませんかね。もうそろそろ観念してもらえませんかね。せめて一回、一緒にごはんとか行ってくれませんかね。私、千塚さんが注文したドリンクに密かに睡眠薬を混ぜるんで、私と話しながら「あれ、このコもしかしてイタい感じ? あ、なんかヤバい女?」と薄々勘づきながらも、お手洗いから帰ってきたら手元のアルコールの苦味が少し増したことには気付かずに、そのまま飲み干してもらえませんかね。ハイ、一気!
そしてそのままもう二度と目覚めることがなくても気にせずに成仏していただけましたら助かります。スペシャルな法要を済ませたあと、千塚さんの血や肉は私が美味しくいただきます。お顔だけはそっくり残して、ホルマリンで満たされた標本瓶に納めさせていただきますね。ほら、やっぱりお顔があれば、おしゃべりだってキスだって、いっぱい出来ますから。
ああ可愛い千塚さん。
私、千塚さんのことじっと見てたいし撫でまわしたいし、喋りかけたいし笑いかけたいし、喋りかけられたいし笑いかけられたいし、ごはん作ってあげたいしそれを食べてもらいたいし、お嫁さんになりたいし千塚さんの子供が欲しいし、一生涯千塚さんに寄り添っていきたいし、やっぱり死んでるより生きたままでいて欲しいです。生きたままの千塚さんが欲しいです。ということで、千塚さんがまだ生きてる頃までタイムスリップ!
千塚さん、今日も生きてる千塚さんが私はとっても大好きですよ。千塚さんに、私きっともうすぐ会えますよね。千塚さんが会おうとしなくても千塚さんのご自宅の住所は控えてあるからそこにいけばいつでも会えるし、出会ったならば千塚さんはきっと私のことを好きになってくれますよね。だって私はこんなに千塚さんのことを好きなんですもの。千塚さん、私はあなたのことが誰よりも好きだし、もっと好きになるし、千塚さんだってきっと私を好きになってくれるから、ふたりでいたらとてもしあわせになれるのが私すごく嬉しくて今もう、ちょっと泣いてます。お付き合いが始まった一年後にはめでたく結婚をし、千塚さんとの間で可愛いこどもたちにも恵まれて幸せな家庭が築けるだなんて私、夢みたいですでに現実が受け入れられません。私と会ったが百年目、盲亀の浮木ジャストフィット、優曇華の花咲き乱れボーイ・ミーツ・ガール、それは運命。そう、私に好かれたのが運の尽き。私、千塚さんのこと、ずっとしあわせにします。一緒にしあわせになりましょう。なれますよ、ね、私たちなら。あ嗚呼、とってもしあわせ。ねぇ、ネバーギブアップ人生!
躁転。一寸先は光だ。いつもこの瞬間が来る。黒で埋め尽くされていた盤面が一手ですべて白に変わるみたいに、鬱が急に裏返されてなんでもできるような気分になる。こんなのも異常だ。それくらい分かる。でも、いつもそう。たぶん今、生理がきた。毎回血が流れ始めると、絡まっていた思考や感情の糸がほぐれて嘘みたいに心が軽くなる。ちょっと軽すぎて飛び出しちゃう。縛り付けていたガリバーを無重力空間で解放させたみたい。
私は突然うきうきした気持ちになって、ずっと既読スルーしていた連絡に返信なんか始めてしまう。バイト先の店長には出勤の希望を送り、ランチに誘ってくれていた美南とも早速会う約束を取り付けた。
「ちょっと、鈴(りん)ちゃん、一旦話止めてもらってもいいかな。私このままだと千塚さん博士になっちゃうから」
「いいんだよ。千塚さんはいいものなんだから、もっと千塚さんに詳しくなって、千塚さんのこと好きになろうよ。あ、でもダメ。本当に好きになったら私、美南のこと刺すからね!」
ちょうど右手に握っていたナイフの刃先を反射的に美南のほうに向けてしまい、慌てて引っ込める。彼女は苦笑いを浮かべた。私たちは美南の家のすぐ近くにあるカフェで約束していたランチをとっていた。
「好きにならないから安心してね。私、結婚してるし」
美南はオムライスをもう半分食べ終わっている。私のハンバーグはまだ運ばれてきたままの状態に近かった。彼女に話を遮られたことで、今までずっとひとりで喋っていたということにやっと気がついた。
「さっきから話を聞いてると、千塚さんてなんだか特殊な人みたいね」
「千塚さんの特性の表層部分だけを見たならね」
さっき美南のほうに向けたナイフで冷めつつある肉を切り、彼女のペースに追いつくように急いで口に運ぶ。
「深層まで切り込んだらもっと変わったところもあるかもしれないけど……」
「そんなことないよ。千塚さんは優しくてかっこよくてとっても良い人。ただちょっとだけ何かの間違いで売れない地下アイドルなんかにハマってるだけ」
「そうなのかなあ。そういえば、なんていうグループなの?」
美南からの質問に、頭の中で火花が上がった。ここ最近は、あいつらの名前を思い浮かべただけで脳みそが発火しそうになる。ゆめいろファクトリー、口にするのもおぞましい呪いの言葉だ。
「言っても分かんないと思うよ。なんだったっけ、軽く忘れちゃったな。たしか、くそみそシスターズとかなんとか」
「へえ、知らないや」
「あいつらのことさえ好きじゃなかったら千塚さんは本当に完璧だよ」
「完璧、なのかなあ。鈴ちゃんその人のこと買い被り過ぎてないかな」
「夢見ちゃいけないっていうの? まあ、もう私は夢見ることを恐れてもいないけど!」
「だけどやっぱり、期待し過ぎるのは……」
美南はそこで言葉を止めた。私には相手が何を言いたいのか、聞かなくても分かるような気がした。彼女は私が過去にどんな恋愛をしてきたのかをもっともよく知る人物だった。
「もう、間違えたりしない」
私の言葉を受けて、美南は唇を軽く結ぶ。その表情は微笑みのようにも見えたし、口をつぐんでいるようにも見えた。彼女は私の過去の間違いを知っている。私もそれを自覚している。だからこそ、もう同じことはしない。していない、はずだとは思っている。そうじゃなきゃ、意味がない。「間違いからも学べることはある」。過去に意味があるとすれば、そういう言葉しかあてはめることができない。
美南が連れてきてくれたカフェは、駅から少し離れた住宅街の中にある。ナチュラルウッドとグリーンの配色がやさしい落ち着いた店で、メニューも店内の雰囲気も尖りがなくてプレーンだ。白木造りのテーブルの上でいちごとチャービルの葉で可愛らしく飾られたチーズケーキの写真を撮りながら、私はまた自然と千塚さんのことを考えている。こういうスイーツと一緒に撮ったいい感じのセルフィーをSNSに載せて、千塚さんの興味を少しでも引きたい。女友達と来ていることをアピールして、一緒に出かける彼氏はいないと暗に伝えたい。今のところ、唯一つながっているLinxでの私の人物像はアイドルオタクの中年男性を思わせる設定だから無理な話ではあるけれど。
「あのね」
彼方にいる千塚さんに想いを馳せていた私に、美南が呼びかける。彼女の顔に目線を遣ると、そこにはほんの少しはにかみの表情が浮かんでいるように思えた。
「聞いて欲しいことがあるんだけど・・・・・・私、赤ちゃんができたの」
「……おめでとう!」
祝福の言葉より先に感嘆の声を上げざるを得なかった。美南の頬がゆるむ。はにかみの中に見えた緊張がするりと落ちて、嬉しさと喜びを感じさせる笑顔だけが残っていた。
「名前は決めてるの?」
「まだ」
美南は小さく首を横に振った。
「男の子なら、貴之にしよう」
「なんで?」
「千塚さんの名前。忘れちゃったの? かっこよくて優しい男の子に育つんじゃないかな」
「その名前はつけないように、よく覚えておかなきゃ」
軽口を叩き、美南は口の端を上げる。カフェの大きな窓からは昼下がりの陽射しが降り注いでいる。この店の採光は抜群。その光は美南だけを照らしているわけじゃないけれど、私には彼女がいつもより明るく、輝いて見えた。恋に落ちた相手を見ているときみたいに。
「今日はすごく良い日だな」
私が言うと、美南はふっと小さく息を吐くように笑う。丸くて角のない笑い方は、ひらがなの「ふ」をそのまま唇からこぼしたようにやわらかい。
彼女から妊娠の報告を聞くような仲になれるとは、出会った当初には思ってもいなかった。私たちがはじめてまともに喋ったのは、警察署からの帰り道だった。その頃、私は当時の恋人に振られたばかりで、毎日死ぬことばかりを考えていた。
ずっと、失恋して自殺するような女なんて馬鹿だと思っていた。ひとりの男との関係が終わったとしても世の中には他にたくさん男はいるんだし、恋なんていくらでも出来る。失恋なんてよくあることだ。どんなに辛くても苦しくてもみんな、そんなことくらい乗り越えている。
喪失感を表すたとえに「心にぽっかり穴が開く」というものがあるけれど、私の心には本当に大きな穴が穿たれたようだった。平穏な状態の心が鍋敷きのように丸く平らなかたちだったとしたら、彼を失ってしまった直後の私の心は底のないサラダボールのようなかたちに変形していた。全神経を集中させて縁につかまっていないと、下方の暗い場所に簡単に滑り落ちていきそうだった。「あ、死のう」と、ふとした瞬間に思った。死を願う気持ちは決意とは違った。「あ、」の瞬間に意思はなく、タイミングやシチュエーションだけがあった。そのどちらもが揃ったときに、人はそれまで必死に掴まっていたサラダボールの縁から手を離してしまうのかもしれない。
私は別れた元恋人のことばかりを考え続けた。考えたくなくても、私のことを一番好きだった時期の彼が自然に何度も思い出された。お互いを想う天秤のバランスが保たれていたあの頃。私の名前を呼ぶ彼の声、そのあとに、彼の唇が私の耳に触れるそれだけで、しあわせだったこと。
「あ、」の瞬間は、鬱々と過去を振り返るひとりきりの部屋に度々やってきた。私は極力ひとりでいることを避け外に出て、生きるためにお酒を飲んだ。
飲んで、吐いて、酩酊して誰かとセックスして、記憶をなくして、翌朝に言動を恥じてもやり場がなくてまた飲酒して全部吐き出して、そんな繰り返しばかりを続けていた。
関係を持った相手に優しくされても、その喜びが持続することはなかった。その代わり、見下されることがあってもダメージが尾を引くことは少なかった。自分が関心を持っていない人間からされたことは、容易に流すことができた。もう会うことさえないのに私を傷つけるのはいまだに彼だけだったし、その傷を彼が癒してくれる日が再び来るのではないかと私はいつまでも心のどこかで期待していた。傷付けられた人に癒してもらいたいと願ってしまうのは、なんて厄介なことなんだろう。
ある朝目覚めると、四方を透明なガラスに囲まれた部屋の中にいた。
パニックになって声を上げた私の部屋の前に男性の警察官が駆け寄ってきた。彼は状況が飲み込めていない私をなだめながら、ここは警察署の中にある「保護室」だと説明してくれた。泥酔者を保護し収容するための部屋らしい。私は酔っ払って路上で寝ていたところを通報されて、連れて来られたのだという。「朝の五時までは出られないから」警察官は私にそう伝えると、あっさりと去っていった。自分がどうしようもなく惨めで恥ずかしく、部屋の隅で私は体を丸めて泣いた。
朝、私は透明な部屋から出され署内の別の部屋へと連れて行かれた。一通り中身を点検されたらしい自分の荷物を受け取って、渡された用紙に住所と名前を書く。担当の警官が私に、誰かここまで迎えに来てくれる人はいないかと尋ねた。ひとりでは帰してくれないらしい。この二年間、恋人以外とまともに連絡も取り合っていなかった私には、朝の五時に警察署に迎えに来てくれる人間なんて心当たりがなかった。
坂出美南は、当時私が働いていた本屋さんのバイト仲間だった。それまで、シフト以外のことで連絡をとったことはなかったし、お店でも特別に話をする仲というわけではなかった。その程度の知り合いだったにも関わらず私が自分の狭く薄い交友関係から彼女に「お迎え」を頼んだ理由は、今後の人生でもう関ることがないだろうと思ったからだった。バイトには彼氏と別れたのを機にふっと行くのをやめてしまっていた。この先二度と会うことがない相手になら、どんな醜態を見せてしまったって迷惑をかけたって構わない。
「クソほど酔っ払ってまして、すみません」
「大丈夫? お水買ってこようか」
「それよりも、今はしょっぱい汁物が飲みたいです。お酒飲んだ後よく思うんですよ、自販機で、『あったか~い だし汁』が売ってないかなあって」
「のんべえだねえ」
そう言って、坂出美南はふっと息を吐くように笑った。私たちは駅のほうへ向かう道を並んで歩いていた。彼女には、警察署から出るときだけ付き添ってくれれば助かるとさっき伝えていた。家まで送らせるのは忍びないし、恥ずかしい。迎えに来てもらってなんだけれど、できるだけ早く別れたいというのが本音だった。この先にある信号がおそらく分岐点になる。
「今日は本当にありがとうございます。ごめんなさい。こんな早朝に……」
「大丈夫だよ。いつもこのくらいの時間には起きてるから。旦那が朝早いの」
「ご主人、怒ってませんでしたか?」
「うーん、笑ってた」
「あの、バイトのことも……その、バックレてごめんなさい」
「もう、やめちゃうの?」
「うん、そうですね」
「そっか」
「すみません、それなのに、こんなときばかり連絡しちゃって」
「まあ、人生色々、事情も様々だと思うので」
軽く下げた頭の上から坂出美南の優しい声が降ってくる。私はその言葉でまた、別れた元恋人のことを思い出してしまっていた。顔を上げた瞬間、まぶたの縁にたまっていた涙がこぼれた。慌てて顔を両手で覆い、その場にうずくまる。涙が手のひらを伝って滴り落ちてくる。まだこんなに泣ける。彼のことが好きで、好きで好きでたまらない。
「あー、あのですね坂井さん、私、彼氏にフラれちゃったんです」
悲しくて苦しい気持ちの正体を口に出すと、分かってはいるけれど、あまりに間抜けだ。世の中にありふれたこんな事象でここまで打ちのめされている自分がみじめで、今すぐにこの場所から消えてしまいたかった。
顔を覆った指の隙間から、坂出美南の足が見えた。彼女は膝をかがめて私に寄り添ってくれていた。
「私なんかが力になれるか分からないけど、宮下さんが良ければ、なんでも話してね」
そう優しく言葉をかけてくれた坂出美南とはもう会うことがないから私は、彼女に促されるまま入った早朝のデニーズでこの恋愛のかっこ悪い顛末を話した。私のモノローグにも似た自分語りは卓上に置かれていたモーニングのメニュー表がランチのそれに変えられるまでとどまることがなく、私と彼女との関係は、それからもずっと続いている。
あんなに苦しんだのに、今ではあの元恋人の顔をちゃんと思い出せるかどうかさえ自信がない。記憶はほとんどのっぺらぼうに近い。私が特別に薄情者だというわけではなく、それはわりと普通のことなんじゃないだろうか。過去の恋は、新しい恋で塗り替えられた。晴喜(はるき)に出会って、私はのっぺらぼうの元恋人を想う苦しみから抜け出し、今まででいちばんつらい思いをする日々の中にはまり込んだ。
「あの女、ちょっと頭がおかしいんだよ」
晴喜の初めての浮気が発覚したのは、見ず知らずの女が私に非通知で電話をよこしてきたことがきっかけだった。そのクソ女は電話口で長々と自分と晴喜との恋愛関係について語り、私に彼と別れるよう求めてきた。
すぐに晴喜に詰め寄ると、彼は自分の無実を主張し、女に責任を転嫁した。今では、そんなセリフはお得意のいいわけであるとすぐに分かるけれど、当時の私は彼が被害者なのだと本気で信じてしまった。相談に乗ってもらっていた美南からのアドバイスもはねつけて、二度目に同じことが起こっても、ただ彼の言い分を信じた。
裏切られての、三度目。そのときに、当て付けのつもりで他の男とデートをした。その相手が祐一君で、彼とのデートはあおいちゃんにそのすべてを話したとしても許してもらえるくらい健全なものだった。それくらい私は晴喜に対して義理堅くしかいられなかった。祐一君と一緒に過ごしている間も、ずっと晴喜に会いたいとだけ思っていた。
それ以降の浮気に関しては、もう私は無駄に足掻くことさえやめた。晴喜はどんなときも「被害者」ではないことは分かっていたけれど、私はそれでも彼を許した。腹の内では浮気相手の女どもへの憎悪の炎がいつでも燃えていた。
数え切れない浮気がやっと終わりを迎えたのは、去年の秋のこと。心はもうぼろぼろになっていながらもまた晴喜を許そうとした私に彼が言った。
「ごめん。これからは、あっちと付き合っていきたいと思ってるんだ」
晴喜をなじる言葉はいくらでも出てきた。私から始まる私のターンだけの古今東西「罵詈雑言」はいつまでも終わらなかった。別れを告げられた瞬間から、私は晴喜を憎んでいた。いや、正確に言えば私はその時に、自分が今までずっと晴喜を激しく憎んでいたことに気が付いた。
「私もAVやって自殺しようかな。かわもと遥みたいに」
それまでずっと言いたくても言えなかった女の名前を晴喜の前ではじめて口にした瞬間、相手の目つきが変わるのが分かった。
晴喜との恋愛を今振り返ってみると、小学生の男の子が描いた一ページ漫画みたいだな、と思う。最初のほうのコマだけはしっかり書き込まれていて、大げさなあおり文句で壮大な展開を予感させるけれど、コマが進むとだんだん絵柄もストーリーも雑になっていって、最後は整合性のない結末でプツッと終わる。晴喜はたぶん私に対してだけでなく、それまで付き合ってきたほとんどすべての女の子に対してそういう漫画を見せてきたんだと思う。かわもと遙も「ずっと一緒にいようね」と抱き寄せられ、「世界でいちばん君が大切」と言われた直後に浮気をされたあげく、突然不条理にラストシーンをつきつけられたんじゃないだろうか。
晴喜と付き合ってから私がいちばんはじめにやったことは、相手が過去に交際していた女について探り、把握しておくことだった。売れないモデルをしていた晴喜について検索すると、ネットの掲示板がその頃には既に死んでいた「かわもと遥」との関係を私に教えてくれた。自殺したAV女優。晴喜と付き合っていたときはまだ、ただの大学生だったらしい。
私はかわもと遙が世の中に公開した文章にたぶんすべて目を通している。この女は晴喜の人生だけでなく、身のまわりのものすべてに弊害を撒き散らすスプリンクラーのような馬鹿だった。仕事の愚痴やネガティブな心情が延々と綴られるプロ意識の低いブログ、攻撃的な言葉が投稿されてはすぐに消されるツイッター、彼女は、自身がいつでも死にたくなる最悪な仕事に就くいつでも死にたい頭のオカしい人間であると、さまざまな場所で吐き捨てた。自傷の痕が分かる手首の写真や精神科でもらった処方箋を載せることもあった。
彼女はそういう場所にある日、実名で晴喜のことを書いた。ふたりで撮った写真まで載せて彼が自分をここまで追い込んだと非難した。彼女は晴喜を一方的に加害者扱いし、自分が男性不信になったことも自暴自棄でこの業界に飛び込んで自分の人生がめちゃくちゃになったことも自分の頭がオカしくなって毎日死にたいと思っていることも全部を晴喜のせいにした。
それを読んで激しい怒りに震えたのは私だけではなかった。
当時ネットを通して彼女を見ていた物好きで俗悪で良識的な人間が一斉に彼女を批難した。
死にたいなら勝手に死ねよ肉便器、最低なのはお前のほうだ死ね、いつまで生きてんの? 死ね、死んじゃえー、死ね死ね死ね、死にたいなら死ねよ、お願いします死んでください、死ねばいいと思うよ。そう言われてそのまままに、かわもと遙は死んだ。
「生まれてすみません、死にます。」それが、彼女の最期のセンテンスだった。
救いようのない馬鹿な女。私には晴喜が不憫で仕方なかった。
こんな女の味方をしてくれる人間なんてもちろんいなくて、一連の事件のウォッチャーたちも、晴喜のことは頭のオカしい女の被害妄想に巻き込まれてしまった不運な元恋人という見方をしていたようだったけれど、それでも、こんな女と付き合っていた恥ずかしい過去を見ず知らずの人間にまで知られてしまうなんて、どんなに悲惨な話だろうか。
晴喜がこれからどんな風に生きていったって、彼のことをちょっと調べればこの話題がいやでも上がってくる。最悪なデジタルタトゥー。晴喜を知る人間であれば、どうしたって彼の後ろにこの女の亡霊を見てしまうのではないだろうか。可哀相な晴喜。私はこんな女とは違って晴喜に迷惑をかけたりしない。晴喜を傷つけたりしない。私は傷付いた晴喜のことを癒してさえあげられる。私と一緒に居さえすれば、晴喜はつらい過去も忘れることができる。私と一緒にいたら、きっと晴喜はしあわせになれる。私は晴喜をしあわせにするし、そうすれば晴喜も私をしあわせにしてくれるはずだ。晴喜とともに浮かぶのは、寄り添うのは、他の女ではなく、私。私しか存在してはいけない。絶対に。
私は、晴喜としあわせになるためにずっと我慢をし続けた。浮気をされても、冷たく当たられても、連絡を取れない時期が続いても耐え抜いた。服装や言葉遣いに難色を示されればすぐに直し、私は晴喜の気に入るような振る舞いばかりを覚えていった。
晴喜はたびたび私に「愛してる」と伝えてくれた。私はそれを疑いもしなかった。
付き合っている間、共に過ごす時間は夢のように輝き、ひとりになった途端に私はたまらなくむなしくなった。どこか恥じ入るような気持ちで毎日を泣いて過ごした。晴喜と会っていないと気が狂いそうだった。他の女と一緒にいるのではないかと心配で仕方がなく、私は憤りと寂しさを不安定に行き来しながら泣き通して何度も朝を迎えた。
それでも耐えていたのは、晴喜は私のことをいちばんに愛していると思っていたから。このまましあわせになれると信じていたから。
「緑色の死体になっちゃったんでしょ?あはー」不自然なほど高いテンションで私は硫化水素自殺を遂げたかわもと遥の話を続けた。
晴喜の好みにならって従順で温和に振る舞うことに努めていた私が、別れを切り出された途端に態度を変えたことは晴喜にとってまだ想定内だったようだけれど、かわもと遥のことを言われたのは相当意外だったようで、「よくそんなこと言えるね」と吐き捨ててきつく顔をしかめた。
かわもと遥のことを知っても、もちろん晴喜にはずっと黙っていた。それはあまりにもナイーブな問題だったし、私までもが晴喜の後ろにあの女の亡霊を見ていることを知ったら彼を傷付けてしまうだろうから、墓場まで持って行くつもりで今まで胸のうちにそっとしまっていた。だけど、私のことを愛さず、裏切った男なんてもういくら傷つけても構わない。関係が終わるなら、きれいにまとめたって木っ端微塵に破壊したって一緒。不平不満と嘘と秘密でもう骨壷の容量もいっぱいだ。
「死ねよカス! どの口がそんなこと言ってんだよ。女死なせといてキレイぶってんじゃねえよ。お前が付き合う女なんて全員生きてる価値もないメンヘラのクソビッチかもしれないけど、マジでお前がさらに女の頭オカしくさせてるからな。全部お前のせいだから。お前の精液に女の頭オカしくさせる成分でも入ってるんじゃないの? マンコだったら何でも突っ込むド畜生だからチンコもキチガイになってんだよ。性病撒き散らすだけじゃなくて精神病まで撒き散らしてんじゃねえよ、クソ汚ねえ病原体。AVクソビッチもお前のせいで精神ぶっ壊れて死んだんだろ。あたしもお前のせいで頭オカしくなったわ、このメンヘラ製造機が!」
私はずっと、かわもと遥の亡霊に悩まされていた。
目立って美しいわけでもなく軽薄で尻軽な頭のオカしいクソビッチは、その奇行によって晴喜に彼の恋人史上最も強いインパクトを残したというただその一点で私をおびやかした。
私は今までの恋人や他のどんな女よりも晴喜にいちばんに愛され、その心に深く入り込めることを願っていた。晴喜の心を私だけの場所にしたかった。生きている女は晴喜と別れればまた違う場所に行ってしまうけれど、死んだ女はいつまでもそこを動かないような気がしていた。
かわもと遥についての情報を収集することは、自傷行為だった。晴喜とのツーショットの残像は、いつまで経っても頭から消えることはなく私を苦しめ、今まではなんでもない日だった一日が彼女の命日であるということを知っただけで不吉な記念日に代わった。かわもと遥のことを知るのは嫌でたまらなかったのに、同時に、かわもと遥のことを知らないと居ても立っても居られない自分がいた。私はかわもと遥に、晴喜がかつて愛したことのある他の女たちや、気まぐれに手を出す女たちの姿さえも投影していたように思う。彼女はそれらの象徴だった。
あおいちゃんが私に会いに来たとき、私は、自分が彼女にとってのかわもと遥なのではないかと感じた。濃度は違ってもおそらく、私たちが抱いていた気持ちの成分は一緒だろう。
かわもと遥がもしも生きていたなら、私は彼女に会いに行ったのだろうか。DVD販促イベントなんかにしれっと参加して、晴喜のことを尋ねるような嫌がらせめいたアプローチをしたかもしれない。もしくは、もっと友好的なコンタクトをはかっただろうか。それは何故だか私にとって少しだけ愉快な想像だった。あおいちゃんは、かわもと遥に会いに行った私だ。
彼女に連絡先を訊いたのは、かわもと遥に会いに行った私がそこからどんな風に相手を手なづけていくのかを知りたかったからかもしれない。
晴喜と別れたあとで、私は彼から数十万の金を受け取った。ワガママで気が強く自己中心的な晴喜が自発的に手切れ金なんか払うわけはなく、私は彼に妊娠していたと嘘をついて堕胎の費用と慰謝料を請求したのだった。ずいぶん揉めた末でのことだったが、私の言葉だけでそれを信じて金を出してきた晴喜は馬鹿なのかそれとも、彼に呪詛の言葉を喚き散らし事務所や親にバラすと詰め寄った私から逃れたかっただけだったのだろうか。半々かなと私は考えている。
あおいちゃんにこのことを話すと「そんな話を証拠もなくすぐに信じるなんて、きっとはじめてのことじゃないんでしょうね」と忌々しげに吐き捨てた。
あおいちゃん大正解。私が知っているだけでも晴喜はふたりの女にこどもを堕ろさせている。私に嫌がらせの電話を掛けてきた浮気相手の名前も知らないクソ女と、かわもと遥。
晴喜から茶封筒を受け取った瞬間、私は嗚呼、死ななくて良かったと、思った。
恋に病んで死んだ女を批難し憎しみ続けていた私はそれでもやはり、晴喜にふられたときもまた、死にたいと思っていたのだった。
たいしたことない容姿で、馬鹿で尻軽で、男に依存して執着して、被害者意識が強くて、誇れるような自分がないくせに自己顕示欲だけは強いかわもと遥は私とすごく似ていると思っていた。
晴喜には、かわもと遥はお前のせいで死んだとなじったけれど、私は本音ではそうは思っていなかった。底のないサラダボールの縁から手を離したのは彼女自身だ。
悲しみなんて乗り越えなくても良かった。誰かに馬鹿にされても真に受けずに無視していれば良かった。かわもと遥が生きていても死んでいてもどうせみんなすぐに彼女のことなんて忘れてしまう。正論を振りかざしたり、右にならえで悪戯に彼女を叩きのめしたりしたのだって、ただみんなあの日の暇をつぶすおもちゃを見つけて喜んでいただけに過ぎなかったのに。
私は、晴喜を不快な気分にさせるためにかわもと遥の名前を出したとき、いつか私もこんな風に、誰かに自身の死を貶められてしまったら嫌だなと思っていた。
身を裂くような辛さに襲われ孤独で夜も眠れなくて悩み苦しみ抜いて選んだ死だったとしても、自分が死んでしまったあとではそれを誰の口からどんな風に語られても反論さえ出来ない。ただ大きな穴に落ちないように、必死に這いつくばっているだけでも、見ず知らずの他人に自身の死を馬鹿にされたり、都合の良いように利用されたりするよりはマシなのではないだろうか。
かわもと遥も、私みたいにすれば良かった、あんな奴のために死ぬことなんてなかった。
泥試合を仕掛けても自分のことだけを考えて図太く強く生きていれば晴喜のことを乗り越えてもっと賢くなることも、しあわせになることだってできたかもしれない。
打ちのめされて弱った人に向かって、強くなれ、と言うのはむごいことだと思うが、だけれどそれは本当で、強くならなくては生きてもいけないというのは、なんて残酷なことなんだろう。誰かを失うたびに砕けた心の再構築を試みると、心は以前よりもずっと強く強く強くなってしまう。不信という壁は厚くなり自己愛の柱はいよいよ強度を増す。もうこれ以上、強くなんてなりたくないのに。
私とかわもと遥は確かに似ていたと、今もやはり思う。だけれど、私たちははっきりと違う。私は生きていて、彼女は死んだ。私は自分の真っ赤な血を守るためだったら彼女の死を暴力的に踏みにじることも厭わない。私はかわもと遥にもそうして欲しかった。彼女の手の内には切り札になるようなカードはなかったかもしれないけれど、それでも、晴喜を憎み罵倒し続けて傍観者を閉口させてまわりを全員敵にまわして嫌われまくっても、自分が満足する着地点を見つけて欲しかった。
どうせ私たちみたいな種類の女は周囲から疎まれているのだし、思い通りにならない毎日に歯ぎしりし続ける毎日を送っている。馬鹿で性悪な人間が、中途半端に世の中の美徳に迎合しようとして死を選ぶほど追い詰められるのだったら、アンモラルにスカッとする一瞬を見つけ生き長らえることの何がいけないのだろうか。
かわもと遥の中にもそんな瞬間がやってきていたら、私は今、彼女と笑顔でハイタッチさえできたような気がする。
私は自分が底のないサラダボールの中に滑り落ちてしまうくらいなら、他人を蹴落としてでもそこに足場を作ることをこれからも選んでいくだろう。自分が傷付き尊厳を失うくらいなら、そちらの方が百万倍マシだ。健全な判断力を持つ他人が私に意見しようとも、この件は私の中ですでに解決済みの事柄なので、どこの誰が私にどんな説得を試みようと、私がこれを再び問題として取り上げることはない。私に対しての苦情を受け付ける機関は二十三年前に営業を停止した。私に反論するすべての人間は悪質なクレーマーである可能性が高いので今すぐ適切な施設にてカウンセリングの予約を取ることをおすすめする。うるさい、私が正義だ!
どこの誰が私に文句をつけてきたって、私は、生まれてきたことを詫びたりなんてしない。生まれてすみませんて言えなくてすみませんと悪態をついてでも私は、生きていく。
5.あ・い・そ・わ・ら・い・も・力尽きて
ヘアメイクさんに髪の毛をセットされている鏡の中の自分を眺めていると、私はいつまでこんなことを続けるのだろうと、整っていく髪型とは裏腹に気持ちはどんどんすさんでくる。
恋人がいる時は相手に好印象を与えたくて昼の仕事に就くけれど、相手と別れれば私はすぐに水商売に戻ってしまう。この仕事は大嫌いだったし、向いてもいなかった。いつまでもこうやってキャバ嬢をやれるわけではないのだから早く堅実な仕事に就かなくてはいけないと思いながらも、制約の多い昼の仕事には長く居場所を見つけられず、私は夜の世界からなかなか抜け出すことができなかった。
恋の病で二週間も店を病欠したせいで、今まったくお金がない。家賃を払って貯金はゼロになった。本当はまだ働きになんて出ず家で千塚さんのことだけを考えていたいのに、稼がなければ生きていけない。私は酔客のくだらない冗談に笑い声を上げ、センスのない下ネタを受け流して、毎日店からもらう日払いで糊口をしのいでいた。
水商売の時給が昼の仕事に比べて良いとはいっても、そこからは天引きされるものも多く、売れっ子でもない限り手元にはたいした額なんて残らない。この一週間、私は毎日店に出て同伴もできる限り組めるよう頑張った。「シャイン」という店名が英語で表記されたこの日陰の店のエントランスをくぐるたび、なかば脅迫されているような被害妄想を覚えながら、私は毎日死体みたいな気持ちで出勤を続ける。
ヘアメイクが終わってフロアに出ると、店長が「ナイス、唯ちゃん!」と私の源氏名を呼び親指を立ててみせた。相手の明るいノリにどう反応をしていいのか分からない。軽い会釈だけ返して、店長の後ろに付いて今日同伴で一緒に店に来たカズキさんの待つ席へと向かう。
本当はカズキさんには私がまた店に出始めたことを言いたくはなかったけれど、同伴バックの五千円欲しさに今日の夕方ついに彼と連絡を取ってしまった。さっきの居酒屋で軽く飲んだだけでもしんどかったのに、まだこれから何時間も彼と向き合わなければいけないのかと思うと気が滅入る。それでも、私はカズキさんと目が合った瞬間にパッと笑顔をつくって、ご主人様の姿を見つけた犬のような態度で彼の隣に膝を寄せる。私は資本主義の犬だ。
一体、いつまでこんなことを続けるのだろう。ずっとずっとずっと何も変わっていない。変えていけない。振り返れば手を替え品を替え、店を替え源氏名を替えて同じことを繰り返しているだけだ。メビウスの輪の中をぐるぐると巡るように、ここからいつまでも抜け出せない。
このままではいけないということは分かっている。私が思考と行動を停止させているうちにも、世間はめまぐるしいスピードでまわっている。今日の夕方にはゆめいろファクトリーのツイッターアカウントで彼女たちのはじめてのテレビ出演が決定したというニュースを見た。千塚さんに出逢うまでアイドルというものにまったく興味のなかった私は、もちろんそれまでゆめいろファクトリーの存在も知らなかったのだけれど、アイドルファンの間では彼女たちはすでにある程度名の知れたグループだったようだ。どの分野の話であっても、その世界に精通したファンたちの間での知名度と世間一般での認知の度合いには大きな隔たりがあるものの、人気というものは一度その隔たりが破られると今までの速度を無視して一気に加速して高まっていくことがある。私はゆめいろファクトリーがそうなれるか否かの、もっともじれったく忌々しい季節に彼女たちを知ることになってしまったようだった。ゆめいろファクトリーにとって華やかな話題が増え始めていることは、彼女たちのデビューからの動向や世間の反応を過去にさかのぼって細かく調べ込んできた私自身がよく知っている。
彼女たちのことは相変わらず苦々しく感じているけれど、この一ヶ月弱の間毎日ゆめいろファクトリーを見続けるうちに、このグループや五人それぞれのキャラクターにどことなく思い入れのようなものを覚え始めたのも事実だった。千塚さんお気に入りのまなこが輝いて見えそうになるたび、私は頭を横に振って自分自身の心の動きを否定した。
可愛いだけのクソガキ集団がニコニコ笑って踊ってりゃあちやほやされて、千塚さんにも好きになってもらえるんだからぼろい商売だよなあと思っていたけれど、彼女たちがステージで流す汗やバックステージで流す涙の量を知り、彼女たちの夢や想いを語る言葉を知っていくと、千塚さんがファンでさえなければもしかしたら私も彼女たちを応援していたかもしれないとさえ思うことがあった。
世間からは、客の前で可愛くして笑ってりゃいいだけだと思われているキャバ嬢でさえこんなに辛くて疲れるのに、それの昼夜問わずの全国拡大版なんだから、その苦労は私なんかの比にはならないだろう。食べたい盛り、遊びたい盛りで精神的にも多感な年頃の女の子が、必死で節制し、時にはまわりからの悪意にもさらされながら、それでも笑顔を振りまくことがいかほどに大変なことであろうか。
「唯ちゃん」
ふいにカズキさんが私を呼ぶ。
「今、ぼーっとしてたよね。何か考え事でもしてる?」
そう尋ねてきた彼の口元は笑顔のかたちをつくってはいるものの、唇は引きつったように微かに震えている。
「ずっとカズキさんのこと考えてるよー」
この場を誤魔化したい一心でくだらない冗談を口にしてしまった。しらけるかな、と思ったけれど、カズキさんの唇の震えは止んで、その顔にまんざらでもなさそうな表情が浮かぶ。
「それならいいけど。ほら、唯ちゃん、最近も仕事忙しいでしょ。寝る時間もちゃんと取れてないからそんな風に上の空になっちゃうときがあるんじゃないかなって心配で」
私はカズキさんに昼間はアパレル関係の会社に勤めていると嘘をついていた。出会った当初、休みの日や空いている時間があるといえば彼はしつこく会いたいと言ってきたので、私は次第に、休みもほとんどない会社で昼間は馬車馬のように働いていると説明するようになっていった。
「心配してくれてありがとう。うん、最近忙しくてここ二週間は休みなしだったよ」
そうなんだ、と私の言葉を飲み込むカズキさんが本当に納得しているのかは私には分からない。相手の本音についてはあえて、考えないようにしている。
「次の休み、いつ?」
「水曜日に半休とれる」
「俺も会社休もうかな」
「え? 休まなくていいよ」
「なんで?」
「なんでって……悪いじゃん」
言葉に詰まって、彼のグラスについていた水滴をハンカチで拭った。気まずさをごまかす仕草の途中で、つなぐべき言葉を探す。
「……半休って言っても、午前中だしさ」
「いいよ。それなら俺にとっても都合いい話だし。ランチしようか」
「うーん、でも、役所行く用事とかあるから、時間読めないなあ」
「一緒に行くよ」
「いいよ、悪いじゃん」
「悪いなんて思わないでよ。俺は少しでも唯ちゃんといたいんだよ」
ありがとう、と発して、またそのあとが続かない。こんな風に言われたら、相手が喜ぶ言葉を返さなければいけないのに。それがどういう台詞であるのかは想像がつくけれど、思い浮かぶ通りに口を動かすことができなかった。代わりに、せめて相手に笑いかけてみせる。
「ねえ、役所行くって言ってたけどさ」
カズキさんが私の目を見つめる。こちらの胸の内を探るような目つきに胃もたれを覚えて、笑い顔の目を細めるフリで、そっと視線を彼の口元のあたりにずらした。
「俺と行くの避けてるのって、もしかして本名バレ気にしてる?」
「いや、違うけど」
こんな質問を投げかけてくる相手の気が知れない。否定する以外こちらには選択肢がなかった。この男に何も自分のことを知られたくない。
「宮下鈴ちゃん」
背後から急に強く押されたような衝撃が走った。私を突き飛ばした男は薄笑いを浮かべている。
「言おうかどうか迷ったんだけど、知ってたよ」
「なんで?」
カズキさんのあまり大きくはない目が見開かれる。早押しクイズの解答者のように、彼は前のめりで話を続けた。
「やっぱりそうだったか! スマホのデバイス名、初期設定から変更してないでしょ。ほら、無線で画像送れる機能あるじゃん。唯ちゃんと一緒にいるときにそれ立ち上げると、いつも同じ名前が出てくるから、そうなんじゃないかと思ってたんだよね」
クイズに正解すれば私が喜ぶとでも思っていたのなら、その選択は不正解だと教えてやりたい。
「これから、鈴ちゃんて、呼んでもいい?」
「やだ」
「お店じゃまずいか。じゃあ、唯りんって呼ぼうかな。それならあだ名だと思われそうじゃない?」
自分も不正解の答えを返してしまうところだった。この不愉快なクイズ大会ではもう黙っていることが得策なのかもしれない。カズキさんは私の言葉を待つようにこちらの顔をのぞき込んでいたけれど、反応がないことを悟ると肩を開いてソファにもたれかかる。
「まあ、その話はどうでもいいとしてさ。今日久しぶりに会ったのに、俺たちの関係ってこの前に会ったときから何も変わってなくない?」
「……この間って一週間ちょっと前に会った日のこと?」
クソみたいな話題が切り替ったと思ったら、またクソみたいな話題がはじまる。ただの客とキャバ嬢であるふたりの関係の一体何についてカズキさんが言及しようとしているのか私には理解しかねたが、それを理解しようという気も起こらない。わざと論旨をずらした質問をぶつけると、彼は一瞬の間を置いて、
「一週間ちょっと前じゃなくて、二週間以上前だよ」
そう返したきり黙ってしまった。
私にはカズキさんのその反応がまた理解できない。以前にこの男と会った正確な日にちなんてまったく覚えてはいないけれど、私たちふたり関係は、たとえ二週間連続で毎日会っていたとしたって何も変わることはないというのに。
「ごめんね」
口先だけの謝罪。眉頭に少し力を入れて媚びた表情を作る。カズキさんは結んだ唇を微かに震わせたまま黙っている。この男は何か気に入らないことがあったり怒っていたりするとき、こうして震えるほどに唇を固く結んで何も喋らなくなる。そしてそのまま無理やり両の口角を上げて、わざと微笑むようなかたちをつくってみせる。怒りをこらえるのが大人の分別だとでも思っているのかもしれないけれど、こんなに分かりやすく腹の内が顔に出るなら、言いたいことを噛み殺して唇をバイブさせたりせずにはっきり言葉にすればいいのに。この表情と対峙し続けているとカズキさんへの苛立ちと、それを我慢している自分を情けなく思う気持ちがぐちゃぐちゃに混ざって、私は一時間三千五百円で丸め込まれている感情を爆発させてしまいそうになる。
「そっかあ、もうそんなに会ってなかったんだねー。どうりでなんか寂しかったわけだー。ねえ、そうそう、聞いてよカズキさん。私最近面白い映画を見たんだよね」
声の調子を無理やり明るくして話の転換を試みる。数ヶ月前にたまたま見たことがあるだけの好きでもなんでもない映画のストーリーを身振り手振りを交えて精一杯話しても、カズキさんは一向に興味を示さず唇を震わせたまま押し黙っている。私の解説がすべて終わるとカズキさんは、「その話、前に聞いたよ」と、不機嫌そうに言った。それなら、序盤で主人公がピザと間違われて石釜で焼き殺されてしまうシーンで話を遮ってでもくれればいいものを、どうして結末を話し終わるまで何も言わないのだろう。
「あれ、話したことあったっけ? ごめーん」
「唯りんて、同じ話を何度もすることが結構あるよね」
「そうみたーい。もうほんと、私、ばかだからー。ごめんね、カズキさん」
「そういうことをされると自分が特別だって思えなくなる」
四十路を過ぎているというのに思春期真っ盛りの中学生のようなことをのたまうこの男は、私から特別な好意を持たれているとでも本気で思っているのだろうか。金を介した擬似恋愛の場所で話題に事欠いたキャバ嬢に、主人公がピザと間違われて焼き殺される映画の話を二度もされた上で、どうして自分が相手にとって特別な人間だなんて勘違いができるのだろう。
「ねえ唯りん、俺たちって付き合う日が来るのかなあ」
カズキさんは私と会うたびにもう何度も繰り返している台詞をまた口にする。
「私はカズキさんとゆっくり仲良くなっていけると思ってるよ」
「でも、唯りんは相手を100%好きにならなきゃ付き合わないって前に言っていたよね。毎回会ってそのパーセンテージを足し算していってもちょっとずつしか増えていかないじゃない。それまでにどのくらいの時間がかかるのかと思うと……」
「うーん、でも私は、恋って足し算じゃなくて掛け算だと思ってるんだ。たとえば最初の状態が10%の好きだったとして、足し算はそこに10%の好きが加えられても20%にしか増えないでしょ。でも掛け算ならもう100%になっちゃうんだよ。好きになるってそういう風に何かのきっかけで一気に気持ちが盛り上がっていくものなんじゃないかな」
私の言葉を受けて返す台詞を必死で探している様子のカズキさんは、この恋の数式上、私側の元の数値が0なのだから何を掛けても無意味であるということにはもちろん気付かない。
「まあ、ゆっくり頑張れってことだよね」
カズキさんは結局勝手に自己完結して自分の言葉に頷いている。
この人はどうして自分がいつか私と付き合えると思ってしまっているんだろう。私に誤魔化され続けているこの状況から一体なぜ期待を持つことができるのだろう。期待が延期されればされるほど、彼が気持ちを病み私に執着していくのではないかと恐ろしく感じていた。
毎日起きてスマホをチェックすると、そこにはカズキさんからのメッセージが何通も入っている。朝方に送られてきているのはその日の天気に関する内容だ。今日は雨が降るから傘を忘れないようにだとか、夕方から気温がグッと下がるだとか、天気予報を見れば済む情報をカズキさんは欠かさず私に送りつける。その後には、昼食はそばだったとか、会社の後輩が昨日合コンした保育士とうまくいきそうだとかの、白目を剥きたくなるほどどうでもいい身のまわりの出来事の報告が日に何件も入ってくる。私はカズキさんの日常やこちらへの想いを適当にスクロールし続ける。
一日返事をしなければ、着信履歴はカズキさんの名前で埋まった。私は架空の仕事で忙しくて電話には出られないから、彼に短いメッセージを送る。心にもない謝罪と心からの営業の言葉。顔だけ見に行くよ、という文面を返しておきながら店に来たカズキさんはいつまでも帰らない。結局、私の顔を店が閉まるラストの時間まで見続けて、それでもまだ飽きずに、次も顔を見に来る。
借金があるという話を、この間はじめてされた。それが具体的にどのくらいの額なのかは言わなかったけれど、その話をした日でさえ彼は私のグラスを空にしたまま席につかせて置くようなことはしなかった。ばかばかしい見栄の対価がサラリーマンの月給を越えているだろうことは明らかだった。
「俺は唯りんが好きだよ」
カズキさんからそう言われても、当たり前に恐怖しか感じない。その後に何やらぐだぐだと続く彼の口説き文句は退屈で、私はついつい意識を逃避させてしまう。今目の前にいる男が千塚さんにすり替わってくれたらいいのにというお決まりの想像で、私は頭の中に愛しい人の姿を思い浮かべる。
千塚さんの薄い唇が縦にそっと開き、一瞬の間を置いてゆっくりとすぼまったそこから「す」という音が発せられたのちに、続けて発音される「き」がこぼれると、横に広がった彼の唇がまるで仔猫のように可愛い形をつくり私に微笑みかけてくれる、そんな感動的な瞬間を。
私が千塚さんと出会ってからもう一ヶ月が経とうとしている。
その時間の経過の早さに焦りを覚え、真夜中にまたオカしなテンションになってしまった私は昨日の深夜、千塚さんを食事にお誘いするメッセージを送ってしまった。返信はそれ以降、ない。
「ちょっと、いきなり攻めすぎですよ」
あおいちゃんに報告すると、ため息交じりの言葉が返された。
「色々アドバイスしてくれてたのにごめん。だって、もう早く千塚さんに会いたくて我慢できなかったんだもん……ごめん」
「自分の気持ちにすごく正直なところはりんちゃんの長所だと思いますよ。ただ、りんちゃんはまっすぐ過ぎて時々、道なきところまで道にして突っ走っちゃいますからねー」
「ね。私、今完全に荒野走ってる。もう、ここどこ? あおいちゃん私どうしたらいいの」
「この先のルートは完全にありません」
あおいちゃんはそう一刀両断した後あわてて、
「もう少し待ってから新しい作戦を考えましょう。今はあまり気に病まなくて大丈夫」
と、私を慰めてくれた。
カズキさんは今日もラストまで店にいた。送り出しのエレベーターが閉まると、後ろからボーイのひとりがからかうような口調で話しかけてきた。
「カズキさんて、ただのいい人なのか唯さんのストーカーなのか分からないですよね」
「そうだね」
ただのいい人であるだけなら、十数万払ってこんな店に来る理由はないだろ、とボーイを一蹴したい気持ちを抑えて、一刻も早く送りの車に乗り込むためにロッカールームへと続く階段を上がる。
スマホを開いてLinxへとアクセスするとやはり千塚さんからのメッセージはなく、彼の日記も更新されてはいなかった。その代わり、ゆめいろファクトリーに関する新たなニュースが話題になっていた。
6.運命は正しく歪む
あおいちゃんからのメッセージに添付されていた手書きの地図は分かりやすく正確だったので、私ははじめての土地でも迷うことなく無事に他人の家の中に侵入することができた。家主が帰ってくるまでまだ時間はあるはずだけれど、できるだけ長居はしたくない。
床には男物の洋服が脱ぎっぱなしのまま散らばっている。踏んづけないようにつま先立ちで部屋の奥にある木製のチェストの前まで移動した。目的の青い缶ケースは、メモの通りにいちばん上の引き出しの中にあった。
気持ちの余裕なんてないはずなのに、心のどこかで、まるで怪盗みたいだと興奮している自分がいた。
ファミレスやファーストフードでまわりの人たちのおしゃべりに聞き耳を立てていると、まったく知らない人たちの普段の生活だとか人となりが見えてきて面白い。だけど、ひとりで来ている人は喋らないからどんな人なのか想像するのが難しいな。
千塚さんと出会った日に彼が腰掛けていたテーブル席には今、白いトレーナーを着た太った女の人が座っている。私はその席を正面から眺められる位置に場所を取り、あおいちゃんを待っていた。
白いトレーナーの女はビッグサイズのハンバーガーを食べている。ヘリコプターがプロペラを回すようにレタスが四方から飛び出して、ぼろぼろとトレイの上にこぼれていた。
あの日あの席に、千塚さんではなくてこの女が座っていたなら、私は今日までどんな毎日を送っていたのだろうか。それを考えようとして彼女をまっすぐに見つめ、私はすぐにその視線を外した。そうしたのは、千塚さんと出会っていなかったらという仮定の想像をやめるためでもあったけれど、単純に、自分の視界に汚いものを入れたくなかったからだった。
私にとって千塚さんはきれいな男の人で、だからこそ、その内面をたくさん想像することができた。彼と一言も喋ったことがなくたって。
見た目が好きじゃなかったら、想像すらしようと思わない。自分が心惹かれた外見には、そのかたちの内側に他よりまさった何かが秘められているはずだと思ってしまう。宝石はきれいだけれど、そんなことは誰が見ても分かるから、そこに自分だけが知っているストーリーが欲しい。物語をもった宝石は特別な宝物になる。私は千塚さんにそういう期待を抱いていた。自分だけの宝物を求めていた。
あおいちゃんから連絡が入る。「今から二階に上がります」というメッセージを確認して振り返ると、ちょうど階段をのぼってきたところだった。
「赤系のアイシャドウ塗ってみたんですけど、どうですか?」
向かい合う席に腰を下ろしたあおいちゃんが私に尋ねる。
「普通に見えるよ」
「良かった」
あおいちゃんが祐一君と別れたことを聞いたのは昨日の夜だった。
同じ大学に通う男の子を好きになり、その彼と自然とうまく行く運びになって、彼女は祐一君と別れることを決めたらしい。自分の一方的な心変わりにためらう気持ちも強かったけれど、長い間ずいぶん悩んで出した答えだったと昨日の電話であおいちゃんは私に話してくれた。夜の深い時間、彼女は野外にいた。ほぼリアルタイムで私に状況を説明し続けるその声は興奮していた。
あおいちゃんから別れを切り出された祐一君は、絶対に別れないと言ってあおいちゃんを殴った。そうされて彼女は、絶対に祐一君とは元に戻らないことを決め、半同棲していた彼の部屋から飛び出した。
赤みがかったアイシャドウを落としても、きっと今日の彼女のまぶたははれぼったいのだと思う。
「悩んでいたことに、気付いてあげられなくてごめんね」
あおいちゃんにはこちらが一方的に千塚さんのことを相談するばかりだったから、きっと彼女は私に悩みを話したくても話せる状況ではなかったはずだ。それを思うと、申し訳ない気持ちになった。
「気付かれないようにしていたんだから平気です」
私の想いをよそに、彼女はしれっと応える。
「まあ、私なんかじゃ頼りにならないもんね……」
「違うの。そういう意味じゃなくて、自分の気持ちに整理がつけられなくてどう話していいか分からなかったんです。祐一がいるのに他の人に惹かれるなんて、あっちゃいけないことだって思ってたから。誰にも知られないうちに気持ちをセーブして、笑顔で祐一のところに戻ろうって思ってたんです。だけど、私、新しく気になった彼のことをどんどん好きになっちゃって……」
あおいちゃんは、長く付き合っていた祐一君を裏切ったのだからたとえ彼から殴られても仕方がない、自分が加害者なのだとも口にした。交際が解消された途端、ずいぶん物騒な関係性に変わってしまうものだ。誰かを殴るよりも、別の誰かを好きになることのほうが相手を傷つけることがあるとしたって、後者に罪があるなら恋愛は利害関係でしかないということになるんじゃないだろうか。そんな風に思うことなんて、別れる前は決してなかったはずなのに。
「あおいちゃんは悪くないよ」
時折肩を震わせて話を続ける彼女に私はそう言葉を掛けた。
「殴ったことに関しては祐一君だけが悪い」
それは正しい見解のはずだ。
「あおいちゃんは悪くない」
自分が祐一君の立場なら決して言わない言葉を、私は繰り返す。
「祐一のこと、好きでしたし、今だって、好きな気持ちがないわけじゃないんです。だけど、もう……」
「……うん。彼、これからしあわせになれるといいね」
「はい。無責任ですけど、私もそう願ってます」
私はあおいちゃんの話を聞きながら悲しいほど、今とても傷ついているであろう祐一君に過去の自分を重ねてしまう。底のないサラダボールの縁に彼が今、必死でつかまっているとしたら、その手を可能な限り、離さないでいて欲しい。
あおいちゃんから頼まれて祐一君の家から持ち出した青い缶ケースをバッグから取り出す。彼女に渡して中身の確認を促すと、印鑑とパスポートというお決まりの貴重品にまぎれて、かつてこの場所で見た親知らず入りのポリ袋も一緒に出てきた。それを、私もあおいちゃんもスルーする。
この祐一君の歯をきっかけにして、いつか千塚さんの親知らずを手に入れ飲み込むことを夢見た私は、実際に人間の歯を飲み込んだらどうなるのかをすでに調べていた。
するとそれは、どうやら消化も吸収もされることなくそのままのかたちで排出されてしまうらしかった。体の管の中をただ、通過していくだけだそうだ。だから私の想像したことは絶対叶わなかったし、そもそも私は千塚さんの親知らずを手に入れることさえ出来なかった。それは未来永劫決定された事実だった。
カズキさんを久しぶりに店に呼んだ日、彼を送り出したあとに開いたLinxで話題になっていたのは、その日まなこの身に降りかかった事件のことだった。
江藤真奈子の過激なファンが彼女の自宅マンションへ侵入し、ベランダから転落して重体。事件を知った私は、SNS内のコミュニティに次から次へと上がってくるファンたちの書き込みをずっと追いかけていた。興奮したまま迎えた翌朝、ネットに配信されたニュースの中で男の死が伝えられた。憎たらしいアイドルグループのスキャンダルとばかな男のあっけなくくだらない人生の終わり方を私は笑っていた。犯人の男の名前が、千塚貴之だと判明する前は。
「助けて」
SNSにそう投稿したのは、ほとんど反射的な行動だった。特定の誰かにすがったわけでも、誰かに反応して欲しいわけでもなかったけれど、混乱を自分の中だけで処理することは無理だった。同姓同名の男がたまたま犯人だっただけで、千塚さんは無関係だという可能性は検索した画面をスクロールするたび薄れていく。Linxを開けば「友人」たちもざわめいていた。事件の経過は早くもまとめられる。マンションに忍び込み、まなこの部屋に隠れていた男はその日たまたま早く帰宅した父親に見つかり、ベランダから逃げようとして足を滑らせたのだという。千塚さんの顔写真がネットに上がる。犯人の簡単なプロフィールは私が何度もなぞってきたものと同じだった。
「助けて」
あおいちゃんと美南のそれぞれに私はメッセージを送っていた。今すぐにふたりに縋り付きたかった。
「ごめん」
まだ返信もないのに私はひとりでメッセージを送り続ける。
「ごめん。急にこんなこと言われても困るよね。大変なことが起きた」
ニュースとまとめサイトのURLを貼り付け、「これ、千塚さんだよね」とだめ押しの確認を続ける。「どうしよう」、「どうしよう怖い」「千塚さん」。
何通目かのメッセージを打っている途中であおいちゃんが私からの連絡に目を通したことが分かった。既読のマークがついて、「どうしたの」と返信がくる。そこから私たちは午前中いっぱいを使ってメッセージのやりとりを続けた。犯人が間違いなく千塚さんであることを確認した彼女は、言葉少なに私を慰めてくれた。かなしい、つらい、と、私の指先からは次々に言葉がこぼれるものの、不思議と涙は出なかった。千塚さんがこの世からいなくなったということに実感が持てなかった。
美南からの返信は来なかった。そんなことは今までにはないことだったけれど、彼女にとっても多少のショックはあるはずで、私にどんな言葉をかけていいのか迷っているのかもしれない。
「さっきは急に、ごめん」
昼を過ぎてから私が送った謝罪のメッセージはそれから何度確認をしても読まれないままだった。どうしてこのタイミングでスルーされるのだろう。つわりで体調でも崩しているのだろうか。それとも、妊娠しているときにこんな話題に付き合うのは胎教に悪い? それもそうか。友達を慰めるよりも、今はお腹のこどもや自分の体のことのほうが大切なはずだった。それを考えると、理由を追求することもはばかられる。
美南だったら私を優しく慰めてくれるんじゃないかと期待していた分、仕方がないと思いながらも見放されてしまったような気持ちだった。私にはむしろそのことのほうが実感を伴って悲しかった。
メディアが報じるニュースで千塚さんの事件について触れられることはその日以降なかったけれど、ゆめいろファクトリーのファンの間ではしばらく大騒ぎが続いた。
私がLinxでつながっていた「友人」たちはみんな彼女たちのファンだったし、私よりもずっと濃密にSNS内で千塚さんと関わっていた人もずいぶんいたようだったから、話題の白熱具合は相当なものだった。非難も擁護も悪ふざけも入り乱れ、みんな千塚さんについて口々に色々なことを語った。あるブログサイトに彼が匿名で公開していたというまなこへの愛情と妄想を綴った日記もさらされた。そこでは、存在しなかったふたりの蜜月が書かれ、まなこと千塚さんは運命的な恋で結ばれていた。
「しあわせストーカー日記」誰かがそれを揶揄して呼んだ言葉のあとに、嘲笑を表すネットのスラングを続けた。
何を言われても彼自身に非があることは充分に承知していたけれど、死んでしまった千塚さんが冒涜されていくのを見るのに耐えられなくて私はLinxを退会した。
「ヤッホー!」
「ヤッホー!」
帽子はショッキングピンク! 蛍光イエローの長袖の上にテラテラひかるライトブルーのベストを合わせ、下にはシルバーのショートパンツを履いていた。私はあおいちゃんと一緒に、初めての登山に来ている。山に登る際の服装に派手な色味を取り入れるのは万が一遭難した場合に発見してもらいやすくするためだという情報を知っていたせいなのか、私の全身は弾け飛びそうなほどカラフルだった。
「りんちゃんは加減というものを知らないんですね」
そうつぶやくあおいちゃんを無視して、私はターコイズブルーとゴールドの組み合わさったパイソン柄のシューズでスキップを踏むように熊笹の道を進んでいく。
「そんなにはしゃいでたら、あとでバテますよ!」
後ろから聞えてくる口うるさい注意に「ヤッホー!」と雄叫びを返す。声は山間にこだました。やまびこも私も、とても元気だ。頂上はまだ遠そうだけれど、このまま一気に登っていけそう。
オレンジ色の虎柄のレギンスを履いた足を大きく踏み出す。そこは絶壁で、私は真逆さまに転落した。
「ヤッホー!」
私が落ちたのは切立った崖に挟まれた谷底のようなところだった。落ちた場所が良かったのか怪我もなく、落下は爽快でさえあった。ずいぶん深いところに落ちてしまったようだけれど、それでも日の光は充分に届き、地面には若い緑の絨毯が敷かれている。
「ヤッホー!」
あおいちゃんに届くように助けを呼んだが、返ってきたのは私の声だけだった。応えてくれる人がいる気配は感じられない。あおいちゃんは私が落ちたことにまだ気付いていないのだろうか。それとも、気付いてはいても見限って先に進んでしまったのだろうか。どちらにしても大変だ。このままでは私は遭難してしまう。
風の中に漂う土の匂いが「きれいだ」と感じた。清浄な土と鼻をスッと抜けていくような若葉の香りが混ざるこの場所で、私はフランケンシュタインの怪物が全面に描かれたライムグリーンのリュックサックから水筒を取り出し、家で淹れてきた熱いほうじ茶を飲んだ。のどかさに、自分が遭難しそうだという事実も忘れてしまう。危機感はほんのわずかな時間のうちに薄くなっていた。
むしろ今や、心のどこかで積極的に遭難を希望してさえいた。わずらわしい世間から離れ、何も思い悩むことなくこの場所に留まっていられたら、私はどんなに心休まるだろうか。そんな願いが心の内に生まれるのを感じながらほうじ茶をすすっていると、私の耳にかすかに人の話し声が入ってくる。声のするほうには背の高い山草が茂っていて、その奥に複数の人影のようなものが見えた。登山者か、地元の人間か。いずれにせよ、遭難騒動には片がつきそうだった。私の束の間の安らぎはどうやらあっけなく終わってしまうようだ。
「ヤッホー!」
やや控えめな声量で呼びかける。草むらの向こうで小さなざわめきが起こった。彼らに近づこうと草を掻き分けると、人影は逃げるようにばらばらに散ってどこかに消えた。七人いた、なぜかそう判断できた。
草むらの向こうには茶碗によそられたご飯のようななだらかな丘陵が広がっている。丘の中央にはガラス製の棺が置かれていた。その中に千塚さんの遺体があった。
透き通った棺の中で白い花に囲まれる千塚さんは、顔だけが仮面のように浮いて見えた。棺のサイドには銀色のスイッチがあった。押してみると、炊飯器が開くように蓋は簡単に上がった。
千塚さんの頬に手を触れる。おとぎ話の王子様がそうしたように、血の色の失せた彼の唇に口付けをした。人肌の弾力は感じられず、かまぼこの表面に口を付けたような冷たく硬い感触だけを覚えた。千塚さんは目覚めない。私はますます悲しくなってしまう。顎を下方に引いて口を開かせ喉の奥に指を突っ込んだ。千塚さんが毒りんごを飲み込んでいるのならそれを吐かせたかったのに、喉の筋肉はぴくりとも動かない。千塚さんの顎を元に戻して、棺の中に溢れる白い花の下に手を沈めた。そのまま、花の下に横たわる千塚さんの身体に手を這わせる。紙のように薄い布地の死装束は、私の手に千塚さんの身体のかたちを正確に伝えてくれる。下半身に手を伸ばし、布越しに千塚さんの性器に触れた。それは弛緩していた。強く摘んだら反対側の自分の指の感触を感じてしまうくらい頼りない柔らかさだった。私たちの性別が逆であったら彼の死体を姦することもできるのかもしれないけれど、女である私は死んでしまった千塚さんを犯すこともできない。代わりに何か別のことで千塚さんの身体に私を刻み付けることはできないだろうかと考える。思いつくアイデアはなく、私は自由にできる千塚さんの死体を前に途方に暮れている。これでいいのだろうか。自分に呼びかけても答えは返ってこなかった。せめて彼の髪の毛の一本や爪の一枚でも持ち帰らなければ後悔するかもしれない。そう思って白い花の下からすくい上げた千塚さんの手指を見て、私は、そこで、爪を剥ぐことを思いとどまってしまった。
千塚さんの身体を記念品のように持ち帰りたいわけではなかった。肉から剥がされた爪ではなく、そこにあるままの手指の方が幾らも愛しく、ずっとずっと欲しいものだった。千塚さんが欲しいですと、私ははじめて会った日に見たきりのなめらかに動く千塚さんの手を思い出しながら、口の中で呟いた。
棺の淵に身体を沿わせ千塚さんの上に軽く覆い被さる格好で、私はいつまでも彼の顔を眺めていた。欲しい、欲しいと口の中でつぶやきながら、何も盗らず奪えなかった。与えて欲しかったのかもしれない、欲しいとつぶやく私はそう考えて、それよりも、与えさせて欲しかったのかもしれないと思いながらまた、欲しい、とつぶやく。
頭を垂れるとかぶっていた帽子が転がり千塚さんの顔の上に落ちた。無垢な輝きを放つ白い花の上にショッキングピンクの円がぽっかり浮かんだ。
私は毎晩千塚さんの夢を見て、いつも千塚さんのことを考えていた。あるときは死んでいる彼で、あるときは生きている彼との想像上の戯れは、緊張を伴って高まり、ピークを迎えると、そのあとはむなしくたるんでしぼんでいった。私の生活はその繰り返しに支配された。
身体はつねにだるさを覚えていたけれど、脳みそが休まらないので手足を動かしていないと肉体と精神とのバランスを崩してしまいそうだった。私は起きている間のほとんどをキッチンで過ごし、ネットでレシピを追いながら強迫観念に追い立てられるようにずっと食べるわけでもない焼き菓子やプリンなんかを作っていた。死にたいな、いちご味のチョコペンで文字を書いてクッキーをデコレーションしてみる。
甘い香りのするゴミを量産し続ける私のもとに美南から連絡が来たのは五月も終わりを迎える頃だった。
「連絡全然できなくてごめんね」
スマホに表示された彼女からのメッセージを確認すると、自分が抱えていた不安が少し癒やされたような気持ちになった。乾いてざらついた砂に水が染み込んでいくみたいに。
「気にしないで。それよりも、この間はいきなり助けてなんて送ってごめん」
画面を見ると、送った文章はすぐに相手に読まれていることが分かる。
「ショックだったよ」美南から返信が来るより前に私は続けた。「千塚さんのことね」。
「今も、どうしていいかわからない」メッセージはリアルタイムで読まれているようだったけれど、返信はすぐこない。その反応の遅さがもどかしい。
「一回、お茶したいな」
「うん。いつでも平気。店もずっと休んでるし」
やっと返ってきた美南からの言葉に私は百人一首の札を取る早さで返信し、「じゃあ、今日は?」と質問を継いだ。
美南が指定してきたのは、四月に一緒にランチをしたカフェだった。私たちの家は電車で一駅しか離れていないから、彼女の家に近いその店は私のところからもそう遠くはない。
いつも大抵そうであるように、待ち合わせた時間に店に入ると先に美南が待っていた。彼女が私に柔らかく微笑みかけてくれるのもいつもと変わらないのに、席に着くと、いつもとは違ってどう話を切り出していいか分からなくなった。今日の美南はいつもと同じに化粧も服装もちゃんとしているのに、どこか寝起きのようなけだるさをまとっているように見えた。
注文したアイスティーが運ばれてくるまで、私たちはとりとめのない話をしていた。それぞれが自分たちの話すべき本題に触れないようにわざと迂回をしていたのかもしれない。天気の話、妊娠している美南の体調のこと、私たちの掛けた席に面する窓から見える花の名前。
「お店入るときにすごくいい香りがしたんだけど、あそこに咲いてるやつかな」
「テイカカズラ、だったかな」
ガラス越しに咲く、小さな花をたくさんつけた蔓性の植物を指して美南が言った。全体的に白い花は、花芯のまわりにだけほんのりと淡いクリーム色がついている。
「よく知ってるね」
「たしかそうだったはず」
美南が口にした名前を検索にかけると、スマホの画面にも同じ花が咲いた。
「正解」
「うちのマンションの生け垣にも植わってるんだよね。ジャスミンみたいな甘い香りの」
表示されたページには同じ言葉でその芳香が説明されていた。名前は藤原定家の悲恋に由来するらしい。身分違いの恋をした定家は死んでからも相手を忘れられず、テイカカズラに生まれ変わって彼女の墓に絡みついたという伝説が短い文章で載っていた。
「鈴ちゃん、ゆめいろファクトリーのこと知ってたんだね」
千塚さんについて話をするにしてはおかしな切り出し方をするなと思った。私がうなずくと、美南はつぶやくような調子で言った。
「江藤真奈子」
久しぶりに聞く名前に、心臓をつかまれたような気持ちになる。テーブルに置かれたアイスティーのグラスの中で氷がカランと音を立てた。私のグラスで発生した音に共鳴するように続けて美南のグラスの中でも氷が溶ける音が聞こえる。
「私の妹なの」
耳から入ってきた声が心臓に突き刺さり、一瞬、自分の時間が止まったように思えた。反応する声がうわずる。目の前の美南はやや伏し目がちのまま、こちらにスマホの画面を差し出した。
「鈴ちゃんに言うかどうか迷ったんだけど、言わずにいたらこのまま会えなくなりそうな気がして……」
画面に表示された家族写真。四人掛けのダイニングテーブルには美南とまなこが隣り合って腰掛け、向かい合う位置には両親だと思われる男女が座っている。姉妹ふたりの容姿はまったく似ていないけれど、母親のほうは少しまなこに似ていた。食卓には木製のおひつが置かれ、伊万里焼風の丸い大皿の上に彩りよくお刺身が盛り合わされている。そこに写っているものは、まなこのブログに載っていた父親の誕生パーティの日の写真と同じものだった。合成を疑おうと思えば疑えるけれど、美南が私をだます理由は見つからない。耳の横に心臓が移動してきたみたいに、自分の鼓動が大きく聞こえ、顔が火照る。私は声を出すことができないでいた。
「母親が違うんだけどね。うちは父親が再婚だから。若いでしょ、真奈子のお母さん」
肩を寄せ合う美南と真奈子の姿を見ると、ふたりの仲は悪いものではないのだろう。間違い探しでもしているみたいに、私は写真から目を離せなかった。このまま画像をずっと見ていても何も変わることはないし、分かることはないんだけれど、ただ、美南のもとにこの写真を戻して、そのあとで一体自分が何を喋ればいいのか見当がつかなかった。
「アイドル活動、頑張ってたみたいだけど……もう辞めることにしたみたい」
何も返せないでいる私の代わりに、美南が自分で言葉を継いだ。
「しょうがないよね、あんなことがあったら。真奈子は口には出さないけど、相当つらいとは思う」
ごめん、と言いかけて私は口をつぐむ。それは「千塚さんサイドの人間」の言葉のような気がした。
「前からライブとかイベントに来てたみたいで、真奈子も覚えてたよ。とくに危ないファンていうわけでもないみたいだったんだけどね。分からないね、人って」
そうだね、と応えたいけれど、私はそもそも千塚さんがどんな人なのか、元から分かってはいなかったのかもしれない。
「大しゅき、だって」
私たちの間で少し続きそうだった沈黙を、美南が不意に破る。
「大しゅき……?」
「真奈子の前で自分をそう名乗ってたらしいよ、あいつ。」
幼児語が気持ち悪いと、彼女は言いたいのだろうか。うまく言葉を返せなかった。美南が真奈子の姉だと知ったショックは大きく、まだその衝撃を受け止められないままだったけれど、それでも彼女の前で、まだ千塚さんのことを非難できない自分には、罪悪感を覚える。
美南が千塚さんを「あいつ」と呼んだことにさえ、私は少しショックを受けていた。彼女が名前も呼びたくないほど疎んじている相手と、私の想う千塚さんを結びつけることができないでいた。私はまだきっと、彼のやったことを受け入れられていない。そのことについて考えるために思考を巡らそうとしても、なぜか自動的にプツリと回路は断たれてしまう。
「気持ち悪いよね。イベントでチェキ撮るときとか、真奈子からそう呼びかけられたいからその名前にしてたわけでしょ」
美南に言われて、そういうことかと合点がいく。好きな人に、好きだと言ってもらえるいちばん手っ取り早い方法かもしれない。私も、千塚さんにそう名乗っていれば良かったな。大しゅき、大好き、愛してる。そして、彼が行動を起こすより早く、彼にきちんと出会っていれば……。
もしもの過去に意識を飛ばしそうになる私を、美南の静かな声が引き留める。
「どんなに好きだからって、相手を傷つけることをするのは間違ってるよね」
伏せられた薄化粧の繊細なまつげは、まばたきのたびに微かに震えていた。そうだよね、と、心から彼女の言葉に同意できたらどんなにいいだろう。私がもし再び千塚さんと出会っていたとして、それでも彼の気持ちをこちらに向けることができなかったら、私は自分がどうなってしまうのか、彼に何をしてしまうのか、それを、あまり想像したくはなかった。
私も少しうつむくようにして、目線を白木造りのテーブルの木目にうつした。
「鈴ちゃんが好きになった相手が、どんな人なのか、どういうことをしたのか、それを知って欲しかったのかもしれない」
ひとりごとのように美南は言い、
「ごめんね」
何も悪くない彼女が謝る。
美南なら、私が今どんな毎日を過ごしているか想像ができるはずだった。お菓子でできたゴミの山については知らなくても、私の考え方や生活がいまだに千塚さんを中心にまわっているであろうことは。そのせいで私の心が不安定に揺れ続けていることだって。だから私に会って、この話をすることを選択したのだろう。
顔を伏せたまま、目を閉じる。それでも浮かぶのは千塚さんの姿。その笑顔。私は一度だって、彼の笑った顔なんて見たことはなかったけれど。嗚呼、見たかった、触れてみたかった。
「まなこに、会えるとしたら、会う?」
不意の問いかけが私の胸をさらにざわつかせた。事件のあとから、一時的に自分の住むマンションに真奈子を住まわせているのだと美南は言った。今は電車に乗せるのも怖いから、どこかに行くときは美南が付き添って、タクシーで移動しているらしい。このあとに真奈子と一緒に出かける予定があると私に伝えたところで、彼女は一旦話をやめた。
「……もちろん、あいつに関する鈴ちゃんのことは話さないし、言わないで欲しいけど」
私の胸の内の逡巡は、言葉にならない声になる。それを汲み取ろうとする美南も、私に話を持ちかけていながら戸惑いを感じているようでもあった。
「こんなこと訊くのは、変かな。鈴ちゃんにとって、どっちのほうがいいのかなって、考えちゃったんだ」
マンションの入り口につながるアーチには、その骨組みに沿うようにしてカフェの窓から見えたのと同じ蔓性の植物が茂っていた。あたりには花の芳香が広がっていた。小さくて可憐なその姿にぴったりの、切なさを覚えるほどに甘い香り。
美南が呼んだタクシーはもう到着していて、私たちは真奈子が外に出てくるのを待っていた。
テイカカズラの這うアーチから、黒と白のギンガムチェックのワンピースを着た天使が飛び出してくる。写真で見るよりもずっと小さい印象の顔、華奢な手足、内側から発光しているような明るい笑顔が、美南を呼んだ。その表情は崩れることなく私にも向けられる。元々の人懐っこい性格もあるのだろうが、姉の友達だと聞いているからか、安心している様子だった。美南はカフェを出る前に電話口で彼女に、一緒にお茶していた友達をついでに隣駅までタクシーに同乗させることの了解をとっていた。
邪気のない笑顔が私には、眩しかった。千塚さんでなくても、この少女になら誰だって特別な物語を期待してしまうだろう。
すぐに降りるからと遠慮をしても真奈子はタクシーの後部座席を私に譲った。
目の前の中学生は、おそらくこちらを気遣って話しかけてくれているのに、私は気の利いた返答もできないでいる。真奈子とはたぶんもう二度と会うことがないのに、この短い時間を繕うことさえできないでいた。口ごもる私の右手の人差し指を、美南がそっと握る。
こんな私のことを見守ってくれる人がすぐ隣にいる私は、きっと恵まれた人間なのだと思う。しあわせ者、という言葉さえ、よぎる。だけれど私にはそういう安らかなやさしさの中に、自分の身を落ち着けることはできなそうだった。
心が求める相手に恋をしているとき以外、私の命はまったく無駄なガラクタだ。何も正しくなくたって、湧き上がる情動に身を任せ矢印のような欲望に従うことでしか生きている実感を得られない。それは、もしかしたら恋ではなくてもいいのかもしれない。だけど、それ以外に、自分の心を動かしてくれるものは私には見当がつかなかった。
私が欲しいものは一体、何なのだろう。ずっと、何かに向かって手を伸ばし続けているような気はしている。まわりから見れば満足に呼吸ができる場所にいるように見えていても、私はいつだって海で溺れる者のようにもがいている。助けて欲しい、そう泣き喚いている。助けて、苦しい、つらい。だけど私はどこがどうつらいのか、どうして苦しいのか、どんな助けを求めているのか、自分でもよく、分からない。脳みそはいつだって叫び声を上げたくてたまらず、脈絡もなく下腹部が切なく疼いて、今すぐにこの場所から走り出したくなるような不快な衝動に襲われていたとしたって。
言葉のつむぎ方も分からないのに、求めているものが何なのか見えてもいないのに、向かいたい場所が思いつかないのに。こんなにも欲しいのに、欲しいものの正体が分からない。
欲しいものに当てはまる何ものかが存在しないことこそが、私にとって最大の不幸だ。
私は早く、再び自分が強く激しい感情に新しく支配されることを望んでいる。欲しいと願えるものが現れることだけが私の中に渦巻く不快感を生きる力に変えてくれる。欲しい、欲しい、私は胸のうちでつぶやきながら、私の指を握る美南の顔をそっと見遣った。目線に気付いてこちらに微かな笑みを向けた彼女に応えるように、私も軽く唇の端を上げる。久しぶりに顔面の筋肉運動を行ったせいで、不随意筋がヒクついた。
サポ希望
