
ポケカにおける持ち時間制の導入
1.はじめに
ツムギです。ポケカプレイヤーです。
ここ最近まで、大好きなポケカを封印してずっと将棋を指していました。

将棋が一段落付いてポケカに戻った際、「何でポケカの対人戦は競技時間が持ち時間じゃないんだろう?」と今更ながら純粋に思いました。
(PTCGLでは実装されているのに何故…?)
ポケカの対戦時間が25分を2人のプレイヤーが共有する方式(以降では時間共有制と呼称します)であるのに対して、将棋の対局は持ち時間制となっており、時間の計測にはチェスクロックと言われる1台に2つの時計がついた特殊な時計が用いられます。対局者それぞれの持ち時間がそこに表示され、2つの時計のうち片方の時計のボタンを押すとその時計が止まり、同時にもう片方の時計が動き出す仕組みとなっています。

先ほどの疑問を晴らす切っ掛けになると思い、今回はポケカに持ち時間制を取り入れた際のメリット・デメリット及び、導入にあたっての課題を整理した上で、実現は果たして可能なのか自分なりに考察しました。
また、将棋における持ち時間制には異なる3種類の設定(指し切り、秒読み、フィッシャー)がありますが、今回は時間切れ=敗北となる指し切りの場合を想定しております。
前回のデッキ構築記事よりさらに主観が強くなってしまいましたが、最後までよろしくお願いします。
2.メリット
①勝敗の明確化
残り時間ギリギリ、サイド枚数的にもどちらに転ぶか分からない試合での両負けが無くなります。自分に勝つ可能性が1%でもある限り、勝負を投げない、降りたくないと両プレイヤーが思うのは真剣勝負をしに来ている以上、当たり前のことだと思います。これはどの競技においても言えることです。どちらが勝つか周りからも分からない、そんな熱い試合が結果的に両負けで終わってしまう、これは見ている側からしても非常に勿体ないことだと思います。両負けによるオポネントの低下はプレイヤーのモチベーションの低下にも繋がります。
また、サイド差が開いている試合でも、現ルールでは負けている側が粘ること=遅延行為をしていると対戦相手、傍観者に受け取られてしまうという問題点があります。意図的に遅延をしているかどうかなんて本人にしか分かりません。もし、細い勝ち筋を掴むために必死に粘っていたとしたら、それを遅延と決めつけるのは大変失礼な行為だと思います。
(実際、CL福岡の配信卓のコメント欄で、遅延行為などの書き込みがいくつかありました。)
ポケカは将棋に比べて逆転のチャンスは全然有る方です。ツツジがあります。カウンターキャッチャーもあります。
そのため、時間を分けて勝敗を明確にすることは、このような批判からプレイヤーを守ることにも繋がると思います。

②遅延行為の減少(一部を除く)
自分ターンを目いっぱい使用した明確な遅延行為は出来なくなり、時間を使う=遅延行為とは受け取られなくなます。時間を使うことが対戦相手に何のデメリットももたらさなくなるためです。ただ、ポケカは相手ターンでも自分が介入することがあるため、そちらでの遅延行為が出来てしまいます。これについては、後述のデメリットの項目に記載しました。

③プレイヤーのデッキ練度の向上
仮に持ち時間制が導入された場合、皆さんはどうしますか?デッキの内容をよく覚えて序盤の山札確認を早めたり、自分のデッキの基本動作のチェックを今までより入念に行うなどして、自分のデッキを早く正確に回すことを意識するのではないでしょうか?
勿論、普段から欠かさずに行っている方もいるかと思いますが、一人一人がこれらをより徹底することで、ポケカプレイヤー全体のレベルはさらに上がるのではないかと思います。
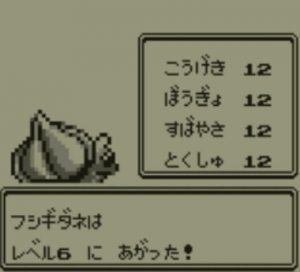
ただ、対戦時間が相手と共有されている現状では、いくら自分の練度・速度を限界まで上げたところで、時間切れが起こらない保証は100%ではありません。仮に10秒ではなえらびを3回決めてターンを渡した試合でも相手次第では、時間切れ両負けとなる可能性だってあります。
上級者同士の対戦ではお互いプレイングが洗練されているため、時間切れとなるリスクは少ないかと思いますが、上級者も初心者と対戦する機会は沢山存在するわけで、その対戦の中には時間切れ両負けとなってしまった悔しい試合展開もあったかと思います。
時間共有制の場合、両者が敗者となってしまい「両負け。悔しい」の短絡的な感情のみでお互いに完結してしまいますが、持ち時間制は勝者と敗者でそれぞれ得るものがあると考えます。
勝者は当然勝ち星を得ることができます。では敗者は何を得られるのか、それは時間の使い方です。
時間の計測に使うチェスクロックは、時間切れで試合が終わった後も対戦相手の残り時間を確認することができます。相手の残り時間を見て、相手と自分の時間の差は何故生じたのか、序盤・中盤・終盤のどの局面に時間を使いすぎたのかを考え、次に生かすよい機会になるかと思います。自分一人では分からなければ、対戦相手に聞いて見るのも手です。自分が沢山時間を使っている間は相手にとって何のデメリットもないし、何より相手の方も勝って機嫌がいいはずなので、恐らく普通に教えてくれると思います。これは時間共有制にはない大きなメリットです。
3.デメリット
①イニシャル・ランニングコスト
チェスクロックは安いものでも2000円弱です。ツツジのSARとだいたい同じくらいの値段です。CLのような3000人規模の大型大会では2000円×1500台で300万円は必要で、さらに故障等も考えると予備として数十台は用意して起きたいです。大会がある度にいちいち機材を準備&動作チェックをするのは、かなりの手間と費用が掛かると思われます。
スマホのアプリを使えば簡単に準備は可能ですが、相手にスマホを触らせたくない人も一定数は居ると思うし、時間が切れそうになったらわざとアプリを閉じる手段が取れてしまう(もしくは誤って閉じてしまう)、スマホのバッテリーが途中で切れるなど、様々な課題があることは確かです。

②相手ターン内の意図的な遅延行為
カードテキストやトラッシュの過剰な確認行為、山札の過剰なシャッフル、自分のカードを相手ターン中に選ぶ際にわざと時間をかけるなど、相手側の時計が動いている状態で時間を奪う手段がいくつかあります。
相手の山札をカットする際は山を2~3回分ける程度に留める、トラッシュやテキスト確認時には自分側の時計を進めるなど、ルールに予め縛りを設けることで対策することは可能ですが、その縛りの盲点を付いた遅延行為が発見される可能性は否定できないし、何よりグレーな遅延行為が発覚した際、現場で対応に追われるジャッジさんが大変だと思います。

③ルールの整備と理解の難易度
現行のカードテキストやルールと持ち時間制度の擦り合わせがかなり面倒になるかと思います。
ハンドトリマーを初めとした、相手に選ばせる系のカードを使った際、どちらの時計を進めるのか、試合中に時計の電池が切れた際の対応はどうするかなど色々と考えることが多過ぎるし、やはりジャッジさんが大変です。
また、持ち時間制度の導入によって一部のデッキタイプが大幅に強化されるのであれば、ポケカ公式側が今後新カードを刷る際に、パワーバランスを考慮する必要も出てくると思います。

4.まとめ
真剣勝負の機会が増えて競技性が上がる点、練習を重ねたプレイヤーが不利になりにくい点などのメリットは確かに大きいと思いますが、それを帳消しにするほどのデメリットが`メガ盛りでした。
ポケカにおいて持ち時間制は、既にPTCGLという形で導入されていますが、それを三次元に落とし込もうとする場合、数多くのトライアンドエラーを経て時間に関わるルール整備を行い、そのルールをどのような手段を持ってプレイヤーに浸透させるのかが大きな課題になりそうです。
このように現時点で制度の導入はかなり厳しいものがありますが、ポケカは他のカードゲームと比べると相手ターンに自分が動くことは比較的少ない方だと思うので、近い将来でもよいので実現してくれたら嬉しい限りです。
また、文章内に言葉足らずな点があるかとは思いますが、決して現在のルールを安易に批判したい訳ではないということをご理解いただきたいです。
時間共有制が大人数の試合を処理するために、とても有用な手段であることについては間違いないと思います。
最後まで、見ていただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
