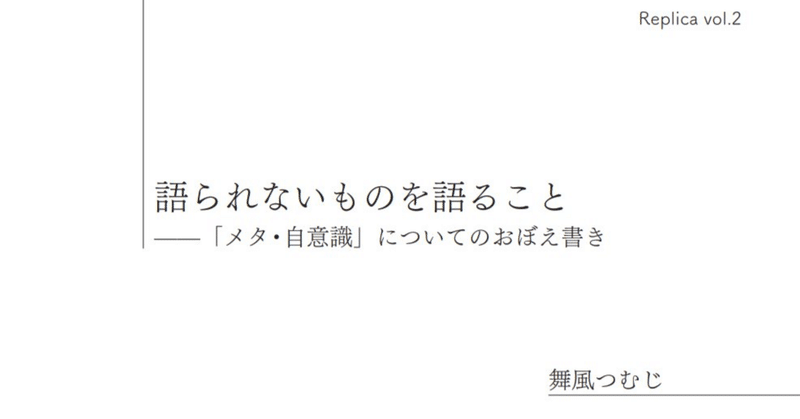
『レプリカ』Vol.2 試し読み
※本記事はC103二日目ネ48bで頒布される『レプリカ』vol.2に収録されている「語られないものを語ることーー「メタ・自意識」についてのおぼえ書き」の冒頭部分(はじめに&第1章)です。
『レプリカ』全体についてはこちらをご覧ください。どれも非常に面白い内容です。よろしくお願いいたします。
【表紙&目次 公開🎉】
— 俺ガイル研究会@C103ネ48b (@kangairureplica) December 15, 2023
#俺ガイル 考察集『レプリカ』vol.2の表紙&目次を公開します! #コミックマーケット103 にて頒布予定です。
表紙イラストは はやせさん(@04Haya_S)、デザインは西村ダイヤさん(@Overcast_games)にお願いしました。とても素敵な表紙をありがとうございます!! pic.twitter.com/iDELGYmudE
はじめに
比企谷八幡とは結局のところどのような人物なのだろうか。ごく一般的な観点から言えば、彼はまずニヒリスティックであり、すぐさま他人に対して意味のない言い訳を展開する、"腐った"冷笑家である。「青春とは嘘であり、悪である」(1巻、十二頁)にしろ、「薄っぺらい奴ほど人に影響されやすいのと同様、薄く切ったほうが味がよく染みる」(同、七三頁)にしろ、彼の言葉はユーモアに満ちた皮肉や、作者の経験から来るであろうパロディでしばしば彩られる。
一方でまた、彼は自己犠牲的な精神を持ち合わせてもいる。好例であるのは6巻と7巻、それぞれ文化祭のシーンと、修学旅行のシーンだろう。彼の自己犠牲を厭わない態度[1]はまさに魅力的な「ダークヒーロー」であり、それゆえに彼は孤高の「ぼっち」として登場した。こうした八幡のひねくれていながらも芯の通った在り方が、当時中学生だった僕の心を鷲掴みにしたのは言うまでもない。
さて、このような見方は、本作を通読することによって生まれる八幡に対する評価としてある程度妥当であるように思える。しかしながらそれは、「他者から見た比企谷八幡」という評価であることは留意されなければならない。本作で幾度も繰り返されてきたように、言葉にするたびに伝えたいことはこぼれ落ちてゆく。我々もまた、同じように他者である八幡の言葉を受け取ることで、彼の言外の意図を捉え損ねていはしないだろうか。一見すると、確かに我々は地の文から八幡の内心を知っているように思える。ただ、この感覚は錯覚に過ぎない。もちろんそれは、彼の意味のない軽口やパロディを真剣に受け取るべきだという意味ではない。しかし、そうしたパロディによって隠蔽された八幡の本心を我々は見落としていないと断言できるだろうか。例えば文化祭直後の「そうやって自分を励まさないと心が折れてしまいそうだ」(6巻、三四八頁)であったり「なんなら端っこの方がぺきっと欠けて夜中に布団の中で少しだけ泣いたまである」(7巻、一二頁)という表現は、恐らく八幡は本当に傷ついたはずなのにも拘らず、前後が軽口で封をされているために我々は軽く読み流してしまう。このように、八幡は自身の主張すらくだらない言い訳によって覆い隠してしまうことが多い。
それでは、我々は八幡の本心を知ることはできないのだろうか。緘黙する彼を前に、我々は無力なのだろうか。恐らくはそうではない。そこで本稿が志向するのは、地の文を媒介してどのようにして八幡が我々……さらに言えば、自分自身からも隠してしまいたいと思っているであろう本心を暴きたてるかを考えることである。地の文の描写ですら現れない彼の本心は、彼自身の欲望に密接に関係しているものでもある。これを看破するということは八幡からすればたまったものではないと思うが、その辺りは諦めてせいぜい悶絶していただきたい。僕の見立てでは、比企谷八幡はシニシストでもなければ、自己犠牲を厭わない高潔な人物でもない。それは彼の複雑な自意識の回路によって出力された虚像であって、彼自身を的確に表すものではない。彼は極めて矮小な、しかしだからこそ愛すべき主人公なのだ。
そこで、本稿ではまず「メタ・自意識」とでも呼ぶべき八幡の心理を形成している構造について分析する。この構造があることによって、八幡は地の文でさえも本心を隠してしまうことが可能になる。逆に言えば我々はこの「メタ・自意識」に対して自覚的になることで、八幡の本心へ到達することができるだろう。
その上で、この「メタ・自意識」を考慮した上で生まれてくるであろう八幡の人物像をめぐるいくつかの主張を考えてみたい。そこでは「八幡は○○である」といったようないくつかの簡潔なテーゼについて、具体的に検討していくことになる。
次にこの「メタ・自意識」を持つ八幡以外の人物を参照する。彼女と八幡の関係は、必然的に「メタ・自意識」の存在を既定したうえで展開されるものであり、そこでは八幡の神髄にせまる記述が多々あるように思える。この部分を読み解いていくことは、我々が八幡自身を読み解く一助となるはずである。
そして最後に、本稿では『俺ガイル』の結末について考えてみたい。言ってしまえば、「メタ・自意識」の存在がいかにして「本物」と関係するかという問いに他ならない。これは延いては『俺ガイル』の解題であり、『結』の結末を夢想することでもあるだろう。
1.八幡の「メタ・自意識」
確かに、度し難いほどの自意識が己の中に渦巻いている。おそらくは自身の自意識すらも否定したくなるほどの自意識が。それは神話の中の存在の迷宮めいた袋小路に閉じこもっている怪物の姿を想起させる。あれは最後、英雄に殺されたのだったか。
己の弱さを晒すことなど俺には耐えられない。臆病な自尊心ゆえではなく、尊大な羞恥心ゆえに。
だから、どれだけ食い下がられても、おどけてまぜっかえして誤魔化して煙に巻くに違いない。
比企谷八幡を形成する心理構造は、こうした部分に集約されていると言える。「自身の自意識すらも否定したくなるほどの自意識」、自身の弱音を韜晦する「尊大な羞恥心[2]」……それこそが、八幡の意識の構造である。本稿では以後、この自意識すら否定する自意識を、自意識そのものと分離しているものと解釈して「メタ・自意識」と呼ぶことにしたい[3]。
自意識とは、少なくとも『俺ガイル』においては自分自身に対する俯瞰的な視点と考えてよいだろう。それは転じて他者の視線を内面化しているということでもあり、その内面化が過度なものとなればいわゆる「自意識過剰」の状態になる。自意識過剰の状態ではしばしば自身の欲望を否定する態度が表れるが、それは多くの場合自身の否定ではない。むしろ視線を過度に内面化しているがゆえに生じる、自身の(多くの場合醜い)欲望を隠し、評価を得たいという自己愛に起因するものだと言える。
対して、「メタ・自意識」は決して「自意識過剰」と同じ意味ではない。メタ・自意識が行うのは、視線を過度に内面化することではなく、内面化した視線そのものを強烈に否定し、過剰になりかける自意識を絶えず制限することである。これは自己愛というよりはむしろ自己愛すらを否定し、隠蔽する姿勢であると言える。そして何より、メタ・自意識の存在は決して自意識の存在そのものを否定するものではない。八幡の中には確かに醜い欲望があり、それを表出させるのを憚る自意識がある。しかしながら、メタ・自意識はそれらをさらに包摂し、保身に走ろうとする自意識を制限していると考えるべきだろう。
このメタ・自意識が我々に影響を及ぼすのは、それが地の文への自意識の表出を妨げるからである。多くの場合、一人称の語りでは自身をやや俯瞰的に見た視点(≒自意識)によって言葉が語られる(『俺ガイル』においての例を考えるならば八幡以外の一人称、例えばPrelude/Interludeを参照されたい)。しかしメタ・自意識は、キャラクターの思考とその語りの間に介入し、本来地の文として出力されるべきものを検閲する。この構造によって、我々はいつまで経っても八幡の本心へたどり着くことができない。
ただし、この「メタ・自意識」は先天的なものではなく、後天的に獲得されるものである。八幡を例にとれば、中学時代の(折本かおりに告白するという暴挙に出たころの)八幡は「自意識過剰」の状態であったといえる。
相模は自意識が強い。そのはずだ。
[…]
なら、相模のプライドは、自尊心は、自意識は。
その懊悩は手に取るようにわかる。
誰もが通ってきた道だ。
甘いよ、相模。それは俺が既に通った道だ。
八幡は自意識に起因する葛藤をばっさりと切り捨てる。そして重要なのは、メタ・自意識が常に自意識を制御できるわけではないことである。メタ・自意識とは、恐らく後天的に獲得されるものなのであり、先天的・本能的な欲望と抱き合わせで存在している自意識はメタ・自意識とはこの点でも大きく異なっている。本能(=欲望・自意識)を後天的に制御できているからこそ八幡は「理性(自意識)の化け物」たりえている。ただ注意したいのは、それでもごくまれに自意識がメタ・自意識の制御を脱し、前面化する場合があることである。そうした綻びには、八幡のメタ・自意識を解体し本心へと到達できる余地があるだろう。
さて、本章で見ていきたいのは、このようなメタ・自意識の構造がもっとも前面化する「八幡の自身に対する評価」である。先に述べた通り、八幡は自身の欲望を隠し評価を得たいという自意識の欲求すらを、唾棄すべきものとして否定する。つまり作中で描かれるような彼の自身に対する評価というのは、多くの場合メタ・自意識に制限されたものであり、これを看破することこそがメタ・自意識を解体するための第一歩としても相応しいものであると言えよう。そこで、こうした部分からまず第一の主張を導くことにしよう。
主張1:比企谷八幡は、自分が嫌いである
多くの読者はここで、八幡の自身の評価には肯定的な主張が織り込まれていることを思い出すだろう。参考までに例を挙げるのならば、「どうして今の自分や過去の自分を肯定してやれないんだよ」(1巻、四二頁)や「せめて俺くらいは俺に優しくしてあげようと思うわけ」(同、一二四頁)に始まり、「むしろ大好きだね、こんな自分が」(6巻、三四八頁)などがあるが、実際には枚挙にいとまがない。
こうした彼の自身に対する肯定的な評価は、ともすれば「開き直り」に思えるかもしれない。八幡はいわゆる「逆張り」的な精神のもと、他者に嫌われがちな自分のことをあえて肯定している、と。しかし、僕の主張はそうではない[4]。八幡の自身に対する肯定的な態度はメタ・自意識の引き起こす韜晦に過ぎず、八幡は決して自身を肯定的に評価しているのではない。八幡のメタ・自意識は、自身のことを嫌悪する態度を見せる自意識そのものを嫌悪する。結果として、我々が見ることが可能なのは、メタ・自意識が検閲した後のものであり、それは反転して自身を肯定していることが多い。こうした仮説のもと導き出せるものが、主張1である。我々はメタ・自意識を解体した先に、八幡の自身に対する否定的評価を見ることができる[5]。
俺は自分が好きだ。
[…]
だが、初めて自分を嫌いになりそうだ。
勝手に期待して勝手に理想を押しつけて勝手に理解した気になって、そして勝手に失望する。何度も何度も戒めたのに、それでも結局直っていない。
——雪ノ下雪乃ですら嘘をつく。
そんなことは当たり前なのに、そのことを許容できない自分が、俺は嫌いだ。
八幡が自身を否定的に評価している部分というのは、あまり多くはない。メタ・自意識が否定的評価を覆い隠すため、それは当然の結果である。上記の引用箇所は、その数少ない部分の中で、もっとも否定が表れている部分といえよう。
この部分を読むにあたってまず第一に考えるべきことは、「嫌いになりそうだ」という言葉が、直後に「嫌いだ」と言い直されることによって明確な虚勢だとわかることである。八幡が自身を否定的に評価するのは、雪ノ下雪乃が嘘をつくという「当たり前のことを許容でき」ず、「勝手に失望する」ような自分についてである。これは何度も戒めたと自身で言うように、文字通り何度も起こっていることであるはずだ。事実僕たちは、これと全く同様の八幡自身の過度な期待による失望を少なくとも一度は経験していることを知っている。
辛いのは、自分が好きだと思っていた子に、そのくらいのことで失望している自分に気づいてしまったことだ。そんなことすらわからなかった、気づけなかった自分にこそ非はあるのに。自身の幼さゆえの無知だけは笑って流すことができない。
このように八幡は、やはり気づくことのできなかった自身のことを非難する。それは相手が誰であれ変わらない。彼は自身の理想にそぐわなかった他者ではなく、そうした理想を抱きかつ他人に押し付けたいという彼の欲求を、そしてそれを制御できなかった自分自身を嫌悪する。そこに見えるのは、欲望を制御しきれなかった己の弱さを恥じ入る、複雑なメタ・自意識の構造である。こうした自身に対する否定的な態度は、メタ・自意識が生み出す八幡の心理構造の理解を促進させるだろう。メタ・自意識とは、自身の欲望を否定するという自意識過剰な態度(と、その保身的態度によって欲求される他者からの肯定や慰め)そのものを否定するために、自身を肯定しているかのように見せる態度のことなのである。
(以下、『レプリカ』vol.2でお楽しみください……!)
(註釈)
[1]もちろん、それを自己犠牲と呼ぶのは憚るべきである(8巻、二〇四頁を参照)が、ここではひとまずそう呼ぶことにする。
[2]当然ながら、これは中島敦『山月記』からの引用である。弱さを隠し、自身が特別であると信じ、市井と距離をおこうとする「尊大な羞恥心」に八幡は気づいている。しかしそれすら口に出せないアイロニカルな態度こそ、まさにメタ・自意識そのものである。
[3]これはいわゆる「超自我」とは構造としては近しいものの、異なるものである。「超自我」は主に社会規範や道徳心によって「自我」を抑えつけるものであるが、「メタ・自意識」は常に自己の中から生まれてくる規範に忠実である。そのため、社会といった外部の規範に反しているか否かという点は「メタ・自意識」の持つ価値判断とは関係しない。
[4]そもそも、『俺ガイル』内においても八幡の自己評価は何度も変わっていく。「チャームポイントだらけのチャーミングな俺を、俺はきっと好きになれると思う(9巻、二六七頁)」などは、まるでそれ以前は自分のことを好きではなかったかのような口ぶりであり、評価が二転三転するその典型であろう。
[5]しかしこれは、必ずしも自身を否定するということを意味しない。ここで八幡が行うのは徹底的な嫌悪である。自身のことを嫌悪しながら、それでもなお否定はせず、変化もせずに日々をやり過ごしていく。それこそが、メタ・自意識が自意識を制限することによって自らに課す使命である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
