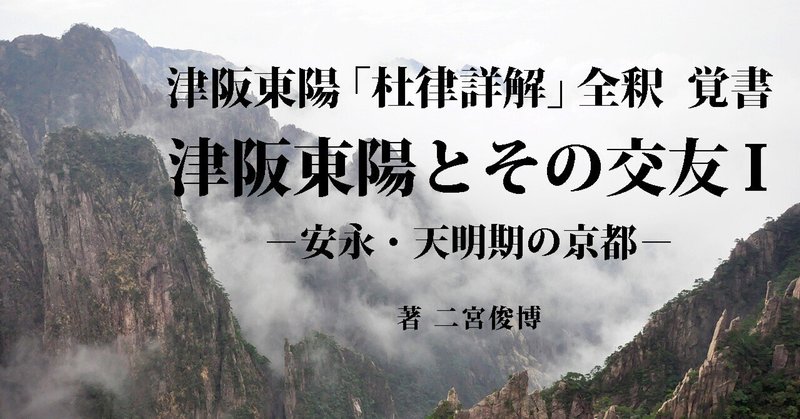
覚書:津阪東陽とその交友Ⅰ-安永・天明期の京都-(8)
著者 二宮俊博
儒者―那波魯堂・皆川淇園・頼春水・古賀精里・藪孤山・柴野栗山
ここでは先輩の儒者に贈った詩を取り上げる。ただし、これらの作は詩友と贈答応酬した作に比べると、おおむね面白味には缺ける。概して相手の学問人品を称えることに終始しているからである。
那波魯堂(享保12年[1727]~寛政元年[1789])
『日本詩選』の作者姓名に「那波師曾 号魯堂。播州の人。帷を京師に下す」と。姫路の人で、京に出て岡白駒(元禄5年[1692]~明和4[1767])に師事し、徂徠学を学んだが、後に朱子学に転じた。東陽より29歳上。『詩鈔』巻七に「冬夜、那波魯堂に詣る」と題する七絶がある。この人は安永9年に阿波に赴任しているから、おそらくそれ以前の作であろう。東陽が京に遊学して間もない頃だと思われる。
當世儒宗自屬公 当世の儒宗 自ら公に属し
文章經術並稱雄 文章経術 並に雄と称さる
不知氷雪嚴寒夜 知らず氷雪厳寒の夜
坐了春風和氣中 坐了す春風和気の中
◯当世儒宗 当代の儒学の大家。『類書纂要』巻十一、人事部に、この語を挙げ、「晋の賀循、朝廷の凝滞皆之を諮訪す。輒ち経礼を以て対す。当世の儒宗なり」と。『蒙求』巻上の標題にも「賀循儒宗」がある。◯坐了春風 同じく『類書纂要』に「坐了春佳風」を挙げ、「朱光庭、程明道先生に従学す。帰りて人に語って曰く、光庭春風の中に在り、坐了す一個月」と。『書言故事』にも見える。
弱齢で詩の技量がまだ十分ではないせいか、語釈に示したごとく出来合いの言葉をうまく並べた感があるのは否めないが(もっとも、詩語を如何に巧みに配置するかが問われるのが漢詩であるからそれを否定しては詩が成り立たぬのも事実だが)、一介の書生に対しても温かく接してくれた大家に感激の思いを抱いたことは伝わってくる。
ところで承句に「文章経術」と並べて記していることには注意してよかろう。東陽にとって文章と学問とは切っても切れない関係にあるもので、それを両立させることに自身のあるべき姿を見出していたからである。むろんそれは、中国の学藝においては伝統的な考えかたであって、とりたてて指摘する程のことではないと言えば、そうである。しかしながら、当時、文章にこるのを「玩物喪志」(『尚書』旅獒)として、これを斥ける北宋の程伊川(頤)流の考え方(『二程遺書』巻十六および『近思録』巻二に載せる門人劉安節との問答に見える)から大きな影響を受けた山崎闇斎派の道学者のように文雅を否定するような極端な見解が一方で存在したことを考慮すれば、一般論を述べたものに過ぎぬとして軽視してよいというものでもなかろう。そして、その評価基準は、他の儒者に対しても同様であったことが後に挙げる頼春水に贈った詩およびその自注からもよく窺えるのである。
※那波魯堂については、古くは猪口繁太郎『四国正学魯堂先生』(大正5年刊)があり、年譜が附されているが、それを基にして竹治貞夫『近世阿波漢学史の研究』(風間書房、平成元年)の「第三章 那波魯堂」により詳細な年譜が作成されている。
皆川淇園(享保19年[1734]~文化4年[1807])
『日本詩選』の作者姓名に「皆川愿 字は伯恭。淇園と号す。帷を京師に下す」とあり、『平安風雅』『春荘賞韻』にも見える。東陽より22歳上。東陽が在京中に贈った詩は見あたらないが、『詩鈔』巻四に七律「答へて皆川筇斎に謝す」詩があり、次のように詠じている。
藝林能事講經餘 藝林の能事 講経の餘
詩巻披來錦不如 詩巻披き来れば錦も如かず
海内大名眞泰斗 海内の大名は真に泰斗
人間至樂是琴書 人間の至楽は是れ琴書
雁池明月陪飛葢 雁池の明月 飛蓋に陪し
竹苑清風厠曵裾 竹苑の清風 曳裾に厠ふ
野性自甘邱壑裡 野性自ら甘んず邱壑の裡
好將山長老村居 好し山長を将て村居に老いん
◯藝林 藝苑。◯能事 長じた才能。◯詩巻 詩集。寛政4年(1792)に『淇園詩集』が刊行されている。◯錦不如 杜甫の五律「韋韶州の寄せらるるに酬ゆ」に「新詩錦も如かず」と。◯泰斗 泰山北斗の略。人々から仰ぎ尊ばれる学問の大家。『新唐書』韓愈伝賛に「学者之を仰ぐこと泰山北斗の如しと云ふ」と。◯雁池 前漢の梁孝王が築いた兎園にあった池の名。貴族の庭園の池をいう。◯飛蓋 蓋い付きの車を馳せること。三国魏の曹植「公讌詩」(『文選』巻二十)に「清夜西園に遊び、飛蓋相追随す」と。◯曵裾 前漢・鄒陽の「書を呉王に上る」(『文選』39)に「何れの王の門にか長裾を曵く可からざらんや」と。『蒙求』巻上の標題に「鄒陽長裾」がある。◯邱壑 丘と谷。転じて田舎。◯山長 書院や私塾の長。『薈瓉録』巻下に「書院ハ私ノ学院ナリ。宋ノ世ヨリシテ処処ニ盛ナリ(中略)書院ヲ主ドル先生ヲ山長ト称ス。(中略)書院ハ多ク山ニ在ルヲ以テ山長ノ号ヲ呼ビナラワシタルナリ」と。
頸聯からは、東陽が淇園に陪して堂上家で催される詩酒の会に参じたように窺えるが、具体的にそのことを示す詩は見あたらない。尾聯は、都会人の洗練された趣味嗜好を持ち合わせておらず、村の校長先生のまま年老いてもかまいません、という意。これまで見てきたように、詩友の太田玩鷗や巌垣龍渓らにこぼした愚口や本音を淇園には吐いていない。この一首だけからは判断しにくいものの、想像するに、東陽の心境に変化があったと考えるより、淇園に対してはそういうことをあからさまに言いたくない、そういう心理的距離が存在したのではなかろうか。
なお、『文集』巻八に「淇園の墨竹に題す」という一文があり、「往に在京の時、淇園先生の画竹を見」たが、当初はたんに形を似せた画工のそれと変わり映えしないではないかと思っていたところ、今度その幅をよくよく鑑賞したら、「筆精飛動、天趣飄逸」で、「真に墨君三昧を得て、毫髪も遺恨無し」だと得心したという。これは文化4年以後すなわち淇園没後の作らしいが、ここでは淇園を先生と称している。淇園が山水蘭竹の画を得意としていたことについては、東陽より一世代後の田能村竹田『山中人饒舌』巻下にもこれを指摘する。
ちなみに、先に大典の項で、『訳準笑話』巻末の「初学作文須用書冊」に大典の著述が挙げられていることを指摘したが、同様に淇園のそれが多く取り上げられている。『虚字解』正続4冊(天明3年刊)、『虚字詳解』15冊(文化10年刊)、『実字解』6冊(寛政3年刊)、『助字詳解』3冊(文化10年刊)、『左伝助字法』3冊(明和6年刊)、『史記助字法』2冊(宝暦10年刊)が⑴「文語を講解する者」に、『医案類語』5冊(安永3年刊)、『訳文要訣』1冊(天明4年刊)、『淇園文訣』1冊(天明7年刊)が⑶「文を作る法程を示す[者]」に、『習文録』6冊(寛政10年刊)、『習文録甲乙判』4冊(寛政10年刊)が⑷「文章を肄習するに便なる者」に挙げられている。
ところで、東陽は京都在住の儒者の多くに対しては、学問的にあまり高い評価を下していないようで、頼春水や菅茶山と親交の深い備中鴨方の西山拙斎(享保20年[1735]~寛政10年[1798])に寄せた七律「備中の西子雅に寄す」詩(『詩鈔』巻四)に「洛儒多くは是れ麒麟楦」と切り捨てている。〈麒麟楦〉は、麒麟の扮装をしたロバの意で、見かけ倒し。初唐の楊炯が朝廷の高官を評した語(『太平広記』巻二六五、軽薄一に引く『朝野僉載』、『唐才子伝』巻一、楊炯の条)。そうした中で、彼が注目していたのは、当時大坂に集まっていた頼春水ら壮年の朱子学者たちであった。
※皆川淇園について、古くは天囚西村時彦『学界乃偉人』(梁江堂書店、明治44年、 再版)があるほか、森銑三「柴野栗山」(『森銑三著作集』第八巻、人物篇八所収)も参照。また高橋博巳氏の前掲書および同氏の編集・解説にかかる『近世儒家文集集成第九巻 淇園文集』(ぺりかん社、昭和61年)も参照。
西山拙斎には、朝森要『関西の孔子 西山拙斎』(山陽新聞社、平成10年)がある。
頼春水(延享3年[1746]~文化13年[1816])
『日本詩選』の作者姓名に「頼惟寛 字は千秋。安藝竹原の人。俗称弥太郎。少にして敏警、今、浪華に授徒す。二弟有り、並に有才を以て称せらる」と見える。春水は、明和3年(1766)2月から天明元年(1781)12月、広島藩儒となって帰国するまで大坂に居住した。その間のことは「在津紀事」にまとめられている。東陽より10歳上。『詩鈔』巻四にある七律「頼千秋に贈る」詩は、東陽が京都に遊学してまだ間もない頃、大坂に下ったおりの作であろう。
吾道修來席上珍 吾が道修め来る席上の珍
舊氈冷落守清貧 旧氈冷落 清貧を守る
彈冠行會逢明主 冠を弾いて行々会らず明主に逢はん
奉檄應須慰老親 檄を奉じて応に須らく老親を慰むべし
安效鄙儒勞訓詁 安んぞ鄙儒に效ひて訓詁に労せんや
將觀大國展經綸 将に大国を観て経綸を展べんとす
文章學術如君者 文章学術 君の如き者は
千百人中一二人 千百人中に一二人
◯吾道 儒学。前掲「舌耕歌」の語釈参照。◯席上珍 座席上の珍宝。儒者の才学を喩えていう。『礼記』儒行篇に「儒に席上の珍、以て聘を待ち、夙夜強学して問を待ち、忠信を懐きて挙げらるるを待ち、力行し以て取るを待つ者有り」と。◯旧氈 「舌耕歌」に見える「旧青氈」と同義。故郷の家を指す。◯弾冠 出仕の準備をする。前漢の貢禹は親友の王吉が官に就いたとき、自分も仕官しようと冠の塵を払ってお召しを待ったという(『漢書』王吉伝)。◯奉檄 親のために仕官すること。後漢の毛義は家貧しく母が老いていたため、召し抱えの通知書(檄)を受けて喜色を満面にあらわしたという。『蒙求』巻上の標題に「毛義奉檄」と。◯鄙儒 見識のない役立たずの儒者。◯訓詁 古典の注釈。◯経綸 天下国家を治める大計。
この詩には「世儒の理学を以て自任して頭巾の気習無く、文藻の尤も観る可き者は、浪速の中井処叔・肥後の藪子厚・阿波の柴彦輔・肥前の古賀淳風等数人而已。皆千秋の友とする所なり」という自注が附されている。寛政の学界を領導することになる、朱子学派の面々について、早くからその存在に着目し動向に注意していたのである。中井処叔は、懐徳堂の中井履軒(享保7年[1722]~文化14年[1817])。伊賀上野での作に七律「中井履軒に贈る」(『詩鈔』巻五)がある。
なお、これは餘談になるが、『詩鈔』巻五に七律「瀬子成に寄す」詩があり、次のように詠じられている。
才鋒到處座中驚 才鋒到る処 座中驚く
大器還看便夙成 大器還って看る便ち夙成するを
禮樂觀光遊上國 礼楽観光 上国に遊び
文章修業泝西京 文章修業 西京に泝る
烟花易溺紅裙醉 烟花溺れ易し紅裙の酔
風月能尋白社盟 風月能く尋ねん白社の盟
努力雄飛丈夫志 努力して雄飛せよ丈夫の志
青袍未必誤儒生 青袍未だ必ずしも儒生を誤らず
◯大器 『老子』第四十一章の「大器晩成」をもじった表現。◯夙成 早熟。◯観光 他国のよいところをよく見る。『易経』観卦に「国の光を観る、用て王に賓するに利あり」から出た語。◯上国 周代、王都に近い国をいう(『左氏伝』昭公27年)。上方。ここでは大坂を指していう。◯泝 大坂から京に向かうのに淀川をさかのぼる。◯烟花 春霞と花樹。元明以降、煙花市とか煙花巷といえば、花街。ここもその意を含む。◯紅裙 紅色のもすそ。妓女をいう。盛唐・万楚の七律「五日、妓を観る」(『唐詩選』巻五)に「紅裙は妬殺す石榴の色」と。◯白社盟 晋宋の慧遠が開いた白蓮社のような詩社の集い。◯青袍云々 『三体詩』巻二に中唐・盧綸の作として載せる七律「呉中に厳士元に別る」詩に「東道若し相識の問ふに逢はば、青袍今已に儒生を誤る」と。なお、この詩は劉長卿の作とみなされている。唐代、官位の等級によって官服の色が決まっており、〈青袍〉はランクが一番下だが、初めて任官される場合いきなり高等官になることはあり得ないから、初任の服をいう。〈儒生〉は、学問をする人。もとの詩は、今も低い官職でしかなく、学問が我が身を誤らせたという意だが、東陽はそれを翻用してとにかく出仕しようと思えば、学問に励むことだ、というのであろう。ちなみに、七律「芥子泉の聘に応じて越に適くを聞く、為に此の寄有り」と題する作(『詩鈔』巻四)にも「大器由来晩成を待つ、青袍終に儒生を誤らず」と。なお、思堂と号した芥子泉(延享元年[1744]~文化4年[1807])は、芥川丹邱(宝永7年[1710]~天明5年[1785])の長子で、天明8年に越前鯖江藩儒となった。
京に遊学する若者に、花街で綺麗どころにうつつを抜かさず、さあしっかり勉強しなさいと激励した内容であるが、この瀬子成なる人物がわからない。あるいは想像するに〈瀬〉は〈頼〉字の筆写の誤りで、頼子成すなわち春水の長子、頼山陽に寄せた詩ではなかろうか。とすれば、山陽が文化8年(1811)備後神辺の菅茶山のもとを去って、大坂を経て入京した際に、本詩を寄せたと考えられる。時に山陽33歳。いささか薹が立っているきらいがしないでもないが、首聯に称えるような才能の持ち主がそうざらにいるとは考えにくい。もっとも、詩の配列から見ると、文化14年(1817)東陽60歳ごろの作になり、これでは山陽に寄せた詩だと言いにくくなるけれども、ただ後の葛子琴の項でも言及するように、『詩鈔』の配列にやや問題ありとすれば、あながちむげに否定できない気もするが、如何であろうか。
※「在津紀事」については、前掲、新古典文学大系本『在津紀事』参照。ただし、そこに東陽の名は見えない。なお、春水の年譜に頼山陽記念文化財団『〝詩豪〟頼春水~その生涯と書~』(平成21年)附載の「頼春水略年譜」がある。
古賀精里(寛延3年[1750]~文化14年[1817])
名は樸、字は淳風。精里はその号。肥前佐賀の人。安永3年(1774)から8年(1779)まで、京大坂に遊学し、片山北海(名は猷、字は孝秩。享保8年[1723]~寛政2年[1790])を中心とする浪華混沌社の面々と交遊した。寛政三博士の一人。東陽より6歳上。次に掲げる七律「夏夕小倉泖にて古淳風に和す」(『詩鈔』巻四)は、安永8年の作であろう。
晩凉湖色爽秋同 晩涼の湖色 爽秋同じ
銀漢涵光玉宇空 銀漢光を涵して玉宇空し
蘋末風薰波瀲灔 蘋末風薫り波瀲灔
荷間露滴月玲瓏 荷間露滴り月玲瓏
乘槎客欲通天上 槎に乗りて客は天上に通ぜんと欲し
倚檻人疑坐鏡中 檻に倚りて人は鏡中に坐すかと疑ふ
萍水相逢須盡興 萍水相逢ふ須らく興を尽くすべし
明年此會各西東 明年此の会 各々西東
◯小倉泖 巨椋池。〈泖〉は、水面の穏やかな湖沼の称。七絶に「小倉湖の豊公堤、月に歩む」、「小倉泖にて蓮を観る」詩(『詩鈔』巻七)がある。ちなみに、六如『葛原詩話』巻二に「泖」の条あり、「我ヵ国伏見ノ巨椋湖、嵯峨ノ広沢・大沢ノ類、ミナ泖ト称スベシ」云々と。◯銀漢 天の河。◯玉宇 ここは大空をいうか。◯蘋末 浮草の葉先。◯瀲灔 さざなみの立つさま。畳韻語。◯蘋 デンジソウ。◯荷 ハス。◯玲瓏 清らかなさま。双声語。◯乗槎客 小舟に乗った遊客。前漢の張騫が槎に乗って黄河の源流を遡り、天の河に達したという故事をふまえる(六朝梁・宗懍『荊楚歳時記』七月の条)。◯倚檻 (建物の)欄干によりかかる。◯萍水相逢 偶然出会うこと。初唐・王勃「滕王閣の序」(『古文真宝』後集)に「萍水相逢ふ、尽く是れ他鄕の客」と。◯明年此会 杜甫の七律「九日藍田崔氏の荘」(『唐詩選』巻五)に「明年此の会知んぬ誰か健なる」と。◯各西東 杜甫の五律「孟雲卿に酬ゆ」に「明朝事務に牽かれ、涙を揮って各々西東」と。
この詩が作られたときには、おそらく国元に帰ることが決まっていたのであろう。その帰国に際しては、「古賀淳風の佐賀に帰るを送る」(『詩鈔』巻七)と題する作がある。
重禽無期涙濕襟 重会 期無く 涙 襟を湿ほす
片帆帰去海雲深 片帆帰り去りて海雲深し
神交別後相思夢 神交別後 相思の夢
天末長懸明月心 天末長く懸る明月の心
*禽は、會の誤写であろう。
◯重会 再会。◯片帆 一艘の船。◯神交 意気投合して忘形の交わりを結ぶ。◯天末 天の果て。極めて遠いところ。杜甫の五律「天末にて李白を憶ふ」詩に「凉風天末に起こり、君子|意如〈いかん〉何」と。◯明月心 盛唐・王昌齢の七絶「芙蓉楼にて辛漸を送る」詩(『唐詩選』巻七)に「寂寂たる寒江明月の心」と。
※古賀精里については、一海知義・池澤一郎『江戸漢詩選第二巻「儒者」』(岩波書店、平成8年)の解説参照。
藪孤山(享保20年[1735]~享和2年[1802])
『日本詩選続編』の作者姓名に「藪愨 字は士厚。茂二郎と称す。肥後に仕へ、国学祭酒」と。孤山はその号。古賀精里は、その門人。東陽より22歳上。安永四年に京大坂に来遊した。東陽とは終生面識はなかったようだが、六律「肥後の藪祭酒に贈る」詩(『詩鈔』巻三)がある。
斯文夙奉庭訓 斯文夙に庭訓を奉じ
終歳窺園未曽 終歳園を窺ふこと未だ曾てせず
君子唯須一德 君子は唯だ一徳を須ふ
聖人不必多能 聖人は必ずしも多能ならず
教明庠序才育 教へは庠序に明らかにして才をば育て
化洽邦家道弘 化は邦家に洽く道をば弘む
功業儒林軌範 功業は儒林の軌範
臨風景慕何勝 風を臨んで景慕何ぞ勝へん
◯斯文 この学問の意(『論語』子罕篇)。儒学をいう。◯庭訓 家庭教育。孔子が庭を小走りで通り過ぎようとした息子の鯉を呼びとめて詩や礼を学ぶ大切さを説いた故事(『論語』季氏篇)による。孤山が父の藪慎庵(元禄元年[1688]~延享元年[1744])から教えを受けたことをいう。慎庵は徂徠に従学したが、後に朱子学に転じた。◯窺園 『書言故事』巻十、地理類に「不窺園」の語を挙げ、「漢の董仲舒帷を下し、発憤して書を読み、三年園を窺はず」と。◯一徳 『論語』里仁篇に「吾が道は一以て之を貫く」と。◯多能 『論語』子罕篇に「吾れ少くして賤し。故に鄙事に多能なり。君子、多ならんや、多ならざるなり」と。◯庠序 藩校。熊本藩の時習館を指す。◯邦家 諸侯の国。熊本藩をいう。◯道弘 弘道の意。押韻のため倒置する。『論語』衛霊公篇に「人能く道を弘む。道、人を弘むるに非ず」と。
また七絶「肥後の藪文学に贈る」(『詩鈔』巻七)には、次のように云う。
關西夫子德華隆 関西の夫子 徳華隆し
賦筆凌雲氣象雄 賦筆 雲を凌ぎ氣象雄なり
教育英才天下樂 英才を教育するは天下の楽しみ
滿門桃李競春風 門に満てる桃李 春風を競ふ
◯関西夫子 後漢の楊震は「関西の孔子」と称せられた(『後漢書』楊震伝)。『蒙求』巻上の標題に「楊震関西」と。◯凌雲 雲の上まで登る。◯教育英才 『孟子』尽心上に「天下の英才を得て之を教育するは、三の楽しみなり」と。◯満門桃李 俊英の士が門下に集まること。ちなみに、寛政11年(1799)、古義堂の三代目伊藤東所が70の寿を迎えたときにこれを祝した「伊藤東所の七袠の寿旦を祝す」詩(『詩鈔』巻五)にも「景仰す春風桃李の門、英才教育典刑存す」と、ここと同様の表現。
さらにもう一首、七律に「藪子厚に酬ゆ」詩(『詩鈔』巻四)がある。これは、伊賀上野での作。
關西夫子實超群 関西の夫子 実に超群
京洛諸儒孰若君 京洛の諸儒 君に孰若ぞ
庠序育人功刻石 庠序人を育て 功は石に刻む
英雄説劍氣陵雲 英雄剣を説き 気は雲を陵ぐ
蹇驢爭得行千里 蹇驢争か千里を行くを得ん
弊帚何曾直一文 弊帚何ぞ曾て一文に直せん
休問皐比鄕曲學 問ふを休めよ皐比郷曲の学
虚名謬自大方聞 虚名 謬りて自ら大方に聞こゆ
◯孰若君 貴殿の方がずっとすぐれている。「孰か君に若かん」の意。◯蹇驢 びっこのロバ。愚鈍の喩え。◯弊帚 破れ箒。三国魏・曹丕「『典論』論文」(『文選』巻五十二)に「里語に曰く、家に弊帚有り、之を千金に享く」と。◯郷曲 辺鄙な田舎。◯大方 見識ある人。
前半四句は孤山を称え、後半四句は自ら謙遜していうが、東陽の名はある程度知られていたことが窺える。
※藪孤山については、今田哲夫『宝暦の詩人藪孤山 詩とその心』(白鳳社、平成3年)がある。
柴野栗山(享保19年[1734]~文化4年[1807])
『平安風雅』に「柴邦彦 栗山と号す。阿州文学、柴野氏」と。讃岐牟礼の人。東陽より21歳上。七絶「柴博士に寄す」(『詩鈔』巻八)がある。これは在京時の作ではないが、東陽が天明八年の大火で京都での生活基盤を失い、一時帰郷した後、江戸に赴こうとしていた時期に、「貴殿は今やはるか青雲の高みに上ってしまわれたが、この素浪人の私を気にかけて下さるでしょうか」という一種の自己宣伝を兼ねた挨拶のつもりで作った詩であろう。そこには就職口斡旋への淡い期待感を滲ませている。時に栗山は、松平定信の推輓を得て昌平黌教授に任じられていた。寛政三博士の一人。
浪迹蹉跎歳月徂 浪迹蹉跎し歳月徂く
生涯只合老江湖 生涯只だ合に江湖に老ゆべし
君今迥在青雲上 君今迥かに青雲の上に在り
能念烟波一釣徒 能く念はんや烟波の一釣徒を
◯浪迹 あちらこちら漫遊すること。◯蹉跎 ぐずぐずして時機を失すること。畳韻語。前に挙げた張九齢詩に「宿昔蹉跎す青雲の志」と。◯歳月徂 杜甫の七古「今夕行」に「今夕何の夕べぞ歳云に徂く」と。◯老江湖 宮仕えせずに在野のままで年老いること。南宋・陸游の五古「嘆を書す」(『劍南詩稿』巻七)に「世方に珉玉を乱す、吾れ其れ江湖に老いん」と。◯烟波一釣徒 『書言故事』巻四、漁釣類に「釣徒」の語を挙げ、「張志和、烟波の釣徒と号す。釣を江湖に垂れて餌を設けず。志は魚に在らず」と。中唐の張志和は『新唐書』隠逸伝に立伝。
なお、ついでに記せば、『訳準笑話』巻末の⑵「名物称謂を訳解する者」に柴栗山著『雑字類編』2冊(天明六年刊)を挙げている。
※柴野栗山については、西村天囚、前掲書参照。
この他、『詩鈔』には、播州赤穂の儒者赤松滄洲(享保6年[1721]~享和元年[1801])の名も見える。巻六の六言絶句「東山芙蓉楼の宴会、洛下の諸賢畢く集ふ。赤松滄洲適に播自り至る。次韻して和して答ふ」がそれだが、これは省略する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
