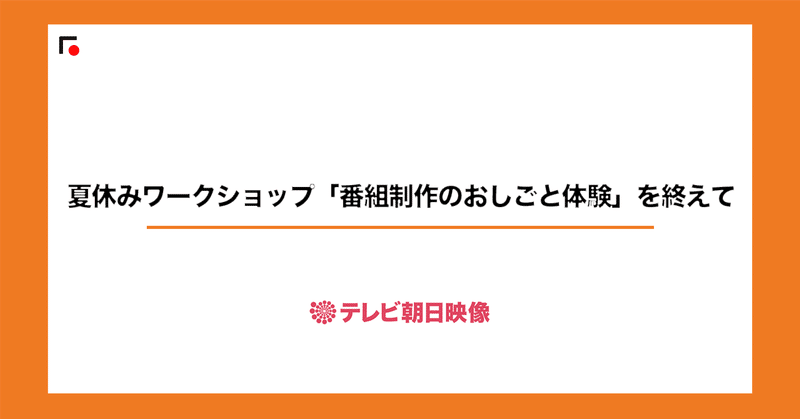
夏休みワークショップ「番組制作のおしごと体験」を終えて
おはようございます!
テレビ朝日映像という制作会社で働いています、鈴木拓郎〈スズキタクロウ〉です。
先日「収録がある日はスタッフは基本全身真っ黒コーデ」ということを学びました。万が一見切れても目立たないように、だそうです。
タンスに黒Tが1枚もなく、収録前日に慌ててまとめ買いした入社2年目です。
さて、初回は入社経緯、2回目はおすすめの映像作品を紹介してきました当note。今回は、先日当社にて行われ、私も企画運営に携わった小学生向けイベント「夏休みワークショップ」について書きたいと思います。
〈夏休みワークショップ「番組制作のおしごと体験」〉
「番組制作のおしごと体験」と題された今回のワークショップは、テレビ朝日映像初の試みとして2日間にわたって開催されました。

映像業界に興味を持つ小学生のみなさんに、イベントを通して楽しく、わかりやすく、テレビ制作の世界を体験して知ってもらうこと。番組を作ることや映像を届けることだけでなく、こういった取り組みも私たちにとっては重要な仕事の一つなのです。
そんな今回のワークショップの目玉は「バーチャルスタジオ体験」

テレビ朝日映像は六本木一丁目の本社地下1階にバーチャルスタジオを所有しているのですが、そのスタジオでカメラマン、音声、フロアディレクター、スイッチャー、キャスターの仕事を順番に教わりながら、1分ほどのニュース番組作りを体験してみよう!という何とも贅沢な企画です。
教えてくれるのは全員最前線のプロ。触るのは全て本物の機材。緊張感も楽しさも全部自分のものにできる。手前味噌ですが、こんな体験はそうできるものではありません。
〈ARK Streaming Studioならではの体験〉
そもそも皆さんは「バーチャルスタジオ」という言葉を聞いたことがありますか?

テレビ朝日映像が2021年に社内に開設した撮影スタジオ
最新システム「VRCAM-NX」を搭載。バーチャルCGと被写体を組み合わせた最新鋭の撮影が可能
背景CGは8種類。撮影カメラは4台。ニュース番組、バラエティ、音楽番組、会社説明会など様々な用途に対応
映像はリアルタイム配信が可能
このような、壁一面が緑に覆われた空間なら見たことがある人は多いのではないでしょうか。非接触が求められるコロナ以降特に見かけるようになった「グリーンバック」は、例えばニュース番組のお天気コーナーなどCG合成が必要な時によく利用されるものです。
当社のバーチャルスタジオは、このグリーンバックを部屋全体に敷き詰め、最新の技術と沢山の機材を駆使してあらゆる空間をリアルタイムで容易に再現することができる、都内でも屈指の施設です。

ボタン一つで小さな緑色の空間があっという間に広々としたニューススタジオに。自分の名前や言葉がすぐテロップになり、一挙手一投足がそのまま番組になっていくという体験。
普段見ているテレビの世界そのものに簡単に入っていけるこのスピード感や臨場感は、テレビ朝日映像ならでは、このバーチャルスタジオならではの楽しさと言えるのかもしれません。
自作のニュースを緊張しながら読んだり、カメラを一生懸命動かしたり、大きな声でカウントをしたり、この時間と空間を精一杯楽しもうとする子どもたちを見て、運営の身でありながら、つい何度も「羨ましいな…」と思ってしまいました。
他にも、カメラマンによるトークショー、ADによるテレビ業界講習、インタビュー体験、ドローン体験、質問コーナーなど、内容はこれでもかと盛りだくさん。
「飽きさせないように」と工夫を凝らした甲斐があって、参加してくれた約20人の小学生は、楽しそうに何度も瞳をキ
ラキラ輝かせてくれていました。

〈私がワークショップにて学んだこと〉
さて私は今回、このワークショップにて
パワーポイントを用いた「テレビ朝日映像ってどんな会社?」説明
小学生へのインタビュー
スタジオでのフロアディレクターの先生
を担当しました。初めての連続、実に多くの学びがありました。
〈1.飽きさせない工夫は惜しまない〉
少し業界に興味があるとはいえ、小学生にとってこのイベントは、知らない場所で初めてのことを聞くという体験の連続です。
こちらが最大限楽しませようと尽力しなければ、すぐに飽きてしまう可能性とは常に隣り合わせ。そのため、この「飽きさせない」ということに、今回とても多くの時間と労力を注ぎました。
例えば、パワーポイント作成1つをとっても
最初にメリットと結論を提示する
音と動きは多めにつける
コールアンドレスポンスを取り入れる
1枚の文字数はなるべく少なく、イラストや写真を多用する
パッと考えてもこれだけの工夫ができます。子供たちの反応は良くも悪くもダイレクトに伝わってきますから、回を重ねるごとに反省して修正して試してひたすら馴染ませていく、の繰り返しです。
他にもインタビューなら、ポジティブかつ答えやすい質問をしてあげること、同じ質問はしないこと。スタジオ体験なら、なるべく実践の時間を多くとってたくさんのものに触らせてあげること。
考えれば考えただけ相手に良い時間を渡すことができます。最大限のホスピタリティを持って相手のことを考え抜くという経験は、人と人とのやりとりで築かれていくこの世界を渡っていくために必要なものだと思いました。
〈2.共通言語を常に意識する〉
これは「飽きさせない」にも繋がることですが、小学生は「フロアD」も「バミリ」もわからなくて当然だとちゃんと意識しなければいけません。
「テレビ朝日とテレビ朝日映像の違いは?」「フロアDってどういう仕事?」など、たくさんの知って欲しいこと。これらを、一つ一つ改めて噛み砕いて、平易な言葉に直して、どんな例えなら伝わるかを丁寧に考えていく作業はとても苦労しましたが、その分伝わったという実感があった時の喜びは大きいものでした。
共通言語で話す意識。今回小学生の前に立ったことで、大いに学ぶことができました。
〈3.教えることで学ぶことがある〉
「教える」という行為は意外と難しいものです。
やり方も手順も知っているはずなのに、いざ伝えようとすると本質を置いてけぼりにしたり、うまく順序立てられなかったりする。「知っている」だけではダメだと改めて学びました。
どういう場所で、どういう仕組みで、何のためにやっているのか。今回、他人への指導のために改めて学んだことが、自分の襟を正し、もっと仕事について自主的に理解しようとするきっかけになりました。
先生という立場は、まだ走り出したばかりの若手こそが積極的に経験するべきことなのかもしれません。教えるために学ぶ。この経験を若手のうちに積むことで、視野はどんどん広がっていくのではないかと思いました。

ワークショップの様子はこちらのYou Tube動画でもご覧下さいませ!
※私もチラッと登場します」
バーチャルスタジオ「ARK Streaming Studio」見学受付中!
https://ark.tv-asahipro.co.jp/
