
2020年 年間ベストアルバム50選
フジもスパソニも、行く予定だった単独公演のほとんども、延期or中止に追い込まれ、なんとも張り合いの無い1年になってしまいましたが、一方でそんな状況だからこそ(?)作られたような良盤にもたくさん出会え、それはそれで得難い体験だったのかもと思います。
以下、50位から順に選出しています。
50.Kllo - Maybe We Could
オーストラリアはメルボルンを中心に活動するエレクトロポップデュオの2nd。パーカッシヴなビートの上を跳ねるようにメランコリックなサウンドが流れていく。The XXと比較されることも多い彼らですがこちらはよりダンストラックに寄っている印象です。もう一歩踏み込んでオリジナリティを洗練させていけばより化ける可能性ありと思っています。

49.Oneohtrix Point Never - Magic Oneohtrix Point Never
鬼才OPNの2年ぶり新作。「架空のラジオ局が朝から夜中まで流したもの」というコンセプトに基づき、爽やかな朝からディープな夜に至る1日を描きながらも、時折異物感が交じるように素っ頓狂なノイズが挿入されたり、なんとも一筋縄ではいかない作品です。表面的にはポップな部分もありながらも、必ず聴いてて「違和感」を感じる部分が出てくると思います。そこがOPNの狙いなのでしょうが。

48.Sewerslvt - Draining Love Story
オーストラリアはアデレードで活動するプロデューサー、JVNKOによる1stアルバム(EPは今年だけで4枚くらい出してたはず)。ブレイクコアはあまり掘らないジャンルではありますが、たまたま手に取った今作は激しくもどこか自分の内面に向かっていくような鬱々とした、それでいて澄んだ空気感がたまらなく好みでした。よく会社の帰り道に聴いています。

47.King Krule - Man Alive!
ロンドンの天才、King Kruleことアーチー・マーシャルの4作目。前作同様、煙が充満したような不穏なダブはそのままに、誰とも関わることを拒否するようなザラついた音だけでなく、ほんの少し柔らかな表現も垣間見えるようになりました。内に篭もっていた熱が少しずつ外に漏れ出る最中のような作品です。

46.Everything Everything - Re-Animator
UKマンチェスターのエレクトロ・ポップバンド。2000年代半ばに雨後の筍のように出てきたダンス・パンクバンドが軒並み姿を消した後にひっそりと現れた彼等は、以来10年以上マイペースに活動を続け、FOALSとのツアー等も経た上で今作でも半歩エクスペリメンタル方面に足を踏み出したまま持ち前のポップセンスを腐らせることなく、洗練された作品を届けてくれました。

45.clipping. - Visions of Bodies Being Burned
サブ・ポップが擁するエクスペリメンタルヒップホップ集団による、昨年発表の「There Existed an Addiction to Blood」との姉妹作。暗闇の中でボソボソと呟くように紡がれるラップはその全てが陰鬱かつシリアスなもの。流す度に「お前はどうなんだ?」と問いかけられてるような重みを感じます。

44.Porridge Radio - Every Bad
UKブライトン出身のロックバンドによる2nd。vo.Dana Margolinの強烈なキャラがまず目を引くバンドですが、今作でも彼女の生々しくも力強い声にグッと引き寄せられます。引き合いに出されるのがヤー・ヤー・ヤーズのカレン・Oなのも納得のパワー。奇しくも今年そのものを表すかのようなタイトルですが、決して後ろ向きにならない力を感じる作品です。
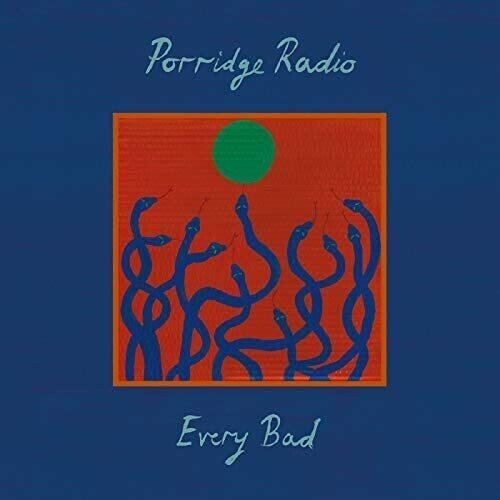
43.Sam Gendel -Satin Doll
LAを拠点に活動するサックス奏者による作品。ヒップホップやアンビエント、現代音楽までを縦断し、いわゆる「ジャズ」を想定して聴こうとすると面食らうほどの多様なアイデアに溢れ、ただユニークなだけでなくそれらを違和感なく錬金してしまえる彼の才能を堪能できる一品です。

42.downy - 第七作品集『無題』
(今まで彼等の作品に触れる機会がなく、あくまで今作だけを聴いた上での感想になりますが)想像以上にプログレッシブで、蛇のようにうねる縦横無尽の音に舌を巻く作品。最終曲「stand alone」は特に壮絶で、これがライブでどのように再現されるのか?というところも含めて今後も追っていきたいバンドの一つになりました。(過去作も聴きます、ちゃんと)

41.Autechre - SIGN / PLUS
「2つの作品を重ねると一つの音として完成する」というアイデア自体は過去に他のミュージシャンでもあくまで「実験的に」なされたことではありますが、オウテカがやると一周してむしろ普通のアイデアに見えるから不思議です。単体で聴いて「今作はイマイチでは?」と思った方は同時に再生して改めて聴いてみることをおすすめします。特に長尺の曲の計算されつくした構成はベテランならではの凄み。


40.Nicolas Jaar - Cenizas
別名義Against All Logicのポップかつファンクなアプローチとは一変し、こちらはひたすら虚無の暗黒へと突き進んでいくかのような作品。IDMやジャズの要素を消化しつつ、「非ダンスミュージックとしての電子音楽」としては極北のような一品です。
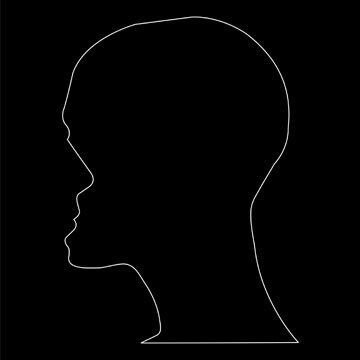
39.Liturgy - Origin Of The Alimonies
NY出身のブラックメタルバンドによる5th。狂乱と絶叫に彩られているにもかかわらずどこか静謐とした印象も携えた作品。他の方が仰っていたのですが映画のサウンドトラックのような感覚もあります。極めて異形ながらどこをとっても美しさを感じます。

38.Tame Impala - The Slow Rush
すっかりベテランかつ有名になったサイケデリック・ロックバンドの新作。1曲目からグッと引き込まれる、強制的に天国に連れて行かれるような音はさすがの一言。
本来なら今年フジロックでその勇姿を見れているはずだったのですが…。

37.Helena Deland - Someone New
カナダ・モントリオールのSSWの1st。鬱で、寂しげながら、優しく寄り添ってくれるようなベッドルームミュージック。しかしどことなくスモーキーで、時折「ひずみ」のようなものを見せる辺り、決して一本調子の作品ではありません。

36.William Basinski - Lamentations
実験音楽の大御所ウィリアム・バシンスキーの新作。全体的に「死」や「終末」といったイメージに彩られており、誰もいなくなった世界でゆるやかに自らも死に向かっていく時に流れているような音楽です。

35.Son Lux - Tomorrows Ⅰ
3部作となる作品の1発目。極めて前衛的なアプローチを施しておきながら「ポップである」ことから全くブレない作品。一応は電子音楽に分類されながらも、むしろ太鼓の音の方が耳に残りやすい。3部作が出揃ってから改めて通して聴いてみたい作品です。(なお、今作を契機に過去作も聴いてみましたがどれも良かったです。特に「Lanterns」がすごかった)

34.Sufjan Stevens - The Ascension
スフィアン・スティーブンスは作品によって「フォーク」「チェンバー・ポップ」「電子音楽」と3つの作風を使い分けますが、そのうちの電子音楽路線の最新作。聞き手を鼓舞するようなものはなく、アメリカの混沌の渦の中にいながらただ淡々と諦念を携えながら絶望を紡いでいく作品。代表作にはなり得ない作品かもしれませんが、この時代に必要なのはこういう音なのかもしれません。「America」は必聴。

33.Moses Boyd - Dark Matter
サウス・ロンドンを拠点に活動するジャズドラマーによるソロ1st。生演奏+エレクトロニクスを主体にヒップホップやファンク、アフロビート等の混合スタイル。アブストラクトな楽曲やミニマルな構成の楽曲も含めて収録曲は多様性に富んでいながら、ガチガチに構築したのではなくいつの間にかバリエーションが生まれたかのような自然体の作品だと思います。

32.Caribou - Suddenly
旧名義(Manitoba)の頃から含めるともう20年選手にもなるCaribouの新作。いかにも地味そうなアルバムジャケットに反して、ドリーミーでありながらブラックミュージックにも接近したグルーヴ感・躍動感に溢れた楽曲が多く、曲展開もアッパーでいながらメランコリックとなんとも派手な一枚。再聴性にも優れ、何度聴いても飽きの来ない作品です。

31.Imperial Triumphant - Alphaville
NY出身の覆面・デスメタルバンドの新作。カオティックかつアヴァンなメタルサウンドをフリージャズ的に展開したらどうなるか?というのを計算なのか即興なのか分からないアプローチで突き詰めた一品。どこまで行っても混沌、混沌、また混沌。

30.SLIFT - Ummon
フォロワー経由で知った、フランスはトゥルーズを拠点に活動しているサイケデリック・ロックバンド。ファズを全面に押し出しつつ、タイトなリズムが絡んでスペイシーなサウンドに仕上げており、そこにややマッチョで野性的なボーカルが入ってくる構成がなんとも中毒性が高い。「迷ったらこれを聴く」くらいには再生数の多かった作品です。

29.Fontaines D.C. - A Hero's Death
アイルランドはダブリン出身のポスト・パンクバンドの2nd。前作同様、エモーショナルな部分を抑制し、いつ爆発するか分からないような危うい緊張感が全編に漂っています。しかし1stのような粗削りさはなく、そういったギリギリの緊張感をむしろコントロール下に置くことに成功したような巧さも感じ、わずか1年でバンドとして飛躍的な成長を遂げているように思います。コロナが落ち着いたらぜひ来日してほしいバンドの一つです。
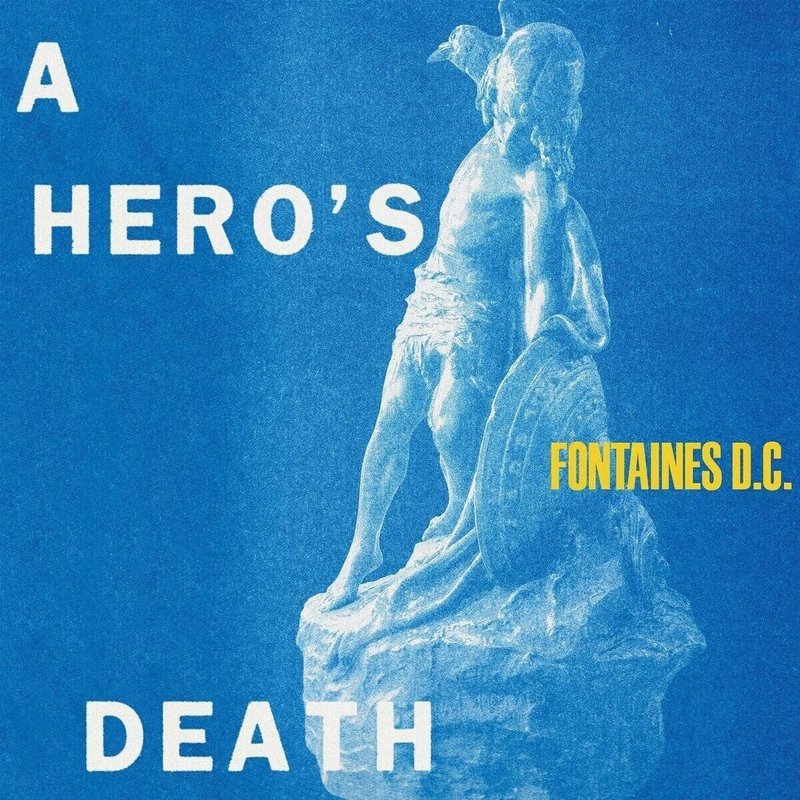
28.Fleet Foxes - Shore
シアトルのインディーフォークバンドの4th……ですが今作はフロントマン、ロビン・ペックノルドの実質ソロワーク。米国のルーツ・ミュージックをポップに落とし込む作風はそのままに、良い意味で「重さ」がなく、このバンドとしては特異な程風通しの良い爽やかな楽曲群は良い清涼剤となりました。

27.Perfume Genius - Set My Heart on Fire Immediately
元々はローファイ・ポップの枠組みでデビューした彼が、10年を経てここまで生々しい感情を吐露する作品を作り上げるとは思っていませんでした。彼の苦悩がそのまま作品に昇華されたことで5作目にして一つの完成形を作り上げたのだと思います。泥臭く、感傷的で、ノイジーで、アンビエントで、生の感情に彩られた渾身の1作です。

26.The Avalanches - We Will Always Love You
極端な寡作家だったこのアーティストが、わずか(?)4年で次作をドロップしてきたのは予想外でした。とにかくネタに事欠かないサンプリング・コラージュのセンスはそのままに、「ピークタイムにかかるような曲ばかりで構成した」ようなひたすら豪華な作品。やや長尺すぎるきらいもありますが、とても愛に溢れたポップアルバムだと思います。
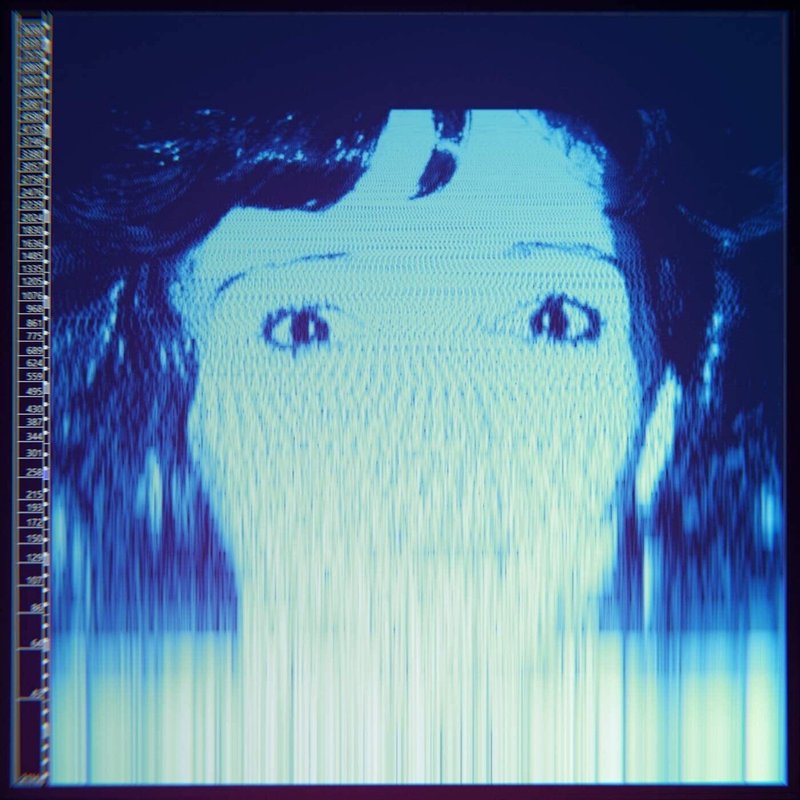
25.Kate NV - Room For The Moon
ロシア出身のKate Shilonosovaによるソロ・プロジェクト。制作には日本人アーティストの協力もあり、どことなく日本のポップスを思わせるアレンジが施された和露折衷(?)ミュージック。洗練されたアンビエント、ミニマルがどこか懐かしくもあるポップスと違和感なく融合された不思議な雰囲気の作品です。
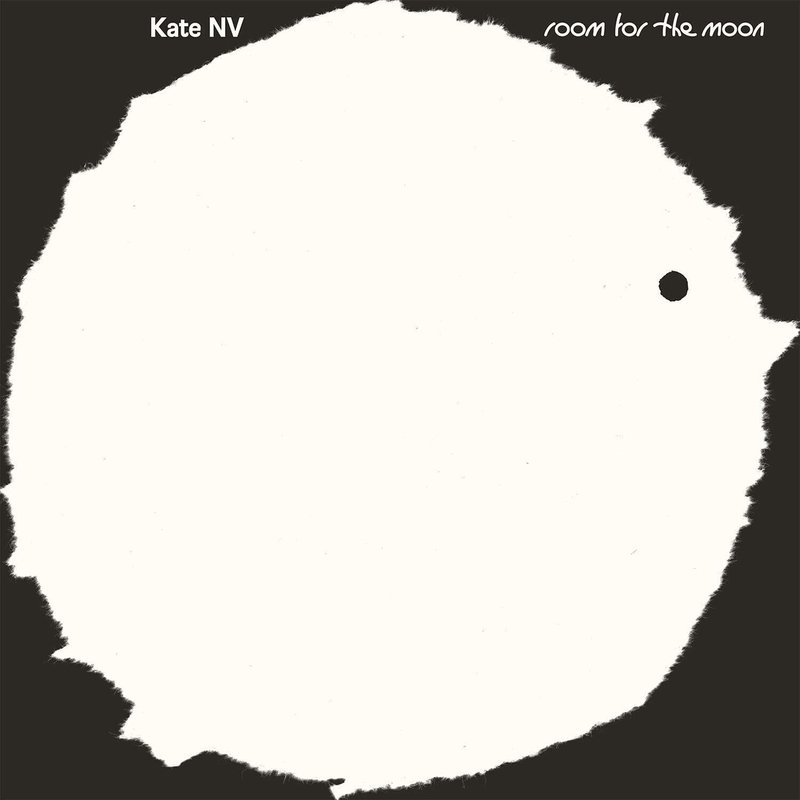
24.Jessie Ware - What's Your Pleasure?
「80年代風」という言葉がついた作品にはやや抵抗感が出るようになりました。80年代リバイバルもやりすぎてちょっと陳腐では?と思うような作品が多すぎたからなんですが、この作品も80年代風と聞いてやや警戒して臨んだところ、確かにディスコチックではあるもののサウンド面はむしろクールそのもの。享楽的な80年代の空気よりも、シリアスな現代の空気がそのまま反映された、懐古趣味と真逆の作品です。

23.Kaatayra - Toda História pela Frente
ブラジル出身の「1人」ブラックメタルバンドの新作。ドラマティックなブラックメタルとアンビエントの融合……までならともかくこのバンドはそこにブラジリアンフォークまで絡んでくるのでなんとも独特な作風ながら、叙情性たっぷりでスッと耳に馴染みやすいのがまた良いです。色んなバンドがあるものだ…。

22.青葉市子 - アダンの風
7thアルバム。沖縄の島々で着想し、「架空の南の島のお話、その映画のサウンドトラック」というコンセプトで作られた作品。コンセプトに合わせてか、空間の広がりを意識したような楽曲が多く、映像がなくても目の前に青く淡い色彩が広がってくるような、神秘的で彩り豊かな音楽です。8曲目「Sagu Palm's Song」が特にお気に入り。

21.Moses Sumney - græ
アルバムタイトルの読み方は「グレー」。本人曰く「白でもなく、黒でもないもの」という存在に東洋の陰陽の概念を絡めたもの。社会的な抑圧、例えば男性性かくあるべしといったものが本当に正しいのか?「こうでなければならない」というものは本当に存在するのか?という問いかけ。ソウル・ゴスペルを基盤にしつつも一つのジャンルにこだわることなく、全てがシームレスに繋がっていく今作は彼のメッセージをそのまま体現した作品です。ダブルアルバムながらトータル60分ちょっとと、意外とサラリと聴けるところも好きです。
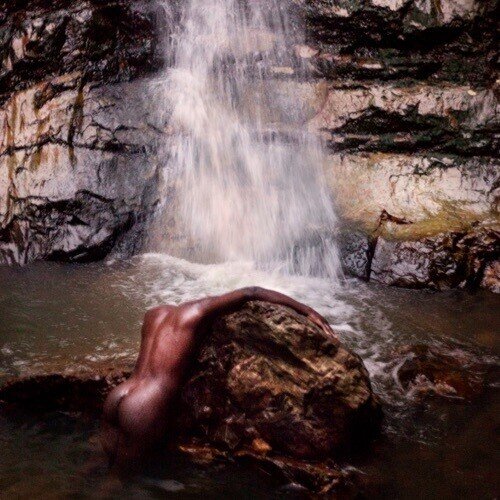
20.Róisín Murphy - Róisín Machine
Matthew Herbertとのコラボでも知られるアイルランド出身のロイシーン・マーフィーの新作は、25年間のキャリアの中でも最高傑作では?と思うほど、始まりから終わりまで一切ダレることなく延々とピークタイムが続くかのような充実作。最高のディスコ・ファンクです。

19.Phoebe Bridgers - Punisher
すっかり人気者になったLAの女性SSWの2nd。一見大人しく幻想的な曲が多いのですが、ラストの「I Know The End」の力強い展開に思わず唸りました。ゆらゆらと揺蕩うようでいながら最後にしっかり地に足のつけた音が出てくることで作品全体に一本筋が通ったように思います。この人も本当はThe Nationalの来日公演に帯同して見れるはずだったんですけどね……

18.Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters
各所での評価も軒並み高いフィオナ・アップルの8年ぶり5th。1曲目を聴いた時点で「あっ、これはヤバイな」というのが分かる、紛れもなくキャリアハイを達成した作品。ある種の狂気すら感じる楽曲群は、人によっては恐怖すら感じるものかもしれません(若干ホラーチックに感じなくもない)。でも人の評価がどうあれこの人は我が道を行くんだろうなぁという感じはしてます。自由だ。

17.Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi
フィンランドのブラックメタルバンドの5th。サイケデリック/クラウトロック/シューゲイザー/アンビエント/ドローンといった他ジャンルを越境しつつそれらを洪水のように容赦なく叩き込む手法に圧倒される一枚。特に最終曲「Taivaan portti」が珠玉で、ドロドロとした混沌を叩きつけたまま駆け抜けていきます。ただこういう他ジャンルを渡り歩くタイプのバンドは結構評価分かれそうだな~とも思っていて、純粋なメタラーからのレビューも聞いてみたい作品です。

16.Ghostemane - ANTI-ICON
LAを拠点に活動するEric Whitneyによるソロ。インダストリアル×トラップ×メタル×ドゥームといった要素を「全て憎悪のために使っている」ような凶悪そのもののサウンドで、今回取り上げた50作品の中でも最も攻撃的な作品です。しかしその攻撃性はどちらかといえば外より内に向かっているような危うさもあり、言いようのない不穏さをたたえています。

15.The Microphones - Microphones in 2020
全1曲、44:44の作品。たった2つのコードの反復で構成された楽曲は、彼の個人史を振り返る自伝的な作品です。過去を振り返りつつも、今の自分は自分でしかないという、ただそこに「在る」ということを肯定も否定もせずに受け入れていく過程を決してドラマチックになりすぎずに俯瞰的に描いていく傑作です。

14.Waxahatchee - Saint Cloud
女性SSWKatie Crutchfieldのプロジェクトの5th。前作はかなりオルタナ・ロックに寄った作品でしたが、本作は彼女のルーツであるカントリー、アメリカーナに立ち返り、おおらかでカラッとした、それでいて多くのグッドメロディを擁するシンプルな作品に落ち着きました。カントリー、どちらかというと男臭いイメージがあるジャンルなんですが彼女が演るととてもソフトでお洒落なアレンジになるところのバランスもいいんですよね。昼休みにノンビリしながらよく聴いています。

13.冥丁 - 古風
広島在住のアーティストによる、「LOST JAPANESE MOOD」と銘打たれた、日本の失われた風景を描き出す一連の作品の完結作。「日本がかつて失った風景」というとノスタルジックな「あの頃は良かった」的な観点で語られがちですが、過酷な労働環境の遊女をテーマにした「花魁Ⅱ」を筆頭に、この作品は日本がかつて抱えてきた「痛み」と、確かにその中で鮮烈に生き抜いた人々に捧げられたものです。前作まではアンビエントが中心でしたが、今作ではふんだんにサンプリングを使用しつつ、ピアノを前面に出した楽曲も頻出する等、表現の幅が広くなっているところも見どころ。

12.Arca - KiCk i
エクスペリメンタルの中でもさらに極北のような楽曲を作り続けてきた、当代随一の奇才、Arcaの新作。一聴すると「ポップになった」とだけで評価されそうに思いますが、自らがノンバイナリーであることを高らかに宣言する「Nonbinary」で幕を開け、自らのアイデンティティーを肯定するだけでなくそれを「外に向けた」ことにとても意義があると思っています。様々な音のグラデーションをあえてまとめることなく昇華していくことで唯一無二の美しさを表現することに成功した作品です。
それにしても、Bjorkとメチャクチャ仲いいですねこの方…

11.THE NOVEMBERS - At The Beginning
前作『ANGELS』からわずか1年で届けられた8th。yukihiro(L’Arc-en-Ciel)が9曲中7曲も参加しているという時点で衝撃的でしたが、彼の参加によりバンドサウンドとエレクトロニックサウンドを非常に高い打点でムダなく融合することに成功し、バンドとしてまた一つ皮が向けた感があります。怜悧なインダストリアルサウンドに重厚さも増し、それでいてポップであることから少しも外れない奇跡的なバランスの作品です。

10.Kelly Lee Owens - Inner Song
ウェールズ出身の女性プロデューサーによる2nd。バキバキのテクノ(ボーカルなし)と完全な歌モノ(自分が歌っている)が混在し、ミニマルな曲、攻撃的な曲、深く沈み込む曲とバラエティに富みながらも芯がぼやけることなく一つの作品にきれいに納まっています。The Velvet UndergroundのJohn Caleとのコラボもあり、1曲目もレディオヘッドのカバーだったりと色々贅沢な作品でもあります。この作品聴いてると「あっクラブ行って踊り倒してぇな~」という気分になってきます。

9.Adrianne Lenker - songs / instrumentals
ブルックリン出身のロックバンドBig ThiefのVo.によるソロ作品。
Big Thiefでは骨太な声と繊細な声を曲によって使い分けていましたが、今作では後者の繊細バージョンで統一されており、幽玄なボーカルが煌めくようなアルペジオと絡み合って、ミニマルながら表情豊かな活き活きとしたフォークサウンドの虜になりました。
今年Big Thiefとして来日する予定だったのにキャンセルになり残念……って今回こんな話題ばっかりでちょっとウンザリしています。

8.Run the Jewels - RTJ4
BLMを象徴する事件と作品の内容があまりにリンクしすぎてしまったため、その側面からのみ語られることが多い作品(もちろん、その視点で語ることが間違いではない)ではありますが、ひたすらに攻撃的なリリックでありながらキャッチーさとユーモアを忘れず、しかしダーティなラップとバッキバキのトラックが死ぬほどカッコいいということも伝えてもいいんじゃないかと思っています。メッセージ性とエンタメ性を高度に融合させた傑作です。

7.Taylor Swift - folklore
6.Taylor Swift - evermore
正直に言うならば、テイラー・スウィフトは好きなミュージシャンではありませんでした。カニエとのしょうもないbeefだったり、良くも悪くも「最大公約数的ポップ」からはみ出てない作風もあまり琴線に触れるものではなかったからです。
ところが、今2作では過去作に見られたような派手なプロダクションはなく、特に「folklore」はともすれば地味で陰鬱とも捉えられかねないほどの静謐さが全編に漂っており、ともすれば従来のファンからは「異色作」と捉えられてもおかしくないほどの変貌を遂げています。フォークロア(民間伝承)と名付けられたように、様々な人物の視点で後に寓話、おとぎ話、伝説と様々に形を変えて語り継がれていく物語が紡がれていきます。姉妹作とされた「evermore」では前編の雰囲気を継承しつつ、少し外に開かれたような明るさを見せながらも、「痛み」「辛さ」といったプリミティヴな感情を乗せながら新たな物語を語っています。
聴き終えた後は質の高いオムニバス小説を読み終えた後のような感覚にも陥り、間違いなく彼女のターニングポイントとなる作品かと思います。
どちらの作品にもBon IverやThe Nationalとの共作が収録されていますが、特にevermore収録の表題曲は今年のベスト・トラックと言っていい、魂が震えるような珠玉の名曲です。


5.Yves Tumor - Heaven To A Tortured Mind
「今年の最強"ロック"ミュージシャンは誰か?」と聞かれたらこの人の名前を出すことになると思います。元々エレクトロニック、インダストリアル、ヒップホップ、ファンクを融合させ、ノイズで化粧を施すような音楽を志向してきた彼が今作で纏ったのはまぎれもなくグラム・ロックのそれ。混沌と猥雑さ、甘美さと退廃、いかがわしさを強烈に放ちながら、しかしロマンティシズムを感じる異形のパフォーマー。一方で過去の模倣にはならず、地に足のついた強烈なファンクネスがギリギリのところで下世話にならないエレガントとなり、無二の個性を発揮しています。
「異形のファッションショー」とも称された来日公演の記憶も新しく、大真面目に「次世代のプリンス」と言っていい存在になりつつあるのではと思います。

4.BUCK-TICK - ABRACADABRA
22th。このバンドはだいたい10年に一度、キャリアを総括する作品を作る傾向にあり、「狂った太陽」「ONE LIFE,ONE DEATH」「memento mori」そして前作「No.0」がそれにあたり、特に「No.0」はキャリアハイを更新する大傑作でもあったことから、「次作はまた視点を変えた作品が来るのでは」と思っていたところ、今作では虐待や自死、中傷といった重いテーマを厭世的に俯瞰しつつ、そこからの「逃避」をポジティブに捉えようとした、メッセージ性の高さが際立つ作品となりました。背景にはもちろんコロナ渦という状況があるわけですが、だからといって前々々作「或いはアナーキー」や前々作「アトム未来派No.9」にあったような重苦しさはなく、カラッとした軽快さがアルバム全編を貫いており、昭和歌謡丸出しの楽曲を配置したり、曲名や歌詞にもいつになく遊び心を持たせるなど、バンドの「余裕」を感じる作風で、BUCK-TICK初心者にもとても勧めやすい作品だと感じます。
今年という状況であるからこそ、多くの人に聴いてほしい名作です。特に「MOONLIGHT ESCAPE」「ユリイカ」「忘却」のラスト3曲は必聴。

3.Neptunian Maximalism - Éons
「海王星の最大主義者」を名乗るベルギーの実験音楽集団による129分の地獄界曼荼羅。
日本やアジアの神仏、精霊、妖怪をテーマにした絵を描く画家・金子富之氏の作品をジャケットに採用し、大太鼓等の和楽器をフィーチャーしつつ東南アジア~インドの民族音楽的アプローチを施し、地獄の炎の中で次の輪廻を待っているかのような混沌とうねりを間断なく与え続ける驚異のエクストリームミュージック。
「マキシマリズムとは無駄を省いたミニマリズムへの反発である」とはメンバーの談。その言葉の通り、多元的で様々なレイヤーが折り重なった、もはやメタルだのジャズだのドローンだのといった分類が無意味に感じるほどの音の洪水に、ただ身を委ねるしかありませんでした。
唯一の欠点はあまりに長大すぎることで、「よし、聴くぞ」と身構える必要があることでしょうか…(笑)

2.SAULT - UNTITLED (Black Is)
1.SAULT - UNTITLED (Rise)
2019年に突如現れた、正体不明のUKのソウル・ファンクミュージシャン。このご時世にアーティストに関する情報を恐らく意図的に隠し、純粋に音楽とメッセージのみを届けようとするストイックな姿勢のアーティストです。
今作はやはりというべきか、BLMに呼応する形で届けられたアルバムです。かたや拳を突き上げた怒りを、かたや両手を合わせた祈りと悲しみをそれぞれ表現してるかのような生の感情をぶつけつつ、しかし決してネガティヴに陥ること無く、ダンサブルで解放的、しかしダイナミックな祝祭の音は聴いてるだけで勝手に体が動き出してしまうほどきわめて親しみやすいものでした。先のRTJの新作もそうでしたが、メッセージ性の高さと大衆性、エンタメ性が非常に高いレベルでまとまっているので、肩肘張らずに楽しめるところがこの両作(特にRise)の最大の魅力でしょう。シチュエーションを選ばずにいつでも聴けるところも好きです。結果、この2作が今年最も再生数が多かったため、この位置に収まりました。


以上となります。かなりフォロワー経由で知った音楽も多く、自分だけでは絶対にたどり着くことのなかった知見を得られるのはSNSを始めて最も良かったと思うことのひとつです。
来年も良いことがあるといいなぁ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
