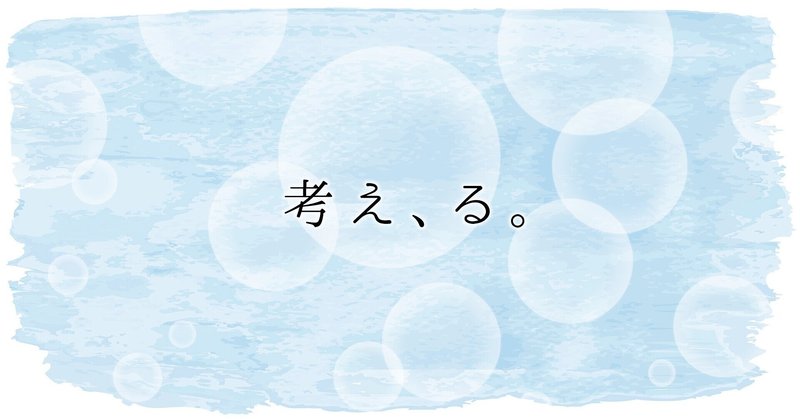
【言語技術で「考える」を強くする①】私が論理思考力を身に着けるまで
「考える」ということをどうすれば習得できるのか?そして教えることが出来るのか?
「考える」を理解して意識的に使えるようになることで、生産性も高まり、品質も高まり、コミュニケーションもうまくいくようになる。
「考える」を身につけてもらうにはどうすればよいのだろうか?私の長年の懸案であった。その答えが「言語技術」にあった。
「言語技術」に関する記事を書き連ねていこうと考えています。これまでに自分自身が思考法を習得し、それを部下に指導するにあたって感じた問題意識や、具体的な学び方など、先人の知見なども拝借しながら執筆できればと思います。できるだけ多くの人がこのテクニックを身につけることで、仕事やプライベートでより良い生活を送るための一助になることができればうれしいです。
第1回目は、私がどのようにして思考力を身につけてきたのか、をお話ししたいと思います。
私が論理思考を獲得するまで
大学院理工学学研究科を修了し、新卒で入社した会社ではプログラマをやっていました。プログラミングは楽しく、自分が記述したプログラムが正しく動作することに喜びを感じていました。
一方、他人の書いた設計書を言語化するだけの職業プログラマに飽きてしまい、2年たった頃に転職を決意しました。2002年当時、まだコンサルタントという職業自体が珍しく、あまりよく知らなかったのですが、名前のカッコよさに惹かれ日系ITコンサル企業に転職しました。
理系出身であることや、プログラミング自体は自分なりに得意だったため、自分自身が”論理的”であることに一定の自信を持っていたのですが、その自信は、入社直後にもろくも崩れ去りました。
ごめん、ちょっと何言ってるのかわからないんだけど
ということを、リーダーからしばしばいわれます。その当時は、なぜ、よくわからないといわれているのか?問題はどこにあるのかがわかりませんでした。この言葉は辛く、自分の全能力を否定されたように感じ、打ちひしがれる毎日でした。
一方で、多くの先輩方に恵まれ、コンサルタントとしての頭の使い方、紙の書き方、立ち居振る舞いなど、様々な指導を受けました。それはそれは苦しく、厳しい指導でしたが、何とか食らいつきました。まずは鵜呑みにしてひたすら実行・習慣化しました。怒られないために(笑)
また、会社が「ロジシントレーニング」と題して、論理思考や仮説思考等の問題が毎週のように提示されます。これにも参加し、問題の解答を先輩が添削してくれるといった研修も毎回欠かさず参加しました。
それらトレーニングを愚直にやってきた結果、ある時ふと感じたのです。
あ、私ロジカルに考えられているな。
と。その時の感覚を言葉にすることはできません。これまでは論理思考を意識して実践していたものが、ある時、無意識にできるようになっていたことに気づいたのです。このようにして、On Off 問わずトレーニングを続けた結果、一定レベルの論理思考力は身についたと感じています。
今振り返ると、それ以外にも「学生時代の論文作成」や「物理実験におけるレポート作成」なども論理的な枠組みで文章を作成したり、考察したりします。これら学生時代の活動も、論理思考のトレーニングとなっていたのかもしれません。
私が学んできた様々な思考法
OJTのみならず、様々な学習をしながらこのテクニックを身に着けてきたのですが、そのために意識的に実践した方法があります。
1.書籍を読む
理論を理解するために、本を読みました。ただこれだけでは十分ではなく、その手法を活用する機会がなければ身に付きませんでした。
これまでに読んできた本の中でのおすすめをいくつか紹介します。
就職した当初にいくつかの本を読んでいました。したがって、意味はなんとなく理解していました。しかしながら、仕事上で活用しなかったため使い道がわかりません。
やるべきことはわかるのですが、実際にどのような場面で適用できるるのかが分からなかったのです。(同じように感じている人は私の周りでも多くいますし、今でもよく聞きます)
2.問題を解く
そこで本で得た知識を実践してみるために、思考法を試される問題も多数試しました。また、自社でのロジカルシンキングトレーニングにも参加し、分類問題や、フェルミ推定など、様々な問題を解き、解説や指導を実施していただきました。
こちらは私が実践したページではないのですが、このページにあるような問題をひたすら回答することによって、思考の癖(だから何?なんでそう思うの?)や、MECEってどういうものなのか?ということがなんとなく理解できるようになってきました。
3.学んだことを仕事で実践
それらと並行して、学んだ手法をとにかく使ってみます。最初は、仕事の中でそれが利用されているポイントを把握する。というイメージでひたすらインプットして評価をしました。
・票の縦軸・横軸がMECEか?
・このページで言いたいことと、メッセージが一致しているか?
・そもそも、日本語の文章として、構造が成り立っているか?
等々
まずは他人の資料をチェックすることで、その観点を学びました。そこから、自分が資料を作成する際のチェックリストを作り、一つ一つの観点を意識的に実践することで習慣化することが出来ました。
4.指導を受ける
指導には様々な観点の指導があるので、論理思考のトレーニングになるということを感じながら指導を受けたわけではありません。しかしながら、これらの指導・指摘の中には、思考力を鍛えるためのトレーニングが数多く存在したことが後になってわかりました。
上記の流れで学んできたテクニックには、例えば以下のようなものになります。
・論点思考
・仮説思考
・クリティカルシンキング
・概念化思考
・水平思考
・ロジカルシンキング
・問題解決思考
等
ぶつ切り(だと自分自身は感じていた)のテクニックを様々組み合わせて日々の仕事に臨んできました。これらの技術習得に多くの時間をかけ、意識的に活用し続け、最終的に無意識にできるようになりました。その結果、仕事の品質・スピード、コミュニケーション含めて、様々なスキルが向上しました。
その一方で、これらの技術が身についたことにより大きな疑問が湧いてきたのです。
日々様々な決定を下しながら生活していることを考えると、意識していないだけで、日常生活においても活用している思考法なのではないか?なぜ仕事になると途端に思考ができなくなってしまうのか?より効率的な学習方法があるのではないか?
ただ、この時点では私には明快な答えが見つかっていませんでした。しかし、ある時ふと出会った一冊の本に答えを見つけたのです。
次回は、「なぜ言語技術を取り上げようとしたのか?」について書きたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
