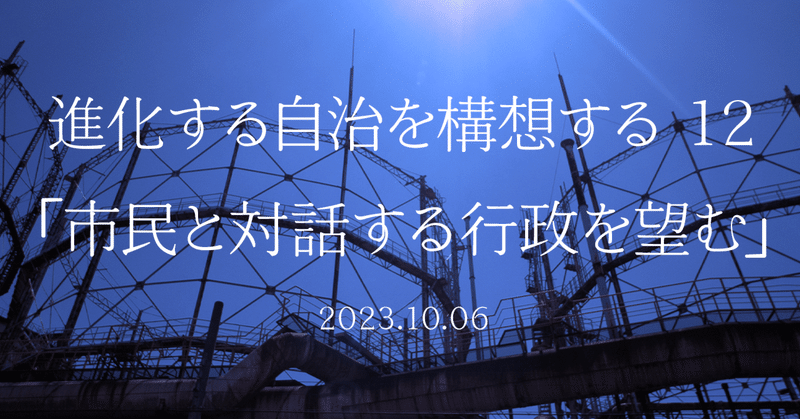
進化する自治を構想する 12「市民と対話する行政を望む」
夢洲IRカジノや万博で問われる「ごまかし」
先週に続いて、今週も引き続き山田明さんの「大阪市をウォッチしよう」をお送りしました。9月最終週になって、IRカジノも万博のあわただしい動きを見せたため、タイムリーな話題提供となったのではないだろうか。
IRカジノにせよ、万博にせよ、この間に顕わになったのは、行政の「ごまかし」であり、市民を欺いてきたこれまでの行政の姿勢だ。夢洲特有の軟弱地盤や地盤沈下の問題は、これまでもさんざん指摘されてきたことだが、市民の質問や指摘にはまともに答えてこなかった。が、ここにきて、軟弱地盤がゆえに50mものくい打ちが必要となり、建設費が膨れ上がり、万博のパビリオンでさえ、独自デザインの建設を辞退する国も現れた。
また、夢洲へのアクセスは咲洲と結ぶトンネルと舞洲にかかる夢舞大橋しかない。以前から、コンテナを利用する物流トラックと建設用トラックとの併用には無理があると、講和く労働者からの指摘があったにもかかわらず、調整で可能、といった楽観論でごまかしてきた。が、やはりアクセスの脆弱さが問題となり、2025年の万博の開幕と同時にIRカジノ建設を始めるという、夢洲のアクセスを無視したような計画を打ち出してきた。
これらは、すべて市民の声や有識者の声に耳を貸さず、独善的な態度で計画を進めてきた行政の姿勢にある。
市民生活に関わる問題も通達ですませる行政
10月5日の「大阪市の樹木伐採と緑化」では、街路樹や公園樹の伐採問題、いわゆる「木を切る改革」についての話題だった。街路樹や公園に関わる事案は、市民の身近な問題でもあるし、日々利用する市民の思いを組んでもいいと思う。しかし実際には、「公園樹・街路樹の安全対策事業」という名の伐採計画は、事前に意見を聞くパブリックコメントとかもなく、実施する直前に「公園樹・街路樹の安全対策事業の実施について」という通達を各町会宛に通知するだけに留まっている。実施計画に対しては、「安全のため」として取り合わない。実施についてでは、「街路樹では、通行障害や視認障害・視距阻害など安全な道路交通に支障を来すおそれが生じてきています。」と記載されているが、剪定という手法は検討したかどうかも明らかにはしていない。
身近な事業こそ市民との合意形成を図るべき
市民は、その自治体の構成員でもあるが主役である。街路樹や公園は、日常的に市民が親しみ、利用する身近な存在。ただあるだけのモノではなく、その姿かたち、朝夕、四季折々、人々に憩いを提供しているのだ。そしてその景観ひとつで、町の様相は大きく変わる。ここ10年ほどの間に、大阪市内の公園は大きく様変わりしてしまった。天王寺公園からは植物園がなくなり、ただの芝生広場になり、市民が無料で利用できるスペースは1/6になってしまった。これが市民公園といえるだろうか。街路樹でさえ、剪定とは言えない切株にしたりしている。安全を旗頭にして、効果・効率で管理を簡略化しているようにしか見えない。それまであった街路樹を撤去したり、公園内の樹木を伐採するだけでなく、もっと街の景観を維持しながら、大阪を訪れる観光客にも、美しい町と思われるような町づくりはできないのだろうか。
何よりも、こうした身近な事業に、市民の声を反映する仕組みをつくるべきではないか。ただ通達を出すだけの行政は、市民の声を排除するので、効率が良いのだろうが、市民の心は、どんどん離れていきはしないか。市民との話し合う機会を持ち、お互いが納得できる解決策を見出す、合意形成を育むことこそ、行政の仕事といえるのではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
