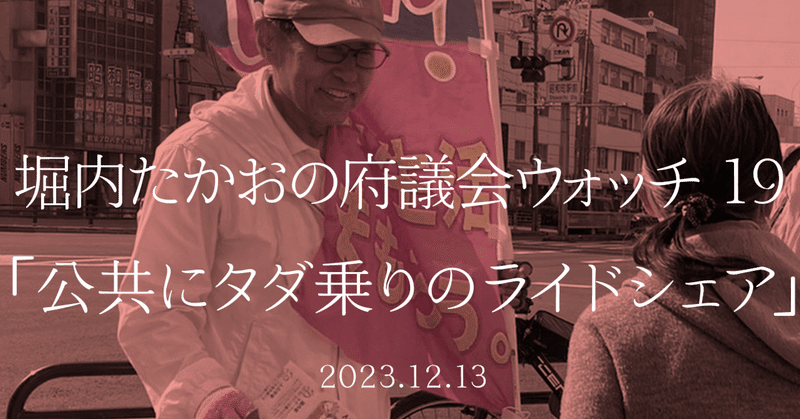
堀内たかおの府議会ウォッチ 19「公共にタダ乗りのライドシェア」
唐突すぎる万博送客のためのライドシェア
大阪府議会で唐突に出てきたライドシェアの問題が、今国会でも参議院で取り上げられている。この問題は、国会では春、秋ともにデジタル社会形成と連動した形で、継続して議論されている問題でもある。
府議会では、万博の送客のためにライドシェアを導入せよ、という主張でした。府議会の常任委員会で、空飛ぶ車がどうも飛びそうにない。次の目玉というニュアンスで、ライドシェアだ、と。日本で初めてのライドシェアをするんだ、ということで持ち出された。
自分たちの存在感を示すためだけの議会発言
万博の交通アクセスの課題については、博覧会協会、国共に問題としている。夢洲には、現在物流のコンテナヤードがあり、大型コンテナ車両や工事関係車両など、大型トラックによる渋滞が続いている。こうした交通状況の中で、ライドシェアを導入するといういうことが、どのような課題を引起こすかということについて、考えが及んでいない。
万博会場へは、一般車両は直接入ることはできない。協会が指定するシャトルバスなどに、乗り換えて会場入りする。その基地局が舞洲であったり、弁天町にあり、基地局まで行くために、利用する手段でしかない。この基地局に運送する観光バスなども検討されており、そうした手段の一つとして、ライドシェアを導入すれば、市内の交通渋滞をより一層深刻にすることになる。
いま万博の交通アクセスについては、安易に新しい交通手段を導入するということではなく、大阪の市内交通、商業交通も含めて、どうするのかという視点が必要。あまりにも全体を見ていない、いつもの吉村知事のように、耳心地のいいキャッチフレーズだけを掲げて、やってる感を出すということにしか見えない。実際、万博とは関係なく、「大阪では新しいことをやっているんだぞ」という、自分たちの存在感を示すためだけの、「ライドシェア」を持ってきているように思う。
斎藤鉄夫国土交通大臣の答弁では、「地域交通の担い手不足や移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応するために」ライドシェアが重要であるとしている。万博の機会を通じて導入するのはどうなのかと問われて、そういうところまでは考えていない、というようなやり取りが行われていた。
一方で、いまデジタル担当大臣がライドシェアを進めようとしている。それが、ウーバーに代表されるような海外のシェア事業者が、圧力を強めていることがある。聞くところによると、霞が関の壁面にウーバーの広告がいっぱい貼り出されているという。i日本でウーバーは、食品の輸送に特化されているが、アメリカや東南アジアでは、ライドシェアの導入が進んでいる。日本でも取り入れろ、という圧力が進んでいるようだ。
目に見える関係と地道な仕組みづくりから
ウーバーのような、仲介手数料を稼ぐ業者の事業規模は、2018年には1億円だったものが2030年には、130億円台に膨らむという予測をしている。※1 そうした一環から進めようとしているのかもしれないが、それにしては、あまりにも不安要素が大きい。
外国で言われているように、過労で事故を起こした場合の補償問題、運転者による加害行為など、いろいろな問題が出ている。
運転者そのものの安全性、乗客の安全性、第三者、つまり歩行者などの一般市民を含む、交通規制そのものの問題があるため、市民のコンセンサスが得られたり、交通行政としての正当性が問われたりする課題がある。
中国では、もともとタクシーが少ない国だったので、乗用車を代替で使おうとする動きがあった。現在は、片手間でやる人と専業でやる人の二手に分かれているという。専業でやっている人は、売り上げが不安定で、保証もなく、先行きが見えない、将来性がない仕事だと言う。
国内の一部で行っているのは、準公共交通として、交通の不便さを行政も一体となってどのように解消するか、という一環でライドシェアというしくみだけを導入して行っている。
身近な事例では、大阪府池田市の伏尾台で、2020年1月から導入されている「らくらく送迎」というしくみがある。※2 年間に1000件くらいの需要があり、お年寄りなど住民に喜ばれているという。顔の見える関係性、目に見える関係性があってのライドシェア。
法律で定められた以外の要素が入ってくるライドシェアでは、そういった仕組みづくりが必要だと思う。
※1 富士経済が2019年に発表した、「日本国内の自動車関連シェアサービスの市場予測」。相乗り型のライドシェアの市場規模が、2018年には1億円の見込みから、2030年には、187.1倍の131億円に拡大するとした。
https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=19014
※2 らくらく送迎
住民と行政、大学、民間事業者の競争から生まれたコミュニティサービスの一環。
2018年10月、総務省の事業に採択され住民ボランティアドライバーによる送迎サービスの実証実験を実施。
2020年1月、大阪府の事業に採択され、送迎サービスをさらに便利に、さらに使いやすくする取り組みを開始。
また2020年12月より、「現在実施されているサービスにIT技術を活用し」専用アプリや予約リモコンからた配車予約が行なえ、安否確認、健康づくりサービスによる生活支援などの実証実験が行われるなど、継続したサービスと実証実験が行われている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
