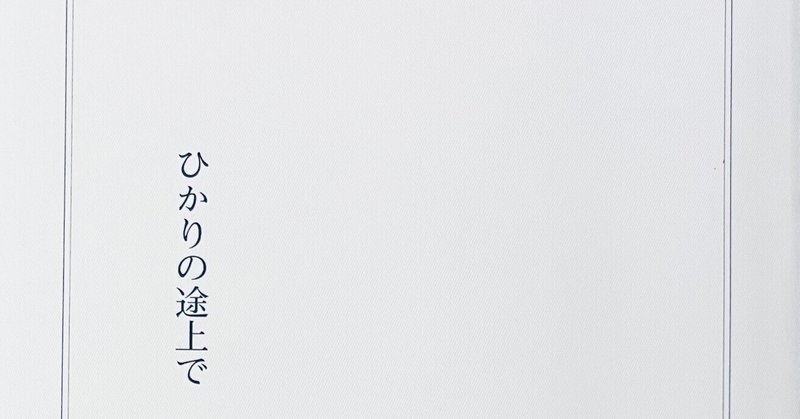
わたしの詩の書き方 「はつ、ゆき」(詩集『ひかりの途上で』より)
以前、「詩の教室」で自分の詩の書き方についてお話したことがありました。
そのときは「はつ、ゆき」という一篇の書き方についてお話しました。
いまの自分の書き方は少し変化しているのですが、基本的な書き方は変わらないのでここに載せておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・
まず、作品「はつ、ゆき」を読みます。
はつ、ゆき
赤ん坊のわたしの目が
窓のそばで
はじめてみひらき とらえた
わずかなこゆきさえ記憶になく
何万回繰り返されても
この身の転生は
ひとと別れるために
小さな冬から冬を渡る
寒い道ゆきでしかなかった
町はずれの焼場から
血のつながらないひとの
耳と薬指の骨を分けてもらい
時刻表が消えかかる停留所で
バスが来るはずの方角を
もう長いこと見続けているのも
生まれる前からの約束だったのだろうか
いまにも降りだしそうな
はつ、ゆきに耳を澄ます
ひとつ
また ひとつ
どこかでいきものが
息をひきとる 純粋なおとが
聞こえてくる
そのゆきおとを追い
てん、てん、てん、
納屋から森のほうへ
兎か 狐だろうか
南天の実のような
真新しい血が続いている
森のけものは思う
ことしのゆきが降れば
あとは
何も聞こえなくていい
何も見えなくていい
ふかく めしいて
みみはなは落ち
くちは月のための
花入れとなり
やっと
誰にも読まれない
冬の暦になるのだ と
てん、てん、てん、
ゆきとともに
南天の実は
とめどもなく落ちる
けれど バスはまだ来ない
いのち乞いをするように
凍えた指先を擦り合わせると
一瞬、狐の目のような
狂暴な血の高まりが
熱のなかをすばやく過ぎ
ゆきの底で ひとの耳と薬指の骨が
からん、と鳴り
またしずかになった
このしずけさは
いま息をひきとろうとする
けものたちの問いかけのようで
ほんとうは ひともまた
ゆきおとのなか
しずかに ほこらしく
ひとりきり、になって
いのちを いのちとして
だいじに 終わらせたいのだ
と わたしは
けものたちにやさしく伝えた
バスはまだ来ない
しろくなり始めた道のうえ
南天の実だけが
わたしの帰る方向へ
点々と続いている
①【言葉をメモする】
「はつ、ゆき」。
この詩は、H氏賞を受けた二冊目の詩集『ひかりの途上で』に収録されていますが、もともとはある媒体のために書いたものです。掲載がちょうど冬だったこともあり、凍るような世界を描こうかな、雪が降る詩を書こうかなとまず単純に思いつきました。
わたしにとって「雪」は、自分が生まれた日に降っていたこともあって、何かの始まりや、一人でいることの静けさへと結びついています。
そこで最初は、もともと自分のなかにある雪のイメージと絡めながら、思いつく言葉を手書きのノートに、途中からWordに書いていきました。
たとえば、「はつゆき」「こなゆき」「ゆき」「行き」「移動」「降る」「道のうえ」「道ゆき」「凍る」「息」「体温」「熱」……という感じでどんどんと言葉をメモしていく。
そうするうちに、雪のなかに一人でいる人のシルエットが浮かびました。その場所は人も車もあまり通らない町のはずれかな……とふと思った。そこから浮かぶ言葉をまた書きつけていって。
町のはずれ、森の近く、降りはじめた雪、いつまでもこないバス、人のいない停留所、一人、待つ……。
この人は何のためにここにいるのか……。それは「ある別れ」のためだと。そう気づくと、誰かの葬儀に出席した帰りにバス停に立つ「わたし」が見えてきました。
わたしは詩を書くときは、言葉を書きつけるうちにうっすらと浮かんでくる想像の世界なかに、実際に神経や感覚を入れていきます。すると目と耳の奥の情景と音が動いていきます。
それを急いで書き写します。すると言葉が増えるにつれ、また情景が動きます。それをまた書きとめていくという書き方が多いです。
この詩の場合も、雪の白さや冷たさに脳内が包まれたとき、それに抵抗するような生き物の体温の温かさが、ぼおっと浮かんできたり、血の痕のようなものが、点々と見えてきました。
あれは、近くの森にすむ狐とか兎などの「けもの」の血かな……赤い実かな……と思って見ていたら、「てん、てん、てん、」と赤い色が落ちる弱い音が聞こえて。
バスを待つ時間と、姿の見えないけものたちの時間と、南天の実の零れる時間。その三つの時間が言葉のうえで重なりあってきました。
その場所で、書きつけた言葉の奥へと耳を澄ますと。けものの死に際の「何も見えなくていいよ、」という細い声が聞こえてきたり。また南天の実が落ちる音が聞こえてきたり。
そうするうちに、一人でここにいることが怖いくらいに迫ってくる瞬間が言葉のうえに訪れて。
具体的に言うと、8連目の
「いのち乞いをするように
凍えた指先を擦り合わせると」
という行です。
その高まりの瞬間に、想像のなかで手にしていた誰かの「骨」がからん、と鳴りました。その音が聞えたとたん、詩は終わりに向かっていきました。バスはこないままで、わたしの時間は続いていくという終わり方です。書くわたしがコントロールするというより、言葉がそこへと自然に流れていきました。
②【一語一語を整える。比喩を試す】
こんなふうに一篇の流れや言葉の通り道をざっと作ったあとには、余分な言葉や形容をできるだけ消し、意識的に細かく一語一語を見ていきます。言葉と言葉を入れ替えたり、行や連の並びを変えたり、リズムを調整したり。推敲します。
「雪」は漢字かな、ひらがなかな……。ひらがなにして、「はつ」と「ゆき」の間に読点、てん、を入れたら、「てん、てん、てん、」という音や、血の痕と響き合うかな……。
「発」と「行」、「果つ」と「逝き」という言葉もそこから透けて見えるかな……など。
6連目で、死んでいくけものたちを「誰にも読まれない冬の暦」に喩えたり、彼らの「くちは月のための花入れ」と書きましたけれど、そう喩えることで、誰にも気づかれないまま終わる生き物の命が季節のめぐりへと戻るイメージが強まるかな……など考えました。
わたしは現在の詩の流れがどうであれ、直喩と隠喩という「喩えること」の魅惑を、自分の詩のなかでは味わいたいと思っています。
比喩は、使い方や組み合わせしだいでは誰にも響かない単なる「独りよがり」になりがちなものですが……。それでもわたしはとくに手元の言葉の周囲を控えめに照らすような「直喩」(「……のような」)で、視界をさりげなく変えてみたいな、ともつねに感じていて。
「喩え」は、凝り固まった自分の神経を遥かな時空に結びつけるためのささやかな道具や階段だと感じますし、単なる散文の流れに光の屈折する場所を与えたり、読む人が心を遠く飛ばせる膨らみをそこに作れるとも思うので、これからもいろいろと試してみたいですね。
一語と一語、一行と一行の接続点にあえて比喩は使わずとも、一篇の詩全体が何かの隠喩になっている入沢康夫さんの散文詩のような書き方にも憧れます。
あとは、説明しすぎないように、耳と薬指の「骨」の持ち主は誰なのか、「血のつながらない」わたしはなぜここにいるのかは明記しないでおきました。
物語の気配を漂わせても語りすぎないように。なるべく気をつけています。そのほうが読む人がこの場所で、一人で、自由に息をつけるからです。
③ 【あえてくり返す言葉】
「はつ、ゆき」では、一篇の最初や途中に出てきた言葉を最後にまた登場させています。「バスはまだ来ない」「南天の実」「点々(てん、てん)と」など……。
そうすることで、読んだあとに余韻が生まれたり、いくつかの連が響き合って、言葉のうえの情景や色の凹凸が深くなることもあるかなと感じています。
それと、いろんな要素を入れすぎないということ。
視点をいろんな場所に移して、さまざまなものについて語ってしまうと、表したいことが散漫になってしまうと思うんです。
とくに自分の詩の場合は、さまざまな要素を入れすぎると、言葉のなかの緊張感、つまり「静けさ」がなくなると言いますか……。
だから、雪や骨の「白」と、けものの血や南天の「赤」という色の組み合わせは、最初から最後までぶれないようにしました。
そして「てん、てん、てん、」という音はあえて何度か登場させて、南天の実の赤い色と響き合う生き物の血の匂いを、ずっと語り手の周辺に漂わせることにしました。そのことによって、一人でいる「わたし」の体温や周りの冷たさ、さびしさが強調されるかなと。
④【ありふれたイメージや言葉を意識して使う】
「南天の実」と「雪」の組み合わせは、雪うさぎの目に赤い実をよく用いることからも、読む人にとってもそんなに突飛な組み合わせではないと思うんです。想像しやすい組み合わせをあえて用いて、読む人の感情が入りやすい場所を作るということも、たまには有効かな……と思っています。
とはいえ、雪と南天の実で作る雪うさぎそのものや、兎の姿を目に見えるかたちで登場させてしまうと「あたりまえ」すぎるので、多くの人が持つ赤い実と雪という組み合わせのイメージを、けものの「真新しい」血の痕や人の骨と重ねる流れにしました。
一見ありふれたイメージを利用しながらも、使い方を限定しすぎない。そこは気をつけている点です。ありふれたイメージや、イメージしやすいものを用いると読む人が入りやすい分だけ、散文化しやすいリスクもあります。だから言葉の運びや比喩などを、散文化する手前で慎重に調整することが必要だとも思います。
いまお伝えしたことが、わたしの詩の基本的な書き方なのですが、まず、こういうことについて書こうかな……と思いながら、浮かんできた言葉をどんどんとノートやパソコンにメモしていきます。
ああでもないこうでもない、と絵を描くように白紙のうえに言葉を配置していくうちに、単語と単語がくっついて短い文章になったり、また離れて別の言葉とくっついたり、という動きを始めます。
そして一行、二行の文章が浮かんだとき、その背後にぼんやりと景色や何かの気配が見えてきます。そこに語り手としてより入っていきます。そこで見えてくるものを言葉で写すと、映像や触感や音の続きがもう少し見えてくるので、それをまた言葉で写します。
出てきた言葉から新しい光景がまた生まれて、それをまた言葉で追いかけていく。言葉、映像、言葉、映像、言葉という順で追いかけっこする感じでしょうか。
詩人によっては、ほかの人や土地の記憶を自分の身体に通過させてそれを書くとか、意識と無意識のあいだを行き来するという方もいますが……。わたしの場合は、ぼんやりと霧がかった場所からやってくるものに目を凝らし、耳を澄ます。そんな感覚が強いでしょうか。
わたしは、ぱっと読んだときに意味が取りづらい言葉と言葉の接続はあまりしないのですが、読みやすい言葉を用いたとしても、ありふれた散文のような言い回しにならないよう、詩ならではの表現ややり方を見せていけたらとは思っています。
いきなり意味不明にするのではなく、言葉の意味を日常の使い方から少しずつずらし、一語の本来の色や音の美しさや純粋さを引き出せたらいいなと。
読みやすくわかりやすい詩がすべていい詩とは思いませんし、平明な言葉を使うのなら、一回読んだらすべてが伝わり、わかってしまう単なる主義主張やメッセージや日記で終わらないように工夫したいですね。
新鮮な意味の組み合わせやふだんは感じていない感覚を言葉のうえに、できたら複数の時空の層を作りながら表せたら……とも思うんです。
そのほうが自分でも書いていて楽しいし、再読してもらえる可能性も増えるだろうから。
⑤ 【言葉の背後にあるもの:辻邦生の文の引用とともに】
書くものにはどうしても、それぞれの書き手の日常での五感の動かし方や言語観や世界観みたいなものが、無意識に出てしまうと思うんですが(作者がそれに抗おうとしても……)。
わたしは詩のなかで、自分の周りに広がる世界を見るとき、何も持たない、何もない、いわば儚いような地点から眺めることがよくあります。
人はいつかいなくなる儚いもの……という意識が子どもの頃からなぜか強くあるんです。だからといって、むやみに暗くなったり、絶望したりするのではなくて。
そういう儚く消えていく、何も持っていないものとしてこの世界を見たとき、いま、窓越しにここに降りそそぐ光のつかの間の美しさだとか、こうしてここにいるということ自体がかえってかけがえのないものとして感じられると思うんです。
そんな愛しいものを書き留められたら……という気持ちで書いた詩がいくつかあります。
そんなふうに何も持たないものの目で周囲の世界を見つめるという態度については、作家の辻邦生も「詩への旅 詩からの旅」というエッセイで書いています。
辻邦生のこの文章を初めて読んだとき、自分が昔から感じていたことがより洗練された言葉で書かれていると思いました。
「自分が漠然と感じ、考えていたことをより完璧な言葉で書いてくれている人がいた……」。そう思えると、わたしはその作家を深く好きになるんです。川端康成やヴァレリーや北原白秋を初めて読んだときもそうでした。
まだ学生の頃にわたしが惹かれた、辻邦生の文章を少し紹介します。
「今ある」ということが無限に「喜ばしく」なければならない。自分がむなしくなり、完全に放棄されて、ゼロになって、そこから「今、ある」を仰ぎ見るようにして考える。そのとき世界は「すばらしいこと」にみちてくる。世界は「在る」というそのことに恵まれている。「自己はむなしく、何も与えられないのが本来の状況だ」とするイデー(考え)があって、そこに身をおくゆえに「木」も「空」も「風」も「雲」もおどろくべき美しい存在として現れてくる。一本の草もなぐさめとなる。「木」も「雲」もよろこびを表わす。
すべてが移ろうこの地球上の時間のなかで、いつか消えてしまう存在であることの儚さと空虚さと、生まれてからずっと変わらないさびしさ。でも虚しさとさびしさがいつもあるからこそ、かえって感じられる身体の奥の熱や温かさも、たしかにあって。
そんなものを純度の高い言葉で、詩として表せたらいいなと、まだ漠然とですが思っています。
わたしの詩の書き方としては、いまお話しましたように、脳内の光景のなかに語り手として入っていって、見えるものや感じることを書き留めて、そのあとに言葉の運びや並びを調整するという書き方がありますが、大きく分けると別の書き方もあります。
それは何かひとつの「もの」について考え、その思考の道筋を言葉にしていく書き方です。
「はつ、ゆき」の入っている詩集『ひかりの途上で』の「林檎」や「労働として」「子、と」という作品や、第三詩集『あのとき冬の子どもたち』の「改札の木」「水の旅」「果実ひとつの」という作品はそういう「考える」タイプの詩です。
機会があればご覧いただけましたら嬉しいです。
わたしの詩の書き方について、一篇を例として簡単にお話しましたが、少しでもご参考になれば幸いです。




※「はつ、ゆき」が収録された、わたしの第二詩集『ひかりの途上で』(七月堂)は、下記の七月堂古書部さんのサイトから新本(第四刷)が購入できます。
