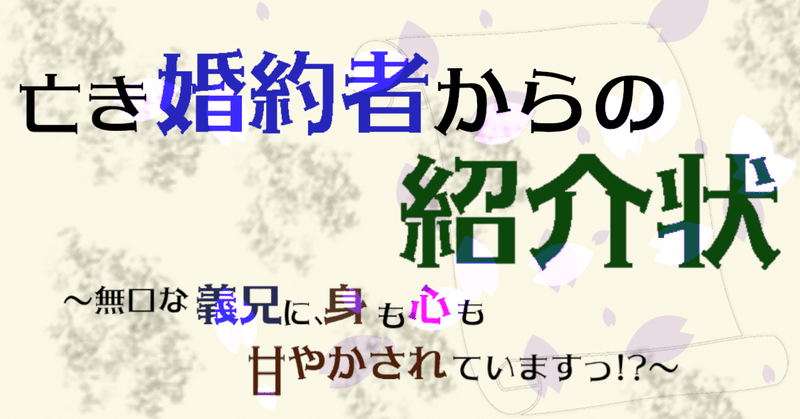
【没案・初稿】 亡き婚約者からの紹介状

『“織田君”のところに嫁ぎなさい。弓枝よりもお前のほうがよく似合う』
祖父の言葉を思いだすと、今でも腹立たしい。
我が家は閨閥で、結婚によって各界と繋がっているのを知っていたから、私もそういう運命になるのだろうとは理解はしていた。
それを告げられたときは、とうとうそのときが来たんだぐらいにしか思えなかった。それと同時に、この先、なぜか私がこの家を動かすことになるのではという気もした。
とはいえ、婚約したという彼、“織田君”とは面識はなく、ただ女性経営者たちの集まりでしか聞いたことがない相手で、すごく興味深い人でもあった。
だれにでも裏表がなく、困っている人には手を差し伸べるという会社のトップとしては、ある意味致命的な性格。
その一方で、玉の輿を狙う女たちにはその性格が魅力的だったらしい。パーティーが開かれるたび、彼女たちは彼の隣にいることを望んだらしいが、一方でそんな俗世的なことに彼は一切興味がなかったらしく、浮ついた噂を聞いたことがなかった。
ひたすら目の前の仕事に集中した彼は、三流企業と揶揄された会社を急成長させ、東証に初上場させた……そしてその三ヶ月後、交通事故で死んだらしい。
生前に一度も会うこともなかった婚約者は、写真の中でも聞いていた性格を切り取ったかのような、優しい微笑みを浮かべている。
会ったことがないからか、婚約者になる予定の人であってもどこか遠く感じてしまい、葬儀場でも悲しいという気分になれなかった。
アテが外れ、やけ酒を朝から呷る日々が続いていた祖父を傍目に、今住んでいるアパートに戻るため、まさに実家を出るところだったのだが、突然の来客でオシャカになってしまった。
『僕が弟の婚約を引き継ぎます』
その元凶は木下本邸の居間でそう宣ったのだ。
永田町の古狸の一員として君臨してきた祖父、重蔵でさえあんぐりと口を開けていたのだから、私には一ミクロンも理解できるはずもない。
『木下先生はオダ・ビルディングにパイプを作りたい。静枝さんは経営を続けたい。そして、僕は静枝さんを迎えたい。ウィン-ウィン-ウィンの関係ですよね』
しかし、彼、浩二さんの兄、健一さんは無表情で淡々と、だが堂々とあの祖父を言い負かしたのだ。
話がまとまるとすぐに私を連れ、あれよこれよと二時間ほど手続きしたあと、今に至る。
「姉さんと違って好き勝手し放題だったから、追いだしたかったのかな」
「違うんじゃないですか」
赤信号で停車中に目の前に広がるビル群を見上げながらそう呟くと、私とは一切目を合わせなかったものの、健一さんにはっきりと言いきられてしまった。
正直、弟の浩二さんに比べると華がない健一さん。彼ともまた葬儀場で初対面だったのだが、どこか野暮ったさを感じる風貌に、本当にこれが兄弟なのかと疑ったぐらいだ。しかし、やはり兄弟だからか、どことなく雰囲気は似ている。
「あなたにしかできないことを成し遂げて欲しかったから、弓枝さんではなく、あなたを嫁がせたかったんじゃないですか」
「あのジイさんがそんなことを考えるわけないじゃない」
なんだその仮説はと、呆れてしまう。
そもそも四大に行くことさえ反対していたジイさんは、女の私が会社を経営することを苦々しく思っていた。浩二さんとの婚約のために家に帰ったときには、私のサイン待ちの書類を机の上に用意していたくらいだ。
『この会社だったら、お前さんのオモチャももっといいモノにしてくれるだろうよ』
もちろん手放すつもりはなかったが、ジイさんも退くつもりはなかったようで、関係省庁の大臣や大手企業様の社長さんの名刺をチラつかせていた。
浩二さんの死の一報があと一歩でも遅ければ、私は丸め込まれていただろう。不謹慎ではあるけど、浩二さんの死は嬉しかった。
「そうですか。ですが、いつか役に立つかもしれません。どうか頭の片隅にでも置いておいてもらえませんか」
「わかったわよ」
しかし、その答えに健一さんは不服だったようだ。青信号で発進した車は少し荒く感じた。
左手の薬指にピッタリと嵌ったブルーダイヤモンドのフルエタニティの重みを感じながら、目的地に着くまで家でのやり取りを思い出してた。
『結婚するならば、家のことを差配するのが妻の役目だ。外出て遊ぶなんてみっともないだろう、健一くん?』
『僕はそう思いませんね。むしろ、静枝さんが経営されている《ライラック》というブランドはほかとは違って、敏感肌の人でも使えるのに発色がいい化粧品だと評判ですよ。木下先生が考えていらっしゃるところに本当に買収された場合、品質は即座に、評判は半年以内にそれぞれガタ落ちしますし、来年の今頃には業績も今の半分以下になるでしょうね』
『私を脅しているのかね?』
『ご自由にお取りいただければ』
正直、健一さんとの話も会社を引き合いにだして断ろうとした。けれども、彼はむしろ続けてくれと言ってきたのだ。それも、祖父に真っ向から反発して。
私に断る理由はなくなったが、それでも彼はどうして私なんかと結婚したかったのだろうか。
もちろん元から健一さんと仲がいい、というのならばまだわかる。けれども、私と織田兄弟はまったく関わりがない。むしろ姉のほうが健一さんと幼馴染なのだ。
それに姉のほうがおっとりとしていて、俗にいう癒し系だ。健一さんは浩二さんの後を継ぐんだから、名前とは正反対の性格をしている女よりも気が休まるはずだ。
そんなことを考えているうちに車はどこかの駐車場に入っていて、すでにエンジンも止まっていた。
「さあ、行きましょう」
ずっと考えこんでいた私を急かすことなく、ずっと待っていてくれたらしい。健一さんが助手席の扉を開けて待っていてくれていた。
慌てて降りると、やっぱりあなたらしくていいですねと残念そうに言われた。なんでだろうかと視線を落とすと、お揃いの指輪を嵌めた左手を差し出されていたことに気づく。
ここにきてはじめて微笑んだように感じたが、その表情は一瞬しか見ることができなかった。
「でも、繋がせてください。僕の妻なのですから」
そのときにはすでに無表情に戻っていた健一さん。先ほどとまでは違った雰囲気から、どうやらここから先でなにかをしでかすらしいと、直感でそう思った。
夫となった人の背中を押すべく、握りしめられた手をしっかりと握り返す。
ビルに入ると、一直線にエレベーターに連れ込まれた。ようやくここで、織田浩二さんが社長を務めていたオダ・ビルディングの本社ビルだということに気づいた。
二人しか乗っていない箱はグングンと上がり、あっという間に最上階付近まで到着する。
扉が開くと、このときを待ち構えていたようで、大勢の人が両脇に整列していた。《ライラック》の従業員数は五十人ばかりしかいないのに対して、急成長中の大企業様。本社だけで百人以上の従業員が私たちを出迎えている。その状況に圧倒されて、おもわず後ろに下がってしまった。しかし、健一さんは慣れているようで、私の手どころか、腰までしっかりと抱いて周りを気にすることなく進んでいく。
さて。
短い間だが、何度でも言わせてもらいたい。
さすがは飛ぶ鳥落とす勢いの不動産会社、オダ・ホールディングス様だ。
社長室も立派なもので、代表室とは名ばかりで基本的にラボで書類仕事をしている《ライラック》とは違って、どう見ても高級な家具が一式揃っている。
そこに私を連れて入った健一さんは、幹部らしき人たちを前にして頭を下げた。ガラス張りの部屋なので、業務に戻っていいと言われているのにほとんどの従業員が興味津々にこちらを覗いていたが、幹部さんたちも健一さんもなにも言わない。
「弟の件、すまなかった。社長という肩書きがあるクセに、まさかあんな無茶な走りをするなんて思わなかった」
あのバカがと吐き捨てた健一さんだけれど、どこかちょっと無理している気がした。そっと彼の手を握ると、優しく握り返してくれた。
けれども、ほかの人たちは気づいていないようで、むしろ新しい社長を待ち望んでいたかのように一人の男性が前に出てきて、分厚いファイルを健一さんに差し出す。
「新社長。早速ですが、新体制に向けての号令をお願いします」
「残念ですが、僕は経営に携わるつもりはありません。これからも営業一筋で生きていきます」
ゆっくりと首を振った健一さんの言葉に、オフィス内がザワつく。私もてっきり彼が継ぐものだと思っていたから、いったいだれが継ぐのかと、血のつながっていない家のことながら考えてしまった。
二人の両親か、それともここにいる幹部のだれかか。どちらであっても、血のつながっていない私には関係ない。
「次期社長になるのは妻の静枝です」
彼の言葉におもわず口をあんぐりと開けてしまったのは、見なかったことにしてほしい。突然すぎて思考が追いつかないのだ。
部屋の内外すべての社員からの視線は私を見ている。私は《ライラック》の代表であり、注目されることに慣れているが、こんな狭い部屋の中で大人数に注目されるのは初めてで、かなり居心地が悪かった。
意図を確かめるために健一さんをまじまじと見てしまったけれど、彼からはなんの感情も読みとれなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
