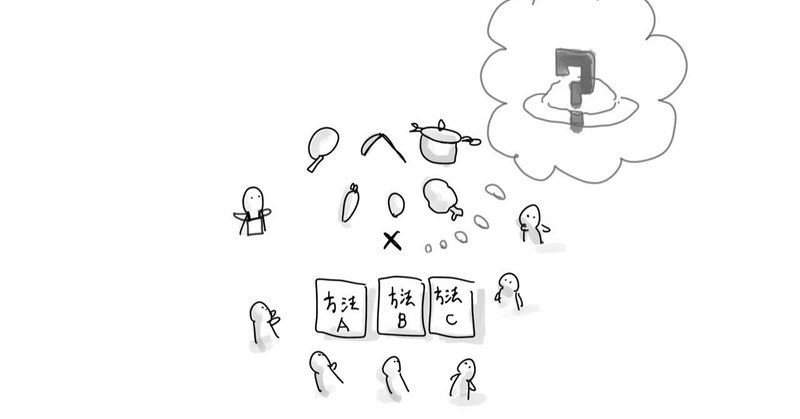
作り手にとって「実験」であること
ぼくはワークショップをデザインして生計を立てています。でも、はっきり自分が「作り手」であることを自覚しながらやろうと思ったのはここ2~3年の話です。
「デザイン」という言葉を使わなくても、あらゆる仕事はクリエイティブであると言えます。保育士も、カウンセラーも、店舗の販売員も、だれもが「作り手」であると考えることができるはず。
そんな「作り手」にとって「実験」がいかに重要か、ということを考える機会をもらったので、今日はその話を書きます。
ワークショップデザインの入門講座へ
ミミクリデザイン代表の安斎勇樹さんの講座「ワークショップデザイン・ファシリテーション入門講座」に参加しました。
ミミクリデザインは、ぼくが7月から入社した会社です。代表の安斎さんはワークショップの研究実践を10年以上重ねる第一人者です。
ぼくもチームメンバーとして、ワークショップデザインの考え方を伝える役割を担っています。そこで、代表が何を行なっているかをもっと知る必要があると考えて、講座に参加しました。
学びになったことは山ほどあるのですが、その中で「ワークショップが作り手にとって実験であること」と語っていたことについて書きます。
実験としてのワークショップ
安斎さんはミミクリの代表でありながら、東京大学の教員であり研究者でもあります。
講座では修士論文で行った実験について紹介されていました。
ワークショップのメイン活動の「制作課題」の文言を変えることで参加者の活動にどのような変化が起こるかを評価し、論文を書き上げています。
同じワークショップを条件Aと条件Bで数十回繰り返し、グループワークの様子をビデオで記録して会話分析を行なったという。くわしくは安斎さんの修士論文を参照してください。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjet/35/2/35_KJ00007628684/_pdf/-char/ja
「民主性」と「協同性」を生み出すために
安斎さんは講座のなかで、たとえそれが論文になろうとなるまいと、ワークショップの作り手にとって、なにかしらの「実験」になっていることの重要性を説いていました。
ワークショップの歴史を紐解いていくと、トップダウンでなにかが作られる制度へのカウンターとして発生していることがわかると言います。そしてそこから「民主性」や「協同性」がワークショップのエッセンスであるとされます。
たとえば、まちづくりのワークショップでは住民参加で庭を作る活動をはじめたことが起源です。社会教育では、識字率を上げるためのワークショップ的教育活動がはじまりに位置付けられています。日本では戦後、教育勅語の解体をうけて、教員たちが集まって自分たちで教育指導要領をつくるワークショップをおこなったといいます。
これらのどの領域でも、ワークショップを主催する人さえも「答えがわからないもの」にむかって「実験」する場が作られていました。
「実験」であることによって、トップダウンで決まったものを伝えるのではなくボトムアップで創出する「民主性」が伴います。また、1人の天才に従わせるのではなくコラボレーションしながら活動する「協同性」も必然となっていきます。
「実験性」がその他のエッセンスを伴わせるのだということが、安斎さんの講座に参加してよくわかりました。
見せかけだけワークショップになる場合
ワークショップを行う時、ファシリテーターにとって実験であることがなぜ必要なのか。ワークショップは正解のない問いを探求するものだからです。
実験になっていない場というのは、ファシリテーターがすでに「正解」を持っている場合です。
すでにある正解にゆるやかに誘導しているだけのケースは結構あります。表面上は参加者が自分で発見したように見せかけながら、実態はファシリテーターが持っていた正解を言い当てさせている。
たとえば、美味しいチャーハンの作り方を考えるワークショップがあったとします。ファシリテーターは料理の熟達者です。
ファシリテーターは「正しいチャーハンの作り方」を自分が知っていると自覚しているとします。「卵をご飯に混ぜてから焼く」「醤油は最後に少し入れる」などがその人流の「正解」だったとします。

参加者がそれぞれの方法でチャーハン作りを実践します。そのなかで、ファシリテーターが考える「正解」の行動を参加者がしたときだけ、「これはいい方法ですね」などとフィードバックをし、それ以外はスルーしていきます。
そうすると、「卵をご飯に混ぜてから焼く」「醤油は最後に入れる」などの方法が、さもその場で編み出されたかのように見せかけることができます。
これは見せかけだけ「ワークショップ」で、実際は「教室」になっています。そうであれば、きちんと「教室」をやったら良いのです。
「美味しいチャーハンの作り方には正解があります!それをお伝えします!」と言われた方が嬉しい。ワークショップは正解を伝える手段としては非効率だと思います。
ファシリテーターも未知への挑戦を
一方、ワークショップにとって理想的なのは、ファシリテーターもやったことのないことをやる場であることです。
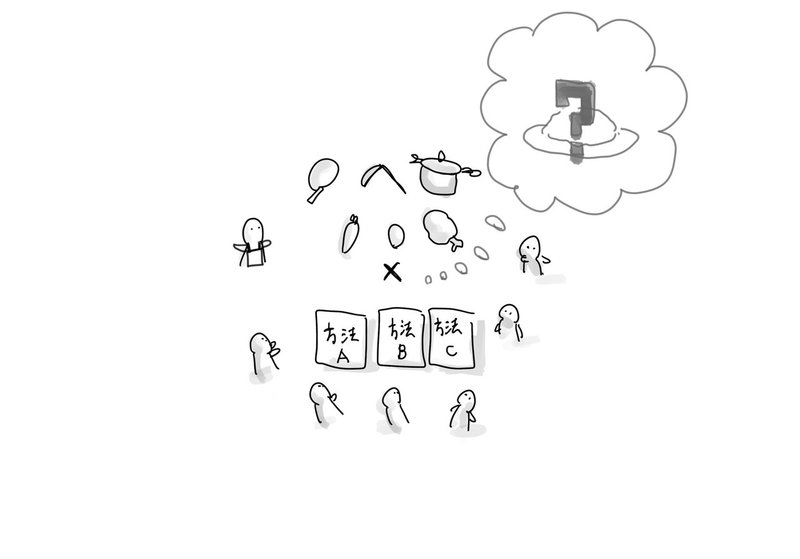
たとえば「新しいチャーハンの作り方を考える」という題目のもと、ファシリテーターも使ったことのない食材や調理道具などを用意し、いくつかの方法を伝えたうえで、参加者とともに実験するというようなかんじです。
最近ぼくが関わったワークショップ「演劇グラフィックレコーディング」は、ぼくにとってもまったくの未知の挑戦でした。
グラフィックレコーディングにもあるていど作法がありますが、演劇でやってみるというのは誰も正解を知らない実験でした。専門家である清水淳子さんさえも。
こういう実験的なワークショップは、参加者にもリスクを負ってもらう必要があります。お客さんとして船に迎え入れるのではなく、乗組員として一緒に船旅をするかのごとく。そうであってこそワークショップは楽しいのです。
実験としての条件
たとえ1度やったことがあるワークショップであっても、ファシリテーターだけがわかる実験要素を入れることができます。
チャーハンのワークショップで言えば、基本の構成だけは同じにしておいて、前回と調理器具を変える、使える食材を変える、グループの人数を変える、などと変更点を明確にしておきます。
それらが変わったことで、参加者にどのような反応を引き起こすことができたか?を評価することができます。
重要なことは、「何を実験するか?」を明確にし、条件と変数を明確にすることです。基本の構成だけ同じにして、道具を変える。あるいは道具は全く同じで、構成を変えるなど。
ぼくも、かつて赤ちゃん向けワークショップを1日に5回、数週にわたって運営していたことがあります。そのなかで、毎回道具を出すタイミングや説明の仕方、道具のレイアウトなどを変更しながら、実験しながら探っていました。
こうした実験が重要なのは、ファシリテーターにとっての楽しみになるからなのです。同じことの繰り返しで、ファシリテーターが飽きてしまっていると場が盛り上がりません。
「ちょっとここ変えてみよう」「こんなふうにやってみよう」というような実験を密かにやることで、参加者にどんな反応が起こるかを見るのが面白がることが、良い場を生むことにつながります。
良いクリエイターは実験する?
この話題って、ワークショップに限った話ではないと思われます。
グラフィックデザイナーもまた、自分が持っている得意パターンでこなすだけではなく、毎回新しいデザインを工夫しているでしょう。
劇作家も、同じ演目を再演する時も、戯曲は変えずに演出や衣装や舞台装置を変えたりして、新しいことを試しているはずです。
美術家にしても、自分の作品が置かれる状況の変化から、観客の変化を楽しんでいるかもしれません。
このように、得意パターンのなかにあえてノイズをいれたり、反復の中の差異を楽しんだりすることは、クリエイターの創作の楽しみを持続させるポイントなのかもしれません。
まとめ
・参加者に正解を当てさせるような「ワークショップ」は、「講座」「教室」という名目でやるべし
・ファシリテーターにとって実験になるようなワークショップは、参加者を「客」ではなく「乗組員」にする
・同じワークショップを繰り返す時も、新しい要素や、小さな変更点を入れることで、ファシリテーターが飽きずに実験を楽しむことができる
・得意パターンの中にノイズをいれたり、反復の中の差異を楽しむのは、デザイナーも劇作家も美術家もやっていることかもしれない
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。いただいたサポートは、赤ちゃんの発達や子育てについてのリサーチのための費用に使わせていただきます。
