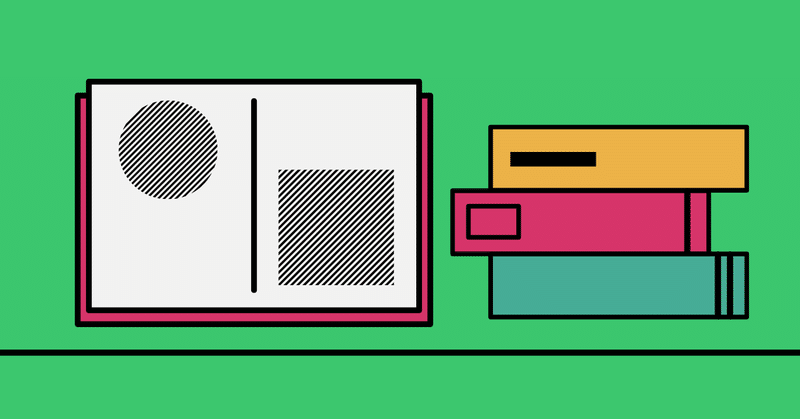
言語との情事――ナボコフ『ロリータ』
作家ウラジーミル・ナボコフは、自身の小説『ロリータ』を、「私と『英語という言語』との情事の記録」であったと振り返りました。
ここでは、そのナボコフの一節をこねくりまわすことで、はじめて『ロリータ』を読んだ(そして読み切れなかった)感想の代わりとしたいと思います。
「情事」というワードが意味するものが、主導権を握り握られ、支配することが服従することであり、服従が支配であるようなシーソーゲームであるなら、「言語との情事」という表現は『ロリータ』にぴったりです。
語り手ハンバート・ハンバートによる手記の形式をとったこの小説には、いたるところに勝手にあふれ出ていこうとする言葉の奔流が走っています。ハンバートの筆を借りた作者ナボコフが、ときに流されるままに言葉を暴発させ、ときに言葉を強く抑制し支配しようとする様は、まさに著者と言語が絡み合う情事です。
当時流行していたばかばかしい歌の歌詞を、ほんの少しいじって口ずさんでみた――ああカルメン、ぼくのかわいいカルメン、なんとか、なんとか、あのなんとかな夜、星と、車と、バーと、バーメン。
英語の原文であれば韻だけで構成されているのであろういい加減な鼻歌を、下宿人ハンバートは大家の娘ロリータと遊びながら口ずさみます。ハンバートはロリータに身体を密着させ、親密にじゃれあう風を装い、ズボンの下でひそかに絶頂に達しようともくろみます。「情事」そのもののシーンで、言語との情事もまた興奮の度合いを高めていきます。
その官能の深淵の際で宙づりになって(芸術におけるある種の技巧に比すべき、巧妙な生理学的バランス)、まるで眠っている最中にしゃべったり笑ったりするように、私は彼女の後について口から出まかせの言葉を何度も繰り返し(ぼくのかわいい人、ぼくのカルメン、カーメン、アーメン、アハハ―メン)、そのあいだに幸せなわが手は陽光にあふれる彼女の脚を品位の影が許すかぎり這いのぼっていった。
すでに主人公も、暴走する言葉も興奮を抑えきれなくなっていますが、ハンバートがついに「絶頂感の最後の脈動」を「ぶちまける」までに、あと3ページを要します。
『ロリータ』が「言語との情事」を記録した小説であること。そして、『ロリータ』が中年男と少女の情事を描いた小説であること。
であれば、小説の執筆を通してナボコフと言語は、それぞれハンバートとロリータに例えられるような関係を結んでいたと考えることもできそうです。
では、ハンバートとロリータの関係とはどのようなものか、と考え始めるとやっかいです。二人の関係を形容する言葉は無数にあるように思えるからです。「笑いを誘う変態と美少女コンビ」と言っても、先ほど挙げた「支配と服従の入れ子関係」と言っても間違いではないでしょう。二人の関係はいったい何だったのかという問いへの答えが、そのまま小説の総括になるようなものです。そもそも、(くどいですが)この小説は情事の記録であるのですから、仮に見知らぬ他人同士の情事を目撃したとして、そこから二人の目に見えない関係性を類推することの困難は容易に想像できます。
しかしそれでは話が終わらないので、ここでは2つ、ハンバートの心に巣食う「不安」と「借り物性」に触れておきます。
ハンバートは常に「不安」に取りつかれています。少女へ性的な欲望を抱いている危険な成人男性であることが、周囲に暴かれてしまわないか。ロリータが自分の支配から逃れ、別の大人(男性)の元へ行ってしまわないか。ハンバートにとってロリータとの関係は、決して平穏さや安定状態にとどまることがありません。
ひとと言語もまた、そのような不安の形でしか関係を結べない、ということができます。個人が発話したり文字に書くことではじめて言語は存在できるという意味で、両者は一見揺るがない上下関係にあるようです。しかし、発話したとたんに言語は、主体が意図した意味合いからズレはじめ、ひとは「私は言葉をコントロールできていないのではないか」という焦燥に駆られます。給油のために立ち寄ったガソリンスタンドで、言葉はロリータのようにふらっと独り歩きを始めてしまう。
だからこそ、作者という概念は一般的に、言語の出自を保証する(コントロールできる)強い主体を想定した言葉とも言えるでしょう。一方ナボコフにとって、作者とはそうではないということです。情事を繰り広げながらも、決して相手を手中に収められない。
もうひとつの「借り物性」とは、ハンバートがロリータをたった一人の運命の女性とは決して思っていない、というドライな認識を指します。
ハンバートは、少女のなかでも特定の年齢層の、決して成熟していないからだを持ち、しかし無意識に成人男性を誘惑するような女の子を「ニンフェット」と呼び崇拝しています。背景には、自分が少年のころに経験した同世代の少女との未遂に終わった性行為の記憶があります。中年男性になってからもハンバートは、少女たちの中に「ニンフェット」という理想を探し続けます。
少女ロリータは主人公が電撃的に出会ったニンフェットでしたが、あくまで借り物の存在です。思い出の少女本人ではないという意味でも、数年経てば少女でなくなってしまう、という意味でも。ハンバートにとってロリータは数いるニンフェットの中で最上の少女であっても、ニンフェットの理想そのものではないのです。
では、作家が書く小説も借り物でしかあり得ない、としたらどうでしょうか。本当に書かれるべき小説ではなく、作家の前に現れた仮の伴侶。とうぜんここで浮かぶのは、本当に書かれるべき小説などあるのかという問いです。目の前の作品の向こうに、常にまだ到来していない理想の姿を重ねてみてしまうような状態。言い換えれば、決して満たされないことがわかっているのに求めてしまうという矛盾を抱えた状態です。
さきほどの「不安」がハンバートの方に宿った負荷だとしたら、「借り物性」はロリータに宿った負荷です。ナボコフは『ロリータ』で、こうした負荷を互いに持ち寄り、渡し合うような二者関係を描きました。それは儀式であり演技でもある営み=「情事」と呼ばれるにふさわしいものですが、一方で、あらゆる「親密さ」の条件でもあるように思えます。
言語との情事としての小説、という読み方から生じる連想はまだまだつきませんが、ひとまずこの辺で終わります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
