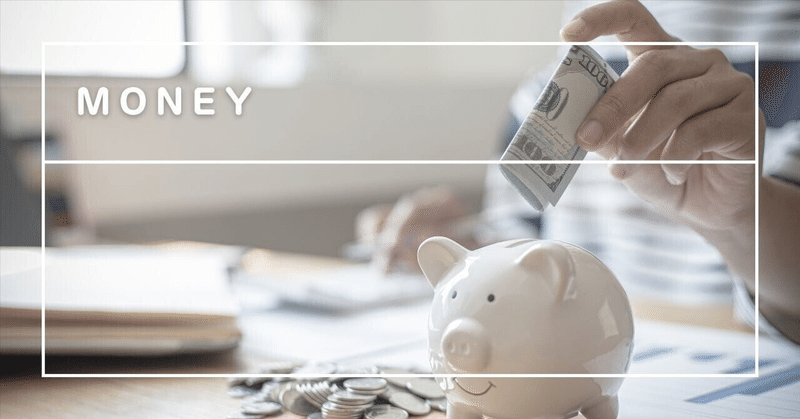
DIY音楽アーティストにとって、適した収益構造を探す、収益化スタイルリスト【概要ビジネス編】
DIY音楽アーティストにとって、アートをお金に換金する方法はいったいどのくらい現在存在しているのか、気になりませんか。僕は気になりました。
なるべく幅広く、全体的に網羅し、まとめてみたので、その内容を共有させていただきます。
1.大きく2つある、マクロな捉え方
まずは、全体像の捉え方についてです。
音楽では主に、表現/技術提供/教育/事業経営の4つの分野があります。
今回は特に、表現の分野におけるマネタイズについてフォーカスしますが、アーティストが技術提供をしてはいけないというルールはありませんので、まずはこちらを抑えていただければ、何か新しい突破口になるかもしれません。
講師、Mix師、などですね。
次に、こちらが今回の本題ですが、もう一方の捉え方について、表現者にフォーカスした内容です。
表現者には、権利/チケット/グッズ/ファンクラブという4つの分野の収入構造がある、ということです。
もうすでにご存知の方も多いかもしれませんが、改めてこれら4つを、詳しくリスト化していきたいと思います。
2.権利収入のタイプ一覧
多くありますが、以下にそれらを挙げていきたいと思います。
2-1.ストリーミングサービスへの音楽配信
これは言わずもがなですね。アグリゲーター、ディストリビューターを通して、音楽をプラットフォームに出品し、90秒以上再生されれば、権利収入が入る、というものです。
2-2.YouTubeのコンテンツ収益化
日本では、ボカロ界隈で特に流行っていますが、UGCを促し、それらの動画から収益を得るもの。例えばリリースした音源の、カラオケ音源をネット上で配布し、他リスナーやアーティストなどが、それらを用いてカバー音源を配信する事によって、著作者に還元される、という構造です。これらの登録に関しては、ディストリビューターで確認を行なっていただくのがベストだと思っています。
2-3.CD売り上げ
DIYだと、あまり全国流通というケースは少ないかもしれませんが、もちろんCDの売り上げは、グッズとしても考えられますが、著作者の権利収入でもあります。
2-4.TikTokなどのSNSからの権利収入
YouTubeとほぼ同じ形ですが、TikTokなどのSNSでの再生に合わせて、権利収入を得る、ということも可能です。Instagramも可能になっているようですね。Twitterは最近、アメリカの音楽会社から訴えられていました。。笑
2-5.ラジオやテレビでのオンエア
ニュース番組で流れたり、ラジオ番組で流れたりする場合は、それらの再生分が、権利収入となって、著作者に還元されます。おそらくオンエアされる前に何かしらの確認があると思いますが、Jasracなどに登録し、そこから分配分を受け取るという流れが一般的でしょうか。
2-6.YouTube広告収入
MVなど、YouTube動画が回ることで、広告費の一部を得られる、というものですね。こちらもメジャーと思います。(権利とは少し違うかもしれませんが似通っているのでここに含めています。)
3.チケット収入のタイプ一覧
3-1.コンサートライブ入場料、オンラインライブチケット
こちらもイメージが簡単な収益スタイルですね。チケットのうち、会場側への取り分以外が、基本的にはそのまま収益になります。
3-2.ライブ配信時の投げ銭
SNSなどで、ライブ配信を行った際に、リスナーやフォロワーの方から直接送られるチップですね。音楽系アーティストで投げ銭額が話題になったニュースは、最近は拝見したことがない気がしますが、コロナ禍の時はReolさんのYouTubeライブが話題になっていた記憶もあります。兎にも角にも、これも大切な収益源の一つですね。
ライバーの台頭も、もう昔の話になりつつあるような気もしますが、ライバー上がりでオンラインにファンを抱え、ショートでバズるアーティストも、よく拝見します。
4.グッズタイプの収益一覧
アーティストによって多岐に渡り、最も差別化されるのがこの部分ではないでしょうか?
4-1.ライブ会場でよく見かける王道グッズ
簡単なイラストやロゴがプリントされた、グッズ群ですね。グッズ制作ができるサイトやサービスも最近はありますね。Tシャツ、カップ、キーホルダー、タオル、など。
4-2.本格的なアパレルブランド
一部のアーティストは、本格的なアパレルブランド事業をされている方もいらっしゃいますね。DIYでどこまでできるのか、という感じですが、これは難しそうですが、やり甲斐もその分大きそうです。ブランディングに沿った展開が大事そうですね。
4-3.NFTリリース
NFTリリースについては、まだまだ詳しくはありませんが、古参アピールができるグッズ、という認識でいます。
また、一部では、ストリーム再生されたうちの数パーセントを受け取る、ということも可能だそうですが、相当なフォロワー数を抱えていなければ、まずNFTプラットフォーム審査で落ちそうなので、当分DIYアーティストにとっては、関係のないことのようにも思えます。
ネット上のファンの証、というような立ち位置でしょうか?うまくピースがハマれば、喜ぶファンが一定数いそうなのも、事実ではあるかもしれません。そういう意味では、ファンクラブの活用に代用できる印象も、個人的には持っています。
4-4.CD、レコード、ラジカセ等
先ほども挙げましたが、音楽を再生プレーヤーで聴く、という体験は、一部のファンの間では無くならないのではないでしょうか。ジャケットなども含め、アイテム感がありますので、大切なグッズの一つですよね。
4-5.詩集、小説
シンガーソングライターなどであれば、詩集や小説を販売するのも、粋な収益源になるのではないでしょうか。現に、そういったことをされている方もいらっしゃいますよね。
4-6.AudioStockなどのオーディオ市場出品、楽曲提供
AIの台頭が目前まで来ている中で、今後どれほどBGMのような物からの収益が上がるのか、定かではないですが、AudioStockなどに登録することで、動画編集者などに購入してもらい、収益を得る、ということも可能です。
Beatの売買もありますね。Hiphop界隈では主流です。
うまくアーティストブランドがはまっていれば、アーティスト性を尊重したアレンジ、などもパッケージとして同業者に売ることもできるでしょう。
5.ファンクラブ
ファンクラブは、そのままです。アーティスト自体にサブスクをし、特典を受け取るという構造。いかにお得感を感じてもらうかが、鍵となるのは間違いないですね。
顔出ししている系アーティストでないと、これはかなり厳しそう。
色々なプラットフォームがあります。
Twitterも最近、サブスクができるようになっていますね。
6.戦略的に組み立てたい
こうしてみてみると、あまり新しいマネタイズ構造はないんだなと感じましたが、いかがでしょうか。
必要なのは、音楽性/話題性/人間性のどの側面を押し出すのか、によって、適した収益構造を優先的に使用する、ということではないかと考えられるのではないでしょうか。
強みがキャラやルックスなら、ライブ配信から、音楽性なら、ストリーム配信から、話題性なら、広告収益から、にフォーカスするのが適していそうだなとは思いますが、、、
音楽アーティストはまず、音楽が何らかの形で売れてから(あるいは話題になってから)、グッズなどが売れるのだと思います。音楽が好きになってグッズを買う、って結構なファンですよね。
話題性/音楽性で何らかのリスナー増加→権利収入増加→ファンメイク(人間性キャラの売り出し)→グッズ収入/ライブ収入
という流れが、個人的には1番腑に落ちました。音楽アーティストならですが。権利収入だけで、ある程度の収益を得ている音楽家も一定数はいると思います。ただ、人気を得る、という点ではなかなか難しい印象もあったりします。
権利収入である程度収益を得る、というのが第一関門、ファンメイクをしてグッズなどが売れるようになる、が第二関門なのかな、、、
ただし結局どれも必要ではありそうです。補完的に作用し合っていると思います。
戦略的に絞りつつも、一つに依存せずに余裕をもつ、ということは、矛盾していますが、生活のためには大切そう。
収益化スタイルリストは、適宜更新予定です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
