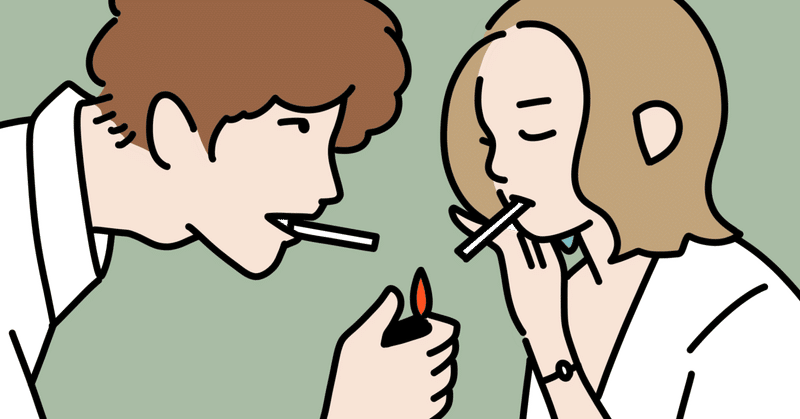
人に優しくしたその分だけ、優しさが戻ってくるように
かりんちゃんは、小学校でよく同じクラスになった。
家が近くてよく遊び、おそらく6年間で、一番仲良くしていた子だったと思う。リカちゃん人形で遊ぶことがすごく好きな、すごく女の子らしい女の子だった。
彼女のことが好きだったが、お母さんはもっと好きだった。とても優しくて、なんでもできる人。マドレーヌを手作りしたり、庭でアロエを育てて、それで火傷をしたときに塗布する薬を手作りしていた。
かりんちゃんのお母さんはいつも私たちに言っていた。
「人に優しくするのよ。何をされても、許してあげるようにしなさい。困っていたら真っ先に助けてあげてね。すごく大事なことなのよ。」
そして、手作りしたジャムを持たせてくれたり、私の前髪を切ってくれたりした。
私は、かりんちゃんのお母さんの前ではそのふりをしていた。一生懸命「かりんちゃんの一番の友達」を演じていたような気がする。
それでいながら、学校でかりんちゃんがからかわれたりした時、私は黙っていた。彼女はその外見や、スタイルの良さ、色素が薄い髪色なんかを理由に、よく仲間はずれにされていた。
でも、私は彼女を助けなかった。自分が標的になるのは嫌だったし、そこまでして助ける理由がないと思っていた。
そしてまた、彼女の家では優しい友達を演じた。
そんな私を、かりんちゃんはどう思っていただろう。私を、一番の友達と思ってくれていただろうか。
小学校はある一定の年齢になると徐々に、クラスに不穏な空気が流れ始めるようになる。それはどの世代も同じじゃないだろうか。なんとなく誰かをはばにしたり、からかったりすることで、集団意識を育んでいくような。
私の学年も例外ではなくて、私もそれなりに嫌な思いをさせられたり、それが怖くて目立つ子にひっついたりしていた。それでも、まだかわいいものだったとおもう。
中学にあがると、小さく燃えていた火種がガソリンに引火したように激しく広がった。他の小学校の子供達も加わり、その火の輪は大きくなった。そして不幸なことに、私は気がついたらその輪の真ん中にいた。
理由は、他の小学校から来たリーダー格の子の名前と、私の名前が漢字もそのまま同じということだった。
「この名前は私だけでいい。もう一人はいらない。」
そう言うコンセプトだった。その子はなにか、会社でも経営したらうまくいくんじゃないかな。人を集め、教え、自由に動かすことに長けていた。
シューズに画びょうが刺さっていることくらいはもう慣れた。でも、誰に話しかけても返事がない。挨拶をしても逃げられてしまう。そのうち他のクラスにまで噂は広まり、廊下を歩いても避けられるようになった。
そんなクラスの雰囲気に先生はなんとなく気がついていて、しかし彼は、そんなクラスメイトたちの肩を持つことを選んだ。
みんなの前で、私に友達ができないのは積極性がないからだ、と怒鳴ったり、忘れ物が多いことを叱った。
一度、とても悲しい思いをしたことがある。
忘れ物が多い私に、先生が言った。
「次に教科書を忘れたら、授業を受ける気がないとみなして教室から出てもらう。」
そして、私はやっぱり、また教科書を忘れた。
私は怖くなって、どうしようか考えた。隣のクラスに斎藤さんという子がいた。その子は小学生の時に一緒に花火をしたり、好きなミシンで遊んだりした仲だった。もしかしたら、その子が教科書を貸してくれるのではないだろうか、と私は思った。
おそるおそる、隣のクラスへ行き、ドアの前に立った。ゆっくりと開き、少し遠くにいる斎藤さんに声をかけた。
すると、彼女はぎょっとしたように私を見て、そのあと、睨んだ。ものすごい剣幕だった。
クラスの子たちも私に気がつき、ひそひそと言い出した。私は慌ててその場から立ち去った。そして急いでトイレで泣いて、教室に戻り、先生に怒鳴られて廊下に出され、もう一度泣いた。
私はそれから1ヶ月も経たないうちに、学校に行かなくなった。
新しい紺色の制服とリボン。革のかばんに、革靴。銀色の自転車。
小学校の時にあんなに憧れて、揃えたもの一式。いまとなってはどれも、クローゼットの中にあると思うだけでおぞましい代物に変わってしまった。
私はそれでもバカみたいに、何度も想像した。
あのリーダー格の子が私の肩に手を回して、笑ってくれている。他の女の子たちも、わたしに話しかけてくれる。教室移動も、更衣室も、ひとりぼっちじゃない。そんな世界を思い描いた。
◇
家族と校長先生に励まされ、最後にもう一度だけ登校してみたことがある。
とにかく覚えているのは、手も足も、頭も、すっかり冷え切っていたということだ。春だというのに、真冬みたいに唇が紫色で歯ががたがたと鳴った。
やっぱり、私と話してくれる人は一人もいなかった。きっとそう申し合わせているのだろう、私が絞り出したように「おはよう」と言っても、こちらを見ることもしなかった。
小学校でいっしょにバッタを捕まえた子も、プレゼント交換をした子も、いっしょに交通安全のポスターを描いた子も、うちの犬を見せてあげた子も、みんな。
そして私はそれに慣れていき、もう誰にも話しかけなかった。見ることも。
かりんちゃんは他のクラスだった。
友達がいっぱいいて、部活でも大活躍をしていた。先輩からも可愛がられ、男の子からもモテていた。
しかし、彼女はなぜか、いつも一人でいた。みんな、誰かと一緒にいたがるのに、かりんちゃんだけが一人で行動していた。
ある日、廊下を歩いていると向こうからかりんちゃんが歩いてきた。美人で、スタイルが良くて、色素が薄い髪。私は、そんなかりんちゃんを懐かしく思って、すれ違いざまに
「おはよう。」
と言ってしまった。おそらく、ほとんど聞こえないくらいの声だと思う。私の声は、本当に小さくなっていた。
言ってからひどく後悔した。聞こえていませんように、と願った。もう睨まれたくないし、無視もされたくない。だったら黙っていればいいのだ。
かりんちゃんは一瞬立ち止まって、私の顔を見た。そして、ゆっくり口角をあげ、にっこり笑った。
「おはよう!」
私はそれが聞けただけでも、この中学に来てよかったと思った。
◇
そのあと、私は転校した。友達がたくさんでき、部活を始めた。すべてが順調だったけれど、いつも絶対守っていることがあった。それは、どんな人にでも必ずあいさつをすることだった。
おとなしい子にも、いじめられている子にも声をかけて、どのグループにも属さない。
それは高校でも、大学でも続けた。
あいさつをしたのは「私はぜったいに無視をしない」と示したかったからだった。一人でいたのは「一人でいることは格好悪いことじゃない」と伝えたかったからだ。もし、誰かが、仲間外れにされて一人になった時、私を見て
「ひとりぼっちなのは自分だけじゃない。」
と思って欲しかった。
そんなこと伝わるのかな。伝わるわけないか。
たまに一人でいる自分を惨めに思ったこともある。恥ずかしいと思うことも。
そんな時は、あの日のことを思い出すようにした。廊下の向こうから歩いてくる一人の少女。
あの時、彼女に声をかけていなかったら、私はどうなっていたんだろう。
たぶんずっと、人におびえていたと思う。嫌われないかといつもびくびくして、人の機嫌をうかがっていただろう。一人になることを避けていただろう。
私は何度でも背筋を伸ばして、みんなに平等に声をかけた。一人で昼食を食べ、にっこり笑った。
心の中には、いつもかりんちゃんがいた。彼女のように勇敢になれるように。
時は経ち、大学生活も終わりに近づいた頃のこと。トイレから戻ると、私の広げたノートやペンの横に小さなチョコレート菓子が置かれていて、一緒に匿名の手紙が添えられていた。
差出人は同じ学部の生徒らしかった。その子はある仲良しグループと一緒にいたが、その中でなんとなく仲間外れにされていた。それでも一人になるのが怖くて、結局4年間仲良しのふりをしていたことが書かれていた。
「微熱さんのことをいつも遠くから見ていました。あんな風に、ひとりでも堂々といられたらいいのにな、って。
一度だけ、廊下ですれ違った時に、私を見て微熱さんがあいさつをしてくれたのが嬉しかった。自分に気づいてくれる人がいるんだって思った。微熱さんは本当に笑顔が似合っている人だね。ありがとうございました。」
今でもその手紙とチョコのパッケージを保管している。
もし、いつか、かりんちゃんに会えることがあったら、私もこんな風にお礼が言いたいと思う。
◇
かりんちゃんはリカちゃん人形で遊ぶことがすごく好きだった。いつか、私に聞いてきたことがある。
将来、素敵な人と結婚できるかな。
かりんちゃんは、「素敵な人」として、リカちゃん人形の公式な恋人であるマイケルだかジョージだかをイメージしていた。私は、その腹筋が割れた、浅黒い肌の人形を見ながら、
きっとできるよ。
と、あいまいに答えた。
でも、いまならわかる。かりんちゃんなら、必ずできるだろう。彼女はだいいち、とても美人だし頭がいい。そしてとても優しい。
きっといい会社に勤めて、イケメン上司に見初められているんだろう。仕事でミスをしてしまって、屋上で少し泣いている時なんかに、その上司がきて、タバコを差し出してくれたりするんだろう。
いや、かりんちゃんはタバコっていうタイプじゃないか。どうだろう。
なんにせよ、彼女には幸せでいてほしい。人に優しくしたその分だけ、きちんと優しさが戻ってくるように。その大きな器がいっぱいになるほどの優しさで満たされるように。そう思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
