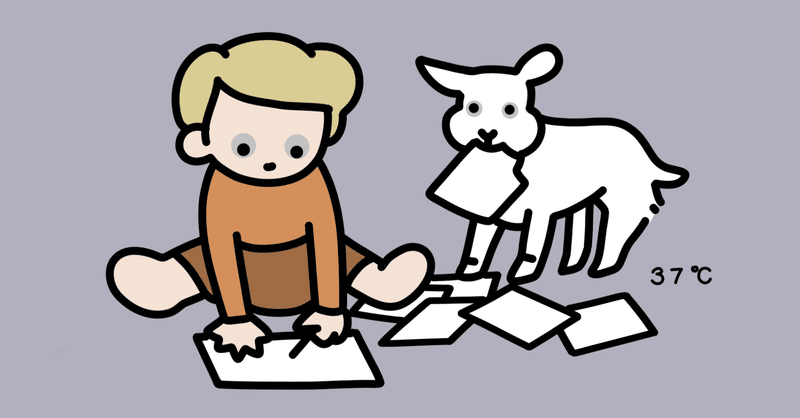
絶対にしてはいけない選択をした私はいま、とても幸せである
17歳の春に母を説得して父と離婚させた。
それは、同級生のRちゃんがきっかけだったと思う。Rちゃんの家はお父さんとお母さんが全く口をきかない。居心地が悪いから、お母さんを説得して離婚してもらった、というのだった。
「すごく楽になったよ。信じられないくらい。今まで経験したことがないほど、私生活が穏やかなの。」
私はそれを聞いて思った。
うちも、離婚してもらおう。別れた方が二人のためだ、と。
Rちゃんの家の事情とは同じではないし、ここではあまり詳しくは書かない。
とにかくそれが、私のしたおそらく最大で究極の選択で、ある意味、絶対にしてはいけない選択だった。両親が離婚してからそのことに気づいた。裁判所で、知らない男の人みたいにスーツを着た父を見た時。母と別の街に引越して、恐ろしく狭いアパートに住むことになった時。
ようやくそのことに気づいたのだ。
◇
小さな頃から、父は私に
「お前はすごくできる子だ。」
と言った。
勉強もできる、スポーツもできる、学級委員もできるし美術も音楽もできる。なんでもできるすごい子だ、と。
「いわゆる、持ってるって言うタイプだ。だから、なんでもできる。今はできないことでも必ずできるようになる。」
そしていつもこの言葉で締めくくるのだった。
「頑張れ。」
私が勉強できたのは小学校までだし、足が速かったのも他の子より早く生まれて体がおおきかったからだ。中学では、ドベから数えたほうが早かった。学級委員なんて面倒を押し付けられてしただけだし、ピアノはいつも先生にため息をつかれていた。
でも、絵だけはたしかに好きだった。上手だったと思う。
保育園の時に好きになって、小学生のうちはよく描いた。描いている私を横からのぞいては、父が言った。
「お父さんも頑張ってる。お前も頑張れ。」
私は父のその「頑張れ」がすごく嫌いで、
こんなに頑張ってるのに、まだ頑張らないといけないの。
と思っていたこともあるし、
あんたが頑張ってることは、私とは何の関係もないんだよ。どうして、あんたが頑張ってるからって私まで頑張らないといけないの。
とも思った。
ある時、一度、大声で怒鳴りながら聞いたことがある。「才能があるある、って。何が根拠でそんなこと言うわけ。」
ちょうど、テストで落第点を取り、部活も行かなくなって、ピアノもやめた頃だった。大好きな絵も描かなくなった。
父は少し悲しそうな顔をして、それでも懐かしそうに話した。保育園の頃に私が描いた絵について。たしか、うさぎの絵だった。他の誰よりも上手く描けていた。
「すごく特殊な色の紙を選んでいたんだよ。保育園児が選ばないような色の」
それを見た時、この子は特別な子になると思った、というのだ。
私は父が、そうやって私を過大評価し、褒めるのが大嫌いだった。
父は私を知らないだけだ。なにも出来ない子供を産んだと、認めたくないだけだ、と思った。
◇
母を父から離して、13年間ものあいだ、私は父とは一切連絡を取らなかった。父がどうしていたのか、いきなり空っぽになった家をどのように片付けていたのか、毎日何を食べていたのか、どんな車に乗っていたのか、何も知らない。
そういえば、父は車が好きだった。
子供がいてお金がなかった頃はいつも、フォルクスワーゲンのビートルという車に乗りたいと思っていたらしい。毎日、その車の写真を見ては、いいなあ、乗りたいなあ、と憧れていた。
「離婚して、子供がいなくなって、金がたくさん貯まるようになったとき。ビートルなんて、実は全然乗りたくないって気づいたんだよね。」
再会してそう話す父は、とても小さくて退屈な中古の軽自動車に乗っていた。父らしくない。車だけはあんなにうるさかったのに。
13年ぶりに会った私たちは、何も話すことがなかった。私たちに共通していた時間は、すべてあの選択につながっている。最悪の選択。
自転車に初めて乗ったことも、誕生日にチキンを食べたことも、クレヨンしんちゃんが好きだったことも、もうテーブルの上に持ち出してはいけないタブーになってしまった。
それでも。
それでも、私の中に流れる血は、父のその顔や匂いや、細くなってしまった首なんかをよく覚えていた。心は確実に溶けていくものとして、緩やかに形を変えた。それは、肌の上を冷たい雨が流れていくように心地よくて、優しいのだった。
おそらく私は、父と仲直りのようなことをしたかったのだと思う。父にプレゼントを贈ろうとした。
誕生日、あるいは父の日。クリスマス。
「プレゼントなんて別にいいよ。会ってくれるだけで」
父は頑なに何度もそう言った。
反対に私にたくさんの服や画材を買ってくれた。
そう、画材。
父は若い頃、漫画を描いていた。
好きで描いていたわけじゃない。会社に頼まれて、社内紙のための小さなページを任されただけだ、と父はいう。
それでも私は、父の漫画がとても好きだった。
工場勤務の社員が主人公で、大卒の同期と高卒の自分のキャリアの差を自虐的に描いたものだった。父は工場員だった。
「これが結構ウケるんだな。」
と、本物の漫画家みたいに朝方まで描いていた。
だから父は、画材にとても詳しいし、いい店を知っている。そこへ一緒に行き、一日中見回った。
オイルパステルがずらりと並ぶのを見ながら、父がふと、つぶやいた。
「微熱は今、どんな絵をかくんだろう。」
私は父に絵を贈ることにした。3ヶ月に1度会うごとに、一枚ずつ。
その絵は、動物の絵だった。羊が佇んでいたり、あひるが首を伸ばしていたりするのだった。
それらを色鉛筆で描いている時、声が聞こえた。たくさんの声。いつもそうだ。私が画家を目指して絵を描き始めた時から、その声はいつもつきまとうようになった。
それは私のよく知っている声だった。学校の先生だったり、近所の人だったりした。友達のお母さんだったり、先輩だったり、大学の教授だったりした。
その声はこう言っていた。
あんたなんかにできるはずないよ。
画家というのは難しいんだから。
一握りの、才能がある人だけがなれるんだよ。
わたしは?
私はなれないの?
私はいつも、聞いてみるのだった。するとその声は決まっていう。
あんたじゃ、なれないよ。
それが、私が今まで信じてきた言葉だ。だから私は、32年間絵が好きで、32年間絵を諦めてきたのだった。
でも、今回は諦めないことにした。どんな声が聞こえても、手を動かしてみることにした。
ストロークは小さく。力を抜いて丁寧に。
少しずつ紙の凹凸を埋めていく顔料。それが層をなして、透き通るように濁っていく様子を見届けることにした。
父が喜ぶ顔を想像しながら、その絵を完成させた。3か月かかった。
私は緊張しながら父に絵を渡したとき。
父は私から絵を受け取り、ただ、絵を目の高さまでもってきて、じっと見つめた。
そして、何も言わずに、鞄にしまった。
私はもっと喜んでくれると思っていたので、なんだか拍子抜けした。少し自信を失ったと思う。やっぱり父も同じなのだ。私にはできない、そう思ったんだろう。
それから、また絵が描けなくなった。
私は絵を途中でやめることに慣れていた。勇んで描き始めても、途中でばかばかしくなってやめる。だって、どうせ画家になんてなれないんだから。一握りの人間ではない。才能がないから。
絵を描かずに過ごしていたら、3か月なんてあっという間だ。また父と会う日がきた。
喫茶店でチーズトーストとプリンアラモードを食べながら、私は、絵が途中でなかなか完成しないので、もう諦めて捨てようと思う、と話をした。
父はどことなく悲しいような、懐かしいような顔をして話した。
保育園の頃に私が描いたのは、ピンク色のうさぎだったこと。それを見た時、この子は絵を描く人になると思った、と言う話だった。
「選んだ紙がね、すごくいいんだよ。小さな子供が選ばないような色なの。」
そして、私にメニューを渡した。食べたいものを食べなさい。お父さんといるときは、何をどれだけ食べてもいいから、と言う。
「画家というのは難しいよ。ほとんどの人にはできないだろう。でも、お前ならできるよ。生きてる絵を見殺しにするなんてもったいない。完成させて、生かしてください。」
そして微笑んだ。
「頑張れ。」
私はその時から、父が私を信じるその方法で、自分自身を信じてみたいと思うようになった。父が私に期待をするように、私がかつて最も嫌った方法で、私も自分に期待してみたいと。
「頑張れ。」
なぜなら、今まで他の誰も、父ほど上手なやり方で私を勇気付けたことがないから。
私はそう考えた時なぜか、自分がとても幸せであるような気がした。
◇
私が両親を離婚させた。あの岐路に立った時、こちらだ、と安易に指をさした自分をずっと恨んできた気がする。
父は私がひどいことをしたと知っているし、私は父がしたひどいことを知っている。
私たちの共通点は、そのときできることをしていたということだけだ。自分にできる最大のことをしていかなければ、崩れてしまいそうだったから。滅びていく地面の上で、必死だった。それだけだった。
あの選択をしてから15年たった今。
それでも、ひとつの新しい家族のカタチをつくった選択であったと、思えるようになった。母は母で、父は父で。その間を行き来する、二人をつなげる子として。
それは、一緒に生きるのが本当に難しかった家族の、もう一つ先の新しいカタチだった。
その日、父と別れて家に帰ると珍しく母が仕事から帰って来ていた。
二階に行こうとする私に、そんなに急いでなにをするの、と聞くので
絵の続きを描いて、完成させてくる
というと、覚えてるかなあ、と母は言った。
「保育園のお絵描きの時間にね、あんただけが桃色のうさぎを描いたのよ。他の子はみんな、何を描いているかわからないような絵だったけれど、あんたのははっきりと、うさぎってわかるの。」
どうだったかなあ、と私は言った。
「女の子はピンクが好きだね。だから、普通はピンクの紙を選ぶけど。そうじゃなかった。大好きなピンクが良く映えるように、あえて草色の画用紙を選んで描いたんだよ。私はあれを見た時、この子は絵を描く人になると思った。」
母は、覚えてないでしょう、と得意になってこの話をするのだった。私は、全く同じ話をちょうど、父からしてもらったばかりだと知られないように、できるだけとぼけた様子で頷いておくのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
