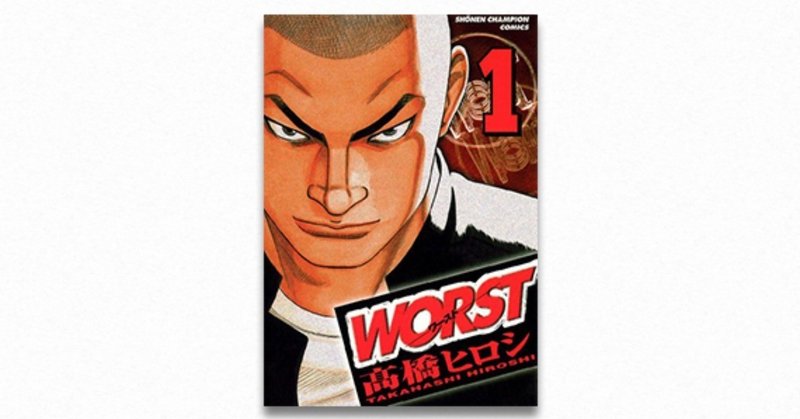
宇野常寛 月島花は坊屋春道を超えられたか――クローズ/WORSTが描いた男性性の臨界点(PLANETSアーカイブス)
今朝のPLANETSアーカイブスは、宇野常寛による髙橋ヒロシ論をお届けします。傑作不良漫画『クローズ』の続編として描かれ、12年の歳月をかけて昨年完結した『WORST』。坊屋春道なきあとの鈴蘭を描いた本作を通じて見えてくる『クローズ』が描いた男性性の臨界点とは。(初出:ダ・ヴィンチ2013年11月号)
※この記事は2015年3月16日に配信された記事の再配信です。
〈「オレはおまえらと同じで/よそを放り出されて鈴蘭へ来たただの勉強ぎらいさ/ただちょっと違うのは/オレはグレてもいねーしひねくれてもいねえ!/オレは不良なんかじゃねーし悪党でもねえ!!〉
髙橋ヒロシによる90年代を代表するヤンキー漫画『クローズ』は、主人公・坊屋春道の自分は不良「ではない」という宣言ではじまった。引用したのはそんな彼=春道が物語の冒頭、転入してきたばかりの高校で貴様は何者だと問われたときの返答だ。舞台となる架空の高校・鈴蘭男子高校はとある街にあるいわゆる「底辺」高校だ。不良少年の巣窟である同校では、その社会の「覇権」をめぐって常に派閥抗争が繰り広げられている。しかし所属する生徒の大半が不良高校生である鈴蘭は常に群雄割拠の状態にあり、もう何世代にもわたり「統一政権」が生まれていないのだという。世代を超えて数えきれないほどの不良少年がその統一を夢見て入学し、3年間をケンカに明け暮れて過ごし、そして鈴蘭統一の志半ばで卒業していく……そんな無限ループが永遠に続く世界に、春道は転校してきたのだ。
春道は圧倒的な戦闘力を見せつけ、彼に戦いを挑む鈴蘭内の各派閥の領袖たちをことごとく破ってゆく。その勇名はやがて彼を他校との抗争の中に導いてゆくが、春道はその挑戦者たちをもことごとくほぼ初戦でノックアウトしてゆく。なぜ春道は「強い」のか。
答えは既に春道自身の口から語られている。春道は「グレてもい」なければ、「不良なんか」でもないからだ。
坊屋春道は劇中でほとんど唯一、鈴蘭の統一など不良少年社会での権力の獲得に興味を「示さない」人物として描かれている。そう、「グレてもいない」し「不良でもない」春道は単に「勉強が嫌い」で「ケンカが好き」なだけで、決してアウトローであることに意味を見出していないのだ。したがって「鈴蘭のてっぺん」にも「大人社会への反抗」にも興味がない。彼が戦う理由はふたつ、仲間を守るためと自分の快楽、面白さのためだ。そんな春道に、鈴蘭の統一や不良少年社会での覇権を夢見る少年たちが次々と挑戦し、そして敗れていくことで物語は進行する。
これが意味するところは何か。髙橋ヒロシがここで描いているのは、ヤンキー漫画がその数十年の歴史の中で育んできた男性ナルシシズムの更新、「カッコイイ男」のイメージの更新だ。春道は不良少年たちの世界──思春期の数年間だけそこに留まることができるモラトリアム空間、疑似的な社会──の中での自己実現に拘泥する少年たちを愛情をもって退ける。「不良」である彼らは一般の社会から疎外されたアウトローであるという自覚を持ち、それゆえにもうひとつの社会での自己実現を権力奪取というかたちで目論む。しかし、そんな自己実現に全く興味を示さない春道に敗れることで、彼らはことごとく転向してゆく。疑似社会での期間限定の自己実現ではなく、ケンカすることそれ自体を楽しみ、魂を燃焼させることに美的な達成を見るという春道の示したモデルに転向してゆくのだ。(劇中で春道と互角以上の戦いを展開することができたのは、同様に権力闘争に興味を持たない林田恵・通称リンダマンのみだ。)
ここで髙橋が坊屋春道という男に託したのは、これまでのヤンキー漫画の美学の延長線上にありながらも、少なくとも従来の意味では「グレてもい」なければ、「不良なんか」でもない男の理想像、「大人社会への反抗」に意味を見出し、アウトローであることにアイデンティティを見出さ「ない」男の理想像に他ならない。だからこそ、この物語では従来のモデルの不良少年が春道の影響下に転向してゆくという物語が描かれたのだ。
そんな坊屋春道の最後の戦いは、全国的な勢力を誇る不良少年グループ「萬侍帝國」の幹部・九頭神竜男とタイマンだ。不良少年社会=疑似社会の頂点に君臨する九頭神はまさにこの物語で描かれてきた古い、従来の「不良」を代表する存在だ。そう髙橋ヒロシは物語の結末に、春道のこれまでの戦いとは何だったかを総括し、改めて読者に示すエピソードを配置したのだ。
タイマンの前半、春道は九頭神に対して劣勢を見せる。戦いを見守るのは春道の後輩・花澤(通称ゼットン)と九頭神の舎弟・トシオだ。呑気にタイマンを見守るゼットンに、トシオは問いかける。「おまえアニキ分がやられているのによくそんなもん食ってられるな!」と。しかしゼットンは動じない。それどころか「オレはあの人(春道)の子分でも舎弟でもない」と告げる。これは間違いなく、春道がその登場時に述べた自己規定の言葉と対応したものだ。「不良」でもなければ「グレて」もいない春道の後輩は「子分」でも「舎弟」でもないのだ。そしてゼットンはトシオに告げる。「九頭神竜男が最強の男なら坊屋春道は最高の男よ! たかが最強程度で最高に勝てるわけがねーだろうが!」と。
「最強の男」とは何か。それはアウトローたちのもうひとつの世界での自己実現=権力奪取を夢見る少年たちの到達点だ。現実の社会と歴史に生きる証を見つけられなくなった代わりに、もうひとつの社会ともうひとつの歴史を生きることで自己実現を果たそうとするアウトローたちの到達点だ。対して「最高の男」とは何か。それは「最強の男」が目指す疑似社会での自己実現に背を向け、いま、ここの一瞬の魂のきらめきに美的な達成を見出す生き方だ。何かのために戦う(ケンカする)のではなく、戦うこと自体が目的なのだ。ある自己実現のモデルを追求し、その中で強弱を競い勝ち抜いた人間が「最強」だとするのなら、最初からそのモデルの限界を前提とし、別のモデルを追求している人間が「最高」なのだ。「最強」が「最高」に「勝てるわけがない」のはそのためだ。
『クローズ』の世界にはたとえばほとんど「大人」と「女性」が登場しない。そう、彼らには乗り越えるべき「父」も、守るべき「女」も存在しないのだ。かつての男性的なもの=最強の男が通用しなくなった新しい世界の、あたらしい男性性のモデルを提示すること、それが『クローズ』の主題であり坊屋春道が体現した「最強から最高へ」の変化なのだ。(そして髙橋ヒロシの手を離れ、オリジナルのストーリーが展開する前日譚の映画「クローズZERO」シリーズはまさに、主人公が父を乗り越え、ヒロインを救い鈴蘭統一を目指す「最強の男」の物語として描かれ、春道の転入直前の春に主人公が鈴蘭を統一を果たせずに卒業するシーンで終わる。映画版の制作者たちは、髙橋ヒロシが坊屋春道という主人公を通して『クローズ』が提示した世界観の本質を正しく理解し、新旧の主人公を対照的に配置したのだろう。)
そして物語は春道の影響下に「最強」から「最高」へとその生き方を変化させていった少年たちの卒業を描いて幕を下ろす。ある者は大工、ある者はボクサー、ある者はミュージシャン──それぞれの夢を現実社会の中に見出し、彼らは卒業していく。たとえその夢が実現できなくとも、夢を追うその過程に快楽を見出すことができれば、彼らは「最高」でいられるだろう。しかし、物語のエピローグは読者をあたらしい迷宮へといざなっていく。当の春道だけが、「最高の男」の頂点に立つ坊屋春道だけが「卒業」することができず、留年し鈴蘭高校に留まったことがエピローグでは描かれるのだ。
そう、この物語では坊屋春道だけが「卒業」することができなかったのだ。もっと言ってしまえば春道だけが「成長」することができなかったのだ。なぜならば、『クローズ』における成長=卒業とは「最強の男」的な生き方からの「卒業」であり、登場した時点で既に「最高の男」である春道にはその必要がなかったからだ。
では、春道はその後どこに向かっていけばいいのだろうか。この巨大な問いに立ち向かったのが、『クローズ』の続編である『WORST』だ。
ここから先は
¥ 540
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
