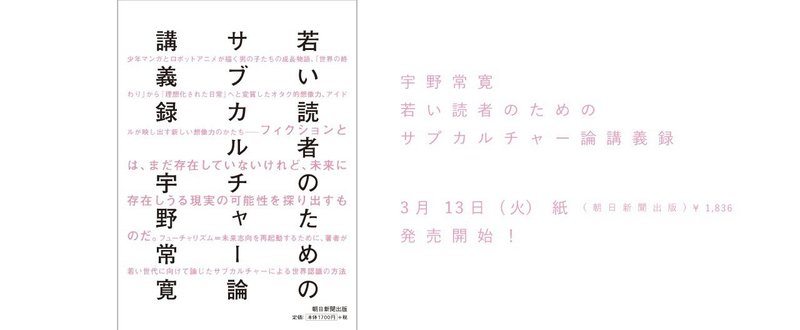
【書籍化記念・無料公開】宇野常寛「若い読者のためのサブカルチャー論講義録」第3回 震災後の想像力とアニメの未来
本メールマガジンで連載していた宇野常寛の『京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 』が、『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』として発売されました! 刊行を記念して毎週月曜日に全4回にわたり、書籍の一部を公開します。
第3回のテーマは「震災後の想像力とアニメの未来」です。オタクがメジャー化し、国内アニメのトレンドがセカイ系から日常系へと移り変わるなかで起きた震災。「終わりなき日常」の破壊がもたらされ、「世界の終わり」が終わった後にアニメーションは何を描くべきなのでしょうか。
※配信記事一覧はこちら。
【書籍情報】
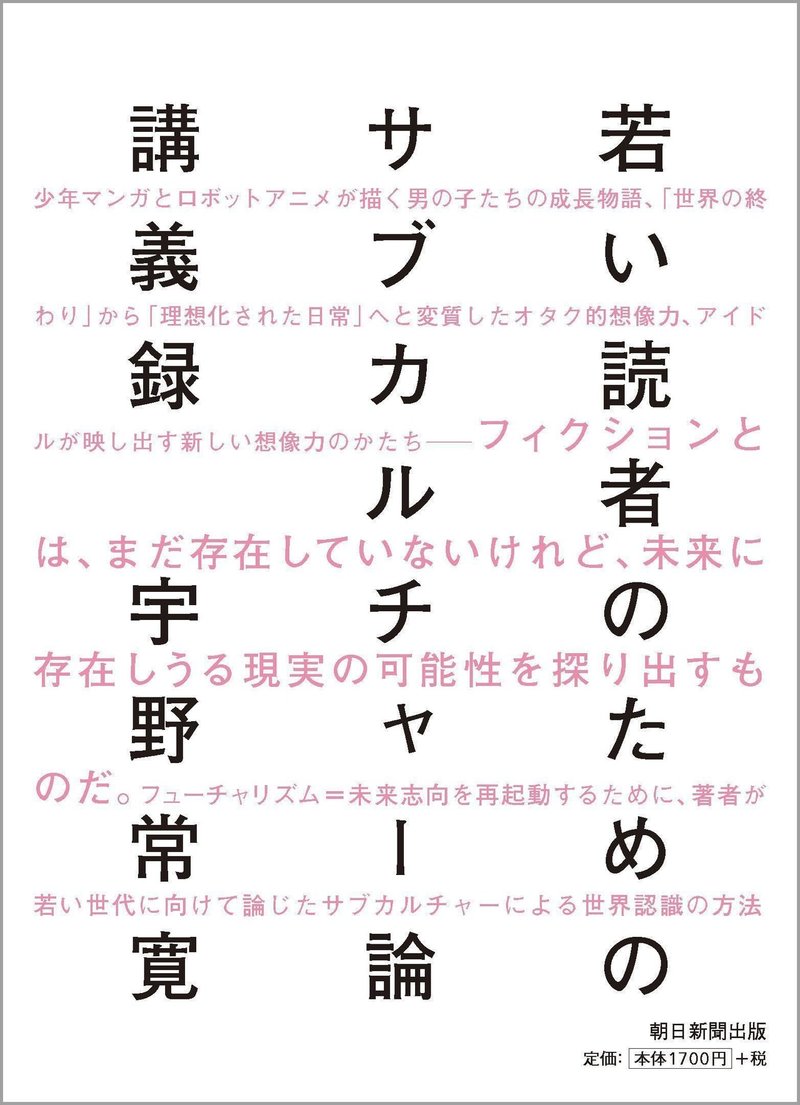
宇野常寛『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』発売決定!
紙 (朝日新聞出版) 3月13日(火)発売/電子(PLANETS)近日発売
Amazonでのご購入はこちらから。
オタクのカジュアル化と『電車男』のヒット
ここまでは、いわゆるセカイ系から日常系への国内アニメのトレンドの変化について解説してきました。そして、これと並行して起こったのが「オタクのメジャー化」です。
『電車男』はみなさん知っていますか? ……だいたい知っているようですね。この作品がブームになったのは二〇〇五年頃です。もともと二〇〇四年に立てられた、2ちゃんねるのある種のネタスレですね。モテないオタク男性が電車内でのトラブルをきっかけに歳上のリア充女性と知り合いになり、そのことを2ちゃんねる上で書き込んで板の住人たちの応援を受けながら交際にまで発展していったという経緯がリアルタイムで報告され、それが2ちゃんねるの外側でも話題になっていく、という「事件」にまで発展していった。もちろん、どこまでが事実で、どこまでが創作かはわかりません。当時の2ちゃんねるとその周辺は、こうした虚実入り混じった感覚を楽しんでいた側面が大きかったと思います。
そして、この「電車男」というスレッドは書籍化を経て一気にインターネットの外側にも紹介されるようになっていって、翌二〇〇五年には映画化・ドラマ化もされ大ヒットしました。
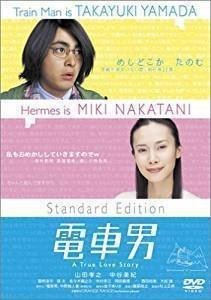
▲『電車男』
このとき『電車男』はインターネットのオタクカルチャーと、オタクたちのライフスタイルを世間に紹介する機能を負っていたと思います。そしてこのとき主人公の電車男は「不器用でモテないのだけど実は心の優しい男の子」として描かれているわけです。これは幼女連続誘拐殺人事件の頃には絶対に考えられなかったことですね。この時期ようやくオタクというものが差別の対象ではなく、単にありがちなキャラのひとつとして世間で受け入れられるようになり、マンガやアニメがカジュアルなインドア系の趣味のひとつとして市民権を得たと言えるでしょう。『エヴァ』以降の第三次アニメブームを経てオタクという存在が量的に拡大していった結果として、メジャーなものになっていった。この流れと連動して、アニメというものの中心が、「ここではない、どこか」のロマンを描くことではなく、「いま、ここ」の理想を描くことへと変わっていったわけです。それがセカイ系から日常系への流れでもあり、涼宮ハルヒが素直になっていく過程でもあるんですね。
これは余談ですが、僕は以前勝手に「涼宮ハルヒシリーズ」の完結編を考えたことがあるんです。もちろんタイトルは『涼宮ハルヒの敗北』です。ある日ハルヒは、「あれ? 私よく考えたらいま満たされてない?」「これでキョンと付き合えたらもう何も望むことなんてないんじゃないか?」ということに気づく。なぜなら、自主映画制作もSOS団の合宿も学園祭のバンドもどれも楽しくて、気がついたらUFOにも超能力にも興味がなくなっていたからです。
そして十年後、ハルヒはすっかり普通の主婦になっていて——もちろん旦那さんはキョンではありません——「スッキリ‼」を観ながら「このメガネのコメンテーターうざいな」とか思っている。そういう小市民的な生活に満足して、ある日シーツとかを干しながら「私、あの頃は友達がいなかったからUFOとか言っていたんだな」ということに気づく、というお話です。
作者の谷川流はここ最近ずっと『涼宮ハルヒ』シリーズの続刊を出せておらず、完結のメドも立っていません。それはなぜかというと、『涼宮ハルヒ』のテーマだったものの答えをすでに作品内で自己完結させてしまっていて、しかも事実上『涼宮ハルヒ』のテーマは京都アニメーションが受け継ぎ、『らき☆すた』や『けいおん!』のなかで答えを出してしまっていますからね。
『マクロス』の光景を現実化させてしまった東日本大震災
しかし、です。よく考えてみてください。『けいおん!』まで来ると、ちょっとかわいいガールズバンド五人組のリア充な毎日が描かれているだけなわけですが、それって本当にわざわざアニメで描く意味があることなんでしょうか?
要するにセカイ系から日常系への流れは、同時に戦後アニメーションの自己解体の作業でもあったわけです。
この戦後アニメーションの「終わり」を体現する映像があります。ちょっと観てみましょう。
『DOCUMENTARY of AKB48 Show must go on 少女たちは傷つきながら、夢を見る』です。
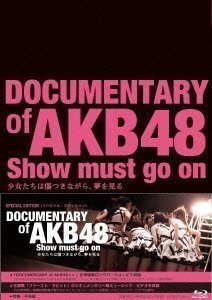
▲『DOCUMENTARY of AKB48 Show must go on 少女たちは傷つきながら、夢を見る』
これはAKB48のドキュメンタリー映画『DOCUMENTARY of AKB48』の二作目(二〇一二年)です。東日本大震災直後の二〇一一年六月にAKBが岩手県の避難所を訪問をしたときの映像です。AKBは震災から五年間ほどかなり頻繁に、被災地訪問をしていました。この映像が撮影された当時、被災者の人たちはまだ全然帰宅できておらず、仮設住宅で避難生活を送っています。なので、仮設のライブ会場の一番後ろで、救援活動に来ていた自衛隊の人たちが警備に当たっているわけですね。
みなさんは西日本に暮らしているからあまり実感が湧かないかもしれませんが、東日本大震災では二万人近くの方が犠牲となり、約五年経ったいまも仮設住宅での生活を余儀なくされている人たちがいます。そんな大災害を被った地域にアイドルが慰問に行き、軍隊が警備している。これはほとんど『マクロス』の世界ですよね。
僕はこれを見た瞬間に「あ、戦後アニメーションって終わったんだな」と思ってしまった。戦後アニメーションの想像力に、現実が思いもつかないかたちで追いついてしまった。まさに八〇年代の若者が夢見ていたような「終わりなき日常」の破壊が起きてしまって、廃墟にアイドルと軍隊がんでいる。現実が、アニメを追い越してしまったわけですね。
かつてバブル経済の崩壊以前には、まだ「終わりなき日常」という感覚にリアリティがあったわけですが、実際には終わらない日常なんてない。「終わりなき日常」とは要するにバブル経済下の病のようなものであった。そのことを僕らに強烈に突きつけてくる映像だと思います。
しかしその一方でこのドキュメンタリー映像が証明しているのは、震災がもたらしたものは決して日常性の「断絶」ではなかったということです。ここで描かれている「現実」は明らかに八〇年代の若者が夢見ていたような「世界の終わり」とは違うんです。彼らは、ある日突然核戦争が起こって、スイッチのオンとオフが切り替わるように日常が断絶してスリルとロマンに満ちた非日常の世界がやってくると思っていた。ところが実際に大災害がもたらしたものは、決して日常の断絶ではなくて、むしろ日常と非日常の混在です。災害の直後から日常性は否応なく徐々に回復していく。しかし世界は災害前とは確実に異なっている。傷跡があちこちに残っている。これは震災のときに東日本にいた人にはよくわかる感覚だと思います。あの、大きな余震が断続的に続き、信憑性の疑わしい放射能についての情報が際限なく飛び交うあの状況は、まさに否応なく回復した日常のなかにノイズのように非日常が入り込む感覚だったと思います。それは決して、かつての「世界の終わり」のイメージのようにスイッチのオンとオフが切り替わるようなものではない。そのことを、この映像はよく表しています。そして、実際に東北の被災地の復興は充分には進んでいませんし、帰宅できていない人々もたくさんいます。AKB48の慰問も、断続的に進んでいます。
〈現実=アイドル〉が〈虚構=アニメ〉を追い越した
こういった感覚は、アニメとインターネットの関係にも言えます。アニメを含めた映像は原理的に虚構のなかに閉じている。作家が演出し、編集した作りものを視聴者はただ受けとることしかできない。しかし、インターネットは原理的に半分は虚構だけれども、半分は現実に接続してしまっている。どれだけ作り手が虚構の世界を完璧に作り上げても、受け手という現実がそれを打ち返すことができる。ニコニコ動画にコメントがつくように、虚構がそれ自体で完結できない。双方向的なメディアであるインターネットは、原理的に虚構のなかに完結できず、現実に開かれてしまう。
震災後の日本に出現したのは、まさにこの感覚だったと思うんですね。「ここではない、どこか」、つまり完全な虚構に入り込んでしまうのではなく、現実の一部が虚構化している。日常のなかに非日常が入り込んでいる、とはそういうことです。
この二〇一一年頃は、アニメからアイドルへと若者向けのサブカルチャーの中心がはっきりと移行していった時期に当たります。
最近では『ラブライブ!』『アイドルマスター』などが代表的ですが、アニメ市場はアイドルものが席巻するようになっています。いまのアニメは良くも悪くも、現実のアイドルブームを後追いする存在になってしまっているんですね。
これはある意味、アニメのような作り込まれた〈虚構〉の敗北だと思います。いまはインターネットという双方向的メディアがあり、〈現実〉とつながってしまっている。みなさんはYouTubeを五秒ぐらい検索すれば、世界のどこかで起こっているちょっとぶっ飛んだ現実や面白い現実に出会えるわけですよね。そうなると、わざわざ作家の想像力で作られた虚構って、相対的に需要が下がらざるをえない。面白い現実に出会うためのコストが百分の一とか一万分の一とかになってしまっている。いままで〈虚構〉でしか担えなかったもののかなり多くの部分が、〈現実〉に奪われてしまったわけです。アニメからアイドルへのサブカルチャーの中心の移動というのはその一側面で、情報環境的には不可逆の現象だと思いますね。
「世界の終わり」が終わった後に
アニメーションは何を描くべきか
ではそんな状況でいまのアニメーションがどうなっているのか、という話を最後に少ししたいと思います。
たとえば『進撃の巨人』について考えてみましょう。原作マンガは震災よりも前、二〇〇九年に連載を開始していますが、わかりやすく昔のゴジラとか、東宝特撮の影響を強く受けているんですね。そういった想像力が蘇ってきた理由は何だろうということを考えると、おそらくは僕たちの生を支配している巨大な力の「見えづらさ」にあるのだと思います。グローバル経済もそうだし、地震や原発もそうです。そして、グローバル経済といってもその実体が何なのかということは具体的にはわからない、というか規模的に実感することが難しいし、そもそも放射能は見えない存在です。これがたとえば、七十年前の戦争のようなもの、たとえば国家同士の総力戦のようなかたちを取っていれば、もっと見えやすかったはずです。いま、私たちは自分たちを支配している巨大なものをどう捉えていいかわからなくなってる。目に見えない巨大な力に大きく左右されるんだけど、具体的にそれをどう解決したらいいのかわからない、敵の姿がわからない。そういう感覚が「正体不明の巨人に襲われている」という設定に重ね合わせられていると思うんです。だから結果的にですけれど、『進撃の巨人』には震災後の感覚がすごくあると思います。まあ、それは物語序盤の話で、単行本十巻目くらいになると壁のなかの人間関係の話になって、当初のテーマ設定の面白さはしだいに失われつつあるんですけどね。残念だけれど、作者が自分で設定したハードルを超えられなかったのだと思います。
あるいは以前この授業でも取り上げた『銀魂』の最近の展開も面白いですね。この作品は以前お話ししたように、言ってしまえば戦後の消費社会を一周回って肯定する、というのがテーマだったわけです。もう個人の人生を歴史が意味づけてくれる時代は終わった。それは受け入れよう。しかし『宇宙戦艦ヤマト』『機動戦士ガンダム』のように架空歴史に逃避することも、すべてを忘れて『うる星やつら』のように生きることもできない人たち——生き延びてしまった維新志士と新選組の物語だったわけです。そして主人公の銀時の選択は、『うる星やつら』的な日常を守るために時折侵入してくる政治的なもの——その偽りの平和を告発するテロリストと戦う、というものです。つまり、普段はギャグ編で何でもない日常の戯れを描いていて、ときどきシリアス編でその日常を守るために銀時たちが大活躍する。
しかしこのバランスが最近は完結に向けてずいぶんと「政治化」していっています。要するに、テロリストたちとの対決のエピソードが全面化して、ほとんどギャグマンガとしての側面がなくなっている。これはやはり現実世界で震災が起こったり国際情勢が緊迫化しているなかで、二〇世紀的なイデオロギー闘争とは別の語り口で自分たちの世界のことを考えなければいけない、という意識の表れではないかと思います。ただ、それがうまくいっているかはちょっとわからないですけどね。
『銀魂』とよく似ていつつも、ある意味で対照的な作品が『おそ松さん』です。『銀魂』と『おそ松さん』ってアニメのスタッフがほぼかぶっているんですが、『銀魂』がどんどん政治化していくのに対し、『おそ松さん』(二〇一五年放映開始)は銀魂の非政治的な部分だけを引き延ばしています。要するに七〇年代から九〇年代の「終わりなき日常」の肯定を徹底的にやっているわけです。だからあのアニメは成長しない六つ子のニート生活が延々と描かれるわけですが、一方、『銀魂』は「もうそれだけではダメなんじゃないか」ということで政治化しているわけですね。対して『おそ松さん』は、アニメという一〇〇パーセントの虚構のなかくらい、「終わりなき日常」を残そうとしているように思えます。
アニメーションのなかでもこうした新しい動きは少しずつ起きてきています。ただ、現状ではアニメーションが現実に敗北してしまっている。だからアニメーションの次の課題は、新しいやり方でもう一回世界のことを描いていくということだと思います。すでに破綻してしまった「世界の終わり」というモチーフを乗り越えて、これまでとは違うやり方で個人と世界を結ぶ想像力をどう手にしていくのか、ですね。
しかし、そういったことができているアニメーションはほとんどありません。いまのアニメーション業界は基本的にブルーレイソフトの売上によって支えられているので、お金を出しているユーザーの平均年齢が高いんです。もともとアニメブーム自体が七〇、八〇年代のものなので、いまの四十、五十代がメインターゲットとなる層になります。
たとえばつい最近、オタク層に大人気だったアニメに『宇宙戦艦ヤマト2199』があります。
この作品、おそらくメイン視聴者は五十代だと思います。いまの現役世代、七十歳から三十代までは映像によって共通体験が作られた世代です。だから映像産業はノスタルジーに訴えるのが一番効率がいいんですね。ハリウッドも『スター・ウォーズ』のように続編とかリメイクだらけになっていますが、それと同じことがいま戦後の日本のアニメーションに起こっているわけです。
もちろんそういったものもあっていいんだけど、もうちょっと新しいやり方で、アニメーションという想像力を使って個人と世界の新しいつながり方を模索したほうがいいと思いますし、そういうことに期待したいですね。
ということで今回は、冷戦が生み出した「世界の終わり」という想像力が七〇年代以降のサブカルチャーを強く規定し、日本の消費社会史のなかで発展していった経緯を見てきました。そして現代において戦後アニメーションは描くべきものを失い、現実のアイドルブームの後追いをするようになってしまったということですね。
(続く)
宇野常寛『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』、配信記事一覧はこちらのリンクから。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
