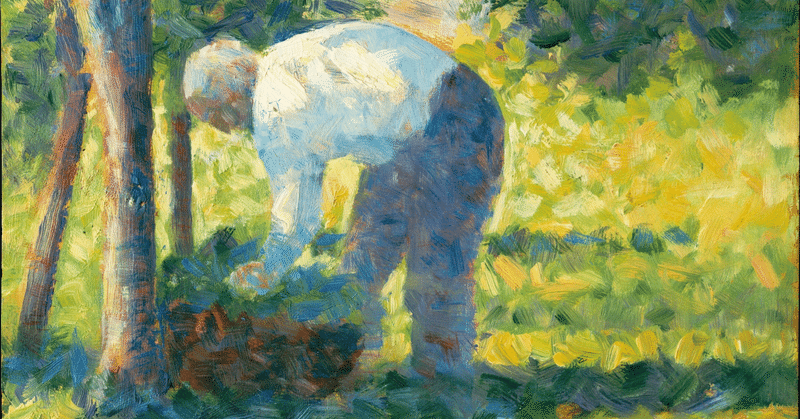
その他:アドレリアンの分類
前回の記事からの続きです。
隠れアドレリアンⅡ
以下が特徴です。
・アドラー心理学に基づくアプローチであると自認しない
・アドラーの功績を認めない
・アドラーの概念や技法の一部を修正し取り入れている
隠れアドレリアンⅠの人々よりもポストモダンの人生観にコミットしており、ナラティブ、構成主義、マインドフルネス、アクセプタンスセラピーのほとんどはこのタイプの特徴を持っているとしています。例えば、ソリューション・フォーカスト・セラピーの『マジック・クエッション(The Magic Question)』はアドラーの『質問(The Question)』の修正と拡張の療法を行っているようです。
名目アドレリアン
以下が特徴です。
・アドレリアンと自認している
・アドラーの功績を認めている
・アドラーの元の形を維持することは限定的で、独自の概念や技法を展開したり、アドラー心理学の根本的な哲学や精神とは相容れない他のアプローチを取り入れている
ドライカースは、「多くのアドレリアンの仲間は、私の考えている基本的なアドラー心理学の概念とは両立しないアイデアを述べている」と述べ、このタイプのアドレリアンによる『ムーブメント』への悪影響を懸念していたことが記されています。
非アドレリアン
以下が特徴です。
・アドラー心理学のアプローチであると自認しない
・アドラーの功績を認めない
・アドラー心理学の概念や技法を明らかに取り入れていない
しかしCoreyという人の著書では、「アドラー心理学の思想と実践の影響は想像できないほど大きく広範囲に渡っており、何らかの影響を受けていない人はほとんどいないだろう」と述べられているようです。
このように整理してみると、「アドラー心理学の影響」を明確にして「元々はアドラー心理学なんだよ」とわざわざ言う必要性はあまり感じません。アンスバッハーが言うように、それらをどうやって実践に活かすかにエネルギーを注いだ方が、よっぽど貢献的であるように思います。
とはいえ、アドレリアンを意識するのであれば、基本に立ち戻りつつ、自らの責任と判断でもって修正や展開をしていかねばなりませんし、哲学・精神・信念・思想といった根幹は持っておきたいものです。
次回の『真のアドレリアン』が最後となります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
