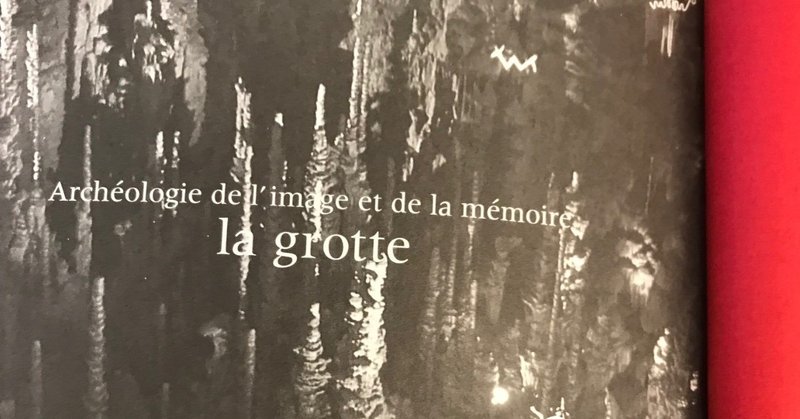
イメージは変身を媒介し、区別を、境界を一瞬宙吊りにする−読書メモ:港千尋著『洞窟へ』(2)
イメージの起源
イメージとはなにか?
という古くからの問いに対して、イメージとは人間がその内部にある意味を、外界のモノに「投影」したものである、とする答え方がある。これに対して港氏は、意味の投影というプロセスは、人間の方が外界に対して一方的に行うものではないとする。それは一方向ではなく双方向のフィードバックループが動き続けるプロセスである。
自分が頭のなかでイメージしていると「意識できる、想起できる」イメージは、外界の様々な様相を「見る」プロセスを通じて、リアルタイムに変化し続ける。
例えば、人類に限らず、他の動物を捕食する生物の場合、獲物となる動物が残したわずかな痕跡からその所在を推測したり、視界に捉えた獲物が次にどう動くか推測する能力を持つことが生き延びる上で有利である。
感覚器官で捉えられる外界のパターンを、いまそこにはいないモノの「痕跡として」見ること、その痕跡からいまそこにはいないモノがどこで何をしているか、過去の記憶を手がかりに想像すること。
こうした内部と外部の境界を挟んだ双方向のやり取りを通じて、イメージは、外部から内部の写像として、同時に内部からの外部への投射として、その輪郭を意識の全面へと顕にする。
パースの記号論の三項関係
外界からの感覚への刺激を「なにかとして」意識すること。このことを理解するためには、「記号」と「その意味」の関係を二項関係で考えていてはダメである。
ここで港氏はパースの記号論を引く。パースは記号を二項関係ではなく、三項関係で説明する。
二項関係で理解される記号現象とは「意味するもの」と「意味されるもの」の結びつきである。遠くの森の中から煙が立ち上るを見て「あの下で火が燃えている」と理解する。この時、煙が意味するものであり、目に見えない火が「意味されるもの」である。
「表象」と「意味内容」の二項関係
「記号」と「指示対象」の二項関係
「原因」と「結果」の二項関係
こうした二項関係が想定されるところには、ひとつの新たな問題が生じる。二項の結びつきはどこでどう決まったのか、と。
煙と火の関係のように、因果的に継起する一連の現象を複数の項に切り分けて理解した場合、そこでは項と項の間に一義的に固定した結びつきがあると考えられるようになる。
これに対してパースは「意味するもの」と「意味されるもの」に「観察者」を加えた三項関係で記号現象を捉える。
そしてこの観察者は複数存在する。ぞれぞれ異なるやり方で観察を、つまり「意味するもの」と「意味されるもの」を結びつける。同じ自然の痕跡に対して、観察者ごとに、あるいは同じ観察者であっても時と場合、文脈によって、異なる意味を解釈する。
ここで記号の意味は「不定的で非規定的」になる。つまり、記号と意味の結びつき方のパターンを予め規定するコードのようなものの存在を要求できなくなる。
三項関係で考えることで、コードの非先行性こそが記号の本質になる。記号を意味へ置き換えるやり方は、予め設定されたコードに基づく置き換え処理ではなく、つどつど、これはあれを置き換えたのだろうと臨機応変かつ柔軟に推測する試みになる。記号は自由なのである。
写像装置の癖がコードとしての外観を生む
この「として」観察する観察者とは、空想上の小人ではない。それは「脳」そのものであると考えたほうが良さそうだ。港氏はG.M.エーデルマンの脳と心の関係に関する仮説へと踏み込んでいく。
脳を調べると、刺激として与えられた外界のものの形と、視覚に関わる神経系の活動パターンに相関が観察される。
ただしこれは特定の外界に対応した神経の配線のパターンがある、ということではない。脳は、多数の相互接続のフィードバックが絡まりあって構造をなすネットワークであるが、そのネットワークの中で生じては消えるさざ波のような信号伝達のプロセスが動き続けており、イメージを意識させるのもそうしたプロセスである。
あるイメージの記憶とは、学習を通して獲得されトポグラフィックに構造化された表象と、その表象を再構築するための指示とからなっている。心的レベルにおいても、イメージは像の投影ではなく、記憶は単純な痕跡ではない。イメージは常に再構築である。 (港千尋『洞窟へ』p.134)
このイメージを意識させる信号伝達のプロセスは常に動いている。そしてその時、神経系を載せた身体もまた動いている。イメージはなにか「出来合い」の「完成品」をどこかから引っ張ってきたものではなく、つど新しく再構築され続けている。再構築のプロセスが同じようなパターンで反復するが故に、そこになにか一貫した即自的に存在するものがあるかのような感じがしてくるのである。
洞窟に入り込むことは脳に入り込むことか
そうして港氏は「洞窟へ」戻る。
洞窟とは、身体である。環境との相互作用としての運動が、身体と環境を結びつけ、分節し、物質的な想像力を取り込みながら、物質的境界を超えてゆく運動となって、次の運動へと連鎖してゆく。オーリニャック期の人間は、洞窟のなかでその肉体の限界を超えて時間的に空間的に拡張しながら、概念空間そのものとなり、変形と反復のなかから、壮大な記号空間をつくりだしたのだ。(港千尋『洞窟へ』p.203)
目を閉じてみる。そして顔中の筋肉を使って、まぶたを強く締めてみる。そうすると無数の光の粒が「見える」。これは「内在光」と呼ばれ、視覚に関わる神経系の定常状態の動きが意識されたものである。
闇が充満した洞窟の中で、人間は自らの神経系が発する内在光を感じ、それと「同じに見える」パターンを、洞窟の岩壁に見つける。
このパターンのある部分は「意味を持ったイコン」として、それぞれの文化で伝えられた特定の何かを表すものとして解釈される。
洞窟の経験はこれで終わらない。この次の段階がある。
それでは人間は、人間ではない存在に変身する。洞窟の闇の中、ゆれるかすかな光に照らし出された壁にうごめくイメージたち。そこで頭の中のイメージと外界に実在するイメージとが異なりながらもひとつになる。
こうして頭の中の記号体系が、洞窟の闇の中に流れ出し、壁面の岩のパターンに結実する。洞窟へ入り込んだヒトは、頭の中のイメージが「リアルに」動き回る空間に、全身で浸ることができる。
このときひとは、頭の中で想像できるイメージ「そのものに」変身することができる。
旧石器時代の洞窟をイメージで充満させた人は、そこで半獣半人、人間でありながら動物であり、動物でありながら人間であるという、イマジネーションの力が可能にする境界を超えた両義的存在に「変身」することができたのではないか。
動物になり、動物と会話し、動物と家族になり、動物の秘密を知っては、また人間に戻る。そういう変身を経た人物だけが、動物との間に、狩る者と狩られる者との契約を打ち立てることができる。
「変身」や「やつし」は、高次の意識を獲得した人間という種がその真骨頂を発揮する場面である。
今日のわたしたちのテレビやスマホやタブレット、パソコンの画面で動き回るイメージたちもまた、日々わたしたちを「何か」へと「変身」させ続けているのかもしれない。あるいは「変身」よりも「認識の産業的生産」とでも言おうか。
おわり
関連note
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
