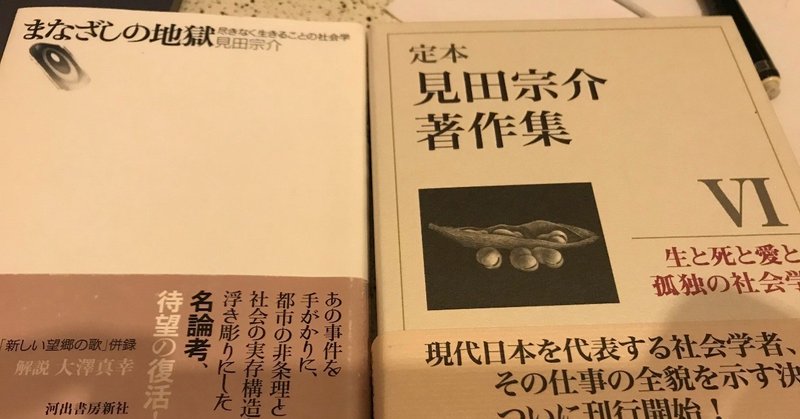
「ひとり」にとっての意味ー読書メモ:見田宗介『まなざしの地獄』
ひとりひとりの個別な個人にとっての意味
私は見田宗介氏の文体が好きである。魅力的な著書がたくさんあるのだが、私が特に「揺さぶられた」一冊が、この『まなざしの地獄』である。
それは「他の何にも還元できない、尽きなく生きようとするひとりひとりの個人」が「意味」を求めてもがき続けた姿が、その残像として置いていった断片を、背筋がヒヤリとするほどの鋭利さで切り取る。
問題は「意味」である。
それも、誰にとっても同じ一般的な意味ではなく。他人が好き勝手に貼り付ける意味でもなく。自分自身が、自分一人が自分のために探し求め、そして取り逃がしてしまう「意味」である。
意味を、ある何かの「欠如」として経験させてしまうのが、近代以降の日常である。
『まなざしの地獄』は、殺人事件の加害者であるひとりの「男」の存在を通して、ひとりの人間が意味をめぐる闘争に引きずり込まれ、その身体の表面がいくつもの「意味」がせめぎあう場と化し、そうして彼が、自分自身を他者とつなぎとめる「言葉」を失い、彼自身の存在を失う様を、点滅するスポットライトがそうするようにして照らし出す。
近代社会と意味
いまこの「近代化」を極め続ける世界において「生きる」経験は、その根っこの部分を大量生産された商品の流れに乗ること、あるいは押し流されることによって立ち上げられている。
例えばこの私などは、衣食住のほぼ全て、自分で生み出すことはできないようになっている。食べるものも、それを調理する道具も、着るものも、出来合いの完成した商品を買ってきたり、半完成品を買って多少手を加えてみたりすることで、賄っている。生きるために必要なほぼすべての「もの」を商品を買ってくることで賄っている。
この商品、特に完成品の大量購入という光景はあまりにもありふれたもので、改めて意識させられるような機会がなければ、それ以外の可能性に思いを馳せることもできない。
まだ買ってない ー 欠如態としての私
商品の流れは、ものの流れにとどまらない。それは商品についてのイメージの流れでもある。
慌ただしく過ぎる日常は、商品についてのイメージの流れに、沈められ、押し流され、五感に触れるもの全てがその流れであるような、そういう経験でもある。
その流れは、街の風景、歩く人々の装い、店のショーウィンドウ、他人の持ち物、などである。それと同時に純粋なイメージとして、マスメディアの中に、紙面に、ラジオの声に、銀幕に、そしてブラウン管から、溢れ出し、脳裏を満たす。
その恍惚からふとわれにかえると、そこにはキラキラした新品をほとんど何も持た無いひとりのわたしがポツンと取り残されている。
かろうじて持っているボロボロの使い古しの商品たち、もう半分以上大量廃棄のプロセスに乗りかかっているようなモノの残滓さえも、一瞬気を抜けば失ってしまいそうなほど、覚束ない足取りの私が放り出されている。
私は気付く。
わたしは、商品の、いや商品のイメージの、欠如態として存在しているのだ。
と。 まだこれを買えていない、まだあれも買えていない。あれはおそらく、一生買うことはできないだろう。
と、めまぐるしく通り過ぎる商品のイメージたちは、私を「それらを持っていない、買えていない、買うことができない」モノとして、理想的には自分に所属すべき商品が欠如したまま一生を終えるかもしれない「不足」という資格で自分自身と関係づける。
欠如としての現実を憎み、それを満たすものを求め
私たちは、その欠如態としての現実からの解放を願望する。解放の手段は簡単である。商品を買えば良いのである。
いや、買わなくても、他の方法でも、手に入れれば良い。
しかし言うは易し。次から次へと、手に入れる「べき」なのに、手に入らない、新品の高価な商品のイメージが、目の前に積み上がっていく。
欠如を憎悪しつつ、同時にまた、いつかキラキラのイメージで満たされることを切望する、しかしその切望がほぼ決して叶えられないこともよくわかっている絶望感。
引き裂かれているのかそれともよくわからないいろいろなものがごちゃごちゃにつながってしまっているのか、それすらよくわからない感情。
こんな感情に昼間起きている間中ずっとまとわりつかれてしまうのも、私たちが皮膚感覚で経験できる日常の光景のほとんどすべてが、新商品の大量生産と流通という仕組みが動いているからこそ、である。
都市からの眼差し
そうした都市「からの」イメージが、ひとりの男の心を捉えた。『まなざしの地獄』の話である。
都市と、「彼」を余計者扱いし虐げてきた出身地の街、その対立。それが、金さえどうにかすればすべてが充足される世界と、どう足掻いても無意味の淵から這い上がることのできない場所との対立と重なる。
商品のイメージに満たされた都市なるものへの空想は、彼にすべてを与え、彼が彼自身を取り戻す、いや、彼自身を全く新しく新品に「買い換える」ことを期待させた。
地方に対する「都」としての大都市や、あるいは異国の世界都市。
都市はまず、キラキラしたイメージそのものとして、マスメディアの表面に踊りでる。
行ってみるとそこには、いままで紙面や画面の表面に踊るだけだったイメージが、実際に建物や人の装い、地面、電信柱の一本一本のの表面に至るまで、張り付いている。
ところが、そこで唯一無二の「ひとりのわたし」が暮らし始めてみると、それらのイメージたちがなかなか、「わたし」に張り付いてくれないことに気づく。イメージは向こうから勝手にはりついてくれはしないのだ。わたしはそれを買わなければならない。
都市は、イメージを身に纏い、纏いつづけるために、永遠に与えられない餌に向かって走り続けるレースに追い立てられる場所だった。
都市「からの」まなざし
彼は歓迎された。新鮮な労働力として。
歓待される体験は一時的な高揚感をもたらした。
しかし、「それまでの自分自身からの」解放を求めて跳躍してきた彼の彼自身に対するまなざしは、新鮮な労働力としてのみ彼らをみる眼差しから、ずれていく。
すなわちこの少年たち、青年たちが、もしたんなる「新鮮な労働力」たることに甘んじようとする限り、その生理的身体と労働力の再生産だけはとにかく保障され、やがてささやかなマイホームを営む条件も、がんばれば入手不可能ではない。
このそれなりの安定を、一つの切実な欠如として感受せしめるものは、これらの労働者階級の、たんなる労働力ではない部分、誇りを持った人間の主体としての部分に他ならない。
けれども彼らを、まさしく「金の卵」という<価値ある>物質存在として要求し歓迎する都市の論理にとって、この物質に付着する自由=存在は、一つの余剰であり、「当惑させるもの」であり、招かれざる客なのである。(p.20)
都市は、ひとりの男を、その身体や頭脳を、「金の卵」「新鮮な労働力」として意味付け、そうして歓迎した。
しかし当の本人は、都市へと逃れ出ることを、「それまでの自分自身からの解放」のための手段とみなし、その先にはより真正な彼という存在についての「意味」が手に入る、買えると、つかの間信じようとした。
実際には、決して買い終わることができないにもかかわらず。
意味のせめぎあいのなかで言葉を失う
異なる二つの意味、時に相対立する意味が、意識に置いて、身体の表面において、ぶつかり合う。
この二つの、あるいは三つ以上の意味の闘争が、ある個人を、自らとその生きる場について語る言葉を奪われたような状況に追い込む。
そこに残された沈黙は、耳さえも閉じてしまう。
聞くためには、他者の言葉を聞くための耳を生かしておくには、それを束の間仮に置き換えておく自分の言葉が必要である。茫然自失、言葉を失ってしまったところでは、他者の声を自分にとっての意味として引き受けることもまたできなくなる。
そうして他者たちから善意も悪意も綯い交ぜにして流し込まれるコトバたちに、直接そのまま晒されることになる。他者の言葉はそのとき、乱暴に一方的にレッテルを貼り、安定した自己のその世界についての意味引き裂く脅威になる。
人間の存在とは、その現実に取り結ぶ社会的諸関係の総体にほかならないのであるから、その諸関係の解体は、確実にその人間の存在そのものの解体をもたらす。P.34
残るのは、彼を彼ならざるものとして見ようとする無数のまなざしにさらされ続けているという危機意識と、そうした眼差しへの憎悪である。
言葉さえも失う/ひとりひとりの他者と言葉を作り直す
レヴィ=ストロースによれば、意味とは「言葉の言い換え」である。
AはBである、BはCであると言い換える、いわば「操作」こそが、「意味する」ということの実質であるという。
そして「言い換え方」はいつもひとつとは限らない。言い換えの可能性はいくつもあり、どの言い換え方が「正しく」、どの言い換え方が「正しくない」ということを分別する基準もまたひとつではない。そもそも正しい、正しくないということさえ、ひとつの言い換えの試みである。
例えば「わたし」というものを、他のどの言葉に言い換えて、意味づけるのか?
そこにはいくつもの言い換えの可能性がある。
「君は、○○だから、この世に存在する値打ちがあるんだよ」
という類の言い換えが、いくらでも溢れている。ぼんやりしていると、そうした言い換え、意味付けが耳の中へ飛び込んでくる。そうして一瞬で「わたし」の意味をどこかにピン留めしてしまう。
都市では、時間も空間も、いくつもの細かい部分へと切り分けられていく。職場の、あの部屋、この部屋に居る私、あのひと、このひとと居る私、移動する電車の中の乗客としての私、買い物をする通行人としての私、一人でランチを注文する私。
そして、それらをすべて貫いて、統一する「本当の私」という想像。
人間の存在が、その時々に関わる相手との関係によってつど決まるとすれば、すべての関係のパターンを貫いて存在する「本当の私」など、ほとんど欠如としてしかその輪郭を表さない。
何にも言い換えられない、うまい具合にしっくり来るひとつの「言い換え」で済ませることができない。その「なんともいえない」ところ、饒舌に言い換えを試み、意味を与えようとする口が沈黙してしまうところに、おそらく「私の意味」という、何も意味せず、そうであるがゆえになんでも意味することができる記号が区切りだされてくるのである。
仮にその欠如をコトバを使って埋めざるを得ないのが、ひとりひとりのわたしたちであるならば、なによりコトバを、完成品の商品の流れの中から買ってくるようなものにしてはならないのであろう。
売り物ではないコトバ、未完成なコトバ、積極的な意味で欠陥商品としてのコトバ。それらへの「言い換えを試みる」ことが、おそらくひとりひとりのわたしたちをその都度その都度なにかから救いつづけ、救い直すのである。
おわり
追記
このあたりから、ひとりひとりのわたしたちの間で、ブリコラージュで「言い換えを試みる」というテーマにつながるのであります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
