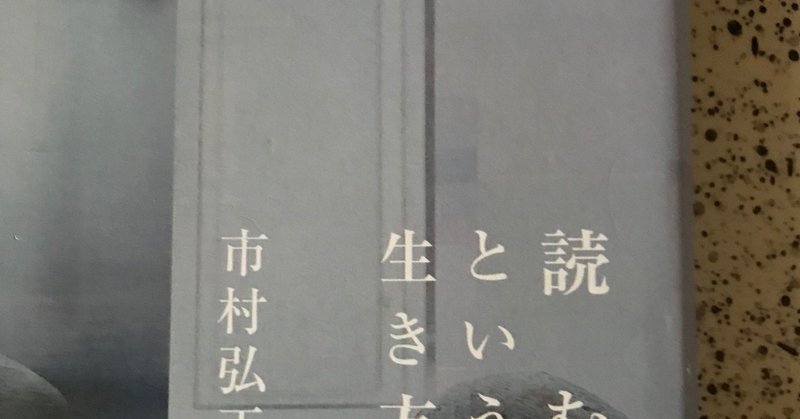
読むことと生きることー読書メモ:市村弘正『読むという生き方』
noteには、いずれかの記事を「プロフィール」に設定できる機能がある。そこでプロフィールの代わりになるような記事を書いてみる。
このnoteアカウントで何をやっているのかといえば、 主に「読書」である。
趣味は読書?
よく本を読んでいる、というと「趣味は読書ですか?」と聞かれることがある。聞いている方は何気なく聞いてくれているようだが、こちらとしては考え込んでしまう。
趣味、というと、愉しみ、嗜み、要するに自分で選び取ってやっている、といったニュアンスがあるように思う。しかし自分の読書に限って言えば、選んでわざわざやっているとようよりも、読まざるを得ない感がするので、読んでいる、というのが正しい。
なので「趣味ですか」に対して「中毒ですね」と応えるようにしている。理性で選ぶというよりも駆り立てられる、という感じ。
読むということは、自己が破れること
市村弘正氏の『読むという生き方』という一冊がある。
学部生のころに恩師に進められ、手にとったのが最初である。ちょうど「読まざるを得ない」中毒に陥っていることを自覚しはじめたころである。恩師には全てを見透かされているようで、選書眼に脱帽である。と、同時に「読まざるを得なくなっている私」もまた、私的個人的に孤独にそうなっているというよりも、すでにたくさんの誰かが通った道に誘い込まれつつあるのだと、妙な感じがした。
「欄外、余白を聴きとる」こと。市村氏は「読む」とはこのようなことであるという。読むということを、あまりにあからさまな「文字」を辿ることではなく、文字の周囲の「欄外」「余白」へ、しかも「読む」から「聴き取る」へ、置き換えていく。
ある一冊の本のある一ページ。たくさんの文字が並んでいる。
そしてその周囲の、余白。
余白は文字を字義通り読むというやり方では「読めない」。そこには何も書かれていないのだから。しかしそこを「聴き取る」ことができる、できる、というかしなければならない。
「欄外、余白を聴きとる」ような読み。市村氏によれば、その読みは、言説の時空の連続性、均一性を破る。そして経験を一義的ではあり得ないこととして認識させる。この読みにおいて経験の意味するところは「未決」のままになり「両義的構造」を露わにする。
欄外、余白、つまり文字に起こされていないこと。あるいは文字に起こされていたとしてもその意味が両義的で、最終的な意味が未決であるようなこと。そうしたことを、表層の記号の辞書的な意味を破ってまで「認識する」には、どうすればよいのか?
「読み」は置き換えであり、置き換えにはルールがある(と信じることもできる)
市村氏は次のように書く。
「読み方や学び方のさまざまな差異があるはずである。それを捉え損なうと、日常の生の基層や生存感覚と呼んでいい位相に思考の触手を伸ばすことができず、差別や抑圧という言葉は学校文化的な学習の記号として流通していくだけだろう。」(p.13)
まず読み方には「さまざまな差異」がある。この差異の隙間を引き受けることが、「日常の生の基層」や「生存感覚」へと「思考の触手を伸ばす」鍵である、と。
読むことには二つの種類がある。
一つは、書かれたテキストの向こう側にある(であろう)正解を、そのまま再生する営みとしての読み(読みⅠとしよう)。この読みⅠは、どこのだれが実行しても、そこで再生される正解は同じものである。それは予め書かれていることを完成品として受け取るのだから。
読みⅠは「正解」を検索する作業である。正解は暗号解読用のコード表のようなものとして、どこかに予め用意されている。
第二の読み
もう一つの読みは、コードを新たに作り出す。この生産的というか生成的な読みを読みⅡとする。
コードを新たにできるかどうかの鍵は、市村氏の言葉を借りるなら「「現実」なるものに固着しないフィクションの感覚と、大切な物事は「実在することにする」という条件法的な思考」にある。
市村氏は現実に「なるもの」をくっつけているが、まさにこのやり方です。現実のような、誰にとっても同じであることは疑いようもないことと信じられていることさえ「なるもの」として、一つのフィクションとして受け取る。そしていくつものフィクションがあり、フィクションの外部にフィクションではない真実のようなものを求めようとしないこと。
誰が読むのか?
この生成的な読みⅡは「読む主体」のようなものを超えていく。読んでいるのは誰か?
読みを実行している身体について、市村氏は次のように書く。
「手持ちの「読み」の文脈に亀裂を生みだし破壊していく力」
「分節不能な境界的な言葉によって隈なく浸透する力」
そうしたいくつもの力によって「書き込まれていく身体」が読むのである。
内面を形成する「部品」は外からやってくる。[…]本やその断片という部品によって構築され、浸透しつくされた時、そのような「内面」を抱える身体をもつ「読書機械」が成立する。
読書機械と書く時、市村氏がイメージしているのは、読む主体というよりも、読まざるを得ない傾向のもとで自動的に動く機械である。
読書機械の材料は、それまでに読んだ無数の言葉の断片である。それらを組み合わせて仮設的にブリコラージュされた言葉と言葉の対立関係が織りなす構造であり、その構造はいつも未完成である。
読書機械
読書機械の読みⅡは、予め内蔵された単一のコードに基づいて入力される言葉ひとつひとつを分類してコード表を再生産するようなやり方ではない。
読書機械の読みⅡは、断片が断片を呼び集める運動である。断片と断片が織りなす隙間だらけのマトリクスの空の結び目に、新しく読んだ言葉が転がり込んで嵌っては、またマトリクスの蠢きによってはじき出されるような。
こういう読書機械としての読み方は、首尾一貫した主体による、あるべき「正統」な読み方から溢れ出していく。
正統な読みが正統であるのは、それが一つのコードに準拠しているからである。ある一冊の本を「正しく」解読するためのコードはこれですよ、というものが、決まりきって存在していると信じられるときにだけ「正統」かどうかが問えるようになる。
書かれたテキストそれ自体の意味、誰が読んでも同じように再生できる意味、というものが存在できるとすれば、それは正しい翻訳の仕方を規定するコード表が予め用意されているときである。
しかし考えてみれば、そのようなコード表は「読めるもの」として存在することはあるのだろうか?
「読書機械」と”昔の機械翻訳” なら、後者のほうがより人間的とさえ
この本の正しい読みⅠは別のこの本に書いてあり、この本の正しい読み方は…、と次から次へとどこまでもさかのぼってしまうはずなのだが、この遡行は案外あっさり止められてしまう。
どれかのコードを最終的なコードということに決めてしまい、そして入力される記号を、機械的に出力されるべき記号に置き換える操作をやればよい、というやり方で。
ちょうどしばらく前のコンピュータがやっていた機械翻訳のようなものだ。
ことによると首尾一貫してこれはこれ、あれはあれ、と置き換えていく意識的な主体というものも、この準拠するコードを単一のままに限っておくという処理の産物なのかもしれない。それこそがまさにコードの外部に、余白とノイズという形で、未読の言葉を削り出し続けるのであるが。
単一のコード、変化しない固定的なコードで、すっきりさっぱり世界の全てを解読できている時代があったとすれば、それこそが幸福な時代だったのかもしれない。
市村氏は書く。「現代」は、このような「非連続性を含む重ね合わせがなければ充分に掴むことができない時代」であると。
現代はいくつものコードが重なり合い、その接触点で「両義性」を露わにし続ける。それにもかかわらず、コードたちは、それぞれ自分こそが唯一の正しいコードであると主張し、この両義性を排除しようとする。
余白を聴きとろうとする
両義的、というか、一義的なものからこぼれ落ち、排除される部分、それは沈黙の声でもある。
沈黙から聴き取るような「読み」(読みⅡ)の余地はどこに開くのか。
沈黙を聴き取るような読みは、正解を量産するコード化した主体が意識的自覚的に行うことではない。沈黙を聴き取る読みは、読書機械において自動的に動き出す。
そこで主体は、次から次へと現れてはつながっていく言葉たちの連鎖を、手持ちのコードで拾い上げようとしては取り逃し、焦り、怯え、茫然自失となりつつも、いつしかその言葉の流れそのものが自己を解体しつつ仮設的に再建しようとし、それでいて途中まで作り上げてはまた解体していくという、そのことに目眩を覚える者である。
では、コード化した意識を一時停止して、読書機械の自動過程を意識の表層に浮かび上がらせる契機はなにか?
他者の言葉が余白を開く
それは「他者」の言葉をうけとることに尽きる。それも単数の他者ではなく、複数の他者である。それぞれの声は互いに矛盾することをいい、互いの余白を露わにする。他者は決して、物分りのよい、丁重で丁寧な紳士ではない。それは無作法で不躾で、無礼極まる言葉かもしれない。
そうしたいくつもの声が自らの唯一の正しさを主張しようとそのコードを露わにすればするほど、同じような他の声のコードとの差異が際立ち、結局コードが単一ではありえないこと、調停しようもなく複数であることが、暴かれる。
問題はこの両義性が露わになった後である。
「意味などすべて無意味なのだ」という具合に、コードを生み出す過程から離れてしまったり、あるいはただシンボルからシンボルへの上滑りに流されてしまったり。これでは両義性を「生きる」ことにはならない。
両義性が生きるのは、シンボル領域ではない。
言葉をシンボルの上滑りにしない。そのための手がかりがおそらく「身体」にある。ここでいう身体というのは、そこで他者たちが織りなす環境世界が自己に迫ってくる厚みを持った表面である。同時に自己が他者と接触する面でもある。身体は自己と他者の中間領域であり、自己を他者へ、他者を自己へと、投錨する。
身体では、自他が区別される以前のところで、他者の他者としての自己がいままさに区切りだされようとされ続ける。
そこで身体をもつ自己も身体をもつ他者も、それぞれ「なんでもあり」なめらかなシンボルの流れとしてではなく、力強く反復再生するパターンとして、姿を現そうとする。
この時、言葉は、身体とともにあるインデクシカルで、アイコニックな記号になる。
その時記号はは身体における環境世界との接続パターンをなぞるように、止むに止まれぬパターンを描こうとする。このことがおそらく言葉をシンボル「だけ」ではないものとして、常に新しく「読む」ことを諦めるべきではないものとして、保つのである。
おわりに
他者を、その他者にとっての他者である自己が、他者からの借り物の言葉に翻訳するというやり方で読まざるをえない。これが「読むということ」である。
ここでは自他の区別も、自己の言葉と他者の言葉の区別も、曖昧になってくる。それらは両義的である。
ぐらぐらと揺らぐところでもって、波の中に溶けていってしまいそうなシンボルたちの横滑りを、しかしそれでもなお、波に漂う流木のような身体、環境に埋め込まれた身体の器官でもって、インデクシカルに、アイコニックに、強迫的に反復せざるをえないパターンで、他の身体との接触のパターンを再生産しつづける。
そこに止むに止まれぬ認識衝動もまた姿を表わす。
こんなふうに書くと「読書」が重苦しいものに聞こえてしまうかもしれないが、逆である。次々と本を手にとることが、何かの流れに流されつつも、その上に浮かび上がりゆらゆら漂う、軽快さを保ってくれるのである。
おわり
これまでの読書メモはこちらに掲載しています
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
