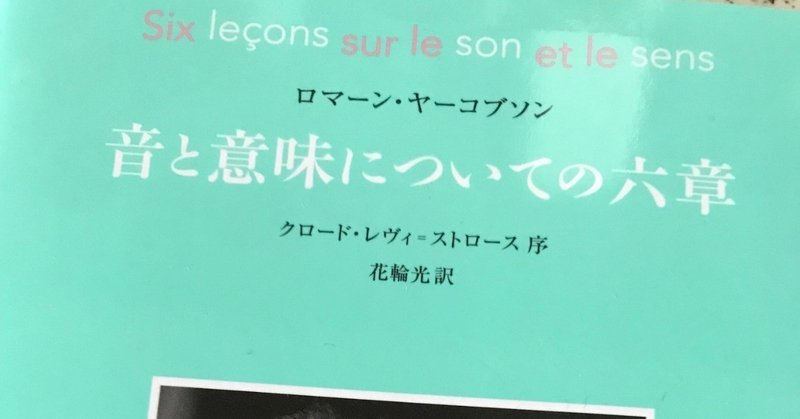
均質でもなく、止まってもいないが、静止した均質さを称えることもできる ー読書メモ『音と意味についての6章』と『井筒俊彦全集第9巻』
このところ井筒俊彦先生の全集を読んでいる。「CD付き」の第九巻「コスモスとアンチコスモス」である。
ちなみに付録のCDはまだ聞けていない。
読み進めると、次の一節に出会った。
「客観的な対象界と認識主体とを二つに分断し、さらに客観的対象界を、無数の事物事象に分割して相互に対立させるものが、この次元の存在を根本的に支配するコトバの意味分節作用である」(井筒俊彦全集第九巻 p.379)
ここで井筒先生が「コトバの意味分節作用」とよぶもの。もしかするとレヴィ=ストロースが「構造」として捉えようとしたものはこれではないだろうか?
という考えが浮かぶ。
動く構造は意味分節体系を産出する?
構造と、言葉の意味分節作用。どちらも、意味をなす項と項の対立関係が織りなすネットワークの伸びたり縮んだり、結び目を結んだり解いたりする動きのことを捉えようとしたのではないか、と思う。
レヴィ=ストロースは、コトバによって、名によって、「無数の事物事象に分割して相互に対立させ」られたモノの名前たちの関係が織りなす織物の姿を捉えようとした。
特にその織物の織られ方のパターンが、隣り合う部族によって微妙に異なっていくこと、地域を超えて次々に異文が増殖し、変化していく様を捉えようとした。
レヴィ=ストロースはこの織物を「出来合いの完成品」とはみなさない。この織物は素朴に実在する客観的な対象ではない。この織物にとって最大の問題は、それが常に「織られる」プロセスの未完の途上にあることである。
ここに至りレヴィ=ストロースの「構造」分析は、固定的な静まり返った石造建築物の姿を描写することではなくなる。構造分析は、項と項の対立関係を織り込んでいく動的なプロセスを、その運動の痕跡として描かれるパターンの観察を通じて捉えることになる。
このあたりのことが端的に表明されているのが、レヴィ=ストロースが、ローマン・ヤコブソンの『音と意味についての6章』に寄せた序文である。
『音と意味についての6章』序文
冒頭、レヴィ=ストロースは、ヤコブソンの構造言語学が自分に教えてくれたことについて、次のように述べる。
構造言語学が私に教えてくれることになったのは、多様な諸項にまどわされることなく、諸項を結びあわせている、より単純な、より理解しやすい諸関係を考察することが重要である、ということである。p.2
諸「項」に惑わされないこと。
項と項を「結びあわせている」「関係」を考察すること。
これについてのヤコブソンによる一節を見ておこう。
「《重要なのは、それ自体として見た、それ自体のために存在する、各音素の(…)個性ではまったくない。重要なのは、ある(…)体系のなかにおける音素の相互対立である》(p.110)」
この”関係”を検出する出す方法が、「変異性を通じて不変異体を示す」というやり方であるという。多数の、無数の要素群が織りなす千差万別の変異のなかで、不変でありうるのは要素同士が相互対立の関係にあるという点である。
構造を構造として記述しようとすること
そしておもしろいのは、構造を構造として記述しようとする営為自体が、当の構造にすっかり巻き込まれているということである。
対象としての構造と、それを観察し記述しようとする観察者が、別々に独立して存在しているのではない。観察者も、その観察行為も、記述行為も、はじめから最後まで構造の中にある。そして観察するという動き、記述するという動きによって、構造をなす項のネットワークに新たな結び目を生じたり、解いたり、縺れを引き起こしたりする。そうしてネットワークとしての構造のパターンをずらすのである。
ちょうど井筒先生の全集九巻は、こうしたプロセスを論じていると読むことができるのではないか。
そのプロセスとは、日常における実体たちが織りなす二項対立の両極を重ね合わせることで、その重畳する「項越し」に、ある項が他の項との区別される限りで生じる瞬間を垣間見る。垣間見つつ、また項たちが実体としてふるまう日常にフォーカスしなおす、というようなことである。
動的でもあり静的でもあり、外部的でもあり内部的でもあり、実体でもあり関係でもあり。そういう対立関係自体を含み、可能にする意味のネットワークの運動が、井筒先生にとっても、レヴィ=ストロース先生にとっても、大問題だったのかもしれない。
言葉が勝手に踊り出て
言葉は、大きな道具箱のなかに整然と整理されてストックされているものではない。ましてや「私」が、その道具箱の中からひとつひとつ吟味しながら掴み出すものではない。
聞いた言葉、読んだ言葉、目にしたイメージ、思い描いた心象、不意に到来したビジョン。そのようなものが飛び込んでくることを引き金として、言葉が躍り出てくる。
私自身、なぜその言葉なのか、他の言葉ではないのか、その理由を考えようにも皆目見当がつかない。
無数の言葉たちがごうごうと流れている。私はその流れに巻き込まれ押し流されながら、たまたま耳に、目に引っかかるひとつひとつの言葉に気づく。
そうした言葉のひとつを引っ張り上げてみると、そこにはぞろぞろと他の言葉が紐付いている。
海に漂う網を引っ張り上げるようなものだ。
もつれ合った言葉の網の目は、うねり波打ちながら、私を飲み込み、網の隙間に絡め取ってしまう。私は網にかかった魚のようであるが拘束されているという感じはしない。もつれた網の塊自体が高速で振動しつつ移動していく為である。
不意に躍り出てくる言葉のバリエーションによって、引っ張り上げられる網の形が変わる。
ある言葉や音やイメージの経験に対して不意に躍り出てくる言葉のバリエーションによって、いわば意味の「六道」が分かれる。人を餓鬼道に、畜生道に、押しやっていく言葉もある。六道の分かれ道は、到来する言葉と、それに結びついた無数の言葉達の「結びつき方」の差異なのだ。
どういう言葉が自分に到来するか、それを見届けようとすることで、自分がいま六道のいずれに転がり込もうとしているのか、言葉にすることができるということが、おそらく人間が他の動物とは異なる特殊な動物、シンボルに憑依された動物であることのメリットでありデメリットなのだろう。
山塊を流体として見ることができる
例えば、山は生きている、と言ってみる。
動植物にあふれているという意味でも生きている。
そもそも岩石は動いている。岩石はマグマが冷えて固まったり、それが細かく削られて、また堆積し、押しつぶされて固まったりする、大きな動きのサイクルの中の、一瞬の仮の姿である。
と、このような具合に、経験する世界をいくつもの記述によって多数化できることが、完全な内部であり完全な外部でもある、意味をなす記号たちからなる「構造」の見事なところなのかもしれない。その見事さは、なによりそれが均質ではなく、止まってもいないということによる。しかもその不均質さは均質性に対立するものではなく、またその非停止性は停止に対立するものでもない。
おわり
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
