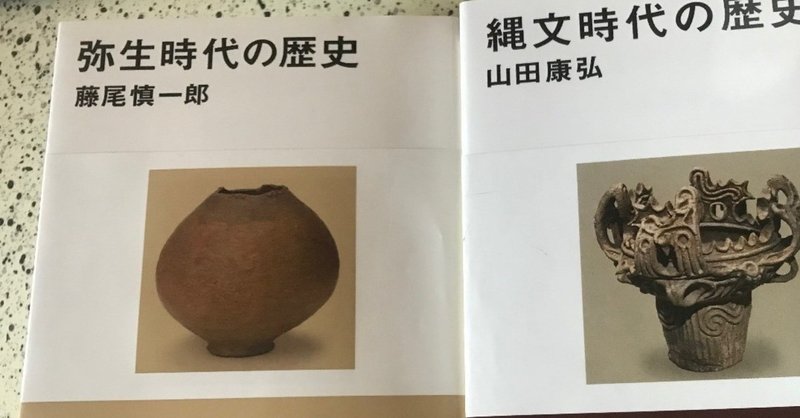
人を動かすということ‐読書メモ:『弥生時代の歴史』(2)
前回に引き続き『弥生時代の歴史』読書メモである。(1)は長々と文献のまとめになってしまったが、これは「なるほどそうだったのか」と教えられる話題が多かった為である。
特に、朝鮮半島南部からわざわざ日本列島に移住した人々の「動機」についての仮説、これが示唆に富む。著者の藤尾氏は移住の原因について、農耕社会に生じた格差ではないか、と仮説を立てる。階級格差から生じる矛盾から逃れようと、移住を選ぶ人たちが出てくる、と。
客観的事実から垣間見られる過去の人々の主観性
この『弥生時代の歴史』は考古学の研究成果に基づく事実が淡々と述べられている本なのであるが、端々に当時の人の息遣いというか、ひとの顔を思い浮かべざるを得ないような記述が散りばめられている。なんというか、客観的事実のシリーズの上に、遠い過去の人々の主観性の鱗片をあぶり出すような、藤尾氏の文章がなんとも読んでいて楽しい一冊なのである。
さて、その真骨頂が発揮されるのは、弥生時代の核心部、「鉄」を巡る話においてである。
初期の弥生の水田稲作や環壕集落であるが、それらは基本的に石器によって営まれた。道具の多くは石器なのである。青銅器はあるのだが祭器として使われたらしく、日用の道具ではなかった。水田や環壕集落の土木工事の基本となる木材を切り出すのも磨製石斧だった。
鉄器が広まりはじめるのは紀元前三世紀になってから
日本列島内で出土した最古の鉄器は、いまのところ紀元前五世紀ごろのものであり、それは中国東北部の燕で作られた鋳造の鉄斧である。しかしこれはレアケースのようだ。
九州北部を中心に鉄器がひろく普及しはじめたのは、最初の水田稲作の開始から数百年を経た紀元前三世紀になってからである。なおこの鉄は燕の鋳鉄ではなく、朝鮮半島南部の弁辰地域の鍛鉄である。朝鮮半島南部の各地に、九州北部の弥生文化の人々が、鉄をもとめてやってきた痕跡が残されている。
なおこの朝鮮半島南部との鉄の交易は、その後の日本列島の古代史を左右しつづけた大きなファクターとなる。その後長らく鉄は列島内でゼロから生産することがほぼできなかったので、どうにかして朝鮮半島南部から交易で手に入れないと行けない。
日本列島各地の有力者をひとつにまとめたもの
一度鉄を使い始めてしまうと、もう石器に戻れない。海を渡る鉄の交易ルートにいかにつながりつづけるかが、日本列島各地に散らばっていった稲作農耕グループの主要な関心事になったわけである。
各地に散らばった様々なグループの間には、生業形態も、価値観も、それなりの幅、差異があったことだろう。
しかし、この「鉄の交易ルートから外れられない」という一点に限っては、各地の集団が一致団結したわけである。
点と点をつなぐような弥生集落のネットワークをひとつの国家へと統一していくきっかけはこれである。その後も、朝鮮半島南部との鉄の交易を確保することが、古代王権の課題でもありつづけたわけだし、鉄を国産出来ると決まった瞬間に、あっさりと遠征を止めたわけである。
倭国大乱は鉄の流通をめぐる争いではない?!
さて、列島の水田稲作地帯が「ヤマト」に統一される過程で生じた争いが「倭国大乱」であるが、従来、この原因は鉄の流通を巡る争いだと考えられてきた。
鉄の流通の入り口を牛耳る九州北部の勢力とイヅモやキビの勢力が争い、結果、イヅモ&キビが勝利し、新しい連合の中心をヤマトに据えた…、と、私もいろいろな所でこの説を読んだことがある。
本書の藤尾氏はこの説に疑問を呈する。理由は明快で倭国大乱後も近畿での鉄の出土が増えないからである。もし鉄を巡る争いであったなら、勝者が作ったヤマトには、膨大な鉄が集まるはずであるが、実際には乱後も、鉄の集積地は九州北部のままなのである。
では、当時の日本列島の人々は、隣人同士で一体何を争ったのか?
人をうごかし、まとめる「フィクション」の力
藤尾氏は、倭国大乱を鉄という生産のための資材=「ハードウエア」を巡る争いではなく、祭祀、まつりの形、人々を統一するフィクション=「ソフトウエア」を巡る争いだったのではないか、と論じる。
人々を統一する「フィクション」を具現化する場が「まつり」であり、その演出には特別な祭器が欠かせない。
倭国大乱の前、列島各地では、個々の集落を超えて、より大きなまとまりで、同じ種類の祭器を、同じまつりを、同じフィクションを、共有する広域のまとまりが出来始めてきていた。銅鐸、銅矛、墳丘、埴輪の原型のような土器など、それぞれ異なるシンボルを軸にすえた、複数の大地域のまとまりが姿を見せ始めたのである。
信念の体系を巡って、広域圏ごとに大きなまとまりが出来つつあったこと、その互いに隣接するまとまり同士の間に差異が生じていたこと、それでいて異なる広域圏同士が隣り合い同じ流通ネットワークを織りなしていたこと。
そこに争いが生じた可能性がある。
しかし、争いつつも、バラバラに分裂することは出来ない事情があった。各地域には、朝鮮半島までつながる鉄の交易ネットワークから外れて引きこもる=過去の生産力の水準に逆戻りするという選択肢はなかったのである。
前方後円墳という統一のシンボル
そうしてなんとか妥協し、折衷して、擁立されたのが「卑弥呼」であり、その統一された新しい意味空間のシンボルが「前方後円墳」であった。前方後円墳は、ある時から一挙に、水田稲作を継続してきた全国各地へ一挙に広まった。元々の様々な差異を超えて、一挙に単一の様式が広まったことの「不思議」。
この統一のシンボルは、その後、文字や、建築物や、制度や、そして何よりも純粋な「権威」へと姿を変えていったわけであるが、最初になされた「統一」自体は何度も崩れそうになりながらも、度々新しい姿で再建され、現在まで続いている。
食うための生産活動という極めて実質的な課題に対応するための統一ではなく、シンボルの為の統一。
あるいは、シンボルのための統一であったからこそ、「食うため〜」の活動の実質がどれほど変化しても、シンボルそのものの外観がどれほど変化しても、シンボルたちの関係構造としての意味のマトリックスは受け継がれたのである。ときにゆらゆらと揺れながらも。
「食べること」を超えて
藤尾氏はさらに議論を進める。そもそも、水田稲作自体が単に食料を得ることを「目的」としたものではなく、大陸と交易する際の交換用の財として、お金の代わりになるものとしての米を得るための活動でもあったのではないか、と。日本列島には、縄文時代以来、コメにこだわらずとも他に食べるものはいくらでもあった。しかし、水田稲作集落の人々、特にその支配者層は、わざわざ水田稲作を選択したのである。
それは初期の弥生の支配者たちにとっては、水田稲作こそが、自分たちの元々の、祖先の世界につながる糸であった。水田稲作を営み青銅器のまつりを絶やさないこと。青銅器や鏡など中国の皇帝から下賜される「威信財」を得ることもまた、そうした糸を切ること無く結び続けるという意志のひとつの表現であっったのだろう。
舶来の青銅器。支配層は、単にゴージャスなものが好きで、キラキラする青銅器を欲しがった…という話ではない。もっと切実な問題がある。青銅器は、祭祀に不可欠だったのである。
守られ、包まれた、特別な空間だと信じるに足るものを
水田稲作という「生き方」を続けるために、首長たちにとっては、水田稲作に従事する住民を、どうやってまとめ上げて働かせるか、なにより頭の痛い問題だったに違いない。毎年毎年必ず豊作ということもなく、また自然災害でせっかく作った水田が土砂に埋まることもある。
そういうときに、来年こそは大豊作!と、人々に「確信」させて、目の前の米作りの仕事に向かわせる、動機づけが必要である。
まだすぐとなりに、山に暮らす隣人たちが縄文時代以来の生業で暮らしていたのである。実際、稲作の集落の住民の中にも在来の縄文人が多く参加していた。水田はやめて、山に戻ったほうがよいと、いつ言い出すか分からない。
そんなとき、末端の庶民のひとりひとりまでもが「安心」してそこに身を委ねられる場所として、その水田稲作が営まれる空間を「特別なもの」にしておく必要がある。
人々に未来の収穫を「約束」し、そのために今日、いまここで、すぐに食料を得られるわけではない労働に向かわせる。そのためには、理屈で説得するというよりも、「まつり」の場を神聖で厳かで、生成力を司る神にいまにも触れることができそうだという、感覚、体験を与えるものにすること、それがなにより大切だった。
その「特別さ」を具現化し可視化するのが、弥生の初期においては青銅器のシンボルだったようなのである。
大陸伝来の青銅器も、列島内で独自に作られた青銅器も、また墳丘も、「もの」そのものに価値があるというよりも、それを使った「まつり」で、人々をまとめることができたところに価値がある。地域のリーダーたちが、そんな祭器を遠くの権威から下賜してもらうためには、それ相応の貢物を送らなければならない。そのための原資となるのが、米だったのかもしれない。
シンボルに満たされる
歴史学の世界では、長らく、経済発展、生産力の増大こそが歴史の原動力であると考えられてきたという。より豊かに、より大量に生産をするために、資源を求め、材料を求め、生産手段を蓄積し、生産の場を大規模化し、人々を更に多く組織し、と、それが歴史の発展であると。
しかしどうやら、歴史は、というか歴史として残るものを織りなした個々の人々は、それ「だけ」では動かないようだ。
生業や日々の活動を変化させるきっかけには、「意味」が必要なのである。つまり、日々のよろこびや悲しみや、満足や不満や、様々な価値の対立を、ごっそりそこに回収してくれるようなシンボルの体系に置き換えるということ。
表層的なコトバで説得してもヒトは動かない。むしろ感覚と、環境世界に深く投錨したシンボルの交代運動に身を委ねているような感じがするときにこそ、ヒトは安心して、何かを信じるのである。
村落が広がり、日々やるべき仕事が決まっており、忙しく働く。
「偉い人」が時に理不尽な命令を下すこともあれば、助けてくれることもある。前例がないと口やかましくチャレンジを潰してくる先輩もいれば、不機嫌そうに黙って言うことを聞いている人たちもいる。
日々季節は移ろい作物が育っていく姿は収穫への期待を高める。と同時に、不意のトラブルでこの作物が全部やられてしまっては、と不安もよぎる。
思わず願掛けをしたり、祈ったり、「こんなものだ」と言ってくれる誰かの言葉を求めたり。
そんなとき、どこから、どんなシンボルを借りてきて無意味を意味で満たすのか?
おわりに
自分たちが未来のために生産活動に従事する空間が、なにか守られた、特別な、安心し信頼できる「故郷」であると保証してくれるコトバやあるいは無言のシンボルは、どこからどこへやってきて、どこで誰から誰に共有されているのか。
昔から親しんできた日本の歴史のはじまりを、このように「信念」あるいは「意味」と、意味を織りなす「シンボル」の話から一貫して整理できるところに、この『弥生時代の歴史』、と『縄文時代の歴史』の二冊の面白さがある。古代史を、ある意味でメディア論的に再考させてくれるという、類まれな二冊であった。
おわり
関連note
↓今回のnoteの前編です
↓『縄文時代の歴史』の読書メモ
↓以前書いた別件の古代史のはなし
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
