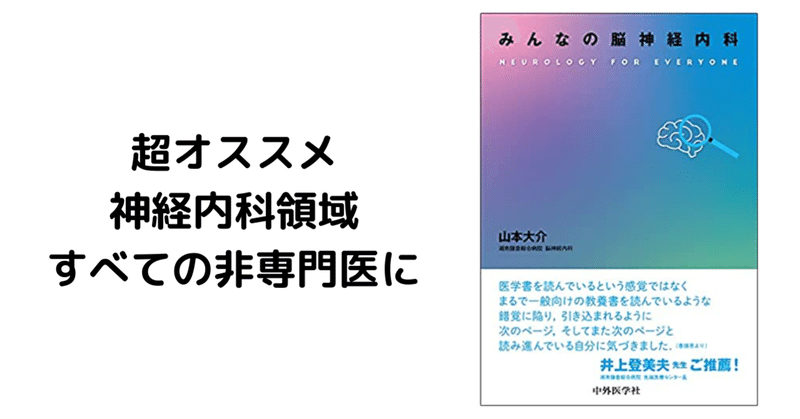
神経内科〜研修医から非専門医まで〜
僕のブログほど(割り切りすぎて、怒られるレベル)ではないにせよ、かなり「初心者向けに割り切った」著書を見つけてしまいました!研修医でもすらすら読める、なのに「明日から即戦力間違いなしの一冊でした!フライングで紹介です!
神経内科専門医だけではカバーしきれないほどの「コモン」疾患〜脳梗塞〜
神経内科というと難病のイメージが強いですが、急性期市中病院にいると比較的多く出会うのが、「脳梗塞」。
生活習慣病の延長として発症する脳梗塞や、昨今高齢化とともに増えてきている「心房細動による脳梗塞」など、おそらく「神経内科医以外がみれないといけない」疾患のトップにもなるでしょう。
これは、循環器医にとっての心不全にも近い印象がありますね。
脳梗塞を「初期対応から専門医に丸投げ」というわけにはいかない病院に務めることは多々あるのではないでしょうか?
神経内科医は循環器医ほど充足していないと思われ、24時間相談可能な体制がどこの病院にもある、とは言い切れないですよね。また、慢性期病院に努めていても入院患者さんが脳梗塞疑いの症状をきたすことも多々ありますよね。脳梗塞診療にある程度自信があることは「必須」だと思っています。
(※特にわれわれ循環器医師は抗血栓薬を頻用し、かつ患者の脳梗塞リスクは通常の入院患者より高いですから、なおさらです。)
初期対応法も、MRI画像診断も小難しいことは一切排除!
脳梗塞初期対応方法についても、かなり割り切って述べてくれています。そのため「明日から使える」内容でした。そう、われわれ非専門医が知りたいのは、エビデンスがどうこう、とかの情報よりも先に「専門の先生だったらこういうときはぶっちゃけどうしてるの?」です。言葉は悪いですが、専門ではない領域について、「まずはその場しのぎ」ができれば良いわけです。その場しのぎをしてから、成書を引っ張ってくれば良い。
しかも、成書だと情報量は多いものの、「どの情報が有用か」がわかりにくいところ。本著では、「どう考えても重要でしかない」ことに絞られています。無駄がない。
MRIの読影も、「T1強調像は脳の形がわかりやすい。T2強調像は病変が白く見える。FLAIRはT2を見やすくしたもの。」と割り切り方がすごい!
こんな本を待ってました!循環器バージョンでもこんな割り切った本が書きたい!
正直、専門医に任せたい、けど「お手上げ」では困る「てんかん発作」
てんかんで神経内科にかかっていて、最近は薬で落ち着いている患者さん。別の病気で神経内科以外に入院したところ、調子が悪くなったりてんかん発作が再燃したりすることもあるでしょう。夜間などに初期対応できないと困りますよね。そんなときも本著の出番です。非専門医のための抗てんかん薬が充実しています!
もっていれば、「神経内科に行った同級生にいつでも気軽に相談できる」感覚
24時間いつでも、気軽に相談してぶっちゃけを教えてくれる他科の友達がいると心強いですよね。そんなとき、「神経内科を専門にした大学時代の同級生に気軽に相談できる」かのような一冊です。
すべての研修医、すべての非専門医にオススメです(たぶん、病院の机の上に置いておけば、1ヶ月に何回かはお世話になる本に「間違いなく」なるでしょう)。
ちなみに、「せん妄」や「認知症」、「しびれ」など、他科の医師にとって「かゆい」ところに恐ろしく手が届いています。たぶん、「買ったらついつい読み進めちゃう」タイプの本だと思います。
ちなみに、、、内科外来をしているすべてのドクターへ
いつかは紹介したかった非専門医向けの「腎臓内科」本もリンクだけ貼っておきます。こちらは「いかに腎臓内科医の守備範囲が『いわゆる内科医』的か、ということをすごく感じさせられる本でした!外来通院している患者さんたちをどう管理していくか?を見直す良いきっかけになると思います。オススメです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
