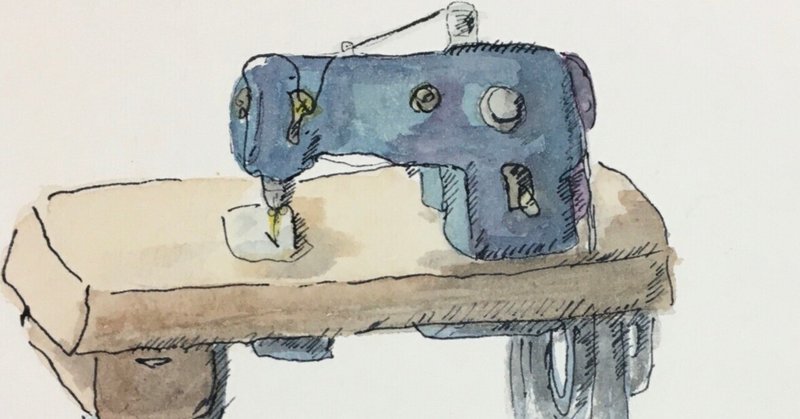
テーラーの父と手伝い娘 ~ 昭和の話
ハ刺し
栃木県出身の父が東京で注文紳士服店を開いたのが何歳の時だったのか、私は知らない。開店した頃の話やそれまでにしていた仕事のことを、娘である私が何十年も生きてからようやく興味を持って聞きたいと思ったときには、父はすでにこの世を去っていた。
私が覚えている一番古い父の働く姿は、小さな二階建ての家の一階に構えた小さな作業場で、背広やズボンを作っている姿だ。
父とは五つ年下の母も、私と兄、姉の三人の子供の世話をしながら、家事以外の時間は作業場で紳士服作りを手伝っていた。
作業場と客の接待用のスペースから成る「店」と、その奥の居住空間は、曇りガラスと木の葉模様のガラスをはめ込んだ戸で仕切られていた。店に来た客には、そのガラスから奥の様子はぼんやりとした色と光の動きぐらいにしか見えなかったはずだ。
そのぼんやりとしている居間で独り遊ぶことが多かったまだ子供の私は、つまらなくなるとたまに作業場に入っていった。たまにはそのまま父の手伝いもした。手伝いには遊びのようなおもしろさもあった。
ある日は、父を手伝って「ハ刺し」もした。
「ハ刺し」とは、背広の襟の芯と服の生地をいくつものハの字のステッチで縫い合わせる作業だ。これによって襟がしっかりして、形も決まる。完成時には見えなくなってしまう部分だからか、父は時々私にも針を持たせ、二つか三つ、「ハ」の字を縫わせた。
大きくて厚い一枚板の作業台によじ登って、まだ小さな手に仕事用の針を持ち、プチ、プチと縫ってみせる。白いメリヤスのシャツを着て首にメジャーをかけた父は、アイロンの手をちょっと休めて、自らがきれいに縫い並べたハの字に続く、出来立ての新しいハの字をちらりと見て、「うん、よし」と言う。娘を見てにっこりするわけでもない。そっけない。それでも「よし」と言われると私はなんとも嬉しいのだった。
ウィンドウ拭き
あれは幼稚園生の頃だったか、あるいはもう小学生になっていたのか。週末になると私は店のウィンドウを拭く仕事を手伝った。朝ご飯の前に、柔らかい木綿布や古タオルを使ってウィンドウを内側から拭くのだ。
「小さいからジンダイとガラスの間に入れて助かる」と、ある日、父はちょっとだけ嬉しそうにそう言った。
私は、年の離れた兄や姉とはあまり遊んでもらえなかった。10歳上の兄はたまにプロレスごっこと称して手加減しながら遊んでくれたが、7歳上の姉からすると私はどうにも相手にしづらいらしく、あれこれ世話はしてくれたが、妹と一緒に笑い転げるようなことはなかった。母は、たぶん末っ子の私を特別に可愛がっていたはずだが、いつも気持ちがどこかにふわふわと消えてしまうような、気難しく何がきっかけかもわからぬまま怒りだす父に常に落ち着かずにいるようなところがあり、私に安心感を与える存在にはなり切れていなかった。
だから、私は、子供ながらにもこう思っていた。他の家族みんながその職人ぶりと仕事ぶりを尊敬しながらも距離を縮められない存在である父に気に入られれば、自分もこの家で認められて生きてけるだろう、と。
商店がいくつか並ぶ細い通りに面して設けられた奥行きの狭いショーウィンドウ。私は、作業場からそのスペースへと昇っていき、手の届く範囲ぎりぎりまでガラス窓を拭いた。そこには完成した紳士服を着たジンダイが立っている。「ジンダイ」というのは、勝手にそう呼んでいただけで、実物は洋裁で使うトルソーだった。人の体幹の部分だから「人体」と呼んでいたのを「ジンダイ」と聞き間違えたままでいたのか、正確な記憶はない。
ジンダイのお腹の辺りにぶつからないように蟹のように横に移動しながら、店のウィンドウを拭いている子供の姿は、近所の人や通行人にどう見えただろうか。健気だな、可愛いな、いいお嬢ちゃんだな、しっかりと育てているご両親なんだろうな。そんな噂もされたかもしれない。あるいはそれが父の狙いだったのか。当時の父の年齢もとうに過ぎると、私は振り返ってそう怪しんだ。なぜなら、父はよくこう言っていたからだ。
「人に好かれなきゃだめだ」
昭和三年生まれ。東京に出てきて、所帯を持って、店を構えて、子供もできた。高度経済成長期に入っていた頃だろうけれど、本家や親戚の経済的な後押しが得られたという話は聞いたことがないので、たぶんほとんど元手のないところからのスタートだったのだろう。人当たりはよく、ウィットに富んだ会話もできた父。だが、彼はなぜか自分の家族にはそんなふうに接することがあまりなかった。言葉遣いも食べ方も礼儀も、常に厳しく子供たちに教えた。人を褒めろ、と彼はよく言った。だが、家族の中だけで子供たちを心から楽しそうに明るい声で褒めてくれたことは、数えるほどであった。
好かれるということは、ちゃんとするということだ。ちゃんと働くとちゃんと好かれるのだ。私はそう信じた。
お茶出し
小学生になった私は、紳士服を注文しに来た客によくお茶を出した。ランドセルを背負った私が作業場のドアから中に入ると、時々知らない男性と父が話している声がした。お客さんだとわかれば、そのままガラス戸の奥に入ることはできない。カーテンで仕切られた採寸スペースや椅子と低いテーブルが置かれた接待スペースへと作業場から回り込んでいって、「いらっしゃいませ」と頭を下げる。
客は小さな女の子がちゃんと挨拶をしてくれるので嬉しそうに目を細めて「はい、こんにちは」とか「これはどうも」とか「可愛いお嬢ちゃんだね」と言う。父は私を見るのではなく、客を見ながらにっこりとする。
台所では、母が客に出す飲み物や菓子を用意している。たいていは日本茶や紅茶と食べやすそうな大きさの煎餅や甘い菓子だ。お盆にそれらを載せると、母は私に持たせて「出しといで」と言った。こぼさないように、お盆を両手に持って、そろり、そろりと居間を通過し、母が開けておいてくれたガラス戸の向こうの店へと進む。待っていた父が手を伸ばしてお盆を受け取り、「どうぞ」と客にお茶を出す。私はぺこりと頭を下げて奥へ戻る。私はその言葉の存在を知る前から「営業」や「受付」のようなことをしていたようだ。
母が「これは危ないから」と私に運ばせなかった飲み物がある。それは、スプーンに載せた角砂糖をウィスキーで湿らせて火を点け、コーヒーに入れてかき回すものだった。これが好きだったお客は、何度か服を注文してくれたお得意さんで、裏地には浮世絵のような柄を選んだことのあるお洒落な人だったらしい。台所で青白い炎に砂糖が崩れていくのを見ていた私は、早く大人になってこういうのを飲みたいなと思った。心配ご無用で、私は晩酌が大好きな大人になっていく。
残業手当
職人や見習いも雇ったことはあったが、基本的には一人で店を切り盛りしていた父は、注文が重なって忙しい時期には夕飯を食べた後もまた作業場に戻り、ミシン仕事や裁断や仮縫いを続けた。
土曜日の夜は子供たちも夜更かししてもよいことになっていた。兄と姉は二階の部屋でレコードを聴いたり友達に手紙を書いたり、そんなことをしていたようだ。私はその世界に憧れていたけれど、まだまだ幼かった私が部屋に入るとなんとなく二人に邪魔に思われるような気がしていた。
一階の様子を見てみると、今夜の残業も終わった父が作業台を片付けている。父は毎朝作業場と店の雑巾がけをし、仕事が終われば作業台の糸くずなどを丁寧に掌にすくい集めてゴミ箱に捨てる。夕飯を終えている私は、居間の食卓を兼ねた炬燵台のそばでテレビを観たり本を読んだりしながらも、時々その一連の動きを見たりしていた。
父が一段高いこちらの居間へと上がってくる頃を見計らって、母は酒と簡単な肴をその炬燵台の上に並べる。飲む酒はたいてい熱燗であった。たまにビールやウィスキーの瓶が置かれることもあった。よっこいしょという感じで父が炬燵台についてあぐらをかくと、私はよく父の膝にのぼったものだ。そうすると父の機嫌が良くなることもわかっていたし、うまくすると肴を一口分けてもらえるからだ。私はくじらベーコンを薄く切ったものや、炒った銀杏、山芋をすったものが特に好きで、父の箸の先が自分の口元にやってくるのを待った。たまには上客に出した握りずしの余りが出てくることもあって、卵焼きや海老がもらえた日はそれこそ大幸運日だ。
「これは酒呑みになるな」と少し赤ら顔になった父は、肴を美味しがる私を見て、ようやく顔をほころばせ、のんびりと猪口を口に運んだ。この残業手当は普段の晩御飯よりもおいしい。ちょっとしか食べられないところが、また一段と美味しさを増すのだった。
父の楽しみはテレビでプロレス中継や自然の動物たちを追ったドキュメンタリー番組を観ながら飲むことだった。さすがに夜更かしも付き合い切れず、私は膝の中でうとうと舟をこぎ始める。ふと気が付くと、いつの間にか父の背中におんぶされた状態で二階への階段をゆっくり上がっている。まるで猿の親子のようだ。子猿は父母と同じ部屋に入り、敷かれた布団の上にゆっくりと移され、そのまま眠りへと引っ張られていった。
輸送と納品
父は、出来上がった紳士服を車で客に届ける時や、仕事の関係であちこち出掛ける時、私を一緒に連れていくことがあった。
私は喜んでついていった。東京の町の中をスバルが泳いでいく。小さな通りも、大きな交差点も、父はすいすいとハンドルを切っていった。個人宅に服を届ける時など、私も上がらせてもらい、その家の奥さんからお土産にお菓子をもらうことがあった。そんな時はなんとも嬉しかったものだ。
外回りのドライブを終えて、家の近くに借りている駐車場に車を止める。もう夕方だ。車から降りた父と娘は、トランクから大きなカバーを取り出して、走り終えた車にかけてあげる。「耳をやってくれ」と父。耳とは、車のミラーの部分だ。動物の耳のように見えるとある日私が言った日から、ミラーは「耳」と呼ばれるようになった。カバーには二つの丸い突起部分が縫われていて、その中にうまく耳を入れるのは私の役目だ。
ボディ全体にカバーを賭け終わると父と娘は手をつないで帰る。この時の父はなぜかいつも優しい。たまに見られる「機嫌が悪い」という現象も、この状況では起きたことがない。もしかしたら父は外に出ていくことで少し気分が変わっていたのだろうか。そもそも、機嫌が悪くなるのは、一人で家族四人を食べさせていかねばならないという、いつ終わりがあるかも知れない緊張感に、内心いら立つことがあったためではなかったか。
つないだ手を父が引き上げると、私の体は一瞬地面から浮き上がる。私はうぉっと声を上げて笑う。家までの道を、夕ご飯が待っている家までの道を、二人はそんなふうに歩いて帰った。
夢の終わり
それから長い年月が経ち、やがて店じまいの日がやってきた。父はまだ働こうと思えば働ける年齢であったが、世の中には廉価な既製のスーツが商品として大量に出回り始め、わざわざテーラーメイドの注文服を頼むような客も大きく減ってしまっていた。
ついでに家までもなくなることになった。父と母は長男夫婦とその子供たちと完全に同居するため、郊外の家に引っ越すことになった。家屋兼店舗は確かに父が建てて守ってきたものであったが、土地は借りていたため、その地代もなかなかに大きな負担となっていたのだ。それに、もう町の中で生活する必要もなくなってきていた。
郊外への引っ越しの翌日、あるいはその翌日だったろうか。まだ荷物が片付かない新しい家で、孫たちも入れた家族みんなが揃って夕食の食卓に着いたとき、兄がどこを見るでもなく、低い声でぼそりと言った。
「今日、家を見に行ってきたけど、もう解体されてたよ」
一度は家業を継ごうとしたが、時代と、それから自分の生き方を見直してサラリーマンの道を選んだ兄。長男というだけで、どれほどの葛藤や父との摩擦もあったか。今でも私には察しきれるものではない。
父はそれを聞くと、ガラスコップの中のビールをぐっと一口飲んで言った。「いちんちか、ふつかぐらい、待てないもんか」
あの、巨大な一枚板、ガラス戸、ショーウィンドウ…。
当時会社員として勤めていた私は、ちらっと父の顔を見たが、その感情を読み取ることはできなかった。悔しいのか、諦めていたのか。男一代、上京して作り上げた夢は、そこで、完全に終わったのだ。
技術の価値
私が結婚して十数年経った梅雨の最中、父は癌でこの世を去った。喜寿を迎えてすぐのことだった。昭和の頑固おやじ、厳しくて、怖くて、でもにっこりとするとびっくりするくらいいい顔をした父であった。若い頃はさぞかしハンサムだったことだろう。戦中と戦後の目まぐるしい変化や苦境がなかったら、テーラーにならずに別の仕事をしたかっただろうか。どんな夢があったろうか。
私は入院中の父の見舞いに行ったとき、そのことを聞きたいと思ったが、とても聞けなかった。兄が母と相談して、癌の告知はしないと決めたからだ。これまでの人生のことや、今会いたい人はいるかなど聞こうにも、下手なことを口にすれば、「俺は長くないんだな」とふてくされて落ち込んで、むっつりと黙ってしまっただろう。癌だということまでは本人も医師に告げられたが、治療して経過が良ければまた家へ帰れるとしか言われない。だが父は自分の体のことはよくわかっていたようで、髭を剃るときも手鏡を使おうとしなかった。自分の外見の変化を見たくなかったのだろう。口では「早く帰ってまた一杯飲んで、山登りをしたい」と言っていたので、家族も「そうだね、また良くなったらね」と繰り返す。いよいよ個室に移されても、そんな会話を家族が交代でしていた。それも優しさというものなのだろうか。ぎこちないような切ないような家族間の約束事の中で、父の本当の夢はついぞ語られることなく、空へ昇っていった。
葬儀も済むと、家族はそれぞれにいつもの暮らしに戻っていった。やがて、朝晩は少し肌寒くなってきた頃、私は夏服と冬服を入れ替えようと、押し入れの衣装ケースを引っ張り出した。普段よく着るものが上になるように服が重なっているので、まずはそれらを取り出す。すると、ケースの一番底のあたりに、それが姿を現した。
濃いうぐいす色のジャケットだ。
私が会社員として勤めていた20代の頃、紳士服の生地が余っていたのを使って、父は私が職場で着られるようにとこのうぐいす色のジャケットを縫ってくれた。仕立てる前に、客にそうしていたように、肩幅、胴囲、着丈とメジャーで測られたことが年頃の自分には気恥ずかしかったことを覚えている。だが、さすがはベテランのテーラーだ。きれいな仕上がりで、オニキスのような黒に金色の縁取りをした、おそらく手持ちの中でも値の張ったはずのボタンが正面と袖口で光っていた。
せっかく作ってもらったジャケットだったが、出来上がりがかっちりとして立派すぎたし、OLの服装としてもっと女性らしい服や流行りの服を着たかった私は、これを数回着ただけで、押し入れにしまっていた。結婚しても、引っ越ししても、さすがに捨てるわけにもいかず、物は良いし、いつまた着るかもわからないと、ずっと眠らせていたのだ。
私はジャケットの肩の部分を両手につかんで全体が見えるように引き上げ、全体をしげしげと見た。それから、実に久しぶりに、袖に腕を通してみた。さっと背負うように襟元を前へと引きながら、洋ダンスについている姿見の前へと歩いていく。体形は変わっていないので、ジャケットは今も体にぴったりと合っている。肩のホールの部分に皺はひとつも寄らず、それなのに両腕を前に伸ばしてみても、どこもつる感じがない。前身頃もウエストにかけて綺麗なカーブを描いている。そうして、女性用に細めに作られた襟は、今も変わらずにびしっとしていて、着物にも似た凛とした強さを感じさせる。
この襟は、白髪が目立つようになった父が、一人でハ刺しをしたのだろうか。
そう想像した途端、鼻の奥あたりがつーんと痛くなってきた。この服が作られた当時は、友達と遊ぶことや、稼いだお金で好きな習い事をすることや、ちょっと恋愛もどきの楽しみや、そんなことに夢中で、相変わらず作業場で働く彼を気遣ったり、彼とどこかへ出かけてゆっくり話そうという気持ちがすっかり後回しになっていた時期だった。
素晴らしい職人さんだったんだな。
私はジャケットを羽織ったまま、その袖やウエストのあたりをそうっと撫でた。
もう、この新しい時代には現れないかもしれない、いい職人さんだ。
私は姿見の自分の顔を見ることができず、部屋着の上に立派なうぐいす色を羽織ったまま、両手で目を覆った。
(イラストは私が描きました。)
~終わり~
元保護犬であった愛犬がシニアとなりお空組となりました。まだまださびしい毎日ですが、これからも保護犬たちが幸せをつかめるように何らかの行動は続けたいと思います。愛ある作品も素人ながら作ってまいりたいと思っています。 お茶一杯分ほどでもサポートをいただけたら心から嬉しいです!
