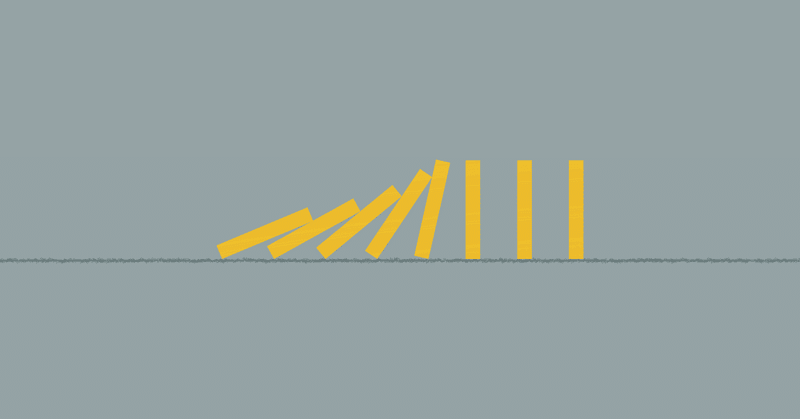
学びの駆動因について考える
人生の師と仰げる人がいること。それは非常に幸せなことだと思います。
私にとっては大学時代のゼミの恩師の先生が、自身の「師」の一人です。
ですが、不思議なことに、私は、その理由をきちんと言葉にすることができません。
「○○だから、尊敬していて、それゆえ、師として仰ぐのだ」ということをはっきりと言葉にできないのです。
いえ、正確に言えば、言葉にすることはできます。ですが、どのような言葉を選んで、師を仰ごうとも、「どうしても自分自身の中でしっくりとこない」のです。
私はこのことを、師が「自身の理解の範疇を超越している存在」であるからという理由で結論付けています。
師のすごさを、自分の手持ちの言葉で語ろうにも、なんだか胡散臭くなってしまう。それは、「他者にとって胡散臭い」のではなく、「自分が語る師に関する言葉が、自分にとって胡散臭く聞こえてしまうから」なのだと思っています。
そして、これは、ただ単に、「師を師たらしめる、その理由」を、自分自身が言葉として有していないことからくる「胡散臭さ」だと思うのです。
では、もしそうだとしたら、そもそも、師を師として仰ぐ、その理由は何なのだろうか、という問いに立ち戻ります。
結論としては、「なんだかよくわからないけれど、この人はものすごい人な気がする」
「この人についていけば、なんだかとてつもないものが学べる気がする」
というように、「なんだかよくわからないけれど、ものすごい」ということを感じることができるかどうか。それにかかっているような気がしています。
これは、様々な物事から得る学びに共通します。
自分自身が対峙している人、もの、出来事。
それらから「なんだかよくわからないけれど、ものすごい」と感じるとき、学びのスイッチは起動し、「なんだかよくわからないけれど、ものすごい」と感じる、その理由を言葉にすべく、その対象となるヒト・モノを「師」とするのだと思うのです。
「なんだかよくわからないけれど、ものすごい」という文節が「○○だから、この人からは○○が学べるのだ」と言い換えられたとき、既にそこには真の学びは存在していないのでは?
私はそう思うのです。
この、師が師たる理由を語れない理由を考える上での補助線となったのが、内田樹氏の「先生はえらい」という一冊でした。以下、一部を抜粋します。
書物を経由しての師弟関係というのはもちろん可能ですし、TV画面を見て、「この人を先生と呼ぼう」と思うことだってあって当然です。
要するに、先方が私のことを知っていようが、知っていまいが、私の方に「この人の真の価値を知っているのは私だけだ」という思い込みさえあれば、もう先生は先生であり、「学び」は駆動するのです。
「学びの主体性」ということで私が言っているのは、人間は学ぶことのできることしか学ぶことができない、学ぶことを欲望するものしか学ぶことができないという自明の事実です。(中略)
学びには二人の参加者が必要です。送信するものと受信するものです。そして、このドラマの主人公はあくまでも「受信者」です。
先生の発するメッセージを弟子が「教え」であると思い込んで受信してしまうというときに学びは成立します。「教え」として受信されるものであれば。極端な話、そのメッセージは「あくび」や「しゃっくり」であったってかまわないのです。「嘘」だってかまわないのです。(P36-38)
私の方に「この人の真の価値を知っているのは私だけだ」という思い込みさえあれば、もう先生は先生であり、「学び」は駆動するのです。
「なんだかよくわからないけれど、ものすごい」と感じる、その理由を言葉にすべく、その対象となるヒト・モノを「師」とする、ということを考えると、「ものすごい」というメッセージを身体に受けた瞬間から、その対象となるヒト・モノから「受信する」メッセージ全てが、「教え」として変換され、その「教え」を享受され続けることにより、「なんだかよくわからないけれど、ものすごい」という理由を言葉にすべく「学び」は駆動することになる。
ざっくりまとめると、自分にとって「わからないこと。言葉にできないこと」の対象になるヒト・モノこそが、学びを駆動させ、「師」となり得る可能性を有している。としたならば、日々は学びの駆動因に溢れていると言えるのかもしれません。
【こちらもどうぞ】
法人事業や研究に関する資金として大切に活用させていただきます!
