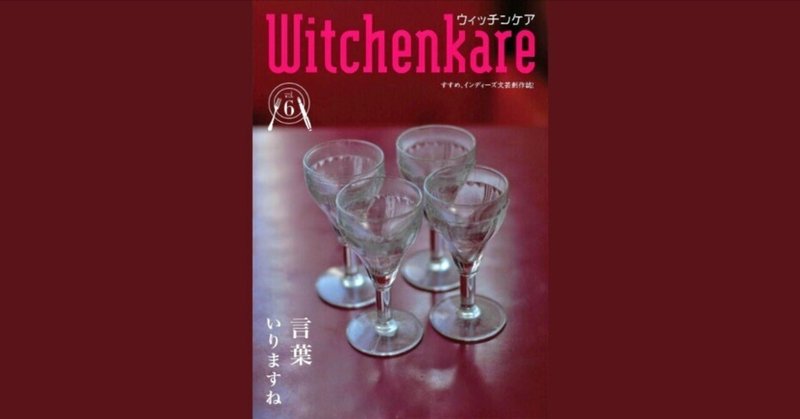
若杉 実/マイ・ブラザー・アンド・シンガー
「ガチャ」
鈍い音が天板を叩き床に落ちた。ドーナツみたくまん中が照明でくり抜かれたリビングに重々しく響く。時計の針はそのとき3時を回っていた。
耳で確認するやいなや目のまえに広がる光景を充血した目が捕らえる。指先の置かれた針板には散乱した血痕が。赤い斑点はひとつひとつ均等に分散され、ライトの反射で小さな光を放つ。
「蛍みたいだな……」
まぶたを半分伏せそうつぶやくも、つぎの瞬間おもわず口の端を持ち上げる。他愛ない記憶の断片によるしわざだった。ガキのころ母を驚かせようとクチからケチャップを垂らし死んだふりを居間でしていたことを想い出したのだ。古典的な血の代替はどう見てもムリがあることを、目のまえの光景がいまごろになって教えてくれている。
グサリといった針は左ひと差し指の爪先3ミリをタテに割っていた。それでもふしぎと痛みはない。ティッシュペーパーで血の流れを抑えると、おもむろにイスから腰を上げ、救急箱がある戸棚を目ざした。
いつかこうなるだろうとわかっていたが、やめられるものならやめている。風呂上がりの一杯とともにミシンと向きあう至福の時間はなにものにも代えがたいものになっていたのだ。
オレの名前はシゲル。年齢は45。ここんとこミシンにハマってる。20年まえの自分なら鼻で笑ってるところだろう。そのころから変わってないが、仕事はグラフィックデザインをやってる。
15年まえに独立して事務所を立ち上げた。事務所といってもひとりだ。以前は10歳下のアシスタントを雇うほどまあまあ潤っていた。だからあるていど目をつむっていたが、そいつがトンデモ野郎で、見習いのくせに自分の名刺をつくってオレの知らないところで仕事を横取りしていた。自分の仕事のゲラを事務所のファックスにあやまって送らせたことで発覚する。もちろん即クビにした。
そいつのひと言ひと言にも気に障るものがあった。
「シゲさん、また渋谷系でいくんスか?」
クライアントとの打ち合わせの帰り、オレの横顔に向かって軽口をたたく。路地に連れ込みその場で張り倒してやりたいところだったが、ぐっとこらえしれっと返す。
「それが悪いか?」
たしかに90年代は猫も杓子も渋谷系だった。クライアントにも同業者にも「とりあえず渋谷系」というイージーな空気があった。中坊から永ちゃん一筋のオレが渋谷系だなんて笑わせてくれるじゃねえかとおもっていたが、背に腹はかえられない。業界内には「渋谷系ならシゲ」というのができあがっていて、それを堅持するため知りたくもない情報を日々かき集めていた。
事務所ももちろん渋谷にあった。ほんとは下北あたりでマイペースにやりたかったが、名刺に渋谷区と世田谷区とあるのとではちがいが大きすぎる。名刺を差し出し「やっぱり!」と会話に弾みがつき、首尾よく仕事が運んだことなんて一度や二度じゃきかない。なにかと都合がよかったのだ。セックス・アンド・ザ・シティのミランダのセリフにマンハッタンとブルックリンの関係を嘲笑するのがあったが、それくらいの差があってとうぜんだろう。
とにかく渋谷を拠点にしているだけで、いつでも攻勢をかけているような気分になれた。ほんとはそんなのどうでもいいことだが、この業界には〝見てくれ〟に命を燃やす手合いがうじゃうじゃいるんだからしょうがない。
そういうオレもかつては〝見てくれ〟の人間だった。
大学進学とともに上京して2年の夏からスタイリストのアシスタントをすることになったのだ。18年という実家暮らしから解放され、あこがれの東京生活を手に入れたとき描いたイメージといえば、お台場のTV局が絶好調だったとき流行ったトレンディドラマ。学生のくせしてTV局に出入りするADというキャラ設定はホントなのかどうかわからなかったが、妙なシンパシーを抱いた。
ネットもない時代だからアルバイト情報誌を買い、まっ先にマスコミのページをパラパラめくる。TV、ラジオ、出版社、広告代理店、CM制作会社、イベントコンパニオン……ひと言でマスコミといっても多種多様だし会社もピンキリ。「はぁ〜」──開いて数分も経たないうちにため息をもらしたオレの目にたまたま飛び込んできたのが「体力に自身があるひと」、いわゆるガテン系のページだった。中とじのまん中にそれがあり、折り癖がついていたのだ。そしてつぎの瞬間「まさか」と目を疑ったが、そこにスタイリスト・アシスタント募集の文字が刷り込んであった。
きな臭さを感じつつ代官山にあるという事務所に電話し面接に行く。するとドアの向こうで水色や黄色のインコが放し飼いにされていた──「やっぱりこういう世界があるのか」。オレはなんだかんだいって面接をパスし、すこしのあいだだけその世界におせわになる。
それから先はいろいろめんどうだから省くが、業界の知己を頼ってゴロゴロしながら大学卒業後にとあるデザイン事務所に入った。出版とかの平面のデザインにいまいち関心が持てなかったが、羽振りのいい時代だったしCDも売れまくっていて仕事にあぶれる心配なんてなかった。
あのころの仲間には一山当てて都心に一戸建てを購入している者もいるが、いまはそんなに甘くない。オレは根も田舎者だからどこかで歯車がおかしくなって、事務所を立ち上げたところまではよかったものの、音楽業界バブルの崩壊とともに仕事はみるみる払底してしまった。
クライアントの合コンで知り合ったアパレル関係の女と結婚していまは川崎に住むが、デザインの仕事は細々とつづけている。もっともフィジカルでリリースするアーティストなんてめっきり減ったため、地元のしょぼい情報誌のデザインとかでなんとか食いつないでいる状態だが。
うちはディンクスだし時間ならつくろうとおもえばつくれる。そんなことから気晴らしにはじめたミシンだったが、これほど血道を上げるとは自分でもおどろきを隠せない。
きっかけは渋谷にいたころ。区画整理のため近所の家が立ち退く際、玄関のまえに不要品を並べていて、そのなかに古びたミシンがあった。最近のとはちがいがっしりした鉄製のボディに、はげ上がったクリームの塗料が頽廃的な美を醸し出していた。オブジェにいいかも、とおもったのだ。そのまま持ち帰りホコリをかむったままだったが、引っ越しのとき気づき試しにやってみようといじりはじめた。
この歳になってもファッション雑誌にはひととおり目を通すし、学生時代の名残りでヴィンテージものとかいまだに買ってたりする。
しかしとうぜんというか、服をデザインするとか裁縫なんてものにはまったく興味がなかった。裾上げはもちろん、ボタンの付け替えすらできなかったくらいだ。だがこのご時世、お直しとかにいちいち持っていくわけにもいかなくなったし、中年のオトコが膝の抜けた501XXをリフォーム屋に持っていく姿は想像するだけでもイタい。
「これ、こんなにボロでも10万は下らないんですよ。渋谷でスニーカー狩りがあったころならその10倍かな」──こう説明したところで店のおばさんには雑巾でできたズボンにしか見えないだろう。
指をケガしたところでミシン熱が冷めることはなかったが、扱うものには変化が見られるようになった。おなじ藍染めでも洋服ではなく日本のトラディショナルなワークウェア、野良着や襤褸がミシン台に乗ることのほうが多くなった。
川崎に引っ越し豊かな緑に囲まれ築40年の団地で暮らすようになったのだからと、俗にいうスローライフをはじめたのである。我ながらずいぶんと角がとれたものだ。
手はじめになんだろうとおもい、身近な食べ物にトライしてみることに。毎日の白米を週2で玄米に切り替え、なるべく穀類を摂取する。べつにビーガンを目ざそうというのでもないし、そんなことばつい最近知ったが、何十年と堆積された都会生活の垢がそれとなく気にもなっていたのだ。成人病対策に間にあうかどうかわからないが、夜型からじょじょに朝型の生活に移し、健やかな目覚めとともにベランダの手すりにやってくるコガラやメジロと会話する〝そぶり〟も日課になっていた。
そうやってピーチクパーチクしながら、プランターから顔を出す葉っぱが、うどんこ病になっていないか覗き込む。野良仕事とまではいかないが、ひとまず家庭菜園でもやってみるかとミニトマトの種を植えると、3週間ほどで花が咲いた。赤くないから失敗したかとおもったが、そのうちビー玉みたいなのがよこっちょから出てきて、それがトマトだと初めて知る。
たったそれだけのことなのに、もんぺの股下をす〜っと抜ける清風を感じながらの土いじりは、オレの気持ちをまるで白洲次郎にしてくれるのだった。ここに引っ越してまもないころ近所の鶴川にある旧白洲邸武相荘を訪れたことで、それとなく意識するようになっていたのである。
日本で最初にジーンズを履き、鶴川に隠居してから野良着とツイードをこよなく愛した稀代のカントリージェントルマン。「21世紀の白洲はオレだな」と勘違いしながらも、時間さえあれば部屋にこもり古布の織目を指先でたしかめながら針をぐいぐいとあてがう。もちろん久留米の半纏を羽織って。その姿はどちらかといえば白洲の奥方、正子なのかもしれないが。
後年になり白洲正子が銀座の染織工芸店『こうげい』の経営者になるのも、野良着、もんぺ等古布の魅力に取りつかれたことがきっかけだったらしい。物資の供給がままならない戦時中、古着をかき集めながら布団や野良着のおもいがけないモダンな柄に正子は感激する。それは単体で成立する世界ではない。柄と柄を精妙に組み合わせて一種のパッチワークとして再生されたものだった。
正子が通暁するもうひとつの世界、陶芸にも〝よびつぎ〟という手法がある。割れた茶碗の破片を寄せ集め、用の美として再生させる。自著『風姿抄』のなかでこう語っている──「欠けたりヒビが入った焼きものを賞翫することなど、どこの国にもないだろう」。
古着とりわけヴィンテージの世界で襤褸は〝ジャンク系〟と呼ばれ珍重されてきた。1981年にパリコレ・デビューした川久保玲が自身のブランド、コム・デ・ギャルソンで賛否両論となったBOROルックもこれと似たようなものだ。あれから四半世紀、やぶれ継ぎはぎはりっぱなファッションに昇華している。
厳密に今日のジャンク系は〝アンファッショナブル・ファッション〟(一過性の流行ではなく永続的スタイル)、つまり労働着カルチャーとして分類される。「お洒落な人より洒落た人になれ(石津謙介)」とはよく言ったもので、内面から湧き出た知性感性美学の結晶として男性服飾はあるべきというのがこのスタイルの建前なのだろうが、アパレル用語としてがっちり喧伝されてるいま、その本質はずいぶんといぶかしくなってしまった。
タンスの奥には多くの〝患者〟が眠っている。週に2日、いや連日やらないと増えるいっぽうか。ミシンの上達はあいかわらずだが、むかしみたいなドジはとりあえずしなくなった。「縫うなら飲むな」──ながらミシンはやめたのである。あくびを嚙み殺し針先に集中するのがしんどい年齢にもなったのだが。
もっとも最近そんなミシン・ライフに光明がさすできごとがあった。下糸の通しが芳しくなかったため、おもいきってミシンを新調したのである。型落ちの展示品で3万。オレにとってそれは浪費ではなく投資だ。独身時代の想い出がつまっているミシンにもちろん愛着はある。だが、現代ミシンの定番であるマイコン内蔵という魅力には勝てない。
その雲泥の差に毎晩オレは目眩をさせられっぱなしだ。いちばんのお気に入りが、ヴィンテージ・デニムの裾上げに絶対不可欠のチェーンステッチ機能。それに水平全回転式の釜で、ボビンすら不要ときた。これじゃいままでの下糸セットはなんだったのか、ばかばかしくなってくる。ほかにも機能満載でさらに熱を上げそうだが、おっと、床に就くカミさんはだいじょうぶか!? ……とおもったら先刻承知よ、と静音設計だ。
女房と畳はなんとかというが、ミシンだっておなじだろ。まるでフィギュアでも舐めまわすようにぐるりと⾒渡し、スイスイと縫う⾃分の姿をあたまに浮かべながらハンドホイールのところをおもわず頰ずりしてしまった。
そのハンドルのすぐ傍にあった〝ブラザー〟の⽂字はもうなくなってしまったが、いまは代わりに赤で塗装された〝シンガー〟のロゴが輝いている。
【初出:2015年月/ウィッチンケア第6号掲載】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
