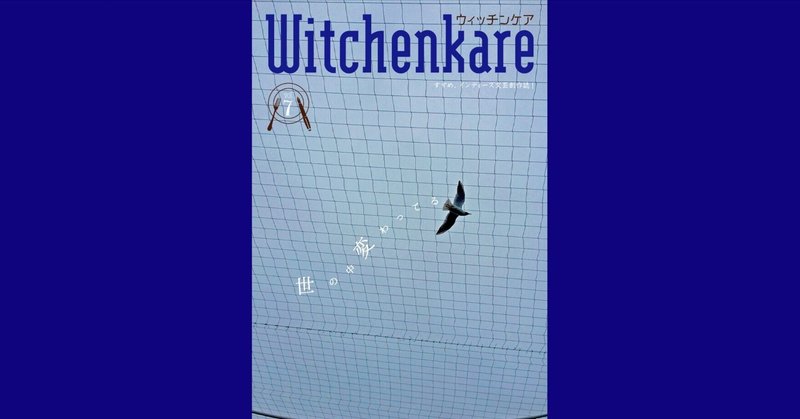
太田 豊/日々から日々へ
たとえば、なぜ雨が降ってくるところを見ようとしなかったのか。
雪の降ってくるところなら見ようとしたことがある。
冬の夜、鼻先に冷たいものを感じて、空を見上げてみると、雪が次から次へと顔に降りてくる。厚い雲に覆い尽くされて真っ暗な夜空から、雪の結晶たちが手をつないだようにかたまりになって、ゆっくりと。
暗い背景の中から数限りない白い破片が不意に現れ、こちらに向かってくる。そしてそれが際限もなく繰り返される。
その雪のひとひらがいったいどこから落ちてくるのか、そこを見きわめようとするのだが、灯りのためか視力のためか、結局はその暗い背景のどこからともなく現れる、としかいいようがない。どのひとひらも、いきなり現れて、現れたと思ったら、あっという間に自分のこの頬や額に降りてくるのだ。
雨ならこうはいかないかもしれない。雨は雪よりも足が速いし、ひとつぶひとつぶも雪より見えにくい。見ようとしたとたんに、顔はあっという間にずぶ濡れになってしまうし、何より、雨がメガネに当たってしまえば、瞬時に明瞭な視界は奪われてしまう。
だが、それをなぜさらにむかし、メガネをかける前の子供のころに思いつかなかったのか。要は、雨の降ってくるところを見てみようなんて好奇心を持ち合わせていなかったということなのだろう。
考えてみれば自分の場合、見ることそのものへの驚きは、中学二年生で初めてメガネをかけたときから始まった気がする。晩の食卓でお茶碗に盛られたごはんのひとつぶひとつぶがくっきりと見えたそのときの驚きたるや。同時にそれまでお茶碗に盛られたごはんを単なる白いかたまりとしてしか捉えていなかったこと、そしてそれがいつからだったのかまったく覚えていないことに気づかされ、また戦慄したのだった。
今では、目が悪くなるという発見が、不便ながらも面白く感じるようになった。小さい字が見えないので本をちょっと遠くに離す、ということは当然のようにやっていたが、少し暗いところでてきめんに字が読めなくなるという事態にでくわしたときにはやはり驚いたし、笑ってしまった。知らないところで自分の認識できる世界はじわじわと狭まっているのだ。
ところで、婚活を始めた。
離婚してしばらく経つからというのと、まあお恥ずかしい話だが、いまだに子供が欲しいのだ。もうトシなので、その子にいわゆる親らしいことはしてやれないかもしれないが、子供が立ち上がったり、ことばを覚えたり、親につっかかったりするところをやはり見てみたい。
そんなわけで、某婚活系アプリの会員になってみた。登録している女性会員の写真と名前が画面にずらりと並ぶ。若い人、お年を召した人、ピースサインをする人、顔の一部を隠している人、さまざまだ。あからさまに美女でございという人も少なくない。下から見上げるアングルばかりを選んでいる人もいるが、これはやはり自分が可愛く映るための知恵というものか。
プロフィールには、本人の写真・年齢・居住地・身長・段階別体型・職種・同居人といったものから、結婚歴・年収・子供の有無などを記す欄があって、本人の興味や志向を表現するための「参加コミュニティ一覧」や自己紹介文を閲覧することができる(ただし「参加コミュニティ」とはいっても、mixiとは違って活動の実態はない)。これを見て希望の相手にメッセージを送り、相手から返事があれば、あとは各自やりとりの後ご自由に、というシステムだ。
とりあえず手当たり次第にプロフィールを覗いてみると、これが恥ずかしいくらい面白い。こんなにいろんな女性が交際相手を探しているという事実にまず感じ入るが、その背景の多彩さには目もくらむ思いがする。小説家だったら、これだけで連作短編集の一冊くらいは簡単にものせるのではないか。
あからさまに美女だという人は美容関係の仕事が多く、口々に出会いのなさを嘆いている。投資信託会社の回し者や、男性に夢を与えるだけの役回りを演じる「業者」もまぎれこんでいるようだ。
胸を打つのは、シングルマザーの大変さだ。幼い子供ふたりと仲よさげに写っている女性の年収が二〇〇万円以内だったりする。本人も、そうした条件がある自分が男性から選ばれにくいことを承知で登録してきている。「本気で相手を探しているので、遊びの方はお断りです」というコメントが胸に刺さる。子供が好きなんだったら、この人とつきあってみればいいではないか、という問いが自分にも突きつけられているようだ。つきあってみて子供がふたりいることがわかるのと、最初から子供がふたりいることを知ってコンタクトをとることとはどこが違うのか。
一方で、いわゆるふつうの女性のライフスタイルを目のあたりにすると、意気消沈しそうになる。みんなそんなに海外旅行とディズニーランドが好きなのか。
もやもやしながら何人かの女性に「いいね!」を送ってみるが、結論からいえば、まあムリだった。何といっても、こちらはもう五三歳、女性の側から見れば、ふつうに考えて歳が上すぎる。二七歳の女性から見ればほぼ二倍、三八歳の人から見たって一五歳も年上なのだ、それは年齢を見ただけでパスだろう。いうまでもなく、自分もまた相手からジャッジされる立場なのだ。
諦めかけていると、ある女性から「いいね!」が返ってきた。ディス・ヒートやフランシス・ベーコンのコミュニティに入っている方だ。さっそくメッセージのやりとりをしてみると、相手はこちらのことも、以前手がけたいくつかの仕事も知っているという。いやはや。ありがたいことだが、これは実をいうと自分にとってよい辻占では決してない。とはいえ、家もどうやらご近所らしいので、お会いしてみることになった。
近くのカフェで待ち合わせをして、しばらくおしゃべりした後、フレンチ・レストランで鴨を食べる。
「私、スラップハッピーの日本公演、行きましたよ」
「オレもオレも! 素晴らしかったよね」
「素晴らしかった〜。あのイギリスっぽさ、たまらないですよね」
「だけど、あの歌詞書いてるピーター・ブレグヴァドって、アメリカ人なんだよね。実は、ヘンリー・カウのドラマーのクリス・カトラーもそう。面白いよね、あのヘンクツそうな感じとか、すごくイギリスっぽいのに」
「ときどきそういう人いますよね、スパークスとか」
「そうそう! もっとさかのぼると、エドガー・アラン・ポーとか」
何のことはない、完全にお友達になってしまった。
気になっている同人誌『子午線』の新しい号が出たというので、東京堂まで買いに行った。が、詩のコーナーに見当たらないので、『シネ砦』と某詩人の去年出た詩集を買うことにする。会計をしようと一階に降りたところで、レジ前に『子午線』を発見、もちろん購入。それで六五〇〇円を若干超える買い物になる。
このごろこういう出費がこたえるようになった、と思う。二〇年前だったら、毎日のようにこれくらい本を買っていた気がするのだが、これはどうしたことか。これ以上本を買っても読みきれないという実感が、じわじわ現実感を伴ってきたということか。
いや、単に分量の問題ではないような気もする。以前だったら、これくらいの買い物なら四〇〇〇円くらいですんでいたのが、今はその一・五倍はかかっている気がする。世のおおかたの趨勢にならうように本の価格も二極化していることは、作っている立場からも実感するし、またある程度やむをえないことだとも思うのだが、やはり買う立場に立つとコストパフォーマンスの悪さが身にこたえるということか。
買った詩集は、詩人自らの装丁。カバーがなかったり、表紙のボール紙ごと裁ち落としたりしていて、がんばっていることは伝わってくるが、正直さほど感心しない。しかし、中を開いてみると、ことばが生き生きと躍動し、心にしみとおってくるのを感じる。
本を出すためのハードルが今よりうんと高かった時代、本人が生きているときには五〇部しか売れない詩集が、それでも作られていた時代のことを思う。
そうか、二極化して読みたい本が高くなったというけれど、実は今までが安くなりすぎていたのかもしれない。自分にとって本当に大事なものを買うなら、これくらいの額にはなって、しかもよけいなものも増えない、ということなのかもしれない。しかし、この意見はほかの人にはあまり賛同を得られそうにもない。
年齢がネックだとするなら、そこをごまかせればなんとかなるのかな? と、一五歳ほどサバを読んで別の出会い系サイトに登録してみた。
しかし……うーん。
派手な化粧をした誘うような目つきの女性、目を隠したギャルふうな女の子、あらわな胸元のアップ。女性のプロフィールはみなとても実際のものとは思えないし、公開されるメッセージも「今日、蒲田でホテルデートしませんか」「87Fカップ150 cm歯科助手です☆」と、男の欲望を刺激する文言ばかり。確かに、男の側の歳はいくつだろうとたいして関係なさそうだ。こりゃ業者と素人売春の巣窟かな? 一方で、「パパ」を募集している人が多いのも、笑いごとではない気がする。
本当に相手を求めてる人はいないのかな、と思ってしばらく探してみるが、やはりなかなか見つからない。この「特定の相手を探しています」というのも全然信じるには足りないし、この「助けてくれる人を希望」というのも、要は「援助してください」って意味だろう。「助けてください」。おや?
「助けてください。
ほのか 28歳 東京都
はじめまして、ほのかっていいます。
フリータでいろいろと仕事を転々として頑張ってきましたが、もう疲れ果ててしまいました。。。。
独り暮らしで、家には寝に帰ってくるだけ。本を読んだり音楽を聴いたりするのは好きですが、もうそのことだけでは自分を支えきれなくなりそうです。
よかったらご連絡をください。少しでもお話をすることができて、自分の外の空気とぬくもりを感じられれば。それで寂しさが埋まればいいなーなんて。」
好きな作家はゴンブローヴィチ、好きな作曲家はラフマニノフ? うーん、どうだろう……まあ、ウソならウソですぐ撤退すればいいや。
ところが、あろうことか、メッセージのやりとりは意外なほどスムーズに進み、実際に会うことになってしまった。
待ち合わせの場所はJR某駅近くのルノアールの前、時間は午後七時半。あまり降りることもない駅で、ルノアールなんてあったかしらんと思うが、案の定とてもわかりにくいところにあって、寒い日なのに大汗をかくことになった。
なんとか時間通りにルノアール前には着いたものの、それらしき人は見当たらない。早くも後悔の念に苛まれる。こんなところで待ち合わせをする人などほかにいないし(もっとも、だからこそ初めての人どうしの待ち合わせに使っているわけだが)、だいたいあのメッセージだってどこまで本気にしていいか怪しいものだ。酔狂にもほどがあるというものだ。
一〇分後、ほのかさんが現れた。薄いグレーのダウンとデストロイドジーンズに、化粧っ気のない貧相な顔つき。伸びすぎたボブの下からこちらを覗く目には、切実さのようなものはまるで感じられない。やられた。完全にお金目当ての人だ。どうする?
「オオタさんですか?」
「……ええ」
オオタというのは、もちろん偽名である。こちらの答えを聞くと、ほのかさんはすぐにむこうを向いて、歩き出した。このまま帰ってしまおうか? そう思った瞬間、ほのかさんがこちらを振り向く。その顔には何の表情も顕れていない。ぞっとする。しかし、目が合ってしまったのでしょうがなく後をついていく。
当然彼女がめざしているのはホテル街である。家路を急ぐ会社員やOLとすれ違うのも、なかなかにいたたまれない。途中で何度も、こちらだけ横道に入ってしまえという考えが頭をよぎるが、話くらい聞いてみないとフェアではないような気もしてしまう。しかし、彼女は何を語りかけてくるでなく、歩みを進めるばかりだ。何も話すことはないのだろうか、いや、それはお互いさまか? と思っているうちに、ほのかさんはどんどんホテルに入ってしまい、フロントの前でこちらを待ちかまえている。つらい。もうどうにでもなれという気分で金を払い、ふたりとも無言のままで部屋に向かう。彼女はこの雰囲気をどう思っているのだろう? こちらが不機嫌そうにしているので、何も話しかけてこないのか?
広めの部屋は、意外にもこざっぱりした木造りの内装で、これで少しは話しやすくなるかと思いきや、ほのかさんはすぐさまスマホを取り出し、「ちょっとすいません」といって、部屋の隅で声をひそめて話し出す。まさか美人局? と思ってひやりとするが、いやいや、それならこんなあからさまなことはすまい。話が終わると、ほのかさんはこちらを見て「2でいいですか?」という。あまりのさっぱりした口ぶりに二の句が継げない。寂しさとかゴンブローヴィチとかはいったいどうなったのかと思うが、いうだけヤボなのであろう。
シャワーを浴びて部屋に戻ると、身体にタオルを巻いたほのかさんはベッドを指差し、「寝てください」という。いうがままに仰向けになると、彼女もベッドに乗り、タオルを外す。痩せた肢体に小ぶりの乳房。シーリングのライトを隠すような位置に入り、こちらを見下ろして口角を上げた。
そのまま顔を伏せ、こちらの乳首に舌を這わせる。何だろう、これは決まった段取りなのか? だが、まことに遺憾ながらそこはくすぐったさしか感じない。こちらからも何かしようと、ほのかさんの胸に手を伸ばしてみるが、その手はあっさりと振り払われた。「触らないで。あたし、乳首が敏感すぎて、ほら、皮が剥けてるでしょ」。確かにそのとおりだ。しかし、乳首に限らず、彼女は自分に触られること全般が嫌なようである。これでは楽しくなりようがない……。
脱いだジーンズの上に置かれたほのかさんのスマホが鳴った。彼女はこちらの股間から顔を上げ、「ちょっと待って」といってスマホをとり、また部屋の隅で話し始めた。何も考える気になれずぼんやりしていると、電話を切ったほのかさんはこういった。
「ごめんね、お母さんが入院しちゃった」
「え?」
「お母さん、糖尿病で、お兄ちゃんに薬飲ませるようにいっといたんだけど、全然飲ませてくれなかったみたいで。具合悪くなっちゃって、あわてて救急車呼んだみたい」
「え? え?」
「悪いけど、あたし帰ってもいい?」
「いや、そりゃいいけどさ、糖尿病ってそういうもんなの? 注射とかじゃないの?」
ほのかさんは、堰を切ったように話し始めた。聞くと、お母さんは糖尿を患っているが、薬を飲むのが嫌いで、周りの人間がしつこくいわないと、今回のように病院に運ばれることがあるのだそうだ。ついこの間までマグロ漁船に乗っていたお兄さんは、体を壊して今はパチンコ三昧。しかし家のことは何もわかっておらず、母親の糖尿病の薬のことも、頼まれはしたものの、まるで深刻に捉えていなかったという。父親はむかし寿司職人だったが、彼女が高校を出ると同時に仕事を辞めて家を出て行き、今は別の女とどこかで暮らしているらしい……。
乾ききった印象のほのかさんの後ろに、いきなりいろいろな風景が見えてきた気がする。しかし、この話にしても、真偽はまったくわからない。ただ、でたらめにしても、こんなタイミングでこんなクレーム必至の申し出はふつうしないように思える。いずれにしてもこちらとしては、この状況から解放される方がありがたい。ふたりはそそくさと衣服を身につけ、部屋を出て、ホテルの前であっさり別れた。お大事に。
夜の街を駅に向かって歩きながらも、何の感情もわいてこない。セックスを覚えたてのころ、外に出たときに、みんなこんなことをやってるのかという驚きで、街や人が違って見えたことを思い出す。今日はそのときとはまったく別の意味で、街や人が違って見える。
電車の中で、眠りに落ちる。細い管を通じて、どこかへ運ばれてゆく。
【初出:2016年4月/ウィッチンケア第7号掲載】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
