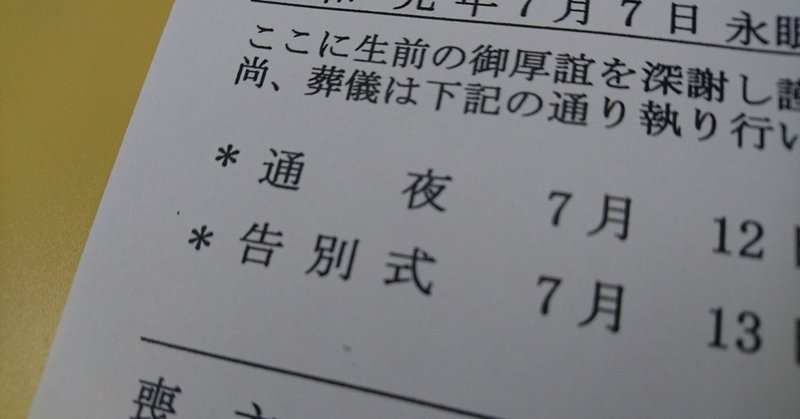
(仏)仏典におけるグリーフケア
キサーゴータミーの話
仏教の経典(仏典)の中に、以下のような話がある。子供のころに読んで、おさなごころに「おシャカさまは嘘つきだな。」と釈然としなかった話だ。
幼子を亡くしたキサーゴータミーという名の母親がいた。彼女は息を引き取った息子を抱えて「どなたかこの子を生き返らせてくれる方はおりませんか」と憔悴している。そんな折、ある町におシャカさまが居ると知り、訪ねる。どうかこの子を生き返らせてください、と。するとおシャカさまは、「よろしい。ケシの実を持ってきなさい。ただし、これまで一度も死者が出ていない家から貰ってくるのだよ。」と応じる。キサーゴータミーは家々を訪ねるのだが、死者の出ていない家がない。そこで彼女は、誰しもが死別による悲しみを経験しているのだと悟り、仏教に帰依した。
これに類した説話はいくつもあって情景描写などところどころ違いはあれど、フレームを概説するとこんな話だ。
はじめてこれを読んだ子供心にも、人が生き返らないことは解る。それなのに「よろしい、生き返らせてあげよう」と嘘をつき、悲しみにくれる母親をその気にさせ、結局は“嘘も方便“となって『おシャカさまの言うとおりにしたら諸行無常と悟りましたおシャカさま流石です仏教すごいですチャンチャン』の物語が嫌いだった。強者の論理で、まったく幼子を亡くした母親・キサーゴータミーの感情に寄り添っていないではないか。
仏典にもケアがあった
ところが近年、異なる見解があることが示されてきた。キサーゴータミーが家々を回ったとき、そこでどんな会話がなされたろうか?という着眼点だ。
想像してほしい、亡くなった赤ちゃんを抱えた母親が、家を訪ねてくる。まずは驚くだろう。しかしつき返しはしないだろう。だれが「ざまあみろ」などと言うだろうか?誰もが同情し、いたわるのではないか。
「かわいそうに。うちも去年、夫がなくなってね。あの時はつらかった。自死を選ぼうかとも思ったけれど、気づけば1年、なんとかやっているわ。」
「それはつらいね。うちもじつは子供を亡くしたことがあるんだよ。あの時は…」
「うちはおばあさんを亡くしたんだ。大往生だったけれどそれでも大変だった。赤ちゃんだなんてつらいだろうね」
これらの会話の数々がキサーゴータミーの骨身に染み渡っていく過程で、母親の心情に変化が生じていくことについては、確かに想像ができる。おシャカさまがすごい、のではなくて市井の人々が心中を吐露し労わりあうことで、いわゆるケアが生じる、という意味では、仏典にもケアがあったと読める。
核家族にもこの説話は有効か?
しかし現代日本では、この説話はどれほどの説得力を持ち得るだろうか。核家族ともなれば、死者を出していない家は散見されるだろう。そして祖父祖母と同じ屋根の下でも、長寿であれば、こどもにとってことさら人の死は縁遠いものなのかもしれない。死はモニターの先にある、身近にはないものかもしれない。それはいのちを軽んじることに繋がるのだろうか?自宅で一緒にテスト勉強をしていた友人を刺殺するような事件が、どうして起きてしまうのだろうか。
仏典は時代時代によって読み方を変えることのできる、それだけ含みの多い、豊かな書物だ。女性軽視に読める内容なども含め、現代にあった解釈の早期波及が必要とされている。われわれ僧侶自身の経典解釈がアップデートされることで救われる感情があるならば、アップデートは急務となるだろう。
Text by 中島光信(僧侶・ファシリテーター)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
