
クレド ー 人生の羅針盤 / をつるの場合
「クレド」って知ってますか
「クレド」。聴き慣れない言葉ですよね。
私も最初聞いた時、「???」となりました。
この言葉と出会ったのは、LDS(Life Design School)でした。
LDSは、自分風にいえば、「自分の内省を手伝ってくれる&自分に対しての仮説&実験する力を鍛える場所。」そこでは、クレドは「人生の羅針盤」と説明されていました。
と、言いつつも、ちゃんとした意味を知っているわけじゃないなと思ったので、定義が説明させれいてる記事の一部をここに引用してから、本題に入りたいと思います。
クレドとは、ラテン語で「信条」「志」「約束」を意味する言葉です。企業活動の拠り所となる信条、価値観や行動規範、経営指針を簡潔に表現した文言を指します。似たものにミッションやビジョンがありますが、これらはクレドとは明確な違いがあります。ミッションとビジョンが何かということを含めて、クレドとの違いを解説します。
ミッションとは
ミッションは、その企業の目的や使命、任務などのことを指します。会社がその経営を通じて、何を目指し成し遂げたいかを表したものです。会社にとって最優先するべき、基礎となる考え方です。
ビジョンとは
ビジョンは、その企業がどこへむかっていくのか「あるべき」「ありたい」姿、目標や方向性を言葉にしたものです。ミッションを前提にして、将来の企業の理想像を明確に示します。ビジョンを社員全員が把握しておくことで、何かを決定する際に企業の方向性から外れないよう注意できます。
クレドとは
クレドは、社員一人ひとりが行動する際の「信条」や「行動指針」を指します。似たような言葉に「バリュー」がありますが、これは組織としての「共通の価値観」を意味し、クレドと同じように「行動指針」として利用されている会社も多くあります。
「クレド」は「ミッション・ビジョン」を支える価値観であるため、ミッション・ビジョンを達成するための指針になります。つまり、ミッション・ビジョン・クレドはそれぞれ連動しています。
出典:https://www.hito-link.jp/media/column/guideline
最初ウェブで調べた時に、人事の方対象のページばかり見つけて、意外にもビジネス感あふれる文脈で使われてて驚きました。
「ビジネス」とか「会社」というものに対してあまり良いイメージを持たなかった自分(就活1mmもしてない)からすれば、こういう形で、ひょんなところから概念をインストールしてもらうくらいの方が、その概念自体とちゃんと向き合えるから良いですね。
=========
さて、LDSでは、「人生を進む上での羅針盤」と説明されたクレド。
ある週の宿題で作ってくるように言われ、直感と勢いに載せて作ったものがありました。宿題を発表する予定の回では、扱うことはなかったのですが、LDS最終回まで、ちらほら登場する存在でした。
そこから、約2ヶ月。
休学して、半年。
いろいろガムシャラに選択&行動&内省をやってきました。
その間、クレドは結構忘れ去られていた存在だったのですが、
最近はぐくむコーチングBasicを修了し、
「自分がここのスクールで学んだことは、自分の生き方を鍛えことでもあった」ということに合点が行った時、このクレドのことを思い出しました。
もはや、保存しているデータのタイトルもわからず、探しまくってPCの奥底から引っ張り出してきたクレド。
見返すと、今の自分が大切にしてたいこととと、ちゃんとつながっていて、
数ヶ月前自分が目指していた方向が、自分が目指したい方向につながっていることや、ノリと勢い(=直感)で書いていたけど、直感ってやっぱり正解に一番近いのかも知れない、と感じたりしました。
をつるのクレド 1.5
とはいえ、このクレドを書いてから数ヶ月、「何もしない」のも含めて色々、仮説→実験→内省 をやってきた自分には、それなりに(心理的に?)厚みが増されているわけで、ちょっと変えてみようかな、と思いアップデートをしてみることにしました。
(アップデートは、いつでもして良いものだからね。)
劇的変化というよりは、ちょっと変わった/微修正したということで「をつるのクレド 1.5」ということで書いてみようと思います。(まあ、タイトルはどうでも良いといえば、どうでもいい。)
クレド1つにつき、そこまでに至った流れを書いていったら、
超絶長くなってしまいましたが、
(もし興味を持ってくれる人がいたら)
目次でとびとびしながら、
読んでいっていただけたら嬉しいです。
===========
では、本文スタート!
===========
競争でなく、共創と協奏で生きる。
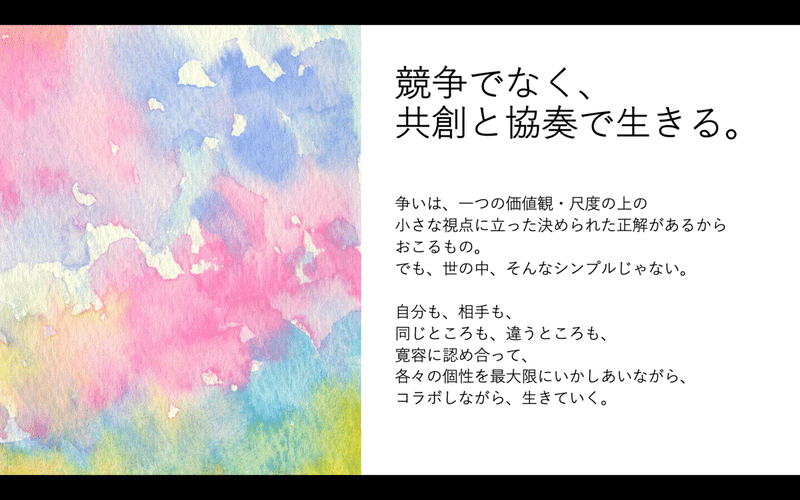
小さい時から、競争が大嫌いでした。
いわゆる「良い学校」に小中でいかせてもらった自分は、学校であれ、塾であれ、点数で競う文化を持つコミュニティと隣り合わせで生きていました。
どんなに先生が良い人でも、面白い授業をしてくれても、
やっぱりそのクラスの文化を作るのは、構成している生徒一人ひとりでもあり、その生徒たちは、小学校・中学校の終わりにやってくる受験に向かって勉強する(必死さ/ストレス抱える度は人によって違ったかも知れないけど)、という社会の流れの中にいました。
点数で評価される、点数一元主義的な世界の中で、
「点数が取れればなんでも良いじゃん」という価値観を持ち、
点数を取るためのテクニック・実力を手に入れるのと引き換えに、
ストレスを抱え、学校で爆発させる(人がいる)。
その構造っておかしいんじゃないか、と激しく思いました。
その構造の中で勝っていく人しか、いわゆる「良い会社」とか「勝ち組」と言われるものになれないんだったら、構造を作る側の人になれないんだとしたら、この世の中終わってるな、と思いました。(当時14,5歳なので見えてる世界は狭かったのです。)
=====
そこから、時は流れて、大学1年生の1学期。
それまで個人競争の中でワタワタしてきた自分は、衝撃を受けるような宿題を出されました。
英語の授業で、リサーチに基づいたレポートを書くという宿題が出され、そこまでは普通の課題だったのですが、先生が「誰かと二人で書いて良いよ〜!ま、一人でも良いけど!」という指示を出したのです。
先生の言い分としては「社会に出たら、コラボして書くことが多いからね!最近書いた本も、国を跨いでオンラインで書いたし。今からその練習ってことでやることもいいと思う!」とのこと。
もう、自分の頭の中ではパニックです。
いままで、何をするにしても課題はだいたい個人でするものだったし、もはやレポートなんて、書く場所によって重要度などが変わってきてしまう。公平な評価ができないじゃんか!二人で書いたらそれをどうするんだ!と。
でも、その時自分はどうしてもやりたいトピックがあり、それを完成度が高い状態にするには、誰かの助けが必要だということも理解していました。
自分はクラスの中では英語力がなく、とくにライティングに自信がありませんでした。でも、そのレポートは英語で書かなければならない...。そのとき、たまたま、自分のトピックに興味を持ってくれた子がいました。
その子は、たまたま、英語の方が得意(日本語は話せるけど、敬語に不安あり)という子だったのですが、日本語が得意な自分と、英語が得意な彼女、言語的に結構良いバランスの二人でタッグを組むことになったのです。
エッセイのテーマは、自分の所属する大学の、いわゆる障害を持つ学生さんに対する学校の取り組みに関する調査。
特別学習支援室のスタッフさんとわゆる障害を持つ学生さん(学校の先輩)に対するアポ取りは日本語が得意な自分が中心で、インタビューと論文構成・執筆は二人で、最後の文法チェックは相方が中心で行い、結構余裕を持って、自分的に納得度の高いレポートを提出することができました。
大学、という、まだまだゴテゴテに点数評価をする世界の中でも、こういう考え方もあるんだ、と学んだ経験でした。
=====
またまた、時は流れて大学3年生の秋。
自分の人生の価値観を大きく変える経験、留学を始めました。
端的に言って、全てのものが新しい生活。
そこで生きていることが、目で見えるものも、見えないものも含めて、
学びでしかない。
そんな環境でした。
たくさん学んだ・体感知を得た物の中で、このクレドに関係することを挙げるとすれば、「違いが価値」であるということ。
日本語を話せる、という当たり前のことが、誰かの役に立ったり
「自分らしさを全力で出すことが美しいダンスをするコツ!」という文化のあるダンスの授業を通して、自分を出すと言うことを練習してみたり
すでに自分にも、持っているもの(価値)があることを体感できた時間でした。
この留学の経験で、「自分が自分である」ということの価値(めっっっちゃ生きやすくなった)を、ものすごく感じるようになり。
そういう感覚で生きている友人たちとの会話やプロジェクトは、
心の安心感と、学びと、わくわくでいっぱいでした。
それぞれ、文化も、専門性も、経験も異なって、
それぞれのワクワクや得意なことの方向性も、もちろん違う部分が多いから、そこは得意なものでお互いをカバーしあってやっていく。
こう言う環境で生きると言うことを体験させてもらって、
自分は、誰がなんと言おうが、
こういう環境の中で生きていくことを大事ししたいんだ、
ということを実感した経験でした。
自分が、「ホラクラシー」とか「ティール」という言葉にすごく惹かれるのも、こういう経験・成功体験・幸せ体験があったからなんだろうなと感じます。
まだまだ、「社会の流れ・相対的価値観」に振り回されそうになっている、弱い自分もいますが、今は自分の心の声を聞くのが一番、と思い、ぐっと不安な気持ちを抑えています。
ただ闇雲に、「みんながやっている」とか、「トレンド的にあったら便利だから」という理由であるスキルを身につけていくよりも、自分のありたい姿を先に見出して行った方が、最終的には、行きたい場所に行く時間も早くなるし効率もいいんじゃないかなあと、自分的には思っているのです。
全てのものに、意味がある
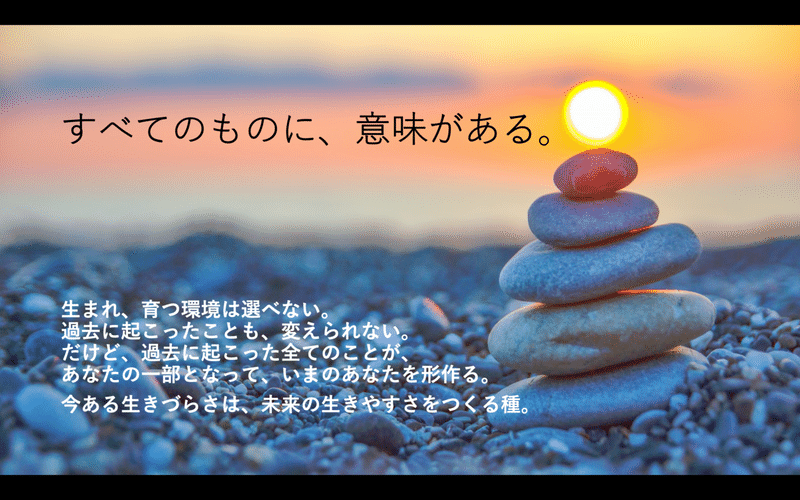
自分は昔、超絶なる悲観主義者でした。自分の思っていなかった方向に物事が動くと、最悪のケースを考えて、それが実際に起こった時のことを想像して、どうしよう、と焦る、みたいな、そんな人間でした。今ある現実と向き合うというよりは、その現実から派生する、起こりうる最悪の事態の、未来のことばかりに気がとられていたように思います。
そんなふうに未来の心配とか、不安に縛られて生きていたある金曜日、自分が結構尊敬していた高校の先生にある誤解をされてしまって、めっちゃ怒られて、弁解するまもなく先生が帰ってしまうというプチ事件が起きました。
当時の自分は大混乱。「尊敬している先生を怒らせてしまった...自分の信頼が崩れる...先生に嫌われて成績下がったらどうしよう...終わる...(当時の自分は「良い成績取らなきゃいけない症候群」真っ最中)」ということで最終的には超頑張っていたその授業の成績がFailになるところまで本気で考え、「一人だと収集つかないやつだ」とプチパニックになりつつも、当時、困ったことがあるとよく相談に乗ってもらっていた友人(ポジティブシンカー)に話を聞いてもらいました。
そしたら、友人に全力で笑われたのです。
知り合いに、サボテン買ってきて枯れたらどうしようって悩んだり、まだ買ってもないのに、猫を買ったことをシュミレーションして、さらにその後死んだときのことを考えて1日落ち込んでる子がいたんだけど、それと同じくらいくだらん。まだどうなるかわからないんでしょ?起こってからその先のことを考えなよ!
と。
確かにそうだなあと思いました。
正直、枯れにくい植物代表のサボテンや、まだ買ってもいない猫が亡くなることを想像で考えてめっちゃ落ち込むって、ちょっと笑ってしまうレベルに面白いなと感じ、自分もこういう思考回路に陥ってるんだなと、ある種客観的に自分を見られるようになり、自分の落ち込みが少し馬鹿馬鹿しくなりました。
そこから、少しずつ、自分の悲観主義は直っていきました。
====
一人一人がそうであるように、
自分の人生でもいろいろ山あり谷ありなことがありましたが、
それをひっくるめて今の自分がいるわけで。
そうかあ、全部今の自分に結びついているんだなあ
(というか、過去の積み重ねでしか今はない=過去の「もしも」はないし、過去にあった「あちゃー」な出来事も、今の自分の一部)
と、いうことが自分の体にストンと落ちた時に、
今ある出来事の良し悪しに一喜一憂することが少なくなりました。
ちょっと大切なものがなくなっても、
「厄落としだよね〜」とか
いきたかったところに行けなかったとしても、
欲しかったものが手に入らなかったとしても、
「今回はご縁がなかったってことだね〜」
と言う感じでフワッと凹み時間を交わすことがデフォルトになりました。
(もちろん、凹みます!が、大体のものは、凹む時間は短め。)
この思考回路の改革に伴い、「現状に対するポジティブ変換」が得意になりました。
実際、思うようにいかなかったことによって、
別のところでラッキーなことが舞い込んできたりすることも度々あり。
今やっていること、今起こっている結果が「良い」ことなのか「悪い」ことなのか、その答えは、今出るものではないのかも知れない。
というよりも、それは正解にしていくだけなのかも知れない
そ言う言う感覚で、日々を生きています。
願いは、叶う。
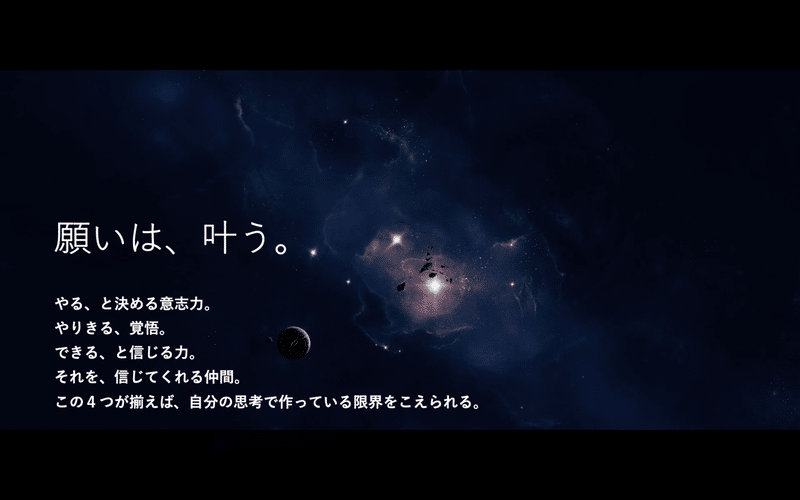
これは、LDSで学んだと言っても、過言ではない。
LDSでは合宿を二回行うのですが、
ぶっちゃけ、精神的にも体力的にも、超きついことをやらされるんです。
やらされる、は、ちょっと違う言い方か。
そういう機会を設けられているので、(無意識でも意識的にでも、選んで、)やるんです。
その中の一つに、大山という結構大きい山に登る日があったのですが、
登山当日、天気は生憎の豪雪。
豪雪です。 マジで豪雪。
「ど う 考 え て も
正 気 だ っ た ら
こ の 吹 雪 い て る 山 を
登 ら ん 」
という雪山を登るのです。
(文字じゃ伝わらないよな〜〜と思いつつ、できる限りのことをする)
往復約9時間。
運動能力フツーピープルの自分にはフツーに登っても辛いです。
しかしその日、雪っていう。
しかも、その日、「山登る」とは聞いていたけど、それ以外何も聞いてなかったので結構な普段着できちゃうという。
9時間登山 x 吹雪 x 運動力普通人間 x 普段着
x どのくらい険しい山かしらん(調べなかった事に関しては自分の責任)
この状態で挑んだもんなので、
どれくらい複雑な思いを抱えながら登ったのか
なんとなく想像していただけるのでは、と勝手に思っています。
登っても登っても先が見えない(雪で) & ゴールが見えない 絶望
自分何やってるんだろー という 嘲笑
死ぬかも知れんというちょっとした 不安
なんでこんな天気で結構することにしたんだろ!というちょっとした 怒り
(本気で命の危険を感じたので)
もう無理じゃないか、という 諦め
その他もろもろ、、、
言葉になるものも、ならないものも含めて
めっちゃいろんなことを考えました。
山頂に近づくにつれて、強くなってくる吹雪。
リュックに入れたペットボトルの水は凍って飲めない。
寒いし、動き続けているので疲れたし、体力も結構限界。
でも、「決めたから、やる」という自分のおきまりフレーズを呟きまくり、時には一歩踏み出すエネルギーを出すために叫んだ理してみて、
目の前の一歩を、ただ、ひたすらに積み上げた結果、
いつの間にか頂上がすぐそこにきていました。
もう最後らへんは這うような感じで、
ガチ吹雪の中、登頂。
しかし、そっからがもっと辛かった。
寒すぎて凍えそうだったので、登頂の余韻に浸ることなく数分間で食べ物・飲み物休憩をして、即効で下山開始。
それまでは、登頂という目標があったから、
目の前に具体的なゴールが見えなくても、見えない「ゴール」に向かって一歩一歩、気が遠くなるような距離でも歩いて来れた。
でも今度は、全く同じ距離を帰らなければいけません。
今までは「頂上につく」ということをゴールに設定して歩いていました。なので、ゴールを達成することに全力を注いでいたため、体力は限界(を超えていたかも知れない。ここはアホであった)。
燃え尽き症候群に近い状態のまま帰る、というのも結構な苦労でした。
息は上りばかりだったと記憶していたので、帰りはまだ下りで楽かなーと思っていたら、ガッツリ上りの道があり(降った記憶はなかったのに...)、
どんどん日が暮れていき、周りがめちゃめちゃ暗くなり、雪は止んだものの代わりに溶けた雪と土が混ざり合ってめっちゃ滑りやすい土壌になるという(個人的)一難さってまた一難、的状況。
途中で迷って引戻ったりして、果たして宿に帰れるのか本気で不安になったりしたものの、どうにかこうにか帰路につき、帰りの寄宿舎に帰ってみたら、全体のグループでも結構早めの帰宅をしていたことが発覚(全体で20名ほどの参加者がいたものの、各々の体力や歩幅に合わせて小さなグループで登山・下山していた)。
みんなの帰りを待ちながら、なんだか訳のわからなかった、とりあえず必死に足を動かし続ける9時間の登山を振り返りました。
そして、意志の力ってすごいなあと噛み締めたのです。
吹雪という山登りには全く持って向かない天候。
登山初心者が多数いて、さらに用意もままならない(普段着に雨がっぱ的な。完全に山をなめている格好の)子達もちらほらいる中で、
それでもみんなができると信じて決行を決める代表・たけさんの、みんなならできる、と信じる力。(だって、どう考えてもハイリスクだし、何かあったら、罪悪感半端ないだろうし、プログラムを提供している会社自体の信頼も失うわけで...。)
文句とかも言わず、それに従う・受け入れるみんな。(一応、残るというチョイスも全然アリだったんです。)
自分も大変だろうに、全力で参加者を鼓舞する社員さんと、運営(同じ大学生)....
外の目から見たら、異様な団体だったと思います。
危険に決まってるじゃん!何やっているの!と。
でも、山登りをするにはその1日しかスケジュールがなくて、
山登りを通して、それ以外では中なか味わえない、感じられない物を感じ取って欲しいという思いがあって、決行を決めて。
そして、みんな、無事帰ってきました。
「どう考えてもかなりぶっ飛んだ選択だな...」と思いつつも、自分はLDSが提供したい「何か」を掴み取りたくて、山登りをすると選択し、心折れそうになりながらも、なんとか山頂に行き、同じ道のりを燃え尽き症候群になりつつ帰りきり。
自分が囚われてきた「自分で自分のリミットを決めてしまう」という構造の縮小版が見えたような気がしました。
何度も、心の中で「体力的にほんとに無理」「足が死ぬる」などなど、途中で帰ろうと語りかける声を耳にしました。でも、「やると決めたからやる!」と、弱音を押し切り、友人や運営の子から「できるよ!」と鼓舞してもらい、時には「やる!できる!」と叫び、本当にやり切ったのです。
そう、心の中で自分にはこの吹雪を上のはリスキーすぎる。多分無理、というリミットを作っていたけど、実際そうでもなかったのです。
この経験は、自分の評価に対する考えを少し改めさせてくれる契機にもなりました。
自分は、自分がやったことに対してちゃんと自分を評価することができない傾向があり、「決めたから、やる。以上。」という感じで、全ての物事を、淡々とやってきました。そして、どんなにそのタスクに体力と時間を使っても、そのタスクを提出した瞬間に次のタスクに移るので、あまり自分を「頑張った」と認めてあげることができずにきたのです。山登りの際も、その傾向はあったのですが、少しは頑張った、と思えた気がしました。(いや、普通吹雪の山を登る人はそんなにいないという相対的な考え方をしたらフツーに頑張った、と言えるものだと思うのです。)
今もそれがうまく行っているかどうかは置いておいて、「決めたから、やる。以上。」という自分が自分にかける暗示の強さ、よく言えば課題遂行能力が結構高かったということは、この時に、少しづつ自覚るすようになりました。
話は本題に戻り、「できる」「やる」という意志の持ち方で自分がどこまでできるかが変わってくること、
また、その気持ちを強く持てる人たちといると、相乗効果で「できる」の範囲が広がることを実感した経験でした。
この一瞬を、生きる
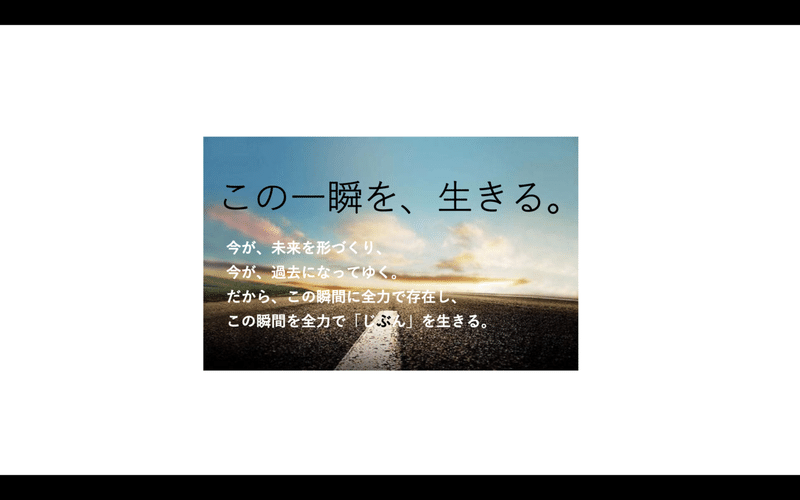
このクレドについては、もうこのスライドに書いてあること、
それ以外に書くことはないかも知れない、と思っています...
(わざわざタイトルを作る意味...)
クレドの一回目のページで、
そうかあ、全部今の自分に結びついているんだなあ
(というか、過去の積み重ねでしか今はない=過去の「もしも」はないし、過去にあった「あちゃー」な出来事も、今の自分の一部)
と、いうことが自分の体にストンと落ちた時に、
今ある出来事の良し悪しに一喜一憂することが少なくなりました。
こんなことを書いたのですが、
だからこそ、今を大事にしたいという思いが、もくもく湧いてきているという感じです。
全てのアクションは、意志決定。
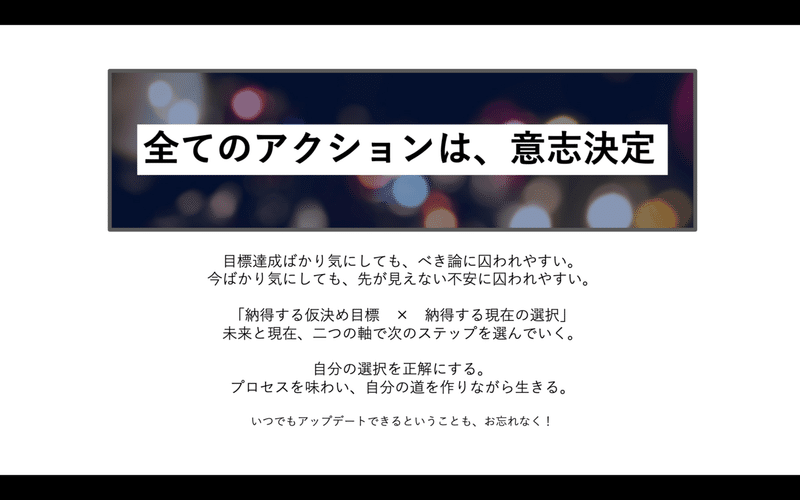
唯一、新しいバージョンのクレドに、加えた一枚。
この半年間、一言で言えば「自分のOS(頭の中にある自分ルール)をガッツリアップデートする」休学をしてきました。
ステップはこんな感じ↓
1)自分が囚われているOSを認知
(これは休学前からできていたものもあったものの、そこから全く抜け出せず、休学を選んだ)
2)そのOSが自分の心として、好きか嫌いかを感じる
3)嫌いなものは、OS変更を試みる
4)じんわりとOSが変わってくることを実感
3)までは、ある程度スムーズに行くけれど、そこから先が大変でした...
自分はずっと、社会的な価値観(あえていうなら相対的な価値観)と、自分の心の声を元にした価値観(あえていうなら絶対的価値観)との押し問答が
ずーーーーーーーーーーーーーーっっと続いていました。(というか今もまだまだ続いていますが)
例えば、就活。
自分にはちゃんとした「今の日本の就活が気に食わない」理由があり、また、休学の目的が就活をすることではタッ施できるものではないと考えているため、いま就活をやっていない、という状況なのですが。
就活を全くしていない自分に焦る自分がずっと消えませんでした。
今、せっかく休学をしているのだから、自分の価値観を明確にする方向にドライブを全力で切って進みたい。
だけど、心の何処かには、まだ一般ルートを言ったほうがいいのではないかという心配する声を持つ自分がいて、二つの価値観が真逆の方向に引っ張るので、どちらの方面にもあまり進めない、という状況が続いていました。
正直、囚われているのを分かりつつ、進めない自分を自覚するのはかなりもどかしく、メッッッチャひきづって暮らしていたのですが、
ある時、ふっとその気持ちが少し軽減された時があり、その時に降りてきた言葉がこの言葉でした。
その感覚が分かり始めて、自分が今まで勇気を出して「あえて何もしない」数ヶ月を作った時間の、自分なりの意味・価値が見えてきました。(それは別の機会に書きたいと思います。)それを自覚できるようになった時、先述の囚われのみから、少し成長できた気がしました。
「意思」でもよかったのですが、あえて「意志」にしました。
アクションは、考えてから選択した結果ではあるけれど、
やり遂げたいことから逆算して、常に、ある自分の意志と直線状の関係にあるものは何か、という基準を元に、選択をしたいという気持ちを込めています。そういう気持ちで行った選択こそ、後悔のない選択じゃないか、と自分は思っています。
当たり前と言えば、当たり前のこと。
でも、それを実行するのはなかなか難しく。
「全てのアクションは意志決定」の感覚を心から持てたということには、
一歩進んだという感覚を持ちつつも、
このクレドにしがみ付いて、日々選択を重ねていきたい(実は、後悔する選択はなく、それをどう捉えるか、ということだとも思うのですが)、
と 自分を奮い立たせながら生きている、今日この頃です。
======
今まで、クレドのフレーズは日本語で書いてきていましたが、
最後の2つは英語になっています。
突然別の言語が入ってくるという、空気読んでない感はすごいですが、
この英語のフレーズの原文を聞いた時に、なぜかズドーンと耳に残ったことばたちです。
ということで、その言葉が一緒に連れてくる文化的背景・自分がその言葉と共に得た経験も一緒に、大切にしたいとおもい、原文の英語のままクレドにすることにしました。
What you feel is who you are.
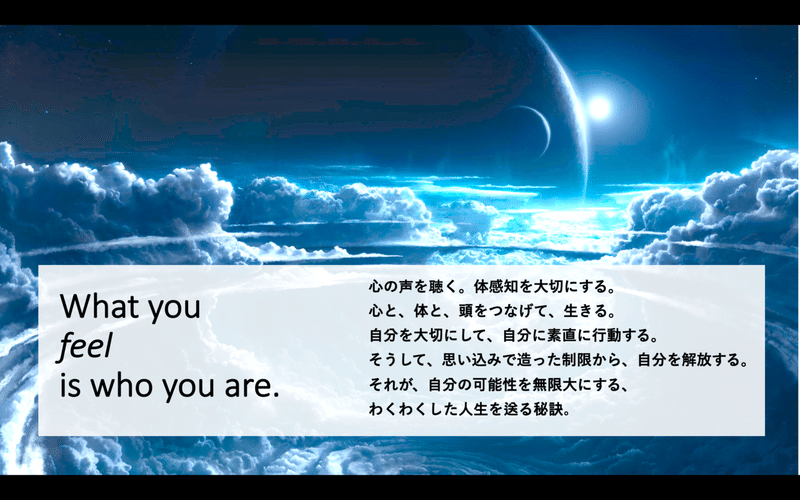
元々は、高校の文学の先生が言った言葉「What you do is who you are」から派生したフレーズ。
そのときは、「良き人かどうかは、普段の行いで決まるからね!」と言われていた、その流れで出てきたフレーズだったのですが、何においてもコツコツ精神でやっていた自分にはとても刺さる言葉で、「これからもコツコツを積み重ねよう」と心に誓ったことばとなりました。
時は流れて、大学2年生の秋。
ココカラ未来会議というのに参加させてもらった(自分はダイバーシティ枠で参加しました)ことがきっかけで、フレーズを一部変更することにしました。それぞれのテーマの中で具体的な課題を一つ選び、それに対する打開策を考える、という1泊2日の"会議"だったのですが、チームで話し合っている際にフラッとやってきたtaliki代表の中村さん言った言葉にとても共感し、自分の大切にしたい言葉を考え直すきっかけになりました。
それは、
「その時の状況とか、環境とか、金銭面とか、いろんな原因があって、自分の思い描いている物を形にできる子は少ないかもしれない。だから、今何を持っているかより、今何を考えているかの方に興味があるんだよね」
という言葉。
心の底から「確かに!!」と共感し、クレドは前述の第一段階から、
「What you think is who you are」
に変わりました。(しかし、まだ最終段階ではない...)
そこからどうやって、「What you feel is who you are」に変わったか。
それには、自分の留学先でのダンスと、教育学の授業が大きく影響しています。私が留学先の大学で学んだ「ダンス」は、普通私たちが「ダンス」と聞いてイメージする、「それぞれのジャンルにそれぞれの型があって、その型をいかに上手にフォローしてやるのか、が上手かどうかを決める」というものではなく、「"あなたがあなたである"ということを出すこと、それが素晴らしい」というもの。
あなたが動ける、と言うことは、すでに自分の中に「動き方の方程式」がある=自分の「ことば」を持っているということで。
それをいかに出すか、を極める。
そんなクラスだったんです。
初めは、自分の思ってたクラスと全然違ったので戸惑いもありました。
でも、
自分を出す&直感で作る
(->友達とシェアする)
->発表する
->クラスメートに見てもらう/受け入れてもらう
->自分もサポートする側に回る
->作る(サイクルの最初へ)
というサイクルを毎回重ねていくうちに、
「自分が自分である」という感覚や、
「自分は自分でいいんだ!(大きな価値観に飲み込まれなくてもいい)」
という感覚、
自分の言語外で起こる「なにか」が存在するんだなぁという感覚
などなど...
まとめきれないくらい、たくさんの「体感知」を得ることができました。
それが、自分の留学時の「覚醒(=毎日がワクワクで詰まっている。毎日がハッピーで、ワクワクが原動力で、人も、機会も、いろんなものが引き寄せられる)」に繋がった、と今振り返って感じています。
今まで、アート(ダンス)を通じて、自分で自分を縛ってきた「べき論」から開放されて、全力で自分を生きていた時、
・他からの「常識(≒べき論)」や他人の価値観で生きてたから生きづらかったこと。
・世の中の人が持っている「べき論」は、大体において、本当は納得してないけどそういうものだから教え込まれているのでネガティヴな気持ちで従っている。
・世の中では自分の「べき論」の押し付け合いが起こっているから、生きづらさを感じる人が多くいる(どこの国や地域でも同じ構造)し、他人にべき論を押し付けることにより、生きづらさの再生産が行われている。
こんなことを体感して、「このままべき論に縛られながら生きるのは嫌だなあ」と思い、留学後の予定(ほぼ決まってた院進学とか、卒業後の進路とか諸々)を全て白紙にして、今、休学をするに至ります。
========
ここまで長々書いてきましたが、「教育学」の方の話、していませんでしたよね。ダンスの授業と並行して教育学の授業を撮っていたのですが、そこでたまたま課題図書として出された、"Integrating Mindfulness into Anti-Oppression Pedagogy: Social Justice in Higher Education"という教科書が、自分の体感知を明確に認識できるきっかけとなりました。
もうこの本は、死ぬときに棺桶に持っていきたいくらい好きな本なのですが、1ページ1ページ、ページをめくるごとに、自分を縛ってきた何かから解放されるような、そんな気がするのです。
この本では、たくさんのメッセージを伝えていますが、特に自分が強く印象に残っている点をさっくりとご紹介します。
ひとつめは、「学習には政治的な思想がどうしても入ってしまうので("lerning is politicized")、我々はその、学んだこと、身に付いていることをいったんリセットする(unlearn)技術を身につける必要がある」というもの。それができて初めて、ソーシャルジャスティスをはじめとする批判的で深い学びをする場が担保できる。そして、人に求める前に、まずは自分たちから始めよう。と続けられています。
ふたつめは、そのunlearnに対する考え方。今まで「学んできたこと(学問だけでなく、社会的な概念、考え方、体の動き方すら含めて全て)」を認知し、unlearnすることは容易なことではない。だからこそ、マインドフルネスを使い、頭を使うのではなく、自分自身を認知して身体の主張に声を傾けることも大切である、と書かれています。
言葉は違えど、ここに書かれているものは、自分がダンスの授業や、友人との会話を通して、学んだものでした。
体感知として自分の得たものが、
既に誰かが綺麗に、体系的にまとめてくれていたと知れたこと。
自分の中で言葉にならないけど、大切なものだと思っていたことが、
言語化されて、学問の一つとして大切に扱われていたこと。
自分の感じたものは、たしかに、ある。
そういう風に実感した時、涙が出ました。
学問で、ここまで感動するのは初めてで、
この境地を知ってしまった以上、
自分が今までやってきたことは、多分人の心からやりたいことじゃないんだなあという実感が強くなったというのも、ほぼほぼ決まってた大学院進学をキッパリ辞めるきっかけになったのかも知れません。
さて、話は長くなりましたが、
このダンスと教育の授業で自分が得たもののコアが、
1)頭だけではなく、体にもinsight(見解/深い理解)があること
2)思考・言語を超えた枠のコミュニケーションの場があること
3)「自分であること」が最もオリジナルであることであり、だからこそ、価値があるということ。
4)心と体をつなげる=自分の心の声を聞くことが、「自分である」ことを助けてくれること、またその感覚を持つことが大切だということ。
になったのです。
はい。これらの学びが、
「What you feel is who you are」
という第三段階のクレドにつながる価値観になっていったのです。
===
また、これは少し異なる考え方ですが、
何かが起こったとき、直感的に、何かを思うことがありますよね。
たとえば、何かが起こって、「嬉しい!」とか「辛い...」とか。
これも、言い方を変えれば、何かの事象(事実)が起こって、解釈が発生し、それに伴い判断がおこってその感情や、思いが湧き上がる。
だから、直感的に思った・感じた(feel)ことを紐解くと、自分の思考回路の癖が、あったりするわけで。
それは、今自分に見えていることもあるし、見えないこともあるし、ときに、自分が認めたくないネガティヴなこともあるのですが、
たとえば、誰かとあって(事実)、今話したくないな...と思ったとき(判断)、実際は自分がその人と比べて劣等感を感じていて(解釈)、その人に大なり小なり嫉妬心があって、そう感じていたりとか。
そう言うことを含めて、その感情・感覚の裏側を考えることで、自分の姿・自分の思考回路が明確になることも多々あると思っていて。
だからこそ、
「What you feel is who you are」
をクレドにしているという部分もあります。
Thank you for being you.
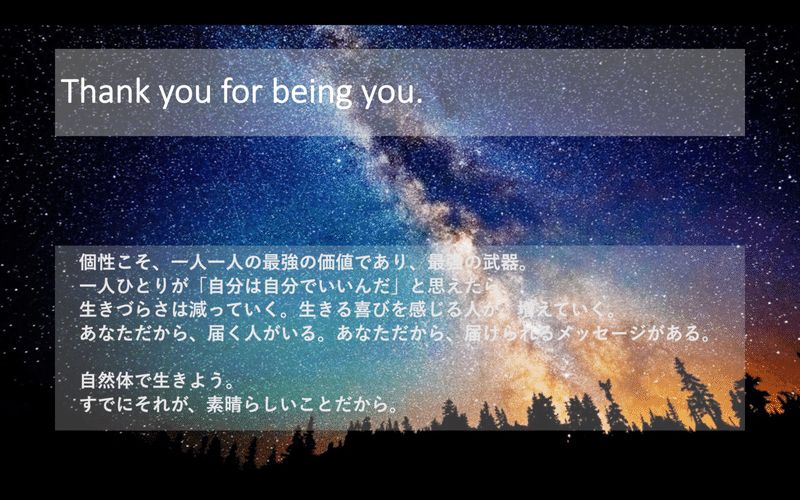
Thank you for being you.
留学した手の時、海外から大学にやってくる学生に向けて、1週間ほどオリエンテーションがあったのですが、その最後に、留学生たちの入学手続きから入寮手続き、オリエンテーションの運営など、たくさんの支援をしてきてくれたオフィスの方が、スピーチの最後に言ってくれた言葉です。
言われた時に、ズトオオオオォォォオオンと心にきて、そこからずっと自分の心の中に刻まれている言葉です。
直訳すれば、「あなたが、あなたでいてくれて、ありがとう」
という感じですが、日本語で言うとちょっと変だなあ、と思ってしまう自分がいて(文化的な差なのでしょうか...)、英語の方がしっくりくるなあと思っています。
クレドについての1つ目の記事の時に
たくさん学んだ・体感知を得た物の中で、このクレドに関係することを挙げるとすれば、「違いが価値」であるということ。
と書いていましたが、「Thank you for being you.」は、まさにこの考え方を別の方向から切り取った言葉ではないかと思っています。
今思えば、自分は常にこの感覚で留学時代を生きていたと思っていて。
自分の友人たちを、本当に、尊敬してて、
見かけたら全力で走って挨拶しに行くのがデフォルトになるくらい
本当に、大好きで。
彼らと一緒に時間を過ごせることを、本当に嬉しく思っていて。
多分そんな感じで、友人といるとハッピーオーラ全開の自分でいられたので、そこそこ言葉が通じなくても、心が繋がってるな〜と思える友達ができたのかも知れません。まあ、もしかしたら、英語という自分にとっての外国語の中で生活している間は、第二言語の限られたボキャブ内でしか思考の範囲が決まらないので、母語の日本語で考えられる歪曲した考え方などに陥ることがなかったのかも知れません。
それはさておき。
「この人たちってなんてすごい/素晴らしい人間なんだろう!!!」
をはじめとした、目の前の人の存在に対する存在に超絶感謝しながら毎日を送っていた時、ふと、
「人間みんな、価値があるじゃん...私にも、価値があるんだ...!」
と、自分の価値を感じられた瞬間があったのです。
言葉にして書いてみると、かなり淡白な言葉に聞こえますが、
ただ「書く・言う」のと、実際に体感できるかどうかは全く異なることで。
自分が、それを実感できたと言うことは、とてもありがたい経験だと思っています。
「愛されたいなら、まず愛せ」
「TAKEしたいなら、まずGIVEしろ」
的な言葉がありますが、
こういう経験をしてきた自分としては、
なんとなく、理解できる言葉なのです。
相手の存在が、友人たちの存在が、周りの人たちの存在が、尊かった。
そしたら、自分にも(少しだけでも)価値の光を感じられた。
うまくできてるもんだなあと思いました。
志は、デカく。
さて、自分の語彙力の限界に挑んだクレドは、以上の8つで終わりになりました。自分は人生いろんなものは流動的に変わっていくものだと思っているので、きっとこれから、どこかでクレドが変わる日が来るでしょう。でも、2020年6月時点の自分の、精一杯の頭の言語化の結果です。
正直、自分で言って結構ハードル高いと言うか、気取っていると言うか、そういう文章も書いてるなあと見返して思っています。中には、自分の中のデフォルトとして、できるようになってきつつあるものもありますが、できてないものも多数。(動いてはいるつもりだけど、囚われは強い...悲しいかな....)
でも、クレド = 目標/志 です。
いまできてなくても、大丈夫。というか、当たり前、というか。
それだったら目標の意味がなくなる...!(と自分に言い聞かせる)
自分のお世話になっている方で、「目標は常に自分の上にあるものだから一生達成することはない」とおっしゃっていた方もいらっしゃったのですが、そのくらいの心持でいきたいと思っています。
アップデートは、いつでもして良いものだから、
PDCAを積み上げて、ちょこちょこ、自分の中の仮説(カッコよく言えば仮説、フツーに言えば頭の中のふわふわの言語化)をアップデートしつつ。
次、自分がクレドを見直そうかな、と思うその時までに、
全力で考えて、決めて、動く、を積み重ねて、
今の自分のできてないところが、少しでもできるようになって
クリアになっていないところが、少しでもクリアになっていたらいいなと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
