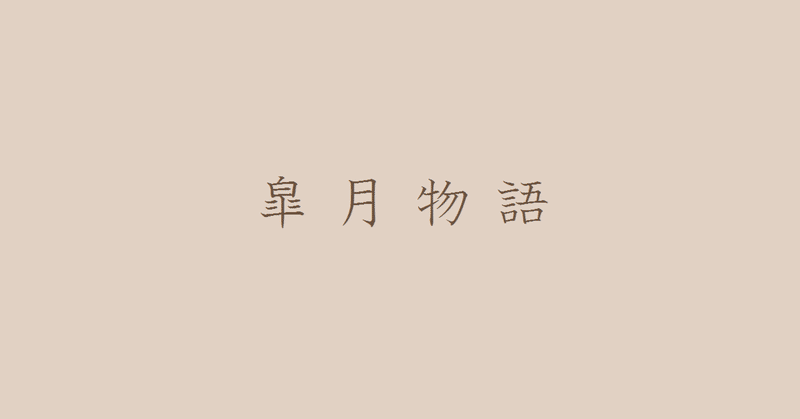
クーペの助手席に身を沈めて(皐月物語 113)
初めて見る車の助手席からの前面展望に藤城皐月は心を躍らせていた。同じ道を走っていても、自転車で歩道を走っている時に見える景色とはまるで違っている。空は広く、障害物もなく、視界が開けていて気持ちが良い。スピード感も刺激的だ。今は明日美が車の運転をしているが、いつかは自分も運転してみたいと思った。
明日美の運転する真紅のレジェンド・クーペは豊川稲荷の横を過ぎ、大きく左に曲がりながら進んだ。中央通三丁目の交差点をそのまま直進して、姫街道を横断した。
皐月はどの道で豊橋方面に行くのかよくわからないので、社会の授業で習った江戸時代の地理感覚で姫街道を左折するのかと思っていた。豊鉄バスで豊橋に行く路線は姫街道を右折する。一度バスで豊川から豊橋まで行ったことがあるが、大回りで時間がかかり過ぎたのでこの道はないと思っていた。自動車で目的地まで行くというのは、今の皐月には想像の及ばない世界だ。事前に地図で調べておけばもっと道中を楽しめたのにと、準備不足を後悔した。
このまま真っ直ぐ進むと、入屋千智に告白をした名鉄豊川線の稲荷口駅だ。千智の家もすぐ近くにある。千智が家にいるのなら GPS(Global Positioning System)では極近距離まで接近していることになる。だが、今二人は違う時空にいる。この瞬間、自分の認識できる世界には、いくら千智が自分の近くにいるとしても、現実は自分と明日美の二人しかいない。このことを皐月は自身に強く念押しした。
皐月が千智に好きだと言った時、幼馴染の栗林真理のことが脳裏に浮かんだ。だが、明日美のことはなぜか全く意識に上って来なかった。恋心としては明日美も真理も千智も、思いの深さは同じで最上位のはずだから、今思うと不思議な心の綾だった。あの時、明日美は皐月の現実世界にも精神世界にも存在しなかった。
稲荷口駅そばの諏訪町12号踏切は遮断機が下りていなかった。踏切の手前で一時停止すると、皐月は千智に明日美と二人でいるところを目撃されやしないかと冷や冷やした。
(ダセえな……俺)
もし明日美と一緒にいるところを千智に見られたとしたら、自分はどうするのだろう。言い訳をするか、それとも開き直るか……自問自答すると、どっちも格好悪い。皐月は何人もの女性を同時に好きになった自分のことを頭のおかしい気狂いのように思えてきた。
踏切を抜けると、右手にスーパーマーケットのサンヨネ豊川店が見えた。
「私、時々サンヨネで買い物するのよ。お魚が新鮮で美味しいの」
「へ~。明日美でもスーパーで買い物するんだ」
「そりゃするわよ」
「さっきフィールの横を通り過ぎたけど、フィールでは買い物しないの?」
フィールは住み込みの及川頼子が近所の店にないものを自転車で買いに来る、愛知のご当地スーパーだ。
「もちろん、するよ。その時の気分でお店を使い分けてるの。この車って大きいから、フィールの方が止めやすいかな」
芸妓姿の明日美しか知らなかった皐月はスーパーで買い物をする明日美を想像したことがなかった。無機質な部屋で暮らす明日美にはまるで生活感を感じなかったが、こういう話を聞くと芸妓の明日美にも人間味を感じる。サンヨネの横を通り過ぎると、皐月は少し名残惜しさを感じていた。
ここから先は皐月が足を踏み入れたことのないエリアだ。レジェンド・クーペの広く低い助手席からは知らない景色しか見えなくなった。車内には皐月には聴き慣れない、都会的で格好いい音楽が流れている。隣には芸妓姿でもなく、稽古姿でもない、大人の明日美がいる。香水もどことなく都会の女性のような洗練された匂いを放っている。皐月は本革シートに身を沈めながら、現実離れをしたこの状況に不安を覚え始めていた。
スキャットのリフレインが印象的なこの曲が何なのか知りたくなり、皐月は明日美のスマホを見た。『SHADOW CITY』という寺尾聰の曲だった。歌詞を聴いても一度では意味が良くわからないが、心細さに拍車がかかっているような気がした。
縋るような思いで隣を見ると、明日美が真剣な顔をしてステアリングを握っている。車の運転はタクシードライバーの永井のように巧みではないが、悠々としていてエレガントだ。芸妓姿の時の華やかさとは違って、美しさの中に儚さを感じるのは、皐月が明日美が命にかかわる病に冒されていることを知っているからだ。そんな明日美の横にいると、事故で一緒に死ぬのも悪くないな、と思った。
坂を下り、国道151号線に出た。観音堂の交差点で信号待ちになったので、皐月は明日美の右腕に手を掛けた。
「どうしたの?」
「ちょっと寂しくなった……」
「可愛いことを言うのね」
「遠いよ……」
タクシーの後部座席にしか乗ったことのない皐月にとって、高級車の助手席はセンターコンソールが邪魔をして運転席まで遠すぎた。
「後で抱きしめてあげるから、もう少し我慢してね」
信号が青に変わった。大きな交差点を右に曲がり、中央分離帯のある片側2車線の道をしばらく進んだ。周囲は田圃に囲まれていて、空がやけに広い。城下交差点を左折すると、もう皐月には考えたことすらない遠い世界だ。陽はまだ高く、妙に健康的なのが心もとない思いにさせる。皐月の暮らす町にこんな空間はない。
車窓を流れる町並みは皐月の生活圏にはない建物ばかりだ。県道400号線沿いに立ち並ぶ全国チェーンの店たちを眺めていると、機能的だと思うが退屈で、駅前商店街とは違った光景に趣のない旅情を感じる。しばらく走ると豊川放水路を渡る橋に出た。皐月の感覚だと、川の向こうが豊橋だ。
交通量が増えてきたので、気持ちよく走るというわけにはいかなくなった。心なしか明日美に余裕を感じられなくなったように見える。皐月は自分の買い物のせいで明日美に負担をかけていることに気が咎めた。
「皐月、大人しくなっちゃったね」
「うん……この辺りは全然知らないから、いろいろ珍しくて面白いよ」
皐月は沈む心を取り繕うように、少しでも明日美の気分が良くなることを言おうと思った。
「今までは車よりも鉄道の方が好きだったけど、車もいいね。道があればどこにでも行ける」
「ドライブならいくらでも連れてってあげるよ」
「ホント!?」
「私もせっかく車を買ったんだし、もう少しドライブを楽しまないとね。今は買い物か雑用にしか車を使っていないから」
皐月には市街地の中を運転している明日美がドライブを楽しんでいるようには見えなかった。
「ねえ、街中の運転って大変?」
皐月は気になっていることを聞かずにはいられなかった。だが、直接聞くことはできない。人の心に手を突っ込むような真似はしたくなかったので、回りくどい言い方しかできなかった。
「そうね……やっぱり事故らないように気を使うわね。それに、豊橋の道ってあまり走ったことがないから、よく知らないの。一応、予習はしてきたんだけどね。でも、そろそろナビに頼ろうかな」
「この車ってナビ付いてるの?」
「付いているけど、壊れてるの。まあ、壊れていなくても古すぎて使い物にならないと思うけどね。スマホホルダーに隠れている小さな画面がカーナビなんだよ。時代を感じるわね」
信号待ちになると、明日美は Spotify を閉じ、音楽を止めた。グーグルMapを起ち上げ、『コンパル』までの経路を出してナビを開始した。
「音楽止めちゃったけど、皐月のスマホにケーブルを繋ぎ直せば聴けるよ。今度は皐月の好きな曲をかけてよ」
明日美の車のオーディオ周りはややこしい。小さな機器がシガーソケットに刺されていて、それに USBケーブルが繋がれてスマホと接続している。
「ねえ、この機械って何?」
「FMトランスミッターって言ってね、音楽をFM電波に変換して発信する機械なんだよ。今まで聴いていた音楽って、ラジオ経由で聴いてたの」
「へぇ~、面白い! 昔の車が Bluetooth なんか使えるわけないもんね。面倒だけど、なんかレアなゲームを攻略したって感じがして楽しいね」
「この車のオーディオって古すぎるから AUX端子が付いていないのよ。でもね、カセットテープは聴けるし、CDだって6枚も入れられるのよ。もっとも私はCDなんて持っていないけどね」
「頼子さんがカセットテープいっぱい持ってるよ。頼子さんがこの車に乗ったら喜んじゃうね」
明日美に笑顔が戻った。どうやら明日美は道順に自信がなくて心に余裕がなかったようだ。皐月は自分のスマホにケーブルを繋ぎ、Spotify にある自分の好きな曲を集めたプレイリストの曲を流すことにした。
「自分の好きな曲を聴かせるのは、自分の心をさらけ出しているみたいで恥ずかしいな……」
「さらけ出せばいいじゃない。私はどんな恥ずかしい皐月でも好きよ」
「本当?」
明日美が口にした言葉は皐月が千智に言った台詞と同じ構文だった。明日美が自分のことをどのくらい好きなのか不安だったが、この言葉を聞いて皐月は安心した。自分が千智のことを好きだと思うくらいには、自分も明日美に愛されていることがわかったからだ。
皐月はプレイリストの中から暗示的な曲を選んだ。≠MEの『君はこの夏、恋をする』だ。皐月はこの夏、たくさんの恋をした。
「明るい曲だね。流れるようなメロディーが心地いいな。私、この曲、好きだよ」
プレイリストをシティーポップからアイドルに変え、皐月は寂しさから解放されたような気分になった。大人の音楽もいいけれど、自分にはアイドルが似合うまだ子供なんだなと思った。
「で、皐月はこの夏、恋をしたの?」
こういう質問をされることは、この『君はこの夏、恋をする』を選ぶ時に覚悟をしていた。もしかしたら自分はきわどい会話を望んでいたのかもしれない……皐月は明日美と恋の話をすることで、自分のこれからの身の振り方をはっきりさせようという気持ちがあった。
「したよ」
「へ~、よかったね」
肩透かしを食らったような気がした。皐月は明日美に恋の相手を追及されるのかと思っていた。
「俺、この夏は明日美に恋をしたんだからね」
「……ありがとう」
明日美はあまり嬉しそうではなかった。何か重大なミスをしたんじゃないかと不安になってきた。
「皐月の家に女子高生の女の子が住み込みしているんだよね。その子には恋をしなかったの?」
試されてるな、と思った。なんて答えたらいいのか、すぐに答えを出さなければならない。見え透いたことを言っても、芸妓の明日美には即座に見抜かれるだろう。
「……少しは、したかな」
明日美の顔が晴れやかになった。
「やっぱりな~。この前のビデオ通話にチラッと顔が見えた子がそうだよね。可愛い子だなって思ったんだ。皐月が恋しちゃっても仕方ないよね~」
及川祐希の存在は明日美にはすでに知られている。祐希の母の頼子と明日美は芸妓繋がりで交流がある。明日美は祐希のことで探りを入れたかったのかな、と皐月は考えた。それならば、いい感じに答えられたと思った。
「ときめきは衝動的だもんね。疼く心は抑えられないよね」
「明日美、もう歌詞を覚えちゃったの?」
「印象的なフレーズしか覚えていないけどね。じゃあさ、この夏、皐月に恋をした女の子っていると思う?」
また明日美が試しにきた。今度は自分の気持ちを言う必要がないので、気が楽だ。それに皐月には明日美の聞きたいことの見当がついている。
「さあ? どうだろう?」
「前、一緒に帰ってた子なんて皐月に恋しているように見えたよ?」
「あいつが? それはねーよ」
やはり江嶋華鈴のことだった。明日美は華鈴のことを気にしていたようだ。
「あの子、皐月に恋していると思うんだけどな……」
それは皐月もそうなんじゃないかと感付いていた。だが確信はなかったし、自分の自惚れじゃないかとも思った。それを明日美は一目で看破した。ただ見破られてはいけないのは、皐月が華鈴に対して抱いている仄かな恋心だ。
「あいつとはよく喧嘩するし、委員会でも怒られてばかりだ。恋愛とは程遠いよ」
「ふ~ん」
皐月には明日美の考えていることがわからなかった。少なくとも嫉妬しているようには感じられなかったが、何らかの不満があることは感じられた。
「まあ、皐月が学校で楽しそうにしててよかった」
明日美のこの言葉によって緊張の続いた会話が終わった。釈然としない気持ちは残ったが、返答に苦しくなる前に会話を打ち切ってもらえたことに皐月は救われた。自分のこれからの身の振り方をはっきりさせるどころではなくなっていた。
車が中心街に近づくにつれて、路面に周囲の背の高い建物が影を落とし始めた。郊外を走っている時には気付かなかったが、すでに陽が傾きかけていた。レジェンド・クーペの車内も気付けばすっかり暗くなっていた。
薄暗がりの中、車の運転をしている明日美の顔が優しい大人の顔から妖艶な大人の顔に変わっていた。俺はこんな女と付き合えるのか……と、皐月はある種の戦慄を覚えた。
「明日美」
「……何?」
「暗くなってきたね」
「そうだね。そろそろライトをつけた方がいいかな」
ヘッドライトをつけている車とすれ違うことが多くなってきた。皐月はこのありきたりの会話にまた救われた。明日美はいつも通りの明日美だった。
挿入歌
寺尾聰『SHADOW CITY』
≠ME『君はこの夏、恋をする』
最後まで読んでくれてありがとう。この記事を気に入ってもらえたら嬉しい。
