
【とある本格派フェミニストの憂鬱7パス目】「必ず観察から入れ。それに立脚しない憶測は、ことごとく現実に裏切られることになる」
相変わらずここで触れたプロジェクトで手一杯なので、今回はさらに手短に。以前の投稿で触れられなかった内容の補足など。
経済人類学者カール・ポランニー曰く「保守派の思想的足跡の支離滅裂さを笑うな。彼らにとっては生き延びる為の現状への最適化こそが最優先課題。だからどんな無茶苦茶な方向転換だって恐れず遂行する。翻って我々革新派は理論的一貫性に拘泥し過ぎる。それで時代の遺物になりやすい…」。そしてまさにこうして「国家の集団脱皮」が加速した1848年改革以降の欧州では「国王と教会の権威主義に宣戦布告した」旧世代の既存活動家達の多くが脱皮の必要性を思い付く事すらなくただただ死に絶えていったのです。
この時代を生き延びた、すなわち当時の社会問題が「国王と教会の権威の絶対性」から「資本主義的活動が生む利益の正しい再分配方法」に推移するパラダイスシフトを見逃さず、正しく対応したカール・マルクスは、なす術もなく歴史の掃き溜め送りにされた他の革命家とはそもそも観察眼が違っていたのだと思います。
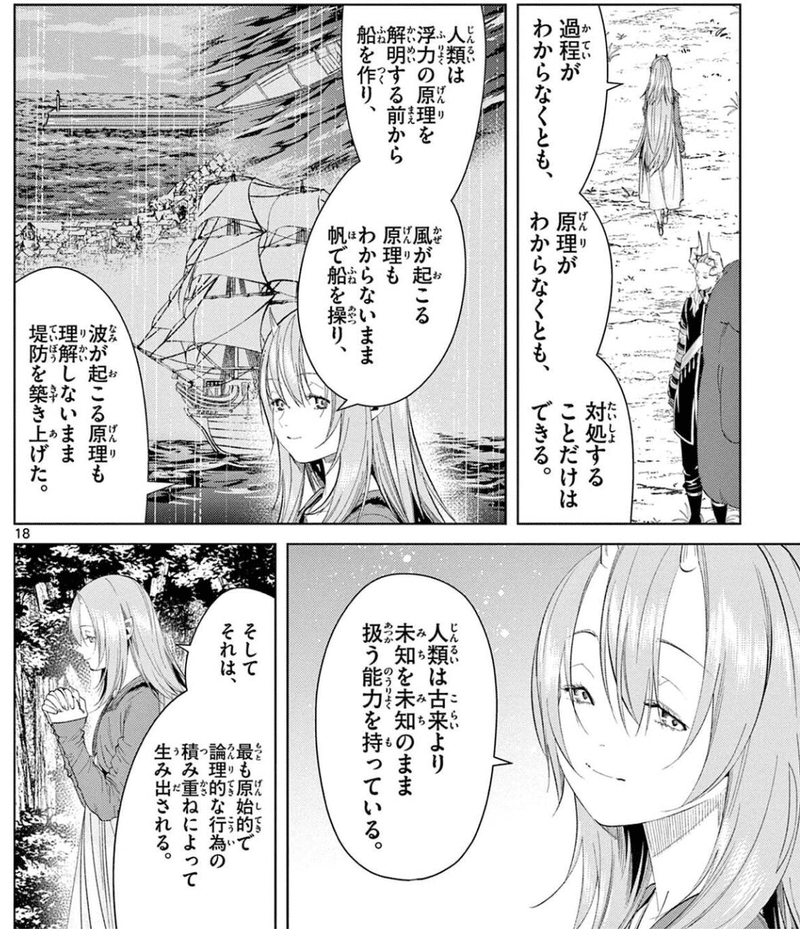

例えばカール・マルクスとフリードリッヒ・エンゲルスの共著「ドイツ・イデオロギー(Die deutsche Ideologie, 1845年~1846年)」にこうあります。
かの大評判の「人間と自然の統一」なるものは商業の場面で昔から厳存しており、産業の発展の高低に応じて時代ごとに別様な在り方で厳存してきたということ、同じくまた人間と自然との「闘争」も人間の生産性が相応の土台の上で「十分に」発展を遂げるまでは厳存し続ける遠いうこと、これの洞見である。工業と商業、生活用品の生産と交換は、それ自体が分配や社会的諸階級の編成を条件付けるが、逆にまたその営まれ方においては、分配や諸階級の編成によって条件付けられている。という次第でフォイエルバッハは例えば今日のマンチェスターでは工場と機械しか見ないが、もし100年前だったらそこで糸車と織機しか見ることが出来なかっただろうし、ローマ平原ではアウグストゥスの時代にはローマの資本家達と別荘しか、今日では放牧地と沼沢地しか見かけないという事になる。フォイエルバッハはとりわけ自然科学の直感について語り、物理学者や化学者の目にしか開示されない秘事に言及している。だが工業や商業がなかったら、一体どこに自然科学があり得よう?
私はこの考えを最初「必ず観察から入れ。それに立脚しない憶測は、ことごとく現実に裏切られることになる」と要約された形で聞いて、今でもその形で信奉し続けています。ちなみに実際の原文はカール・マルクスが国家学者フォン・シュタイン「今日のフランスにおける社会主義と共産主義(Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich, Leipzig 1842年)」を足掛かりとして、フォイエルバッハの「自己疎外の神学」や、マックス・シュティルナーの「空虚な自己の哲学」に反旗を翻す文脈で放たれています。
そういう詳細を知ったのは随分後になってから。そう、そうやってヘーゲル左派から足抜けするまで、カール・マルクス自身もヘンリッヒ・ハイネをこよなく信奉する一介のロマン主義詩人崩れに過ぎなかったのです。結果としてフランスでもドイツでも「ロマン主義者の唯心論的革命運動」はほぼ壊滅。そう1848年革命によるパラダイム・シフト以前に彼は既にそういう変革を生き延びてきたサバイバーだったのでした。
その彼に再びチャンスが巡ってきます。1857年。世界初の国際連動恐慌勃発。それまで産業革命導入による発展が未来永劫続くと楽観的に信じてきた欧州人感が疑心暗鬼に駆られます。「もしかして俺達の考え方、何処か間違ってた?」
盟友ラッサールのパトロネージュを受けて10年の沈黙を破ったカール・マルクスが「経済学批判(Zur Kritik der Politischen Ökonomie, 1859年)」を刊行したのは、まさにそういう時期だったのです。ちなみに「進化は確率論的過程に過ぎない(神の手の介在はない)」と断言したチャールズ・ダーウィン「種の起源(On the Origin of Species)」刊行も、コンドルセ侯爵の衣鉢を継いで中心極限定理(CLT=Central Limit Theorem)に基づいて「文明が発展するには個性と多様性と天才が保障されなければならず、権力がこれを妨げるの他人に実害を与える場合だけに限られる」と断言したジョン・スチュワート・ミル「自由論(On Liberty)」刊行も同年。そう、まさにこの時の欧州の経済的精神的動揺に「待ってたぜェ!!この瞬間をよォ!!」と快哉を叫んだのはなにもカール・マルクス一人ではなかったのでした。
なお、ダーウィンが「種の起源」を発表したのは当時ライバルだったウォレスが同種のアイディアを温めていると知って先に発表する必要性が生じたから。つまり「史上初の世界恐慌に邂逅した欧州人の経済的精神的動揺」と直接の関係はない動機に基づく行動だった訳ですが、それ以前の時代に「種は神から先天的に与えられた属性ではなく進化の産物」「しかもその過程に見えざる神の手は介在していない」というアイディアを発表しても笑い飛ばされて終わりだった事実だけは残ります。そしてその結果「勇気が少しだけ上回っていただけのダーウィンの名前は歴史に残り、少しだけ下回っていただけのウォレスの名前は忘れ去られる」不可逆的展開となってしまった訳です。
一方、ジョン・スチュワート・ミルが自由論を発表したのはこのまま選挙権拡大が続くと政治がポピュリズムに屈するのを危惧しての事でした。彼自身はコンドルセ侯爵同様数学者として大数の法則を信じ「人類がその潜在的可能性を引き出すには挑戦数の最大化、すなわち職業差別や人種差別や女性差別の撤廃が不可欠である」と考えていましたが、衆愚政治は大衆の分別に欠けた感情的判断に阿るのでその原理原則を貫けないと考えて警鐘を鳴らしたのです。実際、当時の英国自動車産業を悪夢に叩き落とし、フランスやドイツの自動車業界の優位を許した赤旗法(1865年-1896年)など彼の考え方が当たってしまったとしか思えません。
そのコンセプト自体はコンドルセ侯爵の時代に既に相応の完成度を見せていました。しかしながら、いかんせん時代が早過ぎて黙殺され、以降も思想的には省みられる事がなかったのです(ただ19世紀からフランスやドイツが初等教育に力を入れ始めたのは、その影響とも)。この意味合いにおいて既存欧州社会が動揺するタイミングを狙って「自由論」を発表したジョン・スチュワート・ミルは、その内容の革新性について相応には自覚的だったと考えられそうです。
それではカール・マルクスの場合は?「経済学批判」の内容が本来の構想のごくごく一部に過ぎず、それがある程度まとまった形で発表されるのが「資本論」第1部(1867年)。結局、生きてるうちに書き上げられず、第2部(1885年)と第3部(1894)は死後、エンゲルスが遺稿を編纂する形で発表されています。とはいえ、そもそも「資本主義的活動が生む利益の正しい再分配方法」そのものが今だ未発見のままな訳で、もし完成度にこだわり過ぎていたら発表時期を完全に逃していた事でしょう。そう、マルクスの天才はその理論的内容自体というより、まず「コンドルセ侯爵の様に早過ぎず、ウォレスの様に遅過ぎない」絶妙のタイミングで自説を公表した時期見極めの鋭さにあったという訳です。
それでは肝心の「経済学批判」の中身とは?
人々は、その生活の社会的生産において、特定の、必然的な、彼らの意思に依存せざる諸関係を結び、この生産関係は、彼らの物質的生産力の特定の発達段階に応当するのである。これらの生産関係の総体は、社会の経済的構造を形づくり、これが実在論の基礎であって、その基礎の上に法律的及び政治的上部構造が立ち、その基礎に相応して特定の社会的意識諸形態がある。物質的生活の生産方法は社会的、政治的、及び精神的生活過程一般を制約する。人々の意識が彼らの存在を決定するのではなく、むしろ反対に、彼らの社会的存在が彼らの意識を決定するのである。
これについても最初は「我々が自由意志や個性と信じているものは、社会的圧力によって型抜きされた既製品に過ぎない」なる要約形で教わったものです。有名な「上部構造」論の出発点ですね。
ただし私自身はこの上部構造論をそのまま継承してる訳ではありません。ヘルムート・プレスナー「遅れてきた国民 ドイツ・ナショナリズムの精神史(Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes,1959年)」によれば、ドイツ社会学の発足は、まさにマルクスの上部構造論や「さよう、自由は人間を解放する。ただし自由にではない」なるモットーで有名なフロイトの精神分析登場の衝撃の賜物だったそうです。しかしながら、それ故に黎明期ドイツ社会学者の皆様は、まるで親からの自立を試みる子供の様に執拗に上部構造論と精神分析への反駁を続け、その結果、実際にそれぞれが別系統の学説を立てるのに成功したというのです。でも本当に?
例えば、ここでいう「黎明期ドイツ社会学者」の一人が「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus,1904年~1905年)」で有名なマックス・ウェーバー。そして彼が「上部構造論駆逐兵器」なる鳴物入りで導入したのが「鉄の檻(Gehäuse)」理論となる訳ですが…
マックス・ウェーバーはその「鉄の檻」理論においてその過程を外骨格生物の生涯に擬えました。①全身を鎧う甲殻は、身の周りの危険から守ってくれる防具であると同時に、形成された時点で概ね成長限界が設定された自動処刑装置でもある。②脱皮の都度生命を危険に曝すが、成功すれば新しい余命を得る。
「割と原型留めてますねぇ、どうして誰も指摘しないの?」「どうせなら「社会民主主義の父」ラッサールが主張した様に「(英国や日本みたいな)脱皮を脱皮を必要としない国家」を目指せばいいのに」と思ったのが4パス目投稿のモチベーションとなりました。今から思えば懐かしい思い出…
もしかしたら我々は「必要なタイミングごとの脱皮が存続条件」という考え方そのものからの脱皮を迫られている?そういえば前掲の経済人類学者カール・ポランニーも主著「大転換」の中でこう言ってます。「英国囲い込み運動については、賛成派と反対派のどちらに正義があったか問うても始まらない。衝突があった結果、その範囲が時宜に応じて常時暴動に発展しない規模に抑え込まれ続けた事だけが重要なのだ」。なるほど、それが「産業革命導入に際して脱皮を必要としなかった国の方法論」だったという分析なのですね。
そんな感じで以下続報…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
