
【数理的溢れ話3パス目】「光あれ」とのみ創造神はのたまひけれ?
やはり予想通り数理関係のシリーズはnoteで参照数が伸びませんね。以下の投稿でも少し触れた様に、しかも、そもそも2017年から数学再勉強を始めた私の語れる数理なんて、その決意を固めて最初に読んだ山本 義隆「小数と対数の発見」に手が生えた程度。もっと本格的な数学展開に興味がある人には猫跨ぎされてしまう程度の内容なのです。
2017年末に「自分の考え方には徹底して数理が足りてない」と自覚して数学再勉強を誓う展開を迎えます。とりあえず、統計言語Rを学びながら半年以上かけて読破したのが以下の2冊。
後者は大著「磁力と重力の発見」を「科学技術史物理バージョン」とすれば「科学技術史数学バージョン」という認識。これまで様々な要約に触れてきましたが、以下の投稿を読んで改めて興味が湧いてきました。そのうち読破に挑戦するかもしれません。
「科学諸表出版革命」と「複素平面革命」
数学者クロネッカー(1823年~1891年)は「自然数を作り出したのは神で,その他はすべては人間の手の仕業だ」と述べたそうですが、実際に欧州で本格的に「貸方と借方の合計が0となる」複式簿記の概念が浸透するのはイタリアルネサンス期、当時先進地域だった地中海沿岸文化圏の算術を紹介するルカ・パチョーリ(1445年~1517年)の「スムマ(Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita=算術、幾何、比および比例に関する全集,1494年1)がヴェネツィア共和国で出版されて以降。それ以前には、そもそも「ローマ数字で考えなければならない」制約のせいで「加法群=加法単位元0を中心として任意の数値に必ず合計すれば単位元0となる逆数が存在する等差数列(結合法則を満たす連続演算)」概念自体があまり広まっていなかった様です。この壁を越える為に、まずはアラビア数字と、(加方群概念そのものの具現化たる)複式簿記概念が広まり、「時間管理に周期性がある」期間会計概念に発展する必要があった訳です。
複素数の効用
だが、なまじ複式簿記概念から出発したが故に乗法群への到達は遅れる事になったとも。前掲の山本義隆「少数と対数の発見」はここで「(貨幣単位未満の端数を嫌い、帳簿を整数で管理したがる)商人気質の壁」を示唆していますが、さもありなん。やがて「関数$${y=a^x}$$におけるxの増分1とyの増分1を揃える魔法の定数ネイピア数e(2.71828182…)」の発見につながる複利計算概念も「72の法則」といった近似計算によって誤魔化してお茶を濁していたという次第。
この壁を乗り越える契機となったのが、大航海時代における測量や(それとも密接な関係を有する)天体観測ニーズ増大によって生じた「桁数の多い乗除算」を楽にする魔法の計算$${ab=c^{log_ca+log_cb}}$$「常用対数表(Table of Common Logarithms)を用いて乗除算を対数化して加減算を行い、その結果を指数化して戻す演算」でした。ここで魔法魔法と繰り返しましたが、まさにルネサンス期の出版革命を契機として、それまで数秘術師が秘伝として弟子だけに伝えられてきたこの種の演算が「科学諸表」なる一般人にも使いやすい形で刊行され、大量頒布される様になった事こそが欧州を「地中海文明圏辺境の後進地域」から「世界の先進地域」へと変貌させた訳です。
魔法といえば、三次方程式を虚数$${i^2=1}$$を用いて解く方法もまたルネサンス期の数秘術師タルターリヤ(1500年~1557年)の考案した秘術の一つで、一般にその解法の発見者とされるカルダーノ(1501年~1576年)は、歴史のその時点における認識だと「数秘術師タルターリヤからその解法を聞き出して勝手に公開した無礼者」に過ぎなかったりします。
さらには、この虚数概念$${i^2=1}$$を指数関数の底の変換演算$${a^b=e^{log(a)b}}$$を用いて変形すれば$${i^2=e^{2*log(i)}=e^{2*\frac{π}{2}i}=e^{πi}=-1}$$と、オイラーの等式$${e^{πi}=-1}$$、すなわち「指数関数$${y=a^x}$$の底が「指数関数の水平方向への増分1を垂直方向への増分1に対応させる」ネイピア数eで、指数に「絶対値1で実数直線に対して垂直の方向を向くベクトル」iを置いた場合、距離πで実数直線上の逆数-1と到達する」数理が自明の場合として導出される訳ですが、フランス革命(1789年~1795年)からナポレオン戦争期(1796年~1815年)にかけての革命戦争時代にガウスらが複素平面概念を考案して広めるまで、その幾何学的意味合いや、加法単位元0と乗法単位元1の関係性をイメージするのは数学者でさえ相応の困難を伴った様なのです。


逆をいえば「科学諸表出版革命」と「複素数平面革命」を経てきた我々現代人は、比較的容易に(加法群概念に従う)実数直線を「半径i(絶対値1=乗法単位元1)の複素円筒座標系」のイメージに拡張する事が出来ます。複素平面概念に従って「水平評価軸上の実数列(実数軸)rの値は垂直評価軸上の虚数列(虚数軸)iの絶対値が乗法単位元1である事によって担保されている」と考えればいい訳ですね。

ところで乗法群$${y=a^x}$$には①指数xが乗法単位元1未満の場合のyは1から0の範囲に分布(収束)。②1以上の場合のyは1から$${\tilde{∞}}$$の範囲に分布(発散)、という性質があるので正元$${y=a^{+x}}$$と逆元$${y=a^{-x}}$$のそれぞれ$${y=a^{0}=1}$$から$${y=a^{-∞}=0}$$の範囲を組み合わせて全体の長さを2で表す事が出来たりもします。複素平面概念の三次元拡張の際の副産物たる「リーマン尺」…この考え方と「無限遠点+∞と-∞は符号なし無限遠点$${\tilde{∞}}$$で交わる」と考える無限周期概念を組み合わせると、」さらに柔軟な数理運用が可能となる訳ですね。


もちろん直交座標系はどちらも実数軸に取る事も出来て、これを(それぞれの次元の1を擦り合わせながら)n次元積み重ねていくのが線形結合$${a_0x_0+a_0x_0+…+a_nx_n}$$の概念となる訳です。
それでは評価軸の交差角度が直角でなかったら? その場合について考えた一例が、いわゆる「相関係数」だったりします。「垂直に交わる2つの円筒座標系の楕円断面を第三軸から回転させて眺める」イメージ。
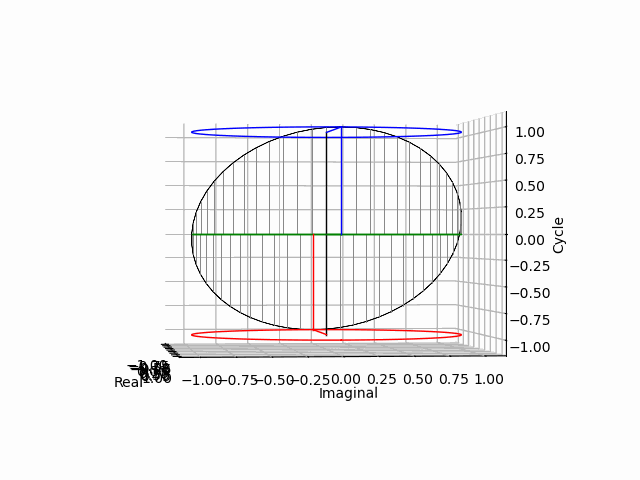
さらに円錐曲線の極座標上の数式表現$${y=\frac{1}{1+εcos(θ)}}$$を援用すれば、離心率ε=1の時、中心0半径1の円弧が放物線$${y=x^2}$$となるので、その指数写像を取る事でベルカーブ$${y=e^{-x^2}}$$に変形させる事も可能。この辺りはそのうちpythonで実際にグラフ化してみたいものですね。
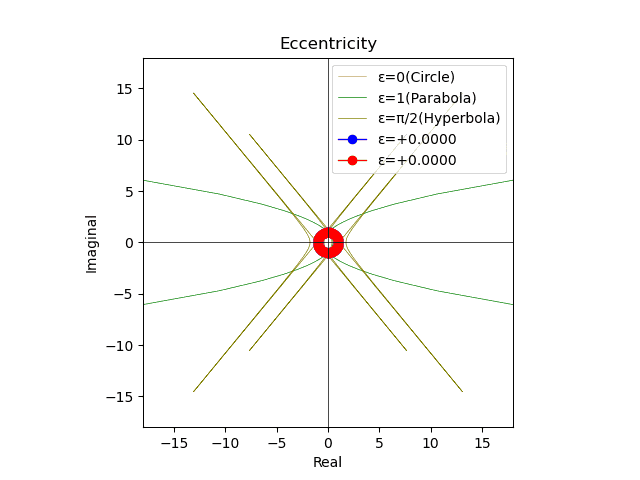

「直径の発見」は人類以前?
とまぁ、ここまでは私が中高生の頃から考えてきた事の2018年からの数学再勉強で掴み直した内容に過ぎない訳ですが…
最終的に到達したのは「人類は直径が半径の二倍であり、また半径が直径の半分である事については、歴史の最初から先験的直感から自明の場合と考え疑った事がない」という考え方でした。ある意味、上掲の数理展開はすべからく、かかる「直線上の推移と回転運動を可換と考える」基本的信念から自明の場合として導出される拡張概念に過ぎないという訳です。

かかる基本的信念の獲得時期は人類以前、カンブリア爆発(約5億4200万年前~5億3000万年前)に突如として「視覚」「視覚情報を処理する脊髄」「前後上下左右への素早い移動を可能とする運動期間」の3点セットを備えた左右相称動物(Bilateria)が現れ、極めて緩慢な動作しかとれない放射相称動物(Radiata)にぐんぐん差をつけて地球を闊歩する様になった時期まで遡れそうです。そう、その概念を実際に認識して著しく発展させたのは人類以降かもしれませんが「前後」「上下」「左右」の$${2^3}$$方向に広がりを有し、かつ回転による座標変換概念をも伴う三次元直交座標系概念自体はこの時代まで遡り、かつ今日なお我々の思考様式を拘束し続けているという訳です。
数学でいうとほとんど「アフィン変換」に対応する領域の話ですね。
「自然数までは神が作りたもう」としたクロネッカー見解よりさらに踏み込んだ? まさに世界創造主が「光あれ」と命じた(そしてそれ以降は何もなさらなかった)かの様な劇的展開。しかしながら、この変化の結果生物史上初めて現れた「百獣の王」アノマロカリスについては、以下の様な悲劇的最後を遂げたという説もあります。
当時としては破格の、全長1mにも達する化石が発見されている。この生物はおそらく硬い殻や棘や毒などで防御したり、泥の中などに潜む用心深い生物を食い尽くしながらその身体を巨大化させる一方、自らの身体や狩猟方法を進化させるのを怠り、狩れる獲物が無くなった時点で絶滅を余儀なくされたのである。
アノマロカリスは原始的節足動物の一種だが、次に現れた「百獣の王」は魚類の先祖で感覚器官や運動器官や「司令塔としての脳」を発達させつつ多種多様化し、その末裔として我々人類が現れた訳である。
古代帝国でいうと略奪遠征によって王室を養った新エジプト王朝と、これを模倣する形で発祥したヒッタイト帝国が揃って成長限界に達し、ついにお互いくらいしか襲う獲物が無くなってカデシュの戦い(紀元前1286年)で激突。双方、相手を滅ぼすのを諦めて人類史上初の平和条約を締結するも双方衰退を免れ得ず、あえなく「紀元前1000年のカタストロフ」を迎えたのが、上掲のアノマロカリス滅亡説と重なります。
その後、メソポタミアには再びアノマロカリス型の繁栄と滅亡を繰り返した新アッシリア帝国(紀元前744年~紀元前609年)が台頭。彼らに滅ぼされ尽くしたエラムの地より興ったアケメネス朝ペルシャ(紀元前550年~紀元前330年)が、これまでの経験を踏まえてより洗練された統治形態で長く国を保ったのが「魚類の時代」の嚆矢だったとも。そしてそういう時代がある意味(精密な海図が作成出来る測量技術の進歩も含めた)航洋技術が進化し、火砲も登場して「(国体を維持するのに十分な火力と機動力を備えた常備軍を中央集権的官僚制による徴税で養う)主権国家」が欧州に現れるまで続いた次第。
ここまで俯瞰してやっと全体像が噛み合ってくる様です。アノマロカリス全盛期「硬い殻や棘や毒などで防御したり、泥の中などに潜む用心深い生物」だけが生き延びた様に、古代帝国時代を神殿破壊や民族強制移住に屈せず民族的アイデンティティを保った「慶典の民」ヘブライ人や神々とそれにまつわる神話/英雄叙事詩を共有する「ヘレネス」ギリシャ人が生き延びたのが興味深いところですね。そして前者からキリスト教徒やイスラム教徒が発症する展開を迎える訳です。
ティグラト・ピレセル3世 (Tiglath Pileser III、在位紀元前744年~紀元前727年)以降の新アッシリア時代(紀元前934年~紀元前609年)はえげつなさが違う。彼らはティルス/テュロス(Tyrus/Tyros)やビブロス(Byblos)といったフェニキア人の本拠地を包囲してレバノン杉に立脚する造船業そのものにダメージを与える道を選んだ。その一方で反抗的な都市国家については、その神殿を破壊した上で全住民を遠隔地に分散して強制移民させる一方で誰もいなくなった現地に別民族を送り込む。この民族抹殺技術は新バビロニア帝国(紀元前625年~紀元前539年)にも継承され、エラム諸都市同様にヘブライ人もバビロン捕囚(紀元前587/586年~紀元前537年)もこの政策の餌食とされてしまう。
しかしヘブライ人はこの時、画期的な方法論を思いつく。「モーセ五書」とも呼ばれる律法(Torah)を編纂し、これをエルサレムの町や神殿に代わる信仰の拠り所とする様になったのである。とはいえこの時点でそれが完全に達成された訳ではなく、ユダヤ属州住人として帝政ローマを敵に回した第一次ユダヤ戦争(66年~74年)と第二次ユダヤ戦争(132年~135年)で再びエルサレム失陥と神殿破壊の屈辱を経験する(エルサレムがペリシテ人にちなんでパレスティナへと改名されたのもこの時)。だがこの時途方に暮れたのは最後まで神殿を離れられなかった神官達と一部強硬派(ユダヤ教の神殿祭儀とユダヤ王朝に価値を見出してきたサドカイ派)だけだった。
大半の信徒は二つのグループに分かれた。最初のグループはどちらかというと少数精鋭派で、在野におけるシナゴーグ活動を中心に展開してきたファリサイ派のラビ達を新たな精神的指導者に選んだ。彼らは第一次ユダヤ戦争に敗戦して神殿も破壊されたのを受けてエルサレム南西部のヤブネ/ヤムニア(Yibnah)に集まり、これからはトーラーに加えて「タルムード(Talmud、口伝律法)」も信仰上の拠り所としていく事、ただし以降はヘブライ語で執筆された聖典のみしか認めない方針を固める。今日我々が知る意味でのユダヤ教徒が誕生した瞬間であった。
一方、離散ユダヤ人(ヘレニズム・ユダヤ人)の多くが既にギリシャ語しか解さなくなっている問題が、既に(アレキサンドリアでギリシア語の七十人訳聖書が編纂された)プトレマイオス朝(紀元前306年~紀元前30年)の頃から問題となっていた。そして切り捨てられた彼らは、他の外国人同様に「ナザレのイエスが選んだ12使徒と(ヘレニズム・ユダヤ人や外国人に実践が易しい方向に律法を緩めてくれた)義人パウロ」を精神的指導者に選ぶ。今日我々が知る意味でのキリスト教徒が誕生した瞬間であった。
すると原罪概念の大源流とは?
もしかして古代メソポタミア時代、人類を生み出した神々は戦争に負けてとてつもない負債を負わされ、それを肩代わりさせる為に人類を生み出したとされていましたが、大源流はそれ? それともヘブライ民族の「どんな犠牲を払っても民族として生き延びる」精神の残滓とか?これ以上踏み込むとさらに長くなるので以下続報…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
